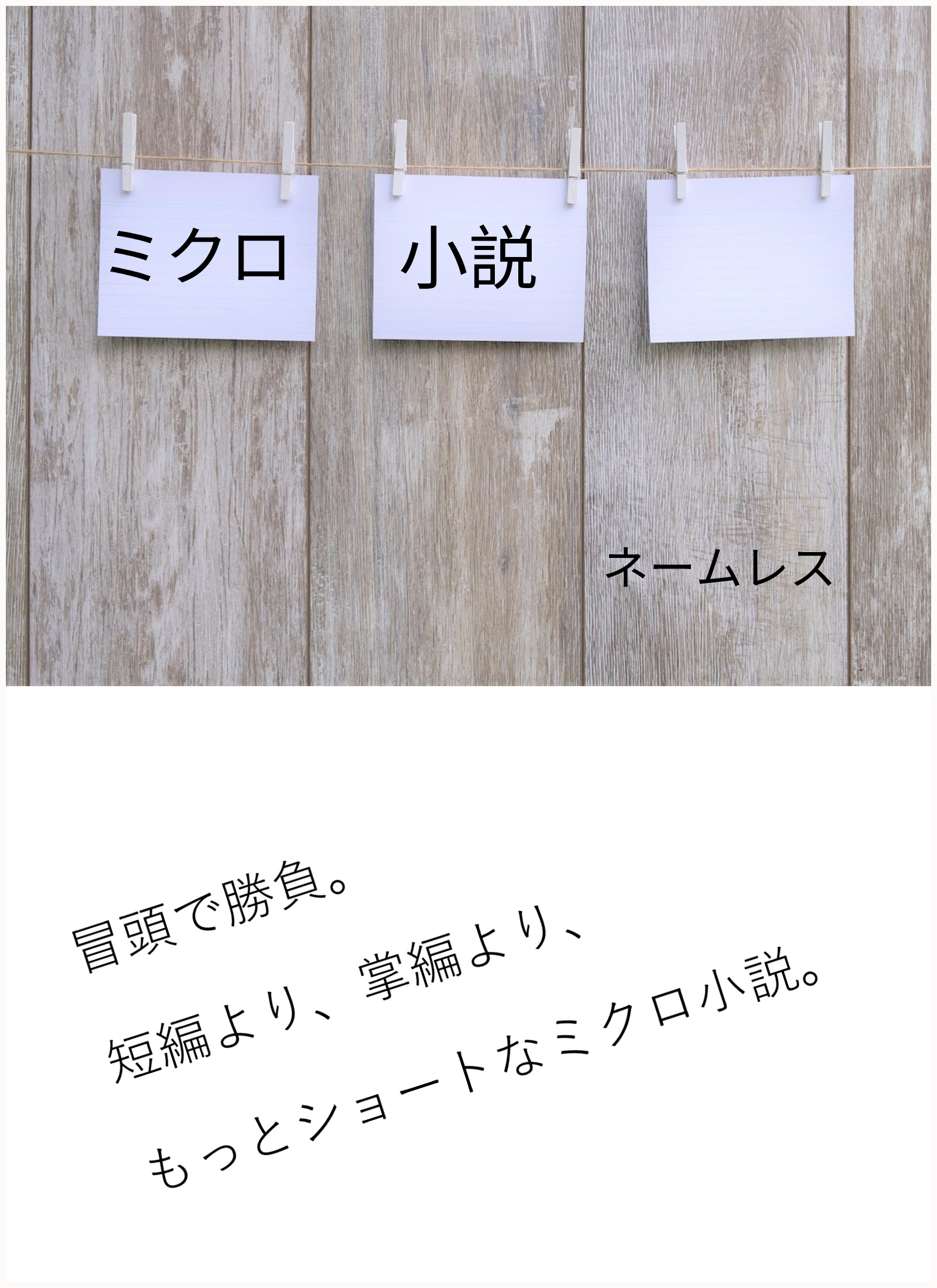第54話 6月24日 水曜日①
今日僕は放課後あらためてコインランドリーの裏にある駐車場を訪れた。
車が数台停まっているけれど今日は閑散としていた。
もっともふつうの駐車場とはこういう場所だ。
女子高生が女子高生を恐喝しているなんてのは非日常のできごとで事件以外のなにものでもない。
駐車場にきても彼女の手がかりを何ひとつ掴めずに引き返そうとしていたときだった、駐車場の真向かいに【紺野聡 明美】という表札のかかった大きな家を見つけた。
漢字にはきちんと「こんのさとし」「こんのあけみ」とふりがなが振ってある。
この家があの”コンノ”「紺野明美」って人の家なのか? たぶん間違いはないと思うけど。
高校からもそんなに遠くない教員住宅の区画を抜けた数十メートル先にその家はあった。
「紺野明美」って人も「山村澪」もこんな近くにいたのか? 僕の家からだってわずか五百メートルくらいのところだ。
これくらいの距離なら真夜中でも家にきてうちのポストに封筒を入れていけるはずだ。
一瞬彼女が家にいるかもしれないという可能性を考えた。
でも、まあ、この時間なら家にいないだろう。
訪ねない手はないと思った。
僕は玄関まで行き一度心を落ち着かせてからチャイムを鳴らした。
甲高く――ピンポーンと鳴る。
間違いだったら謝って帰ろう。
家の奥のほうから――は~いという声がした。
あ?!
「紺野明美」という人の声じゃない。
間違ったかもしれない。
なぜなら僕が押した玄関チャイムに反応したその声の主は、もっと声が低くてガラガラとした男の人の声だったからだ。
引き戸の玄関を開いて顔のぞかせたのは声とぴったりと合致っている年配の人だった。
顔にしわはあるけど品のある人だ。
応対してくれたのは表札の「紺野明美」という人ではなく表札にある「紺野明美」という人の夫である「紺野聡」という人の可能性が高いと思った。
それならここで結論を出すのはまだ早い。
夫婦ならば無関係じゃないんだから。
「どちらさまですか?」
「あの、突然すみ」
「ああ、きみかい?」
僕がまだ、――すみ、までしか言ってないのにその人は僕を知っているようだった。
「えっと、僕のことを知ってるんですか?」
「西川くんだろ? まあ、上がりなさい」
三和土の上でそう手招きされた。
「は、はい、すみません。ではお邪魔します」
躾どおりに挨拶をして「上がり框」に足をかけ、躾どおりに玄関のほうに靴先を向けて揃えた。
なんの警戒心も持たずに家のなかに上がらせもらう。
僕のことを知っているうえに名字が紺野。
あの”コンノ”って人、「紺野明美」さんの夫でほぼ確定だろう。
紺野さんはお茶を運んでくると僕が正座しているすごく高そうな大理石のテーブルの上にコトンと置いた。
湯呑みだってデザインが凝っていて指に合わせたような凹みがあって持ちやすそうだ。
僕の目線の先にはまたまた高価そうな籐椅子がある。
ただ見るからに小さくて「紺野明美」さんの物かもしれないと思った。
「さあ、どうぞ」
「あ、はい、いただきます」
言ったもののまだお茶には手をつけない。
家の中も絵画や壺、骨董品やさまざまな装飾品でいっぱいだった。
「遠慮せずに」
「はい。あの澪さんは?」
「今日は学習センターに行ってるよ」
澪という名前を口にしても通じた。
やっぱりここがあの”コンノ”という人の家で間違いない。
”コンノ”が「紺野明美」さんで夫が「紺野聡」さん。
そして姪が「山村澪」だ。
「学習センターってS町のですか?」
「そう。澪はそこでボランティアをしてるんだよ」
「ボランティア?」
「ああ。まあいろいろ事情ある人たちの手伝いさ。澪自身もそういう事情だけどね」
「あの澪さんは学校には通学ってないんですか? U町高校ですよね?」
「今は休学中」
「休学、ですか?」
「そう」
「どうしてですか?」
いじめが原因だろうな。
わかっていたのに口をついて出た。
「澪に聞いてないのかい?」
「はい」
「だったら僕の口からは言えないな。うちのもなんか言ってなかったか?」
うちの? ああ、奥さんのことか? 僕の家に白い封筒を入れていた”コンノ”イコール「紺野明美」って人だ。
「えっと、うちのというのは紺野明美さん。澪さんの叔母さんのことですか?」
「そう。明美のの弟が澪の父親なんだよ。まあ、僕からしても義理の弟ってことになるけど。あれは酒好きギャンブル好きの甲斐性なしでな」
甲斐性なしって「紺野明美」って人も言ってたな。
「それも澪さんに直接訊いてほしいと言われました」
「そっか。澪は毎日シフト制のアルバイトをしてるんだ。忙しいときは土日もね。四時間働いてあとは学習センター。先にボランティアに行ってそのあとにアルバイトってパターンもある。予定はあの娘のリズムで臨機応変に変わることも多い」
四時間か。
腑に落ちた、白い封筒に入っていた現金は三千五百二十円。
それを時給換算すると八百八十円。
S町の高校生のアルバイトの平均の時給もだいたいそれくらいの額だ。
あの白い封筒の金額とぴったり合う。
ということは彼女が毎日アルバイトで稼いだ額を叔母である紺野明美さんがそっくりそのまま僕の家のポストに入れていたということか。
「紺野明美」さんがあの娘から預かった封筒を持って僕の家きたときに入っていたお金は彼女が土曜日に働いた分のだ。
僕のように完全週休二日制で働いてるわけじゃないんだ。
アルバイトで稼いだ分は全部僕の家のポストに入れたようだけど……。
あの三人は彼女を恐喝していた。
もっともあの三人はその前に彼女の財布を盗んでいるし、他にも物を奪って転売しているからそのお金を使って大納言で散財していたということだ。