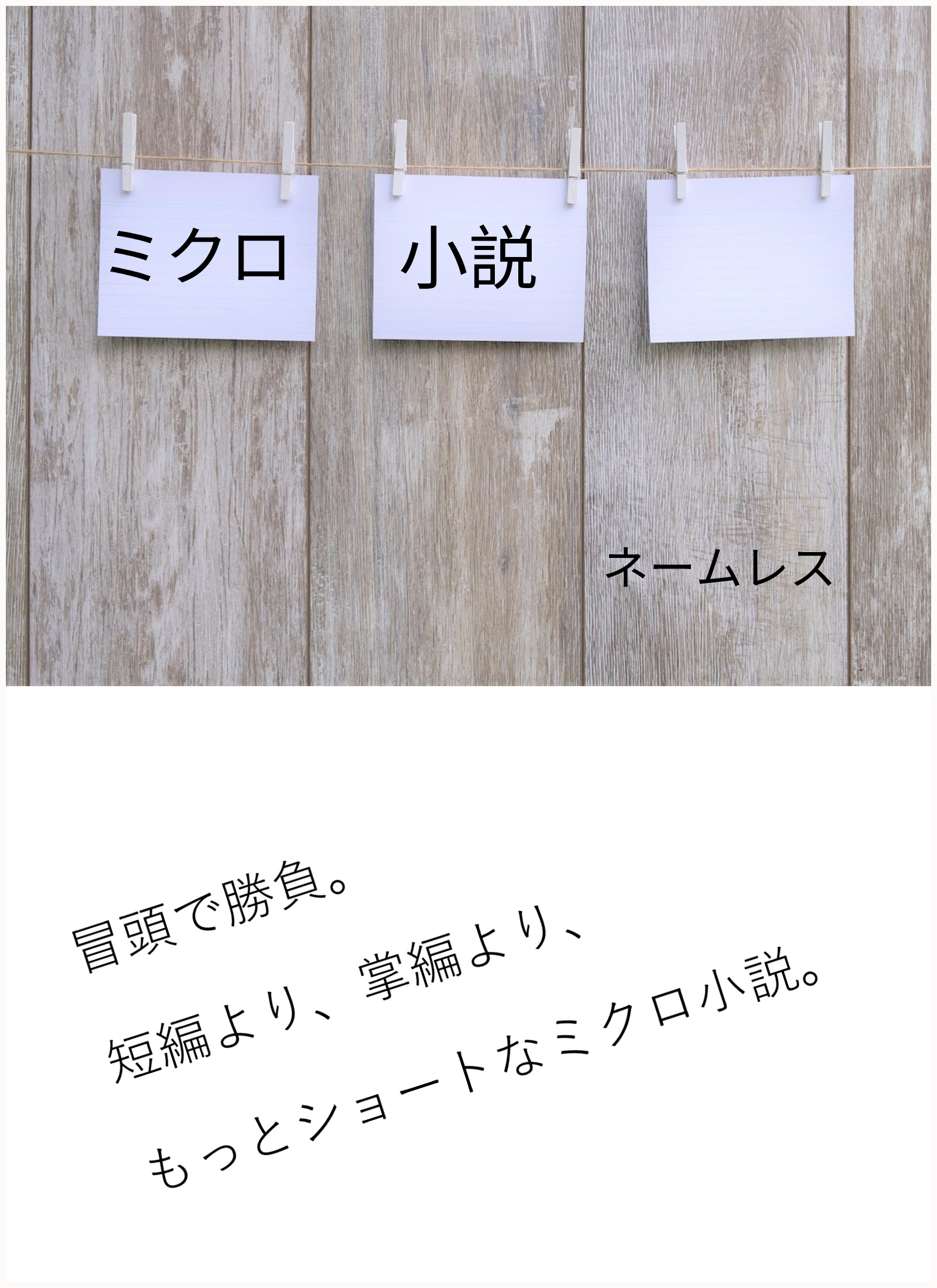第62話 6月26日 金曜日③
僕は電話を終え、すこし離れた歩道にいる彼女のところへ向かう。
「今日は長かったね?」
彼女はずっと待っていてくれた。
僕がまたふつうの高校生に戻るならば……。
きみも、「山村澪」も、またふつうの高校生に戻らなきゃいけない。
いや、知らないうちに大人に助けられていた僕が一緒に連れていかなきゃいけない。
同じように親の呪縛に縛られているなら開放してあげなきゃ。
つぎに彼女と逢って彼女のスマホを見れば心のなかで引っかかっていた何かが鮮明になるはず。
「ねえ。山村さん。明日アルバイトかボランティアが終わったらまたこの電話ボックスで逢えない? シフトだから時間が変わるんだよね? 時間は任せるけど」
今回はきちんと約束を交わしておく。
「何時がいい?」
こう返された時点でOKって意味でいいんだよね。
自問自答する。
「いつもの」
正確な時間がわからないからゆとりを持たせた。
「わかったよ。じゃあいつもの」
彼女はふふっと笑った。
”いつもの”で通じた。
もし僕がアルバイトしている時間だったら大将にまた休みをもらおうと思った。
「あの。ところで僕が毎日電話ボックスから菊池さんに電話してることどうやって知ったの?」
「きくちさんって誰?」
「遠縁の人」
「へー、いつものその人に電話してたんだ?」
「え?! 知らなかったの?」
「うん。ただ、きみ、じゃなく拓海くんのお母さんが体調を崩してるっていう話はきいてたの」
僕の呼び名が拓海くんになってて単純に嬉しかった。
「誰に?」
「うちのお父さんの弁護士さん。私がここで電話をしてたのはその弁護士さんなんだ」
「ああ、なるほど」
彼女がここで電話をしていたのはそういう理由だったんだ。
たとえ逮捕されたとしても、たとえ憎んでいたとしてもやっぱり親子。
お父さんが拘置所にいるとすれば被告人に接見できるのは原則、担当弁護士だけだ。
お母さんが早くに家を出ていって、ずっとお父さんのとふたり暮らしなら彼女なりにお父さんを心配するのも当たり前か。
僕にもあるんだ親に対するあの好きか嫌いかどっちかを選べない感情が。
たしかにそんな話なら紺野さん夫婦の家で電話はしづらいだろう。
そういったナイーブな話をするなら道の駅の公衆電話でもコインランドリーの公衆電話でも町外れのコンビニの公衆電話でも無理だ。
そう、それができるのはこのガラスで囲まれた誰も通称はしていないこの「旧駅前電話ボックス」だけ。
弁護士さんに聞いたってことは、僕が今どういう状況なのか警察や検察も把握してるってことか? まあ、警察も検察も逮捕権や捜査権を持つ組織なんだから
僕の家の現状を調べるのなんて簡単なことだろう。
それだけの力を持っていても詐欺グループの摘発は一筋縄じゃいかない……。
とくに組織の上に行けば行くほど尻尾が掴めない。
「女子高生特権使ったから」
女子高生特権っていうのはものすごい特権みたいだ。
下手したら警察や検察を超えるくらいなんじゃ?
「そういうことだったんだ」
「ごめんなさい」
彼女はまるで体のどこかを斬られたように顔を歪めた。
それだけお父さんの罪を背負ってしまってる。
僕はそろそろアルバイトに行かないといけないから今日はここで彼女と別れた。
本当はそんな顔を見ていたくなかったから早めに切り上げただけ。
なにより明日また逢うって約束の”お守り”もあるから。