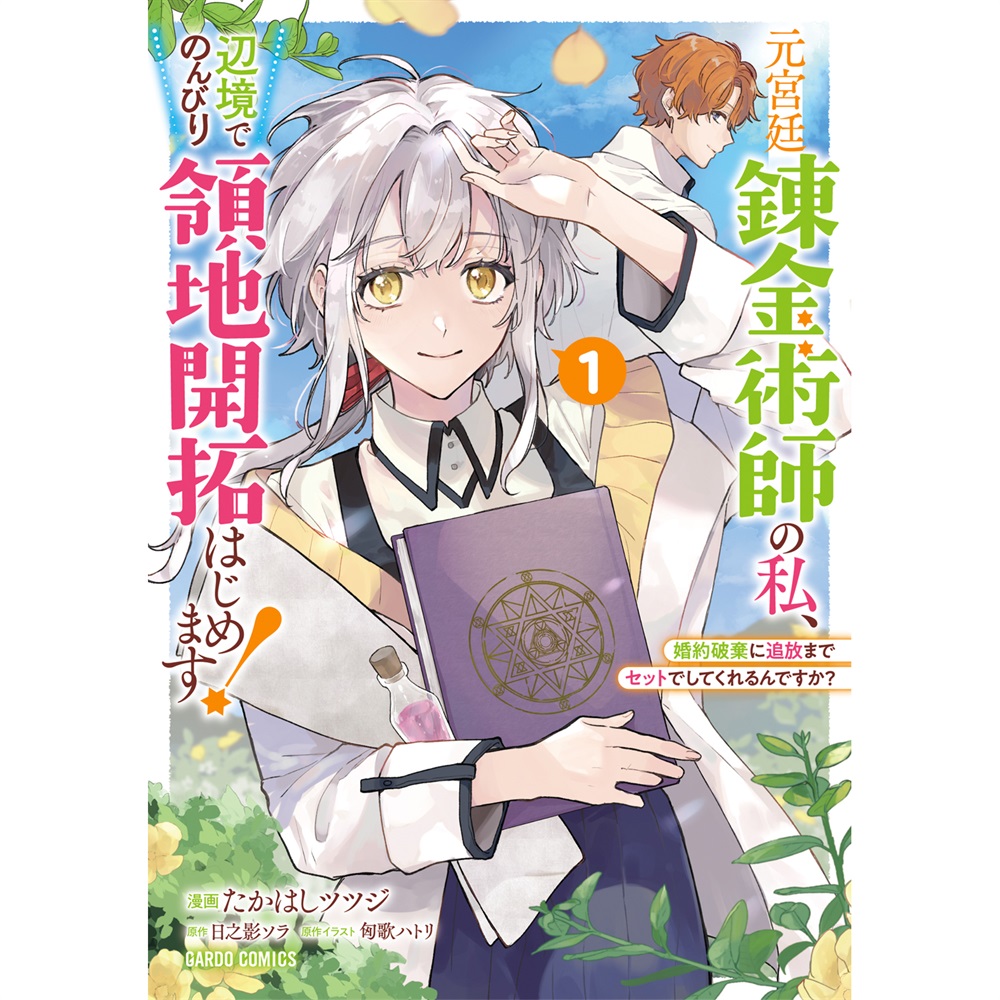寿退社を目指して③
夕食、入浴と済ませて、後は寝るだけ。
部屋も一人一部屋用意してもらえて、実に快適だった。
俺は寝る前に少し、ベランダで夜空を見ながら涼んでいる。
「サラス以外は同じ部屋でもよかったんだけどなぁ」
そうすればいつも通りハッスル……は、さすがにやめたほうがいいか。
一応ここ、ジーナだけじゃなくてアイギスの屋敷でもあるし。
今夜は帰ってこないみたいだけど、もしバッタリ遭遇したらその場で一刀両断される。
「おっかねぇ」
「こんなところにいたのか?」
「ん? ああ、ジーナか」
いい香りがする。
彼女も風呂上りだろう。
くそぅ、俺たちだけだったら一緒に入っていたのに。
邪なことを考える俺の隣にジーナが歩み寄る。
「風が気持ちいいな」
「そうだな」
二人で並び、夜空を見上げる。
「カナタとサラスは? 風呂では一緒だっただろ?」
「二人とも先に出た。今頃はもう夢の中だと思う」
「あいつらはどこでもすんなり眠れるよな。羨ましい限りだよ」
「タクロウは眠れないのか?」
「場所によるかなぁ。初めての旅行先とかは緊張して眠れなかったりする」
「私もだ。遠征では枕を持参していた」
「あ、それ俺も昔やったけど無意味だったわ」
他愛のない会話で盛り上がる。
しばらく話が弾んで、一呼吸おいてからジーナが言う。
「姉上のこと、家族のことも、黙っていてすまなかったな」
「――! 別に気にしてない。言いにくいことだってあるだろ。家族でもな」
「そうだな……」
「今さら聞くのもなんだが、よかったのか? 騎士を辞めるって、ジーナにとっては大きな決断だっただろ?」
「――ああ」
彼女は深く頷く。
亡き両親と、優秀な姉の後姿を見続け、自身も騎士の道を進んでいた。
彼女にとって騎士道を歩むことは、そのまま人生の意味だった。
騎士を辞めるということは、これまで信じて歩んできた道を外れることを意味する。
「私なりによく考えて出した結論だ。後悔はしていないよ」
「ジーナ……」
「タクロウ、私はみんなと一緒にいる道を選んだ。騎士としての人生も大切だが、それ以上に……タクロウたちと歩む未来を、私は見たいんだ」
「――!」
彼女は微笑む。
月明かりに照らされて、ほんのり頬を赤く染めて。
健気な笑顔だった。
抱きしめたくなるほどに。
「タ、タクロウ?」
「あ……つい勢いで」
抱きしめてしまっていた。
仕方ないだろ。
ジーナが愛おしすぎて、我慢できなかったんだから。
「俺はこの世界にきて日が浅いし、レベルもジーナに比べたら低くて頼りないけどさ。その選択が間違っていないって思えるように、俺もジーナを支えるよ」
「タクロウ……」
「今はこんなことしか言えない。格好悪いけどな」
「いいや、タクロウは格好いい男だ。世界で一番! だから私も、タクロウに惚れているんだよ」
「ジーナ……ありがとう」
この笑顔を守りたいと、心から思う。
今はまだ弱々しくて、頼り甲斐なんてないと思うけど。
なるべく早くレベルを上げて、ジーナにとって頼れる存在になろうと思った。
◇◇◇
翌日。
朝食を済ませた俺たちは、ジーナの案内で王都を出発した。
栄誉騎士ラランの行く先に心当たりがあるという。
俺たちは王都を出て東に進みながら、道中にラランについて話をする。
「ラランってどんな奴なんだ?」
「そうだな……一言で表現するのは難しいのだが、わかりやすい性格をしている」
「どんな性格だよ……」
「好きなことには夢中になるけど、嫌いなことからは逃げる。そんな感じだ」
まるで子供みたいな性格だな。
ジーナと同い年ってことはとっくに大人のラインは超えているはずだろ。
「やれやれだな」
「タクロウとそっくりですね」
「おい貴様、言葉には気をつけろよ」
「わ、脇はやめてください!」
俺のテクニシャンな手の動きを見てサラスが怯えた。
口の軽さはまったく治らないが、弱点をいじられる感覚はしっかり身体にしみ込んだらしい。
日々の成果をしみじみと感じながら、いつの間にか森の中に入っていた。
しかもかなり怪しい雰囲気の森だった。
俺は少し不安になり、ジーナに尋ねる。
「お、おい、本当にこの先にいるのか?」
「わからない。あくまで候補の一つだからな」
「候補ってなんだ? 街でもあるのか?」
カナタが俺の代わりにしたかった質問をしてくれた。
ジーナが答える。
「ラランは王都の周辺にいくつか隠れ家を持っているんだ。そのうちの一つが、この森の奥にある」
「へぇ! 隠れ家ってなんか格好いいな!」
「危ない研究とかしてそうすねぇ」
奇しくもサラスと同じことを連想した。
研究者の隠れ家で想像するのは、魔女の館かマッドサイエンティストのラボだろう。
果たしてどちらかな?
「いや、単に人が多い所が苦手なだけだぞ」
どっちでもないんかい!
「騎士になったばかりの頃は王都の中心部で暮らしていたんだが、年々外に離れていって、いつの間にか隠れ家を作っていた。隠れ家なら、一日誰とも話さなくていいから楽だと言っていたな」
「どんだけ人見知りなんだよ」
「タクロウとそっくりじゃないですか。引きこもり同士仲良くなれそうでよかったですね」
「俺は週に一回は外に出てたからな! 一緒にするなよ!」
「同族嫌悪でしたか……」
断じて一緒ではない。
俺はゲーム内のチャットで他人と交流してたからな。
会話だってあったぞ?
つまり俺のほうが社会に適応できているということだ!
「ここだ」
そう言って先頭を歩いていたジーナが立ち止まる。
隠れ家に到着したらしいが、俺の視界に映っているのは木々と地面だけだった。
今のところ家っぽい建造物は見つからない。
それは俺だけではなく、カナタがジーナに質問する。
「どこにあるんだ? あたしに見えないんだけど」
「近づけばわかる。ほら」
「――!」
一同は驚愕する。
ジーナが前に手を伸ばすと、手首から先が消えてしまった。
「だ、だだだ大丈夫ですか! 今すぐ治療しますから!」
「落ち着けサラス。これ結界か?」
「正解だ。ここには偽装の結界が施されていて、外からは何もないように見えるだけだ」
「な、なるほど、そういうことでしたか。驚かさないでくださいよ」
ホッと胸をなでおろすサラス。
俺もすぐには気づけなくて一瞬焦った。
守るための結界ではなく、惑わすための結界か。
ジーナが先陣をきる。
「私たちに危害はないから、普通に進めばいいぞ」
「おう」
「わかった! おー、見てタクロウ! 身体真っ二つ!」
「こらこら、遊んじゃダメだろ」
カナタは結界で遊んでいた。
子供みたいだけど、はしゃぐ姿はとても可愛い。
「見てくださいタクロウ! 顔だけ浮いてます」
「草」
「なんで私だけ塩対応なんですか!」
「やっかましいな! 誰だよさっきから家の外で騒いでる奴!」
「「「――!」」」