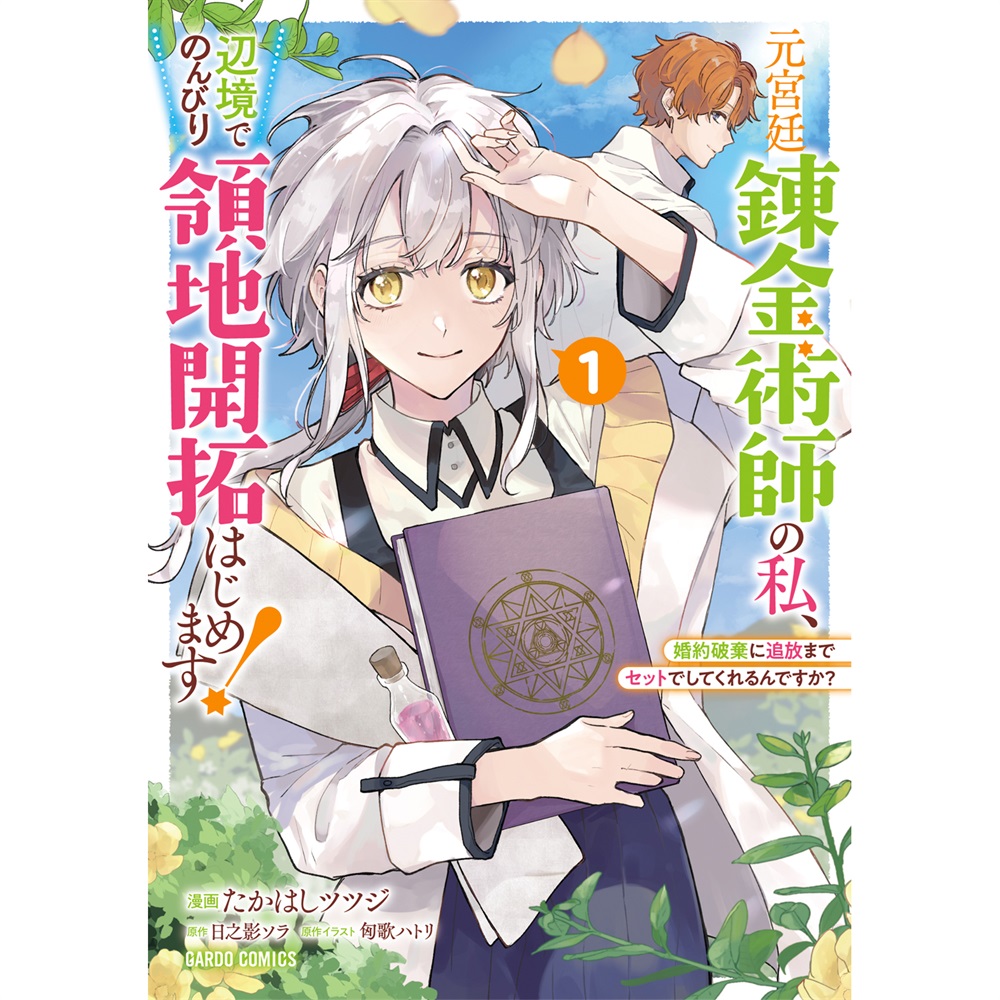寿退社を目指して①
タクロウたちが退出した後、アイギスは大きくため息をこぼす。
「はぁ……ジーナ……なぜあんな男と……」
彼女が感じているのは呆れと怒り、そして心配である。
しかし、怒りはジーナに対してではなかった。
アイギスが怒りを向ける対象はただ一人だけである。
「ヒビヤタクロウ……」
彼女は過去の経験から男を毛嫌いしている。
それはどうしようもないことであり、誰もが知れば同情するだろう。
ただし、だから男であるタクロウに怒りを向けている、というわけでもなかった。
彼女は怒っている。
ジーナと結婚したタクロウに対して。
心の底から腹が立ち、悔しさがあふれ出ていた。
騎士を辞めると宣言したジーナへの怒りや失望よりも、タクロウへの怒りのほうが遥かに勝っている。
それもそのはずである。
なぜなら彼女は――
「よくも私の可愛いジーナを! あのドブ男め!」
極度のシスコンである。
もう大好きだった。
狂おしいほどにジーナのことを溺愛していた。
アイギスの仕事机の下や引き出しの中には、ジーナの写真が大量に隠されている。
幼い頃のジーナから、成長したジーナの姿まで。
成長記録と呼ぶには不自然な量とアングルの写真を眺めながら、アイギスはうっとり顔になる。
騎士団はおろか、本人すらも知らない本当のアイギスの姿がここにある。
その素顔のだらしなさは、誰にも見せられない。
ジーナ本人にすらも……。
「はぁ、可愛いジーナ……自分の意見をちゃんと言えるようになったのね。成長したわね」
これまで一度も、自分に反抗したことのなかったジーナが、今回初めて意見を口にした。
威圧しても、否定しても、彼女は曲げることはなかった。
アイギスは高圧的な態度を取りつつ、内心では泣きたくなるほど喜んでいた。
彼女がジーナに厳しく接するのは、すべて彼女の勝利のため。
もしも時、誰かに頼るのではなく、自分自身の力で乗り越えられるように。
身体を鍛え、多くを学ばせ、彼女の未来が明るくなるように願った。
ダメな男に引っかからないように騎士団で隔離し、なるべく遠方の任務は受けさせないように配慮もしていた。
「やっぱり失敗だったわ。他の騎士に向かわせるべきだった」
タクロウたちの下にジーナを派遣したことを、彼女は死ぬほど後悔していた。
緊急の任務で手の空いている騎士がおらず、駆け出し冒険者が集まる街だと知っていたから、ジーナに経験を積ませるには最適だと考えたのだった。
事前の調査でアダムストが関与している可能性は低いと判断していたこともある。
しかし実際はアダムストと交戦し、あまつさえ男と結婚して戻ってきた。
アイギスはもう一度、盛大にため息をこぼす。
「はぁー……私は姉失格だ。だが、ジーナが幸せなら……」
それでもいいと思う心がある。
アイギスはこの世界の人間、故に嫌でも理解している。
男女の結婚が、本物の愛なくしては成立しないという現実を。
二人の指輪を見た時点で、彼女たちの思いが通じ合っていることは証明されていた。
それを否定することは、女神を否定することと同義であり、憚られる行為である。
もっとも、それはそれとして……。
「やはりゆるせん! あのゴミクソカス男ぉ!」
普通にタクロウのことは憎んでいた。
怒りを通り越して殺意すら感じ始めている。
退職前に任務を与えたのは、自身の心の整理と、彼という男を見極めるためでもあった。
誰も彼女の本心を知らない。
ただ一人の例外を除いて。
「ニーア」
「――呼んだ?」
アイギスの呼びかけに答えたのは、マフラーが特徴的な小柄な少女だった。
彼女はいつの間にかアイギスの背後に立っている。
アイギスは驚かず、淡々と事情を説明し、彼女に依頼する。
「ジーナのことを見張りなさい。任務への協力は基本的にしなくていいわ。どうしても必要な場合は、あなたの判断に任せる」
「了解した。報告は随時?」
「まとめて最後に聞くわ」
「わかった」
「頼むわよ、ニーア」
彼女は小さくこくりと頷き、アイギスの背後から気配が消える。
「はぁ……」
「一ついい?」
「わっ! ま、まだいたの? ビックリさせないで」
消えたはずのニーアが再び背後に現れて、気を抜いていたアイギスは少し驚いてしまった。
優れた騎士であるアイギスでさえ、彼女の気配を察知するのは至難の業である。
アイギスは呆れながら尋ねる。
「それで何かしら?」
「……いい加減、妹離れしたほうがいいと思う。ジーナも大人のなんだから」
「なっ、よ、余計なお世話よ!」
「束縛はジーナが可哀想」
「うるさいわね。あなたも似たようなものでしょ」
「アイギスほど変態じゃない」
「変た……ちょっとどういう! あ、待ちなさいニーナ! このタイミングで気配を消すのは卑怯よ」
姿と気配は消えて、行ってきますという言葉だけが響く。
二人は上司と部下であり、唯一の友人でもあった。
◇◇◇
アイギスとの話を終えて騎士団隊舎を出てすぐ、ジーナは俺たちに深々と頭を下げた。
「すまなかった、みんな。私の事情に巻き込んでしまって」
「謝んなって! あたしらは家族なんだ! 助けあうのが当たり前なんだよ」
「そうだぞ。むしろ最初から相談してほしかったな」
「カナタ、タクロウ……ああ、すまない。ありがとう」
「ちょっとー、私だけ仲間はずれで寂しいんですけどぉー」
「実際お前だけ他人だからな」
「ひどい! 私とタクロウは一心同体なんですよ! もはや家族以上の関係じゃないですか!」
その発言は誤解を生むからやめてもらいたい。
周りに誰もいなくて助かった。
「一先ず宿を探そうか。任務のこととか、聞きたいこともあるし」
「宿は必要ない。王都には私の屋敷がある」
「え? 屋敷?」
「ああ。今日はみんな私の屋敷で寝るといい。案内しよう」
と、言われて案内されたのは……。
「こ、ここがジーナの家なのか?」
それはそれ大きな屋敷だった。
貴族たちの豪邸が並ぶ区域に、他の屋敷に引けをとらない大きさと豪華さの屋敷がある。
まさに異世界の貴族が住んでいそうな……。
カナタとサラスも目をパッチリ開けて驚いていた。
俺は間違いなんじゃないかと思い、改めてジーナに聞く。
「ほ、本当にジーナの屋敷か? 見栄を張ったりしてないよな?」
「何を言う。家族に見えを張る理由があるか? 正真正銘、ここが私の屋敷だ。ああ、姉上のことなら心配しなくていいぞ。あの人は忙しくて、めったに帰ってこないから」
「いや、そういうことじゃなくてな」
「お帰りなさいませ、ジーナ様」
「――!」
入り口の前で時間をかけていると、屋敷から執事風の老人が顔を出し、ジーナの名前を呼んだ。
俺はビクッと反応して、身構える。
「ああ、出迎えありがとう、爺」
「爺!」
「ジーナ様、この方々はご友人でしょうか?」
「私の新しい家族だよ。結婚したのだ」
「なんと! それは大変めでたいことですね。心より祝福申し上げます」
「ありがとう、爺」
何なんだこの会話、この空気!
これじゃまるで、ジーナがいいところのお嬢様みたいじゃないか!
いや、そういうことなのか?
俺はごくりと息を飲み、ジーナに尋ねる。
「あの、ジーナさん、もしかして……貴族だったりする?」
「ん? 言っていなかったか? 私の名前はジーナ・アデラート。ここ王都を拠点とするアデラート公爵家の生まれだ」
「あ、聞いてないですね」
ガチの貴族じゃねーか。
公爵家って、確か貴族の位で一番上だろう?
つまり彼女はこの国で、王族に次ぐ権力者の令嬢だったというわけか。
ゲロ吐きそう。
そんな相手と結婚した俺って……。