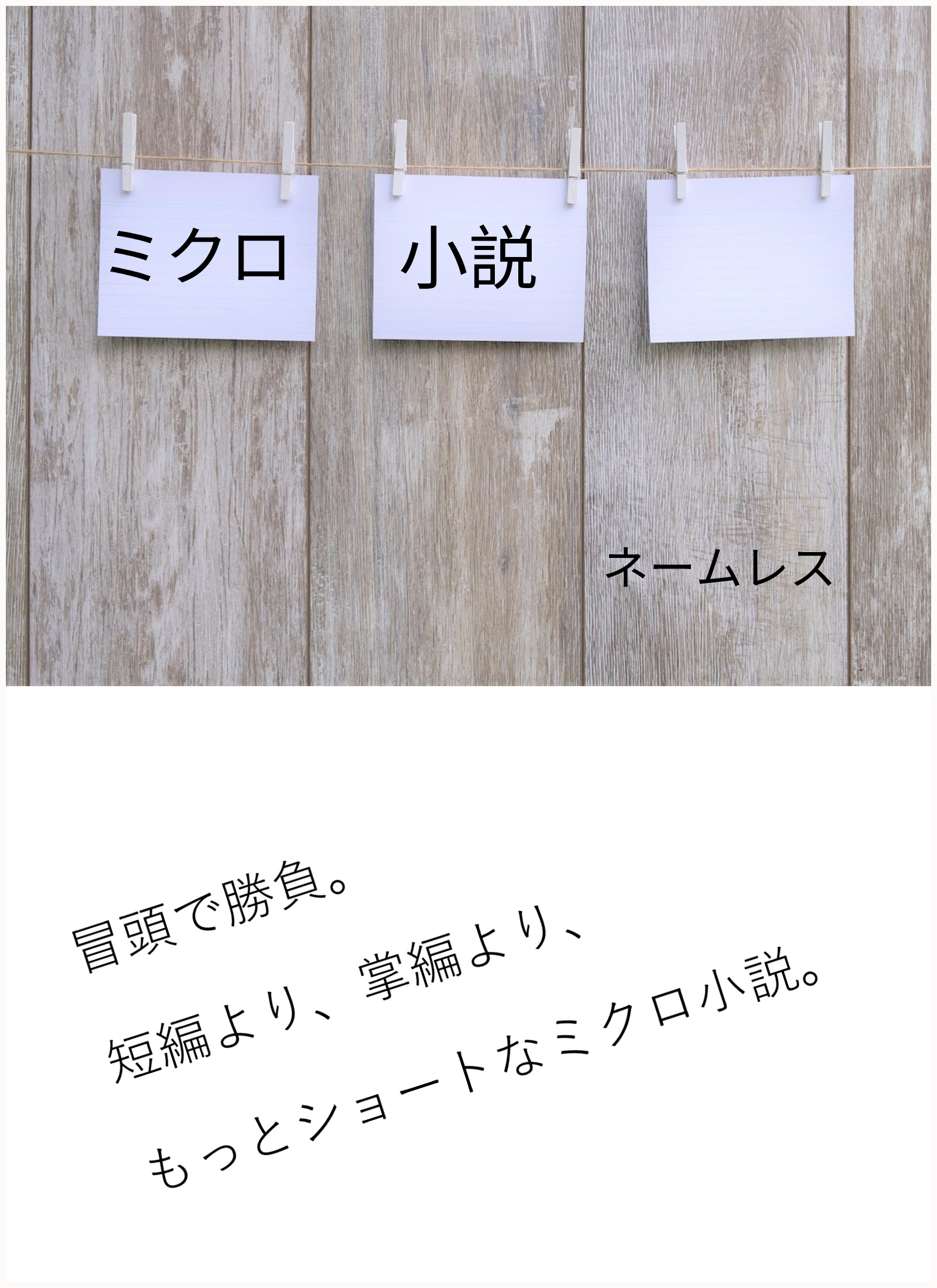第28話 決壊
おじいさんは山でかりをおばあさんは川下で洗いものをしていた。
おばあさんは本当に“くの字”に曲がった腰のまま竹籠をじゃぶじゃぶと振っている。
水流に逆らって竹籠の中を転がっているのはさくらんぼたちだ。
竹取の翁が作った籠を好んで使っているのは高品質だからにほかならない。
色つやの良い実も、まだ白んだ幼い実も傷のある実も玉石混交に竹籠の中を転がっている。
おばあさんは、さくらんぼを川に落とさないように手で壁を作り目利きをしつつシワシワの腕を一生懸命に振ってはこびりついた泥を落とす。
竹籠を水に浸した瞬間だけまるで煙幕のように茶色い水が立ちのぼる。
そうかと思うととたんに下流へと流れていく。
おばあさんは、手元のさくらんぼがきれいになっていくことに夢中で水嵩が徐々に増えてきたことに気づかないようだった。
「おや……」
おばあさんのところどころ綻んだ着物からでているふくらはぎはシワシワでモチモチしていて手足の皮膚は餅のように伸びる。
おばあさんはなにか違和感を覚えた。
もうすこしで膝が水に浸かってしまう?と不思議に思い、辺りをきょろきょろと見ました。
すでに川原の砂利は泥水に浸かっていた。
乾いた灰色の小石と濡れた黒い石とでくっきり境界線ができている。
おばあさんはなにごとかと思い“くの字”の中腰から――よっこらしょ。と掛け声を上げつつひょいと鈍角の“くの字”に姿勢を変えた。
三百六十度に首を振ると、まるで水攻めにあっているかのように水に取り囲まれていた。
――ありゃ。と驚いたおばあさんは竹籠もさくらんぼもそのままに目をしばたたかせた。
まるで机でもひっくり返すようにすべてを放って大急ぎで岸へと踵を返した。
そしてそのまま、針でも踏んだように大股のまま大きく足を振り上げた。
――ドーン。と乾いた一発の銃声が響く。
この独特な音は火縄銃の音だ。
おばあさんはすぐにおじいさんの銃だと気づきその場に立ち止まった。
いっそう危機感を募らせたおばあさんの耳元にけたたましい鳥の泣き声が聞こえてきた。
――キャキャキャ。となにかの奇声とそれをともなう硝煙の臭いが鼻腔をつく。
その臭いはどうやら山の上から流れてきたようだった。
同時に鬱蒼と茂った木々の隙間から数羽の鳥が羽をばたつかせて水平に低空飛行していった。
「そうかえ、おじいさんは野鳥を狙ってたんか」
おばあさんは、うす緑とうす茶色二種類のふわふわした羽毛が舞っているを見た。
よく映画で見かける羽毛枕を銃で撃ったように羽毛が散っていた。
一目散に逃げる鳥とは対照的に哀し気な羽根はひらひらと地をめざしている。
――ドーン。もう一発、銃声がとどろいた。
おばあさんはおじいさんがなにかの異変を知らせてくれたのだと思い膝まで浸かった足を上げて一生懸命に水をかき分けた。
ふたたびじゃばじゃばと飛沫を上げ一目散に小高い土手を目指す。
岸に居たんじゃ流されてしまう。そんな思いで無我夢中で走った。
たるんだ皮膚が水と風になびく、とちゅう何度も水圧に足をとられながらも水没していく岸の際まで辿りついた。
そこからいっきに加速して急勾配の土手を駆ける。
踏まれた青草が根元からザザっと倒れた。
おばさんは足裏のくしゃっという感触に心から安堵する。
これでもう、大丈夫だ。と。
左足が水圧を押しのけて最後の水飛沫を上げたとき、水位はすでに太腿あたりまであったようだった。
竹籠は流されてとうに行方はわからなくなっている。
川の中にぷかぷかと浮いているさくらんぼも、ゆっくりと四方八方に散っていって姿を消した。
息せききったおばあさんは四つん這いで土手の天辺まで這い上がりそこで倒れるように座った。
おばあさんは腰に当たった小石の痛みさえ感じないほどの放心状態に陥っていた
。
肩で息をしながらおじいさんのいる山をちらりと見上げたとたん――ゴゴゴゴ。と重く鈍い音が山伝いに聞こえてきた。
ズンズンと足元に衝撃を感じる。
地震かのう? そう思うのも無理はないほどに土手全体がガタガタと揺れていた。
土臭さに、それに草を擦り潰した青臭さと、川の生臭ささが混ざった臭いがあたりに漂っている。
ほどなくしておばあさんの眼下に見える濁流に一玉の桃がどんぶらこではなく岩と木々にグシャグシャ潰されて下っていった。
「ああ。桃が……」
あとを追うように無数の桃、そして柿やさくらんぼ、ほかの果実も流れていく。
黒い水と撹拌されてまるで芋洗い機にでも巻き込まれたように濁流に消えた。
おばあさんは唖然としながらそれをながめていた、いや、ながめるしかすべがなかったのだった。
とたんに別方向からも木々や土砂を含んだ土石流が流れてきた。
それはおばあさんの目の前をいく濁流と合流し勢いをさらに増した。
波打った川の水量は通常の五倍ほどには増えていてもうどこが川岸だったのかもわからなくなっていた。
おばあさんはしばらくその場から動けずにいたが、その光景を目に焼きつけ命からがら家のほうへと足を向ける。
おばあさんは落ち込んだ様子でトボトボと歩いた。
じいさんは無事なのだろうか?と気が気ではなかったが家に着くとおじいさんは優しくおばあさんを迎え入れた。
「じいさん。無事じゃったか?」
「ああ、大丈夫じゃ。すぐに逃げたからのう」
「そうかい。そうかい」
「ばあさんこそ。大丈夫じゃったか?」
「ああ。この通りじゃ」
おばあさんは訥々と、さっきの出来事をおじいさんに伝えた。
おじいさんはただ寡黙に聞き入った。
おばあさんはどれほどの恐怖を味わったのかを身振り手振りで饒舌に語った。
おじいさんは話に相槌を打ちながら、今日の獲物を足しただけの鍋をそっと差しだした。
「ばあさんや。冷えたろう」
とり肉とネギを煮込み塩で味付けしただけの質素な鍋だ。
「じいさんや。ありがとう」
おばあさんはたいそう喜んで口一杯に頬張った。
「おいしいのう」
強張った心がほぐれたのかおあばさんはニカっと笑顔を見せた。
口元のしわをニュルっと緩ませてまた汁をすすった。
「た~んと食えや、ばあさん」
「はいな」
「ばあさんや。また別の町にいくかのう?」
「そうしようかのう。おや、この肉やけに固いのぅ」
「そうかのう? ほれ、ばあさんや」
おじいさんは、使い古された小さな握りばさみをおばあさんに手渡した。
おばあさんは肉を食べやすいように、じょっきん、じょっきんと切っていく。
――――――――――――
――――――
―――