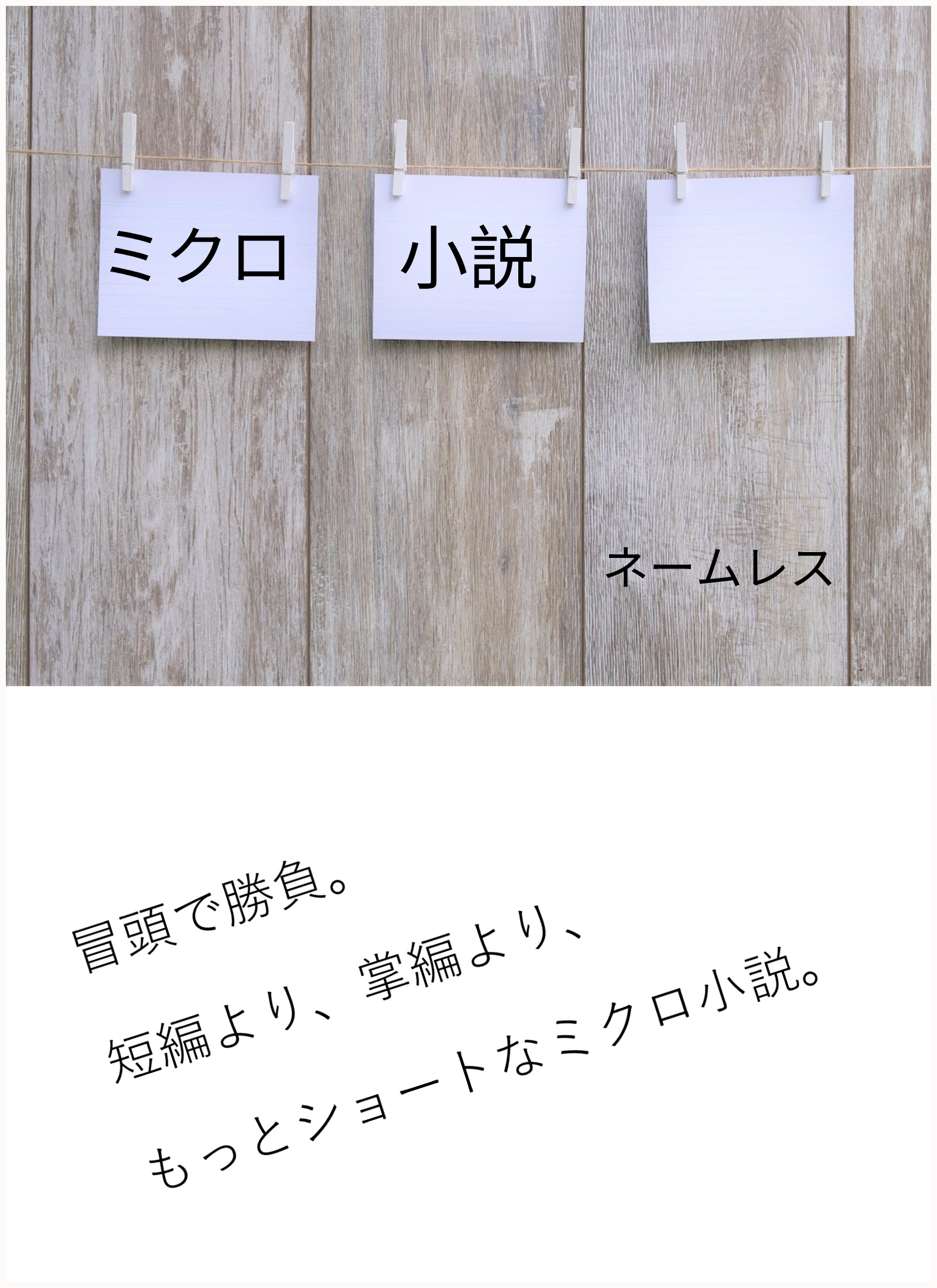第26話 仕組み
しばらくして鴎はやってきた。
そのあいだにもふたりの民がハズれを引いた。
また被害者が増えてしまった。
「鴎。あの奇術師が町の入り口にきてからの当落の記憶はありますか?」
「はい。私が見ていたかぎりの結果はすべて引きだせますよ」
僕は鴎の耳元であることを訊ねた。
それに鴎はすぐに答えてくれた。
「青鬼さんそれって?」
「そう。簡単なトリックですよ」
「じゃあ、あれはイカサマなんですか?」
「そうです。これ以上被害者を増やさないように僕が参加してきます」
※
「すみません。つぎ僕いいですか?」
僕は参加しようと声を上げた。
だだ、参加したい人は山のようにいる。
それもそうだろう、二分の一であのお宝がもらえるかもしれないのだから。
ここは民のみなさんにはすまないと思うけれど……そうるすしかない。
「あの、僕は参加料を倍払います。いいえ、三倍、いや十倍払います」
どうだのってくるか?
「おっ、色男の兄ちゃん。いいよ。いいよ。どうぞ参加してよー」
ほかの民からは白い目で見られている。
むかしも鬼属ということで、よく、そんな目で見られていたな。
ただ、ここにいる民にも僕の意図を汲んでくれている人だって存在する。
声をださずに――頑張って。といってくれてる人もいるし。
握り拳で応援してくれている人もいる。
それに応えないと、いや、ここにいるすべての民のために……。
「じゃあ決まりを説明しますね~?」
奇術師は見世物を披露する前にいつも同じことを話す。
「はい」
決まりは知っているけれど、その説明を一言一句逃さぬように聞く。
新しい発見があるかもしれない。
――で、最後の説明。
選んだほうに、お宝が入っていたらぜんぶお兄さんのものね。
「はい。わかりました」
よくいうな。
アタリなきからくり箱を前にして。
「では、どっちの箱にしますかー!?」
両手を大きく広げて観衆を扇動している。
これが見物人たちを自分の味方につける興行か。
「右の箱でお願いします」
「右の箱でいいのかな~?」
「はい」
「お兄さん。いまなら変えることもできますよ~。もっとよく考えて!」
「いいえ、右でけっこうです」
「そう。じゃあ右の箱。開きま~す!」
「お願いします」
奇術師は高揚しながらふたを開いた。
「ああっーと。残念~ハズれ~!」
想定内だ。
「そうですか。ハズれてしまいましたか。あの、ちなみにですけど左の箱の中を見せてもらってもよろしいですか?」
「ああ、いいともさ。では、さっそくお宝を確認どうぞ~。当たっていたらこれぜんぶお兄さんのものだったのにね~!? ああ、おしい!」
「僕が開きます」
奇術師の動きがピッっと止まった。
「えっと、いや、それは困りますよ?」
「どうしてですか?」
「いや、これはわたし主催の興行だから」
「なにか疚しいことでもあるのですか?」
「い、いやそんなことはないさ」
「では、僕に」
「いや、ちょ、ちょって待ってくれ」
「どうして」
「だから、さ」
奇術師の語尾が強まった、と、ともに額に血管が浮きあがった。
怒りの表情それだけ暴かれたくないってことですね。
そのからくりが白日の許に晒されたらあなたの信用はいっきに地に堕ちる。
……僕らの揉めごとに空気も悪くなってきた。
防人なのにこんなに騒がせてしまって申し訳ない、が、ここはすこし我慢してもらおう。
民たちの表情もどこか曇ってきている。
「こ、これは他人に触らせたくないんだよ。わたしの商売道具なんだから」
まだ、もったいつけている。
それもそうか。
でも、僕はもうその仕組みを見破っている。
――あっ、青鬼さんだ。
――防人も、こんなことするんだ。
――鴎ちゃんもいる。
僕たちのことを知ってる民も集まってきてしまった。
正体を黙っていてほしいという、お願いも、さすがにもう効果はない。
なにより誰かの口から”防人”という言葉がでてしまった。
この奇術師はここで逃がしたら、二度とこの町には近づかないだろう。
なんとしてもここでお縄にしないと。
奇術師の顔が見る見る蒼褪めていく。
彼に僕の正体がバレてしまったようだ、でも、それももう問題はない。
逃がさない。
「えっ、防人? ほら、ほら、どう? 箱の中」
奇術師はお宝の入った箱を必死で僕に見せてきた。
強引にこの場を成立させようとしている。
「こ、この見世物のどこに問題が?」
奇術師は横のハズれの箱に移動して挙動不審のまま僕に箱を傾けた。
そのあとは慌ててアタリの箱に手をかける。
「ほ、ほら、ちゃんとこっちにはお宝が入ってるし。どっちにもお宝が入ってないなんてイカサマはしてないでしょ?」
「たしかに、金銀財宝のお宝が入っていますね」
「で、でしょ。だ、だったらなんの問題が?」
「じゃあ、右。開いてください?」
「へ? だって、こ、こっちの箱だってもう開いてるでしょ。ハズれ。ほら、空っぽなの見たでしょ? お兄さん右を選んでハズれたんだから」
「それはどうでしょうか? 空っぽかどうかなんてそれはあなたのふたの開きかたしだいでどうにでもなるんですよ」
「えっ、な、なに、えっと、そ、それってどういう?」
僕は宝の入っていない葛籠の箱のふたを一度パタンと締めた。
また箱のふたに手をかけて、右側からふたを開く。
――あー!?
民たちの声がいっそう大きくなった。
それはそうだろうハズれだった箱の中にもお宝が入っているのだから。
「この箱のからくりはこうだ。あなたが箱のふたを【右側から左側】に開くと中に宝が入っている。反対に【左側から右側】にふた開くと中にはなにも入っていない。そう見えるからくり箱なんだ。見世物の終了後にいったん布で仕切ってお宝を入れ替えているように見せるのは大衆心理をよく突いている」
「……あっ……あの……」
返す言葉もなくなったか。
「つまりこの箱は両開きなんですよ。参加者が選んだ箱を【左側から右側】に開いてハズれの印象を付ける。そして答え合わせとして残った箱のほうを【右側から左側】に開いてアタリのお宝を披露する」
「えっ、いや……あの……あの、その」
奇術師は慌てふためき陽気だった口数も減っていった。
「両方の箱に宝が入っていればあとはあなたがどっちの方向からふたを開くかだけ。アタリもハズレもあなたしだい。それでは絶対に宝は当たらない。いや、当てられないという仕組み」
民たちが、さらにざわつきはじめた。
それは奇術師を糾弾する声になっていった。
――イカサマだったのか。
――見物料を返せー!
――早く、捕まえろー!
「これでも僕は防人なんです。賭博法違反でお縄です。鴎」
「はい」
「なっ、ちょっと、待ってくれよ」
「話は『仲裁奉行所』でうかがいます」
※