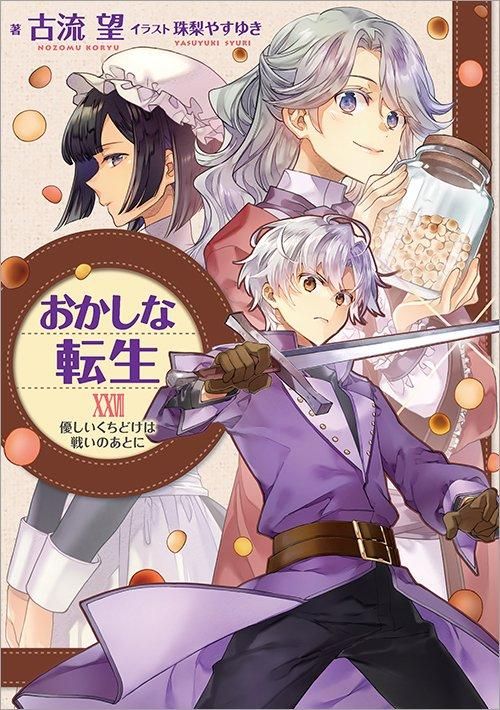377話 龍の守り人
「ははは、やってくれたな」
「陛下、笑い事ではありませんぞ」
執務室の中、カリソンは上機嫌に笑っていた。
笑っている理由は、勿論ペイスのこと。
他に類のない褒美を準備したというのに、それを全て断ってきた。そのことが愉快で笑っていたのだ。
そんな陽気な国王に対し、国務尚書であるジーベルト侯爵は渋い顔をしている。
こちらに至ってはまさに苦虫を嚙みつぶしたような顔のお手本になっていた。
ぐっと奥歯を噛みながら、怒りを堪える様な顔。
「畏れ多くも陛下がお与えになる名誉を、突き返すなど不敬が過ぎましょう」
怒っている理由はシンプルだ。
ペイスがカリソンから与えられる栄誉を全て断ったから。
自分であれば心から感激して受け取っていたであろう名誉と賞賛を、投げ捨てるように突き返した所業を、失礼だと感じたのだ。
「そうか?」
「そうでございましょう。いささか、増長しているのでは?」
「おいおい、増長してるならば貰えるものをさっさと貰って、お代わりでも要求している。謙虚で無欲な姿勢を褒めるべきだろう」
「そうは申しましても」
人間、何が腹の立つことかと言えば、自分の価値観を否定されることほど腹の立つことは無い。
自分が美味しいと食べている料理を、不味いと言われたとき。楽しく鑑賞していたアニメが駄作だと評されたとき。或いは、自分が惚れている異性が、どうしようもないクズのような相手に惚れてしまった時。
自身の肯定的な評価を、他人がクソミソに貶して来る時ほど腹の立つときは無い。
価値観の否定は、自分を丸ごと否定されるような強い嫌悪感を持つものなのだ。
翻って、ペイスのやったことはどうだろうか。
最高位ともいうべき栄えある勲章の授与や、貴族であれば誰でも誇らしいであろう王女殿下の後見人の地位。
他ならぬジーベルト侯爵も、もしも自分に与えられるとするなら随喜の涙を流して感動するに違いない。
そんな、素晴らしいものを、まるで価値が無いとばかりに即座に断ってきた。それも、満座の中で。きっぱりと。
ジーベルト侯爵が不愉快に感じるのは、ある意味では当然だろう。
自分が欲しくてたまらないものを、ぺいっと捨てる現場を見たに近しい。
欲しくて欲しくて、抽選にまで応募したのに外れたチケットを、たまたま貰ったけど要らないからと捨ててる人間を見たら、腹の一つも立つだろう。
「お前が怒るものでも無かろう。俺がやると言ったものを、あいつは要らんと言っただけだ。要らんものを要らんと言ってはならぬ法があるとは、知らなかったが?」
「む……」
カリソンの言葉に、ジーベルト侯爵は口ごもる。
確かに、ペイスとカリソンの間での話に対して、無関係である自分が怒るのもおかしい。理屈ではその通りだ。
しかし、感情の問題は理屈では無い。
カリソンは、理屈と情緒の間で葛藤する部下を、楽し気に扱う。
「それに、あれは無欲で断ったわけでも無い」
「と言いますと?」
ジーベルト侯爵は、カリソンの話の続きを促す。
「そもそも、今回与えようとしたのは、名誉だ」
「はい」
「多大な名誉を与える。これで少しでも王家に対して忠誠を篤くし、娘にも信頼できる後見人を用意してやれると思っていたのだがな」
「その名誉を断ったのですぞ」
「……恐らく、娘の後見人がただの栄誉だけではないと見抜いたんだろうよ」
「王族の後見は大変に名誉なことですが、それを断ってしまう理由ですか」
王女の後見人。
これは、王女の活動の全てを後見することで、王女に対して自分たちの都合の良い考え方を与えることも出来る。
故にこそ、今現在、他の大貴族たちがこぞってその地位を求めていた。
カリソンとしては、出来るだけその手の政治的カラーが薄く、権力欲の少ないものが欲しいと考えている。
その点、ペイスならば満点である。
権力欲の薄さは、間違いない。もしもその気があり、権力を握ろうと考えているならば、もっと幾らでも握れる権力がある。寄宿士官学校で動いても良い。王立研究所を荒らしてもいい。或いは中央軍を始めとする国軍に入ってもいい。フバーレク辺境伯やボンビーノ子爵家のような高位貴族に対して、親族である地位を振りかざすのも可能だろう。
どれにしたところで、あのペイスの才幹と人脈と魔法が有れば、今以上の地位や権力を得ることは容易である。
しかし、ペイスはそんなものに執着を見せたことは無い。
この権力欲の薄さは、王族に対して極めて強い影響を持つ地位に据えるにはもってこいだ。
また、政治的には新興貴族となるが、モルテールン家は割と中立的立ち位置に居る。
これは、カセロールが傭兵まがいな立場で出稼ぎしていたころの名残。
モルテールン子爵家自体は当代が初代という新興貴族であり、立ち位置は軍家でカドレチェク公爵派の地方領主だが、ペイスの嫁は当代フバーレク辺境伯の妹というのもバランス的には良い。近年になって、カセロールの妻であるアニエスの実家と関係を修復したりもしている。
中央の宮廷貴族でもありつつ地方の領主貴族でもあり、南部閥でありながら東部閥の嫁を持ち、新興貴族でありながら伝統貴族とも関係を修復しているモルテールン家。
政治的立ち位置の中立性というなら、パーフェクトに近しい。
王族の後見人には、相応しいと言える。
だが、実際にこういった中立的で権力欲の薄い人間が後見人になったならどうなるか。
後見される王族としては誰よりも信頼できる相談相手になるだろう。しかし、当の後見人は極めて多大な苦労も抱えることになる。
自分の立ち位置が偏っている人間ならば、例え外圧を加えられても、配慮する相手はごく一部で良い。自分の所属する立ち位置と近しい人間の意見だけ聞いていればいいのだ。敵対する相手の言うことなど、聞く必要はない。
ところが、中立的な人間だとそうはいかない。上と下、前と後ろ、左と右。色々な方向に気を配り、中立的な立ち位置で有り続けねばならない。
王族の後見人とは、ある意味で防火壁のようなもの。
正しい道に案内し、より良い人間へと成長できるよう導かねばならない。
気苦労は絶えないことだろう。
国王としては欲しい人材だし、栄誉であることは確か。しかし、その後に待ち受ける苦労は並大抵では無い。
勿論、苦労に見合うだけの褒美は与えるだろう。しかし、ペイスはそもそもそんな苦労を抱え込んでまで名誉を欲してはいないということだと、カリソンは考える。
「あいつは、そこまで俺の腹を読んだのだろうよ。その上で、断ってきた。なかなか出来ることでは無い」
国王としては、最大限の勧誘をした。しかし、ペイスは断った。
王女の後見人になることでガッツリと王家にまとわりつかれ、今回の晩餐会であったような“独特な知恵”を搾取されることを嫌がったのだろう。
「だが、俺にも面子というものが有るからな。何がしかのものは贈ってやろう。今度は拒否はさせん」
「そうなると、完全な名誉となるものがよろしいでしょうな」
贈り物を贈っておいて返品される。それそのものは、一般人は気にしない事項。
国王が与えたものを、突き返されたから問題になり、こうしてカリソンやジーベルト侯爵が悩んでいるのだ。
ペイスに対し、名誉を与える。これは確定だ。
昨今の政治情勢が、そうせざるを得ない状況を作ってしまっている。
ペイスが、龍を倒し、その資源を使って魔法技術に貢献し、更には王子と親しくして使節団でも立派に補佐を果たした。
傍から見れば、相当に王家に、そして神王国に貢献している個人。
これに何も与えない。本人が断っているとは言っても、第三者から見ればペイスの無欲とは見えない。何も知らない十代の少年を搾取している、と見えてしまう。
ケチな上司に、部下が喜んでついていくだろうか。
否、騎士にとっては忠誠は売り物。出来るだけ高値で買ってもらってこその忠誠だ。ケチな王の下では、忠誠心も低下するというもの。
命を懸けて戦うことも有るのだ。その結果がはした金ではあまりに理不尽。実際にケチられたわけでなくとも、そういう評判が広がってしまうのが不味いのだ。
ペイスは、一度公衆の面前で褒美を断った。
だが、それを推して尚も報酬を与える。それぐらいせねば、国王として資質を疑われる。
「そうだ、称号を贈ってやろう」
カリソンは、丁度いい褒賞があったと思い出した。
「称号、ですか?」
「うむ」
神王国には、国王の許可が無ければ名乗れない呼び名というものがある。
自分自身で“国王の寵臣”などと嘯いてみたり、我こそは“国軍の要”などと言い張って見たり。そういうことを誰にでも許せば、混乱のもとになる。
故に昔から、不文律として存在するのが称号。
例えばジーベルト侯爵であれば、国王も認めた「王の右腕」という称号がある。別にカリソンがそう呼ぶようにと与えたものではないが、そう名乗っていいと他ならぬカリソンが認めたのだ。
ペイスにも、同じようにふさわしい称号を与える。
これならば、ペイスにも実害はないし、都合の良い時だけ称号を使えばいいのだから利益にもなる。ある意味で王のお墨付きだ。使いどころは多い。
ならば、どんな称号を与えるか。
いっそ、実利の殆どない名誉職。それも、本人が喜ぶような称号が良い。
「では、どのような称号を?」
ジーベルト侯爵が問う。
しばらく考えていたカリソンは、これという一つに絞る。相応しいのが無いのなら、新しく作ればいいと。
「龍の守り人」
侯爵は、それは良いと笑顔を見せた。