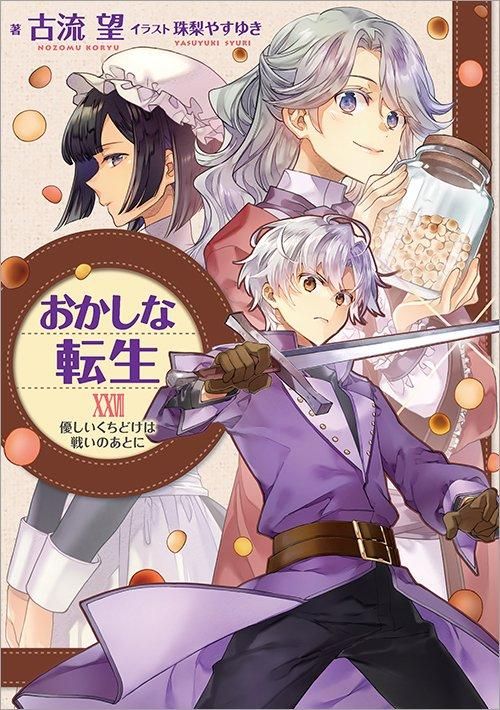363話 ご機嫌
モルテールン領ザースデン。
領主館の執務室で、調子はずれな鼻歌が流れる。
「ふんふん、るるるる~」
「坊、ご機嫌ですね」
「それはもう」
鼻歌の主は、目下機嫌よく執務をこなすペイス。
ご機嫌な理由はと言えば、先だってペイスに与えられた国王陛下の“お願い”である。
「陛下からの勅命ですから、遠慮なくお菓子が作れますよ」
「普段から遠慮なんてしてねえでしょうが」
「それはそれ、これはこれ」
ペイスは勅命と言い張っているが、勅命として必要な命令書が無いので、あくまで要請である。
しかし、ペイスにとってみればそんな些細な違いはどうでもいい。
大事なのは、お菓子を作る大義名分が有るかどうかだ。
お菓子作りの前には、些事諸々は無視してよいのである。
仮に隣国で紛争が起きようが、大貴族家でお家騒動が起きようが、或いは隕石が降ってこようが、今のペイスにとっては全て些事だ。お菓子作りこそ最優先である。
「しかし、ひと月も満たない時間で新しい菓子を作れ……ってのは王様も無茶を言うもんで」
陛下の要請は、出来るだけ速やかに、最長でもひと月以内に新しいお菓子を作って欲しいというもの。
「僕なら出来ると思ってのことでしょう。駄目なら断っていたでしょうし、陛下もその可能性を考えていたからこその密談です。何の問題も有りません」
「じゃあ、坊には新しい菓子にあてがあるんで?」
「そうでなければ、こんな話は断ってますよ」
ペイスは、自信をもってシイツの質問に頷く。
そもそも、ペイスはお菓子を作りたくて作りたくて作りたくて仕方がないのだ。諸々の制約や、時間が無いということで諦めてきたお菓子が山とある。
また、一度作ったスイーツとて研鑽の余地は多分にあるわけだし、何なら同じスイーツを何度作っても良い。お菓子作りは奥が深い。どれほどの時間と材料とアイデアがあろうと、足りるということはあり得ない。
そんなペイスにとってみれば、新しいスイーツを作れるかどうかなどは愚問というものだ。秒で新スイーツを提案出来る。
「何が良いか。迷いますね」
「迷うって何ですかい、迷うって。普通はどうしようかと悩むもんでしょうが」
「そうは言っても、作りたいお菓子はいっぱいありますからね」
「へえへえ、坊の頭の作りが俺ら常人とは違うってのは知ってましたぜ」
全く新しい、諸国の要人たちをあっと言わせるだけのスイーツ。
普通は、こんな話を受けてからじっくりと検討や試作を重ねるものである。
ペイスの頭が常人と違うことは今更だが、それでも都度驚かされる従士長。
「チョコレートを活かして新しいお菓子を作るのも良いです。王家の予算でたっぷり舶来品を買い付けられますし、優先的に船を確保できるかも。いや、モルテールン領のブランドイメージを高めるために、焼き菓子で行きますか? でもそれだと目新しさに欠ける。元々の目的が社交の華ですから、いっそ話題にしやすいものが良いでしょう」
「はあ」
勝手に自分の世界に入り始めたペイスの独り言を、シイツは適当に聞き流す。
「チョコレートにも色々ありますからね。そういえば、リコリスがチョコレートパフェを作ったんでしたよね」
「ええ。リコリス様主催のスイーツ品評会でね」
ペイスがヴォルトゥザラ王国に出張している間。リコリスがただ待つだけであったかと言えばそうではない。モルテールン家の嫁という立場から、社交を取り仕切ったりもしていた。
軽くティータイムに姉や義母を招く程度のことは普段からそれなりにしていたのだが、モルテールン家の看板を掲げての社交采配は初めてのこと。
色々と苦労があったとペイスも聞き及んでいる。
「羨ましい……チョコレートパフェなんて、作り甲斐があったでしょう」
社交の内容はスイーツの品評会であり、リコリスは以前にペイスが作ったフルーツパフェを発展させてチョコレートを用いたパフェを用意した。
ペイスにしてみれば、素直に羨ましい。
チョコレートパフェを作る大義名分など、出来ることなら自分が貰いたかったとも思う。
色々なスイーツを一気に盛り付けるパフェは作り甲斐も有るし、見栄えもする。
作る方はさぞや楽しかっただろうと、ペイスは勝手に頷く。
「リコリス様が何十日試行錯誤して作ったと思ってるんですかい。そう簡単に作れるものじゃねえでしょう」
「そうは言っても、羨ましいものは羨ましいです」
「そうですか」
リコリスは新しいパフェを考案するのに、寝る間も惜しんで頑張っていた。
それを思えば、のんきに羨ましがっているペイスはおかしい。
世の中、新しいお菓子を作らねばならない状況に追い込まれることを、羨ましいと思える人間などペイスぐらいである。
「いっそ新作スイーツの一つってことで王様にお披露目してみますか?」
折角ならば、リコリスの新作スイーツも賞賛されるべきではないか。
苦労して作ったというのならば、尚更それにふさわしい名誉を与えてあげたい。
「愚問でさあ。却下」
しかし、シイツは即座に首を横に振った。
「何故ですか!! きっと話題になりますよ?」
「リコリス様が寝込みますぜ? 身内だけで集まるのにも苦労してたってのに」
リコリスが社交を取り仕切るにあたって、つくづく自分はこういう表向きの目立つことが苦手なのだと言っていた。
元々双子で生まれ育ち、何かと社交的で活発な姉の陰に隠れていたリコリス。昔から、自分に注目が集まることは苦手なのだ。
姉ばかりを構って自分が蔑ろにされることであったり、自分を居ない者のように扱われたり、姉の代替品として見られたりといったことは、勿論嫌がる。しかし、それと目立つことは話が別だ。
まともな役柄を貰えない役者は辛いが、主役を張るのとは別問題である。
「むむむ」
「むむむじゃねえです。大体坊は、新作をって話なんでしょうが。チョコレートパフェは、既に大勢に披露されてしまってますぜ。フバーレク家の若奥さん、ボンビーノ家のジョゼお嬢、カドレチェク家の嫁さん。何なら、レーテシュ家の年増まで」
「錚々たる面々ですね」
「坊が苦手な連中で」
フバーレク家の若奥様と言えば、現フバーレク辺境伯の本妻である。
リコリスからすれば義理の姉であり、ペイスからみても義姉に当たる女性だ。
フバーレク家の令嬢であったリコリスは以前から面識があり親しんでいる人物だが、ペイスとはあまり付き合いが無い。
字面では姉という近しい関係なのに、実際は疎遠。会うと気まずい思いをするという意味で、苦手としている。
ボンビーノ家のジョゼと言えば、言わずもがな。
モルテールン家から嫁いだジョゼフィーネのことである。
モルテールン家の五女にして、ペイスにとっては末の姉。ペイスの小さい時からお姉ちゃん風を吹かせてくる相手だ。
他家に嫁いだにも関わらず、ペイスとの距離感はいささかも変化していない。つまり、遠慮を知らない。
苦手意識というなら昔からだし、今も変わっていない。
カドレチェク家のお嫁さんと言えば、リコリスの双子の姉。ペトラ=ミル=カドレチェクのことである。
旧姓ペトラ=ミル=フバーレク。
とにかく明るい上に積極性のある彼女は、リコリスの旦那であるペイスに対してはかなりフレンドリーに接してくる。
社交性の高さ自体は付き合う上で好ましいのだが、リコリスと一緒に居るときなどは、いささかタガが外れやすい。
一緒になって燥いでいると、大変に疲れる。
出来ることなら、もう少し距離を離してほしいという意味で、苦手な相手だ。
更に、レーテシュ家の女傑こと、ブリオシュ=サルグレット=ミル=レーテシュ女伯爵。
これはもう、ペイスにとっては鬼門と言える女性である。
貴族として強かな交渉をする上に、謀を巡らせることに熟達している智謀の将。ペイスをして、苦渋を舐めさせられた経験を持つ、油断できない相手である。
気楽にこんにちはと挨拶出来る相手では無く、顔を合わせるときは常に頭の隅に策謀を警戒していなければならない。女狐と綽名される、モルテールン家にとっての好敵手といえる。
この女性を苦手にしていない貴族男性など、彼女の旦那であるセルジャンぐらいなものだ。
誰にしたところで、一癖も二癖もある。
ペイスが苦手にしているという表現は正しい。
「違いありませんね。姉さま達やレーテシュ家のお姉さんは、仕事以外では出来るだけ会いたくない」
「おうおう、嫁いでいった連中に会いたくねえってか」
「語弊がある言い方ですね。既に嫁いだ姉さま達は、僕がどうしても遠慮してしまう相手です。頻繁に会い過ぎればそこだけ優遇になりそうで、他の姉さま方の不満を生みます。かといって、会いなさ過ぎては不仲を疑われる。嫁いだとは言え、大切な姉です。良い距離を保っておきたいというだけでしょう」
ものは言いようだが、適度な距離感を保ちたいという意見にはシイツも同意する。
「たまには、里帰りもしてもらいたいもんで」
「そうですね。しかし……チョコレートパフェが駄目となると、他のパフェも駄目でしょうね」
またも、ううんと唸り始めるペイス。
「パフェにそんなに種類があるんで?」
「それはもう。素材の数だけパフェがあるので、無限と言って良い。まあ、目新しさは減るでしょうが」
「俺ぁ、今、とても怖い思いがしてますぜ。頼みますから全部制覇しようとか言わねえで下せえ」
「はははは」
「笑ってねえで、約束して貰いたいもんで」
ペイスの笑いには、冗談半分の響きがあった。
だが、半分ぐらいは冗談で済まなそうな響きがあった。
ペイスとしては、時間と材料さえあるなら、パフェの研究もしてみたいと思っているのだから当然である。
パフェの道も奥が深い。巨大なジャンボパフェのような色物含め、極める為の道のりは果てしないだろう。
「会話にしやすいお菓子となると、イチゴ……もとい、一期一会を大事にしないといけません。他所で食べたことが有るお菓子だと、話題にするのも遠慮がでます。そうですね、やはり誰も食べたことが無い、今でしか食べられないスイーツが良い。そうだ、そうしましょう!!」
「はあ」
かれこれ五分は独演会を続けたあたりで、ペイスの思考も大分まとまったらしい。
新しいスイーツを思いついたと、ペイスは満足げだ。
「ということでシイツ、ちょっと出かけてきます。山の頂上まで」
「はあ……はぁ!?」
ペイスの言葉に、従士長は目を丸くするのだった。