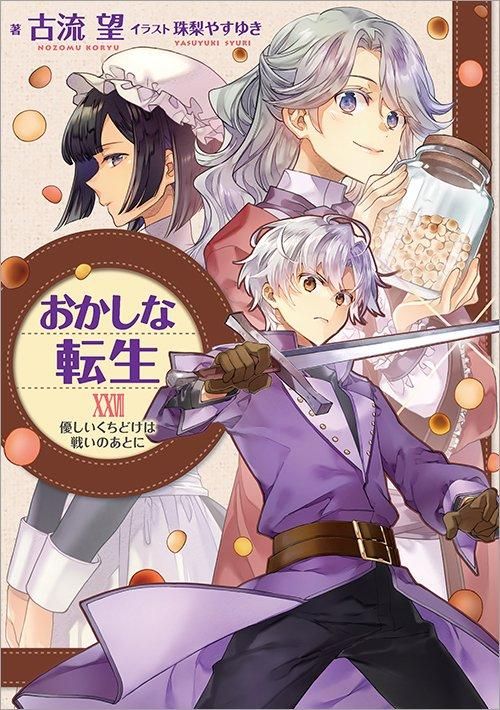362話 下命
国王カリソンは、ペイスの姿を見るなり言った。
「菓子を作れ」
答えるペイスは、秒もかからぬ即答である。
「分かりました、喜んで拝命いたします」
うん、とお互いに頷きあう主従。
何かしらのシンパシーを感じて居そうなやり取りであり、両者はそれで十分なのかもしれないが、他の人間にとっては説明不足を二乗したぐらいには訳が分からない。
「まてまてまて、ペイス、少し落ち着け」
ペイスの暴走を止めるのは、いつだって父親だ。
カセロールは、陛下の前であることも脇において息子を抑える。
はいどうはいどう。やっていることは暴れている馬を落ち着かせることと変わらない。
「落ち着いていますよ!! これ以上ないほど!!」
「どこがだ」
「父様はこの僕の落ち着きと冷静さが見えませんか? 今すぐにでも動き出せるほど冷静ですよ」
「見えん。分からん。知らん。陛下の御前でありながら動き出そうとする状態を、落ち着いているとは言わん。取りあえず深呼吸でもしろ!」
すぐにでも駆けだしそうな息子を、宥めるカセロール。
放っておけば、このまま何をやらかすか、知れたものではない。
それでなくとも、突拍子もないことをする息子なのだ。生まれた時から手塩にかけて育てて来たカセロールは、愛息子がお菓子に関してだけは遠慮も斟酌もせず、我慢と忍耐と、おまけに遠慮を放り投げることを知っている。過去の実績と信頼がある。
肉食獣を檻から、いや、大龍を檻から放つような真似は、断じてできないと、必死である。
「くくく、やはり面白い奴だな」
「はっ、お目汚し大変失礼いたしました」
そんな親子のやり取りを楽し気に眺める国王。
からからと笑う様は、心底面白そうである。
仕える王に対し、息子の素っ頓狂な行動を恥じるカセロール。
如何に王とカセロールの間に強い信頼関係があろうと、それで不敬を働いていい訳では無いのだ。
「構わん。ここに居るものはお前たち親子が少々突飛なことをしても動じる様な人間ではない」
「恐縮です」
王城にある一室。
王の信頼篤い貴族のみが入室を許される小さめの部屋に、国王を筆頭に十人弱。
幾人かは王の護衛たる近衛であるが、ペイス、カセロール、スクヮーレなどは呼ばれた側。特にスクヮーレとカセロールなどは、呼び出しを受けた当人の暴走を止める保護者兼ブレーキ役であろう。
国王側は、護衛を除けば記録係の書記官と、実務担当の国務尚書ジーベルト侯爵ぐらいが目ぼしい人間。
本当に、国王の側近と寵臣だけの、密会というやつだ。
ついでに言えば、今まで散々にペイスのやらかしてきた騒動に振り回されてきた面子であり、お菓子狂いの奇行には免疫のあるメンバーでもある。
「陛下も、お戯れはほどほどに」
「はははは。許せ、これも信頼あってこそだ」
「ははっ」
カセロールと国王は、二十年以上に渡って親しんできた仲。無論、主従というものは弁えているが、それを脇に置いたとしても培ってきた信頼は篤い。
少々のお遊びで揺らぐような関係性ではないので、国王としても遠慮なく茶目っ気を出せるというものだ。
ジーベルト侯爵が諫める声も、軽いものだった。
その場の雰囲気がどうしようもなく緩んだところで、改めて国王カリソンが咳払いと共に本題を話始める。
「それで、お前の息子に頼みたいことがあってな」
頼みたいこと、との言葉に、モルテールン子爵は神妙に頷く。
「陛下がお望みとあれば否やはございませんが……」
カセロールは、ちらりと息子を見やる。
お菓子を作れと言われたことは分かっているので、どんなお菓子を作れば良いのかとそわそわし始めた息子。傍から見ていると、やんちゃな小型犬がご飯を前にして待てと言われているようにも見える。どこか愛嬌が有るのだが、些細なきっかけで暴発しそうな危うさも同居している感じだ。
このまま放し飼いは出来ないと、カセロールは困惑すること頻りである。
「少し、説明するか。ジーベルト」
「はっ」
カリソンに呼ばれて、書きつけていた書類から顔を上げたのは、初老の貴族。
国務尚書を務め、国王の右腕ともいわれるジーベルト侯爵である。
大分、頭の方が寂し気になっていることを当人も気にしているのだが、こればかりは自然の摂理だろう。
デコの大きな国務尚書はずいと進み出て、説明を始めた。
「さすれば、先ほどの使節について」
「というと、ソラミ共和国の使者ですね」
今更確認するまでも無いが、念のための確認。
この場で先ほどの使節と言えば、ペイスとも面識のある女誑し以外ない。
「左様。殿下に同道したお二方は、小職よりも詳しいかと存ずるが、このソラミ共和国との国交は、今後重要なものになると考えられる」
「そうですね」
神王国の仮想敵国であるヴォルトゥザラ王国は、今でこそ大人しいが、いずれ神王国に牙をむくであろうことは明らか。
そうなった際、ヴォルトゥザラ王国を挟んで神王国の反対側に有るソラミ共和国が神王国と友好的であるのは外交的にも軍事的にも大きな意義を持つ。
それは、使節団と先んじて交流を持ったペイスやスクヮーレにとって既知の話。
「故に、先だっての使節においてヴォルトゥザラ王国との親善を成し遂げ、ソラミ共和国とも友好関係を構築する端緒を作ったことを、大々的にルニキス殿下の功績として諸外国に喧伝する必要がございます」
「誇れる外交的功績ですからね」
統治者として、優れた成果が得られたことを宣伝するのは、今後の政治をやり易くするためにも必要なことである。
誰だって、無能の部下としてこき使われるのは御免だ。自分の働いた結果が、より大きな成果に結びついていると実感できる方が働き甲斐もあるだろう。
優秀な人間と言うのは、それだけで一定の求心力を持つもの。戦いに勝利して大きな利益を得るのも優秀さであるが、それと同じぐらい舌戦に勝利して利益をもぎ取るのも優秀さ。王子が無事に外交を務めて来た。その上、今後重要になる新興国との交渉も纏めたというのであれば、優秀さをアピールするのに十分な成果と言えるだろう。
軍務的功績に劣らない、外務的功績だ。
これを利用しない手は無い。
「そこで、王子殿下の主催で、改めて成果披露を行う社交の場を開催したいというのが、王宮としての結論でございます」
「ふむふむ」
王宮として何かを宣伝しようとするなら、人を集めてその場で話をするのが一番いい。
知らしめたい相手をはっきり選べるし、広めたい内容もコントロールできるからだ。
広報宣伝の為にも、或いはプロパガンダの為にも、利用できるものは利用する。
「社交と言っても、何を目的とするのか。ここは意見の分かれるところ」
「そうですね」
人と人が交流するとなればどうするか。SNSなど存在しない社会なので、まずは集まって親交を深めるべきだ。
しかし、人間には得手不得手や好き嫌いがある。
ダンスの苦手な人間は舞踏会に参加するのは嫌がるだろうし、音楽の好きではない人間が音楽鑑賞会などに呼ばれれば、眠気を堪える方に必死になって社交どころではない。
何を目的として社交をするのか。
社交の名目は、集めるメンバーの満足度を高めもし、低めもする重要な要素である。
「軍務尚書は、使節を招いた上で狩猟会を開いてはという意見でしたし、我々としては王宮内で舞踏会を催してはどうかという提案をいたしました」
「なるほど」
軍人が、自分たちの良い所をより強くアピールするなら、狩猟を行うのが良い。動物を狩るという一連の流れは、軍事行動と相通じるものが多い。
また、内務系の人間であれば儀典を司る部署が活躍できる舞踏会を推すのも道理。
それぞれの派閥が、自分たちにとって少しでも有利になるように動くのは、相も変わらない宮廷政治の姿である。
ペイスなどは、別に全部やれば良いのではないかとも思ったが、下手に口を出すと藪から蛇を出してしまいそうだと聞き役に徹する。
「結局、陛下は晩餐会をお選びになられました」
「晩餐会ですか」
夜に食事を伴う交流会。
晩餐会と呼ぶそれは、王家の主催する社交会としては一番一般的だ。王道中の王道と言って良い。
美味しいものを食べるのが嫌いな人間などまず居ないし、仮に多少の失敗があったとしても、酒のせいだと言い訳もできる。
また、豪勢な食事というのは普段の自分たちの食事と比較するのも容易であり、もって王家の権威や財力を分かりやすくアピールできる。
その上、人を誘いやすい。狩猟に行こうと言われれば弓だ馬だと事前に準備も居るが、王家の振舞う食事を食べに行こうというだけなら、その日に誘っても問題ない。
参加者を増やしたいなら、一番良い選択と言えるだろう。
「うむ、俺はそれが最も外交的な成果を喧伝できると判断した」
「賢慮の上の英断かと存じます」
そして、外務閥としても晩餐会は望ましい。
大方、他の派閥に押されている外務閥が、ここぞとばかりに外交的な成果をアピールしたくて張りきったのだろう。
「そこで……どうせなら、諸外国の要人たちを驚かせたい」
「晩餐会で、でしょうか」
「そうだ」
食事の席で驚かせたい。
なるほど、とペイスは頷いた。
国王カリソンの言っていた冒頭の意味が、ようやく分かってきたと。
「ルニキスから聞いた。ペイストリー、お前はヴォルトゥザラ王国でも随分と“やらかした”そうだな」
「やらかしたなどとは。恐れながら臣は精一杯王子殿下の補佐を務めたまででございます」
「怒っているのではない。むしろ褒めているのだ。ヴォルトゥザラ王国の連中を驚かせ、恩を売りつけられたというのだから、良くやった。だが、ヴォルトゥザラ王国で出来たことを、俺の下では出来ないとは言わんだろ?」
他の人間にはやってあげたことを、仕えるべき主君に対してやらない、などということは言えまい。そんなもの、王に喧嘩を売っているようなものだ。
ペイスは即答で王の望む答えを返す。
「勿論でございます陛下」
「お前は菓子作りを好むと聞く。そして、今までも多くの菓子を作り出してきたと調べもついている。ならば、ルニキスの為に、その知恵と腕を揮ってもらいたい。国威の為だ。この際、常識の範囲内であれば制限なしで良い。求めるものは“外国の大使たちを唸らせる菓子”だ。出来るか?」
「陛下の勅命とあれば謹んで拝命致します!!」
ペイスは、足元が三センチほど浮き上がっている。
より正確には、浮き上がって見えるほど、明らかに浮かれている。
国家予算を使って、国王の勅命という錦の御旗を掲げ、最高の材料を使って好きなだけお菓子を作っていいと言われたのだ。
これを喜ばず、何を喜ぶのか。
「では、任せたぞ」
最敬礼で応えるペイスの顔には、満面の笑みが浮かんでいた。