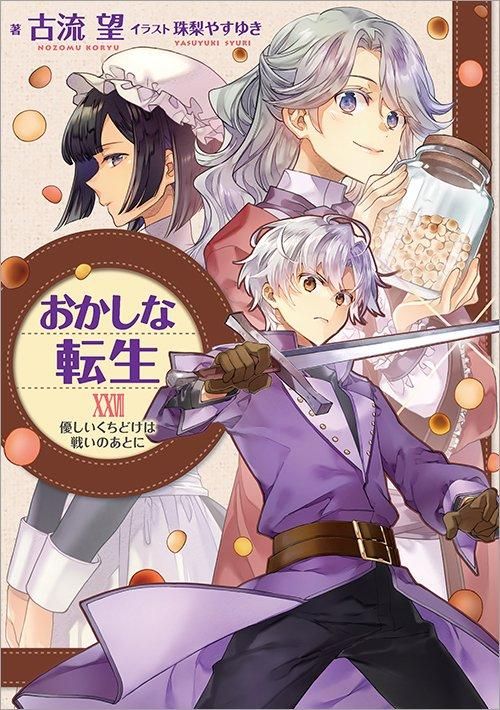330話 素材の泣き声
「総員、隊を整えよ!!」
スクヮーレの声が響いた。
先日国境を越え、いよいよヴォルトゥザラ王国の首都に入る。
それに合わせて、今一度隊列をきちんと組みなおす。
今回の使節派遣は、王子殿下が率いていることになる。
つまりは、使節団全員が神王国の看板を背負っていると言っていい。
諸外国の要人も多く集まる中、神王国の軍隊が“訓練不足”と見られる訳にはいかないのだ。舐められれば不要な諍いも増えるし、相手も外交交渉で強気に出てくる。どう考えても不利益が大きい。
故に、多くの人が見るであろう場所では、一分の隙も無い完璧な行軍を見せつけねばならないのだ。
ここで一糸乱れぬ動きを見せることで、神王国の騎士は侮りがたいという評価を獲得せねばならない。
国軍を預かる責任者として、スクヮーレの気合も漲ろうというもの。
「進め!!」
流石は精鋭と言われるだけのことはある。
スクヮーレも含め、或いはペイスも含め、全員が足並みを揃えて進む。
目指す先には、首都の正門が有る。
それを目指して進むこと約一時間。
ヴォルトゥザラ王国の首都は、門本体が重厚な青銅製であることを除けば、煉瓦で出来ている。
異国情緒満載の雰囲気ではあるが、更にその門の前にも異様なものが有った。
ヴォルトゥザラ王国の正規軍である。
すわ、戦いが始まるのか。
などと警戒する必要はない。仮にも大国の使節団が来るのだ。正門前に兵を並べた上で、使節を迎え入れるセレモニーである。
「全体、止まれ!!」
最後の号令は、ルニキス王子のものだった。
「そこに見ゆるは、神王国の使節団とお見受けする。疾く名乗られよ」
神王国王子を迎えたのは、ヴォルトゥザラ王国の王子である。
日に焼けた茶褐色の肌に、馬上にある精悍な姿。
背はやや低め。剣を履いているが、鞘の形状から見ても神王国の騎士剣とは明らかに違う曲剣だ。
事前に先ぶれも派遣されており、神王国使節団であることは明らかなのだが、それでも憶測で判断してはいけない。
名乗り合うまでが儀礼である。
「ルニキス=オーラングッフェ=ハズブノワ=ミル=プラウリッヒである。貴国の第六王子生誕の報せを受け、国王陛下より祝賀の言葉を預かって参った。其は誰ぞ!!」
対する神王国側も、誰何に名乗りを上げたからには正式な使節であることが確定する。
南大陸で共通する礼儀作法として、馬上のまま挨拶をして良いのは、目上か同格だけだ。
そもそも戦場であれば、馬上の挨拶は宣戦布告と相場が決まっている。
偉い人間、例えば軍の指揮官などに危害を加えようとしたらば、馬から降りたところを狙うのが楽だ。
人間の急所というのは頭、喉、胸など、総じて上半身に固まっているもの。足を切られるより、喉を切られる方が致命的である。
故にこそ防具を着込むし、急所は出来るだけ守りを固め、そして手の届きにくい所にある方が良い。
馬の上に居る人間は、下馬している人間から見れば急所が相当に上の方にあるわけで、馬の上に居る方が安全だ。
また、逃げるにしても馬の上に居たままの方が、すぐにも逃げられる。
“馬を下りる”というのは、危険が増える行為であり、基本的に立場の弱い者の方が行うもの。
特に、乗馬文化が盛んな神王国では、馬から降ろされるというのは恥ともとられるのだ。
門前に居る集団の、リーダーと思われる人間が馬上から誰何してきた。そう、馬上からだ。
ならば、神王国王子としては相手が格下の時は侮辱されたことになる。
お前は誰だ、とキツ目に返答するのも、王子としての体面があるから。
「ガハラ=ロズモ=マフムードである。王の名代として、貴殿らを歓迎しよう」
マフムードの家名を名乗ったことで、目の前の日焼け青年が王族であると判明した。
ルニキス王子を含め、神王国使節団の緊張が、若干和らぐ。
大国の王族同士であれば、馬上と馬上で挨拶を交わすのも失礼にはならない。
更に言えば、使節団はガハラ=ロズモ=マフムードの名に覚えがあった。この国の、第一王子である。
神王国第一王子とヴォルトゥザラ王国第一王子。
国の格の違いを言うならば神王国の方が若干上かも知れないが、同格というに問題はない。
「歓迎痛み入る、ガハラ王子」
「うむ、早速だが、ルニキス王子の歓迎の準備が出来ている。このまま城まで我が案内しよう」
王子同士の合意が有るならば、その意を汲むのが良く出来た臣下というもの。
早速とばかりに護衛のスクヮーレ達は隊列を組みなおし、先方の案内に従うような陣形を組む。勿論、ペイスも補佐役としてチョコチョコと動く。
たっぷりと、二時間ほどかけて街中を行進し、城まで案内される神王国一行。
その足で、ヴォルトゥザラ王国国王へ挨拶を交わす。
少なくとも、表向きの使節としての役目は、それだけで終わりである。
あとは、使節団としての外交になる。
夜。
ヴォルトゥザラ王国での歓迎は盛大に行われた。
「ルニキス、紹介しよう。此れなるはロズモ公。我が祖父でもある」
ガハラ王子は、歓迎パーティーでルニキス王子の饗応を担当するらしく、付きっ切りであれこれと話をしていた。
その途中で、王子に声を掛けてきた老人を、紹介する。
「お初にお目にかかりますルニキス殿下。エルシャド=シャハム=ロズモと申します。我が国にお越しいただきましたこと、心より歓迎いたします」
「神王国第一王子ルニキスである。歓迎痛み入る」
言葉少なく応えるルニキス。
ガハラの祖父として紹介されたのは、ヴォルトゥザラ王国でも屈指の大貴族であるロズモ公家の当主。神王国でいえば公爵家の当主にあたる。
要注意人物の一人として事前に情報を得ていたルニキスは、警戒を強める。
当然、護衛として傍に居た面々にもその緊張は伝わった。
「神王国の王子殿下がわざわざお越しとは、我が国としては喜ばしいことでありましょう。どうですかな、この国の感想は」
「実によい国であると感じている」
お互いにニコニコとしているが、会話の内容はかなり物騒である。
そもそも、公爵家の当主が“我が国”と、国家を代表するような口ぶりで物を話しているのが危ない感じだ。
少なくとも神王国で、スクヮーレ辺りが「我が国」などと言えば、国を自分のものだと思っているのかと敵対派閥から揚げ足を取られるだろう。身内同士の間や、百歩譲って自国の親しい貴族同士ならばまだしも、隣国の王族に対して使う言葉づかいではない。
故に、返答も無難に終始するし、言葉数は少ない。
「良い国ですか。そう言ってもらえるなら嬉しいが……我が若かりし頃、そう、もう三十年ほど前になりますか、実はとある戦いに出向いた折、同じ言葉を聞いたことがありましてな」
「ほう」
「我が国には、良い所が三つある、と」
「三つと?」
話の流れが読めないながら、引き込まれる感じが有るのは流石の話術なのだろう。
ルニキスとしても、聞いて損の無い話であれば、情報を得るのも使節のうちと割り切る。
「一つは、兵士。我が国の兵士は鍛えに鍛えた戦士ばかり。数だけ揃えたようなにわか仕込みとは違います。一族の男たちが、誇りを持って戦いに臨むのが我らの戦い方。如何ですかな?」
「確かに、ヴォルトゥザラ王国の兵は屈強であると聞く」
「そうでしょう、そうでしょう」
ヴォルトゥザラ王国は、南大陸でも覇を競う大国。
その原動力が何であったかといえば、兵士の質の高さだろう。
この国は、神王国とは違って騎士階級が存在しない。貴族と兵士と平民と隷属民で成り立つ社会である。
複数の有力で強力な貴族たちがそれぞれに力を持ち、最も有力な一族が王として諸家を纏めているのだ。
切磋琢磨を続けてきたヴォルトゥザラ王国の兵士は、平民を徴兵した神王国の一般兵や、信徒を動員する聖国の神兵とは練度が違う。
勿論、神王国人のルニキスとしては反論もある。兵士が幾ら強かろうと、統制の取れた神王国の“現代的軍隊”の相手ではない、という反論だ。騎士を中心にしっかりと統制の取れた神王国軍は、一兵一兵の質は低かろうと負けはしない。まして、騎士と兵士が戦ったなら騎士が勝つ、という確信がある。
故に、ここは愛想笑いと社交辞令の塊で乗り切った。
「もう一つは、女。我が国の女は諸国も羨む美女揃いですからな。我が娘もそれはそれは美しく、王妃となってからもその美貌を称えられております」
「なるほど、素晴らしいな」
現代人が聞いたのなら眉を顰めかねない言葉ではあるが、公は本気で自慢している。
ヴォルトゥザラ王国は交易が国家財政に占める割合の大きい交易国家としての側面を持つ。故に、色々な土地の色々な民族が混在し、そして血が混じりあっている。
多くの民族が混じった土地柄であれば、多種多様な風貌の人々が居る訳で、必然的により多くの“女性の好み”に適合する女性が見つかりやすいということになる。
美女が多いというのは、あながち間違いではない。一種類の美人が大勢いるわけでは無く、色々な美しさを持った女性がそれぞれに魅力を放っているということ。
それはそれで羨ましい話だと、ルニキスは相槌を打つ。
「そして最後の一つは、食です」
「食? 食事のことか?」
「左様。この国には多くの国から多様な食材が集まるのです。世界中の食が集まっていると言っても過言ではない。美食を好むものであれば、我が国に住むことは至上の幸せと言えましょう」
はははは、と公は笑った。
南大陸の交易に大きく影響力を持つヴォルトゥザラ王国は、食材も豊富。それは公の言う通りの事実だ。
食材が豊富であれば、食文化が豊かになることも道理。
なるほどと、王子は頷く。
「今日の会場にも、我が国が最高の食を揃えております。我が国で最高ということは、即ち世界でも最高。是非ともルニキス殿下にはご堪能いただきたいですな」
さあ、ご一緒に、と笑顔で手を広げた公。
どうやら、一緒に食事を摂る為の長い長い前振り口上であったらしい。
食事が山と積まれている一角に、極々自然に誘導されていくルニキスだったが、そこで一人の銀髪を見つける。
「この程度のお菓子では、素材が泣きますね」
ペイスの呟きは、とても小さなものだった。