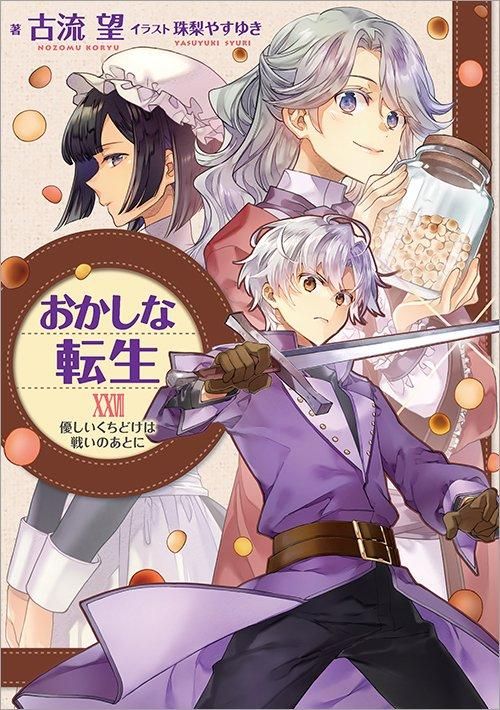305話 ペイスの気付き
ホーウッド=ミル=ソキホロは、研究者である。
世の中に未知というものは限りなく存在するが、無限の無知から零れる一欠けらの真理を求めて、生涯を費やす業の深い人間。それが研究者だ。
今日も今日とて、研究者は余人には理解し難い作業に没頭する。
「所長、今日も徹夜ですか」
「いや、先ほど仮眠を取ったところだ。実験の数字が揃ったので、一通りまとめて検証しようと上がってきたところだ」
ソキホロ所長の勤める研究室は、モルテールン領立の研究所。モルテールン家が全額出資して建てられた研究所であり、ここでは日々様々な研究が行われている。
とりわけ重要な研究として行われているのが、モルテールン領の主力輸出品であるお酒の研究。より良い味の酒を造る為、そしてより効率的に作る為、酒造りの職人も含めたかなりの規模で日夜研究を行っている。
という建前になっている。
勿論、酒造りの研究も研究所の目的の一つではあるが、もっと重要なことは魔法の研究。
モルテールン家で作られた“魔法の飴”や“龍の素材”についての研究が、秘密裡に行われている。
これらの研究は、勿論公に出来るものではない。従って、研究所の建屋がある場所の地下に、隠すようにして研究施設が存在するのだ。
ソキホロ所長は、勿論地下にも出入り自由である。
しかし、地下に籠ってばかりでは誰にだって怪しまれるし、健康に悪い。そこで、どうしても隠さねばならないこと以外は地上にある建物の方で作業するようにしているのだ。
中年の熟練研究員は、紙に書かれた数字を見つつ、部下が用意してくれたお茶を飲む。
字は走り書きの様に汚いながら、間違いようの無いほど整理された数字の数々。普通の人間であれば意味が分からないだろうし、それでなくても暗号めいた身内の符丁で書かれたデータを、ソキホロ所長は見つめる。
「ふむ、ふむ、見たまえハーボンチ卿」
所長が声を掛けたのは、若手の研究員。貴族号を持つ歴とした貴族であり、その点ではソキホロ所長と同じ。王立研究所での研究員の座を蹴ってまでモルテールン領立研究所に雇われた変わり者である。
「す、す、凄いですね。や、やはり魔力の貯蓄量は形状に関係があるようです」
吃音症気味の若者は、結果を見て驚く。
「うむ、例の飴の件で前々から分かっていたことだが、龍金でもそれを裏付けられたのは大きい」
「しかし、加工が……き、金属を完全な球形に磨き上げるのは、相当な職人芸ですよ?」
目下の研究は、魔法金属として世に出た龍金の効果的な利用法を模索すること。
最近では、メッキや箔として龍金を用いることで、少量の龍金でも広い範囲を覆う利用法を検討中だ。これが為せれば、モルテールン領の領主館を丸ごと龍金で覆ってしまうようなことも可能。さすれば、物理的な対策と合わせて魔法対策に大きく貢献する。実現すればモルテールン家の利益になるとあって、支援体制も万全である。
勿論、一足飛びにすぐに研究成果が出るものでも無い。段階的に模索していく中、まずは龍金の特性を保ったまま、どこまでの加工に堪えうるかを調査中だ。
飴であれば糸状に細く加工しても大丈夫だったのだから、金属の加工も可能だろうという目算である。
「鍛冶職人を雇えばよいだろう。幸いにして研究費は余裕がある」
モルテールン家の潤沢な資金は、潤沢な研究予算をうむ。
かつてソキホロ卿が王立研究所に居たころであれば、三つや四つは研究室を丸抱え出来るような予算を与えられて研究を行っているのだ。
やろうと思えば、金に物を言わせて好きなだけ自由に出来る。しかし、そうは言っても制約はあるのだ。
「か、鍛冶職人の手配は出来ると思いますが、龍金を触らせるのなら領主様の許可がい、要ると思いますよ」
「ああ、そうだな。確かにその通りだ。こっそり連れてくるわけにもいかないだろうしね」
「それよりも、地下の機密エリアに金属を加工できるし施設を作って、じ、自分たちで色々と試せるようにしてはどうでしょう」
「ふむ、なるほど。良いね。それでいこう」
龍金はモルテールン家の財産であり、ソキホロが幾ら研究所長という地位にあるとて勝手に人に譲ることは禁止されている。つまり、どうあっても管理は必要になるということ。
外部の職人にブツを渡して、逐一指示を出して管理監督する手間を掛けるぐらいなら、軽い実験の為の金属加工程度は自分たちで出来るように、整備してしまえばよくないだろうか。部下の提案には聴くべきものが有った。
何とも贅沢な思い付きであるが、それが出来てしまうのがモルテールン領立研究所の強みでもある。
「発注書は、君に任せて良いかな」
「それは構いませんが、サ、サインは所長のが要りますからね。それに、今いる部屋ならともかく地下を弄るなら別途報告も……」
上司と部下として、いつも通りの風景。
そこに、乱入者がやって来る。
「失礼、ソキホロ卿は居られますか?」
「ああ、ここにいるよ」
「伝令が来たそうです。通しても良いでしょうか」
「面通しは大丈夫?」
「はい。自分の知り合いです」
「なら、通してくれ」
警備の人間に案内されてきたのは、武装を固めた若い兵士だ。
ソキホロたちのところの手前まで案内されて、敬礼をする。
「ソキホロ卿はどなたでしょうか?」
昨今の情勢を鑑みて、モルテールン領はザースデンを中心として防備を厚くしている。兵士の数も増やし、巡回も頻繁に行うようになっているため、治安がすこぶる良くなった。
研究所にやって来たのも、そんな兵士なのだろう。ソキホロの顔を知らないという点で、普段からザースデンに居た人間でないことは明らかだ。
「私がそうだが、何か用事かな」
「はっ、ペイストリー様から伝言を預かってきました」
「ペイストリー=モルテールン卿からの伝言? 聞こう」
「はい、『手が空き次第、館の執務室に来て欲しい。手が離せないようなら、デジデリオにその旨を持たせてこちらにやって欲しい』とのことです」
「うむ、了解した。これからすぐ向かうと伝えてくれ」
「はい」
どうやら、主君筋からの業務連絡であったらしい。
幸いにして、丁度実験が一区切りついたばかりのタイミングだったのだ。実に間の良いことであると、早速とばかりに領主館に向かうソキホロ卿。
来客の多い領主館に出向いたところで、さほど待つことも無く執務室に通される。待ち時間の短さは、来客の重要性と用件の緊急性の掛け算の結果だ。ソキホロが極めて短い時間で通された時点で、何をか況や。
「お呼びと伺いましたが」
執務室の中には、ペイストリー=モルテールン領主代行や従士長シイツが居た。珍しい所では見慣れない若衆もいたが、領内の最重要人物達と親しげな様子や、どこか顔形に見覚えがある気もすることから、モルテールン家従士の身内なのだろうと察しが付く。
「ソキホロ所長、ご足労をお掛けしました。どうぞ座ってください」
ペイスは中年男を両手を大きく広げて歓迎した後、早速とばかりにソファを勧めた。
断る理由も無いので、それではとばかりにソキホロは腰かける。何とも心地よい弾力が、研究で疲れた体を覆う。
「所長、調子はいかがですか?」
「最近はようやく落ち着いて、研究を進められるようになりました。いやあ、徹夜は何度も経験しておりましたが、目の回る忙しさというのは初めてですな」
「そうですか。体調には気を付けて欲しいですが、無理はなさらないように。貴方のような人材を損なってでも進めねばならない研究など、うちには有りませんから」
「恐縮です」
研究というものは、時間を掛ければ成果が出るというものではない。
しかし、成果を出す為には時間が必要であることも事実。
最近の領立研究所は、幾人かの若手研究者を採用しつつも研究の幅を広げていた。全てを統括しつつも、自分の興味の赴くままに実験や調査に明け暮れるソキホロ。正直、身体がもう一つ欲しいと思うほど忙しい。ただ忙しいのではなく、やりたいことが多すぎるという多忙さだ。研究者としては充実していると言えるだろう。
多少の雑談を交わしつつ、場を温めるソキホロとペイス達。ある程度ほぐれた雰囲気になったところで、切り出したのは中年男の方だった。
「それで、呼ばれた理由は何でしょう」
お互い、暇な身ではない。そろそろ本題に入っても良かろうと、居住まいを正すソキホロ。
ペイスも真剣な顔になって声を小さめにする。
「少し、確認したいことがありまして」
「確認したいこと?」
「農業の研究部署について。王立研究所では、幾つかありましたよね?」
問われて思い出そうとするが、つい最近まで働いていた職場のことである。さほどの苦労もなく問われた内容については思い出せた。
「ええ。魔法系の農学研究チームや、土木系の土壌改良班などもありました。メインは農学研究室や有用植物の研究室ですが」
「そこで、果物の類を研究しているところはありましたか?」
「……果物、と言っても幅が広いですが」
果物というのは、基本的に食用である。勿論食べられない果物というものも存在するが、多くは食べるために果実を育てるもの。食料資源の安定的な確保というのは為政者にとって非常に重要な政策課題であり、この観点から研究を進める研究室は有るはずだ。
或いは、食べられない果実であっても有意な使い道を模索しているところもある。柑橘系の果物の匂いが、一部の害虫や害獣が忌避する匂いであるなども知られていて、食べること以外に使い道を探るというのも研究所として意義は大きい。
また、有効な使い方を研究するという意味では薬として使うところも有るだろう。先ごろ、航海病の治療に対して果物が効果的であるという報告と、その裏付けとなる研究成果が発表されている。研究の発端はペイスらしいと聞き及ぶものの、薬として有効なことは変わらない。
更に、植物の植生や分布を調査するフィールドワークなどもある。特定の果実がどの程度の範囲に生えているかを実地で調査することで、例えば害獣の行動などを推測し、農作物の食害等々を事前に防ぐ試みというのも長らく続けられていた。
一口に果物に関する研究と言っても、該当する範囲はとても広い。
「ベリー。それも、品種改良をしているような研究室です」
べりー、べりー、と口の中で何度か呟きながら、視線を空中で固定するソキホロ所長。ややあって、考えがまとまる。
「ありました。食用植物研究室と薬用植物研究室が互いに競い合っていたと記憶しています」
「食植研と薬植研ですか。農学系と薬学系ですね……」
じっと考え込むペイス。
「一体、どうしたんです?」
ペイスの沈思黙考に対して、不安になるのは情報提供した側である。何か拙いことでも言ってしまったのかと、動揺してしまう。
「研究成果の横流しが行われているかもしれません」
ソキホロの動揺は、更に強くなるのだった。