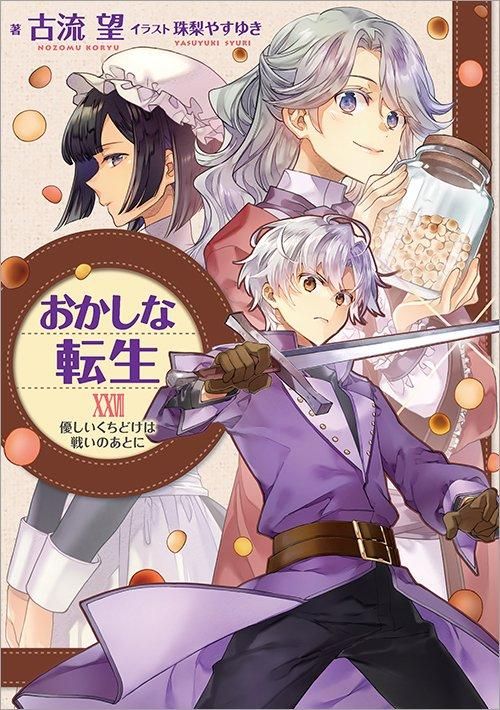273話 根回し
王都の中心部にある王城では、毎日の政務が粛々と行われている。
農務や工務、或いは商務や法務の日常業務から、突然飛び込んでくる事案まで。多くの宮廷貴族が官僚として働き、国を支えていた。
そんな宮廷貴族の中でも最も上の立場に立つ男。内務尚書ジーベルト侯爵。三権の中で内政を司る彼は、仕えるべき主から呼び出され、執務室をノックした。
「陛下、お呼びとのことですが」
「おお、ジーベルト侯爵。待っていた」
豪華な執務室の中には、高級品だらけの内装に負けず劣らず高級品を身に着けた男が居た。
神王国国王カリソンである。
元々神王国の十三代を数えるにあたり、かつての国王は基本的には政務の殆どを部下に任せることが多かった。何事もよきに計らえとするだけで、大抵のことは恙なく回る。
しかし、それは同時に部下の専横を招いた。国王の勅命が乱発される事態を呼び、ついには内乱を呼ぶこととなり、それに乗じた他国の侵略によって国を危うくした。
斯様な経験にかんがみ、王権の強化を徹底的に図ったカリソンは、対外的には融和政策を取りつつも内部統制の強化を行い、粛々と中央集権の体制を整えて行った。かつては高位貴族が当たり前に持っていた下級貴族の任命権であったり、王家から与えられた物品を勝手に売買する権利を取り上げた。貴族は全て王の任命制としたし、王家からの下賜品は売買を許可制としたのだ。これにより、地方貴族が独自の勢力を形成することや、王家の権威を利用した金稼ぎを防ぐことに成功している。
更には高位貴族同士の婚姻を許可制にするなど、多くの政策を断行し、王家の威光を強め実権を増やしていった。
そうした数々の施策の結果、今までは口頭一つで済んでいた裁決も書類となり、王の仕事が増大したのは仕方のないことだ。
今日も今日とて執務室に缶詰めになっていた王に対し、侯爵は恭しく頭を下げた。
「陛下のご命令とあれば何時でも。それで、如何いたしましたか?」
そこそこ高齢と言っていい年の侯爵だが、王の前で不敬な態度はとらない。王が座って仕事をしているのに対し、背筋を伸ばしたまま立って会話する。
「うむ、実はカドレチェク経由で陳情が届いた。モルテールンについてだ」
「モルテールン男爵ですか」
モルテールン男爵といえば、最近は噂にならない日が無いほどに有名な家である。諸事の調整役たる内務としては、仕事を倍増させて下さった御方であり、文句の百や二百はぶつけたい相手である。苦情を手紙に書きなぐっていいというのであれば、必要な羊皮紙の長さは廊下の長さを超えてしまうに違いない。
そんな厄介ごとしか植えていない畑から採れる陳情事。どうあっても普通の陳情とは思えないわけだが、わざわざ公爵経由で届けられたというのであれば、聞かないわけにもいくまい。
「ああ。内容は、例の大物についてだな」
「ドラゴン、ですか」
先ごろモルテールン家の御曹司がドラゴンを討伐したことは侯爵も承知している。ことが事だけに、カリソンから何とか後付けでも王家からの命令で動いたことにして、パレードを出来ないかと言った検討や、どうにかして王家も一枚噛んでいたことに出来ないかといった相談を受けたのでよく知っている。結果的に早々に噂が広まってしまったこともあって、流石に今から後付けは無理だろうという話になった。顔に皺が刻まれる年になっての徹夜は堪えたわけだが、この程度は羊皮紙の真ん中程度の苦情である。
「ああ。モルテールン家は、大龍の頭蓋骨を王家に献上するとともに、その他のものについて王都で販売する許可を求めている」
「売るのですか!!」
ドラゴンの討伐などというものは、超特大の武勲である。侯爵は、子々孫々まで語り継がれる武勇伝であるし、その証としてドラゴンは剥製にでもして飾っておくものだと思っていた。実際、内務系の貴族は皆そう思っているはずだ。この点、手柄と呼べるような功績を立てることが難しく、誰の目にも目立つ業績を欲しがる内務系の思考の癖のようなものだろう。
細々とした調整であったり、様々な確認であったり、或いは色々な調査であったりといった、裏方仕事が多い内政の仕事。
上がいついつまでになになにを手配しろと命じてきたなら、手に入るかどうかを調べ、予算内で購入手続きをし、物が届くまで気を配る。ちゃんと届けられたなら、予算の中から支払いを行い、適正な執行だったかを確認し、記録する。
一事が万事この調子で、ミスなく堅実に、確実な仕事こそが内務に求められること。
毎日毎日ルーティンワーク。だからこそ、内務系の人間は、華々しく、煌びやかな活躍というものに多かれ少なかれ憧れを持つものだ。
その点、常に有事に備える軍務系は違う。軍人が華々しい活躍をするときというのは、戦場において劣勢の中で孤軍奮闘するであるとか、手ごわい相手と火花散る争いを繰り広げるであるとか、とにかく命が幾つあっても足りないピンチと背中合わせになっている。華々しい活躍などというものは御免被りたいのが当然の発想で、何事もない平穏な状態こそ心から望むこと。それが軍務系貴族の心だ。
ドラゴンという、大活躍の証拠を売る。これは軍務貴族だからこそ出た発想なのだろうなと、侯爵は妙に納得感を覚えた。
「そうだ。まだ内密に根回しをしている段階とのことだが、耳聡いものは既に動き始めている」
「でしょうな。して、誰に何を売るかは決まっておりましょうか」
供給が限られていて、需要が高いものというのは、売り手が有利になる。それにもまして誰もが欲しがる一品物の販売となれば、これはもう完璧に売り手側の言い値がまかり通る状況だ。
ちょっとした有名人であっても、私物を欲しがって金を出す輩は居る。それを思えば、ドラゴンなどというのは本物の英雄が手に入れた戦利品であり、欲しがる人間にとってみれば、どれだけお金を積んでもよいお宝だ。爪の一本、鱗の一枚でも手に入れれば自慢できる代物。命知らずが偶然手に入れた落とし物を売るのとは違い、今回の様にまとまった数と質が有るとなれば、むしろ手に入れていない方が恥ずかしいレベルになるだろう。
金が有るといえば貴族。彼らは見栄っ張りだ。
ドラゴンの素材を持っていないとなればどうなるか。
お金が有れば買えたのに何で買わなかったんですか? もしかしてお金が無かったんですか? みんな持っているのに貴方ぐらいですよ。ぷーくすくす。と、こうなる。
友達みんなが持っているのに自分だけが持っていない状況は、現代の小学生でも堪えるのだ。貴族ともあろうものが、持っていない状況を座視できるだろうか。
ドラゴンの素材を差配する人間は、きっと大きな利益を手にできる。誰に売るかは重要な話だ。
「決めていないということだ」
「決めていない? 売ると決めていながら、ですか?」
「そうだ。モルテールン家は競売形式の販売を検討中だそうだ」
「それはまた、混乱が広がりそうですな」
競売。オークションともいうが、物を売る売り手側が値段をつけるのではなく、買い手側が値段をつける販売方法の一つだ。
買い手側が複数いて、売り手側の供給が限られる場合。特に、一点ものを売りに出す場合によく使われる。
買い手側が値段をつける際に競わせることから競売と言われ、高い値段を付けた買い手に、売り手側は品を売る。ここら辺の話は常識レベルなので、侯爵としてもいちいち確認したりはしない。
さてもさても、トラブルに愛されたモルテールン家が競争を煽ろうというのだ。何が有っても不思議ではない。
「ああ。それ故、国軍を警備に回したいというのがカドレチェク家の要望本旨だ」
「国軍を統括するものとしては正当な要求かと思いますが……」
中央軍は、王都の治安維持も担う。
王都で混乱が予想されているというのなら、事前に備えるのは当然の職務である。
モルテールン家が龍の素材を売りに出す。それも競売で。王都が荒れるのは間違いないわけで、それ故に迷惑料として龍の頭を献上するのだろう。狩った動物の頭部をハンティングトロフィーとして飾り物にするのは良くあることだし、ドラゴンの頭部ともなれば王家に献上する格としては申し分ない。
王家としても面目を施せるし、多少の面倒ごとならば大目に見れる程度の貢献ではある。例えば外国の要人が来たとして、龍の頭蓋骨を見せれば間違いなく驚いてもらえるし、会話のネタとして関係性を円滑化させる潤滑油になるだろう。ドラゴンを倒せる人間が居る国に戦争を吹っかけてくるのは躊躇するだろうし、何かにつけて一目置かれることになる。
唯一無二である以上、金銭的価値には代えがたい代物だ。
「軍を動かすのに必要な予算については、大龍の頭でお釣りがくるな。王家としては許可を出すと決めた。問題は……」
「経済的な混乱、ですかな」
「そうだ。だからお前を呼んだ」
カリソンが侯爵を呼びつけたのは、別にモルテールン家に恨みがあるわけでもカドレチェク家に含むところがあるからでもない。ごく単純に、相談事の職責で一番ふさわしかったからだ。
侯爵も老いたとはいえ伊達に内政官のトップを務めているわけでは無い。王が何を言いたいのか、即座に察する。
「そうですな。緊急の対策が必要でしょう。まず間違いなく、潰れる家が出ます故」
「むぅ……やはりか」
モルテールン家が王都で龍の素材を売る。これだけならば混乱といっても大したことは無い。珍しい一品物であるが故に取り合いは起きるだろうが、その程度の騒動は混乱の内に入らない。かつて、とある大貴族が名のある職人に作らせた一品物の全身鎧が売られたことがある。戦場の鹵獲品だったのだが、これも王都で売られ、当時は大層話題になった。過去の前例があるのだから、別に特別な品を売るなという話では無い。
問題は、売り方が競売、オークションであるという点にある。
結論から言うのであれば、この話が事実として広まった時点で、王都経済は最悪壊滅する。更に、王都経済だけならまだしも、神王国経済が破綻しかねない。
そんな馬鹿なと考える人間は、経済の恐ろしさを分かっていないのだ。
「一番人気は龍の血だそうだ」
「血ですか?」
「傷を治す力があることはほぼ間違いないようだな。病気を癒せるかどうかは未知数との調査結果だ」
「それはまた。欲しがるものは多そうです」
龍の素材。それも、噂に聞くような“癒し”の力がある血液のようなものが出回るとしたら。欲しがる人間は腐るほど居る。落札価格が金貨を下回ることなどあり得ない。むしろ金貨は何百枚必要だろうかというレベルになる。
オークションとはつまるところ金での殴り合いだ。大金を持つ人間が、持たない人間を足蹴にして蹴落とし、欲しいものを手に入れる過酷な生存競争がオークション。手に入れられるか、入れられないかの二択しかない。資金量のみがものをいう、残酷な現実でもある。
入札の競争相手を想定するならば、手持ちの資金は多ければ多いほど良い。歴史上初めてのオークション。想定落札価格などあってないようなもので、予想など付けられない。不安に思う人間が、どうしても落札したいと考えるなら、目いっぱいで準備をしたくなるのは当然だ。
つまり、誰も彼もが現金を集め出す。金を貸し付けていた人間は、露骨に回収に走り出すだろうし、新規に貸し付けてくれる人間も激減するだろう。目ざとい商人などもこぞって売掛金を清算し、現金を調達しだす。そして、現金需要の増大は、負債清算の連鎖を生み出していく。
現金の価値が一気に上昇する。そして起こるのが金融収縮だ。
市中に出回る金の量が減れば物価は下落し、物価の下落は賃金の下落を呼び、賃金の下落は消費の減退を呼ぶ。
これが一時的なものであればまだましだ。しかし、金融収縮の恐ろしさは、一度収縮し始めると収縮が収縮を呼ぶ点にある。
「事前に国で買い上げるわけにはいきませんか? 出来れば現金以外で」
「そして王家が総どりにするか? 国中の恨みを王家が買うことになる。経済は良くても、次はクーデターを警戒する羽目になるだろうな」
売主の匙加減一つで悲喜が生まれる状況は、諍いを生む。ましてそれが転売となるならば、利益を得た王家に対して向けられる妬みは強い。
マスクを買い占めて、高値で転売するようなものだ。どう考えても悪手である。
ならば、恨みや妬みは、売り手ではなく買い手同士で向け合ってもらうべき。オークションで売るのは、その為なのだ。モルテールン家の狙いもそこにある。
売り手が利権を持ち、誰に売るかを匙加減一つで決めるからこそ、売ってもらえなかった人間は売り手を恨む。オークションにしてしまえば、買えなかった人間の恨みは、買えた人間、つまりは売り手以外に向かう。
それが分かっているからこそ、王家が全てを買い取るなど悪手だと言い切れるのだ。
「ならば、何とかしてモルテールンから現金を回収する手段が必要です」
侯爵は、そう断言した。
モルテールン家にのみ現金が集中する状況が不味いのだ。
やるべきことは、合法的で合理的な現金回収手段。或いは、現金の増産である。
「……あの異端児であれば、もしかすれば既に対策を打っているかもしれんぞ?」
「そんなまさか」
あり得ない。
冗談であったはずの言葉に対してそう言い切れなかったのは、王も侯爵も、もしかしたらという思いがぬぐい切れなかったからである。