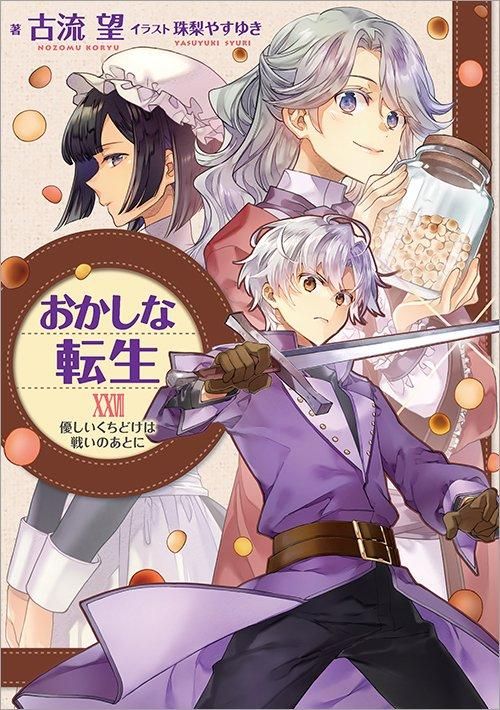176話 意外なスポンサー
かつて、古代ローマの市民が享受していた公共サービスを指して「パンとサーカス」と呼んだ詩人が居た。
市民が政治的無関心となる原因は、食に困ることのない経済的安定と、生産性が無くとも楽しめる娯楽であると。
愚民化政策を執る為政者への批判であるとも、民主主義の衆愚性を批判しているとも、或いはローマの政治の素晴らしさを評した言葉だとも言われる、諸説ある言葉。
経済的苦境や飢えは論外であるが、古代ローマのみならず、為政者という者は一般大衆の娯楽には大いに気を付けてきた。人間とは時に理性でなく突発的な感情で政治家の支持を決め、また利己的な感情で不支持を決めるからだ。
誰だって、苦しく辛い毎日を過ごすよりは、明るく楽しい毎日を過ごしたいもの。楽しい毎日には、当然、楽しい娯楽が無くてはならない。
競技、お酒、賭博や美食、或いはスポーツなど、娯楽と呼べるものは沢山ある。
神王国での娯楽といえば、競技と賭博。いわゆる競馬や、闘技と分類されるような戦士の腕比べのような決闘もどき、或いは狩りなども軍人の能力を計れるという点で人気が高い。
勿論、これらの競技はよほどの事情が無い限り、誰かが胴元になって賭けの対象となる。
だがしかし、これらはどちらかといえば男性向けの娯楽。世の中は大よそ男女半々。いや、戦乱が絶えない社会で男性の死亡率が女性のそれより高いことを思えば、数だけなら女性の方が多い。つまり、男性向けの娯楽だけでは片手落ちと言わざるをえない。
女性向けの娯楽といえばなんであるか。神王国人ならば、芸術を挙げるのでは無いだろうか。自身を美しく飾り立てること、美しいものを鑑賞すること、そしてそれらを称えること。神王国女性にとっては美とは娯楽である。神王国女性の美に対する目はかなり洗練されている。
刺繍は貴賤を問わず女性の重要な技能であるし、絵画鑑賞は貴族女性にとって基礎教養の範疇。服の美しさを品評することも社交を兼ねた娯楽になりがちだし、音楽鑑賞なども女性にとっては身近な娯楽。
さて、ここで問題になるのは娯楽の男女差。
男が女に趣味を合わせるにも、女が男の趣味に合わせるにも、中々難しいものがあることは想像に易く、厳つい髭男が刺繍などといえばユーモラス過ぎるだろうし、鍛えていない女性に闘技をやらせるのも非道な話。
男女では楽しめるものに違いがある。だが、これでは困るのだ。
例えば男女で仲を深めようと思ったなら、出来ればお互いに共通の趣味、娯楽を話題にしたいもの。男性が女性を初めてエスコートしたのが、女性の全く興味のないことであった、などとなれば興ざめも甚だしい。
この問題を解決するには、王都のとある場所に行けばよい。
そこでは、男女問わずに楽しめる、とっておきのスポットがあるのだから。
「ここがそうですよ」
ヤントとアルが一人の女性を助けた後、その女性を送り届けた先は劇場だった。
何代か前の王が建てた国立の建物で、代々の王が時折王妃や愛妾と共に訪れるという由緒正しい場所。
演劇や音楽劇、或いは演奏会などが主要な演目で、入場するには最低でも身なりを整えた紳士淑女で無ければならない。
王都でも一等地に建ち、白い大理石のような石造りの、神殿を思わせる威容。正面は重厚な青銅製のドアが、顔を映すほどに磨かれている。どう見ても三階建て以上はありそうな上に、馬車が十台以上並んでも余裕なぐらいの幅。収容人数が如何ほどであるかは、想像すらできない。国王臨御の興行を行う大舞台から、少人数が間近で楽しむ小舞台まで、幾つもの舞台が用意されている娯楽の殿堂。
あまりの凄さにヤントとアルが圧倒されていると、女性は正面玄関ではなく、建物を迂回するわき道の方に進んでいく。
「ここから入れるんですよ」
建物の脇の隠れた部分に、簡素な木製のドアがあった。
無論、建物の立派さを損なわない程度に装飾されている扉ではあったが、正面の目立ち方に比べれば月とスッポン。ペイスとヤント程度の違いがある。
ドアにもそれ相応の重みがあるのだろう。ギギと鳴る扉を開け、中に入った瞬間。
「エルザ!!」
身長二メートルはありそうな、ひげもじゃの男が、とびかかって来た。
「何だっ!!」
咄嗟に思わず剣を抜いた新人従士二人。
有事に即時対応できる心構えが出来ていた点は、モルテールン家の部下として褒められるべきものだが、この場合はタイミングが悪い。
服装が明らかに“無理やり乱された”状態の女性を連れて、抜剣した若い男が二人。良からぬ輩が押し込み強盗でもしてきたのではないか、と誤解されてしまった。
女性を抱きかかえ、そのまま強引にアル達の傍から引き離し、二人から庇うようにしたひげもじゃ男。そして、状況は更に悪化しだす。
「お嬢様!!」
「お前ら、うちのお嬢をこんな目に合わせて、只じゃおかねえぞコラ!!」
次から次に、奥から男が出て来る。ワラワラと集まり、剣呑な雰囲気が強まるばかり。
「先手必勝だコラっ!!」
集まっていた中から、ヤントやアルと同い年ぐらいの若い男が殴りかかって来た。顔にドーランのような白粉を塗りたくり、地肌がすっかり見えなくなっているにもかかわらず、憤怒の感情だけは明らかに見てとれた。殴りかかる拳は、手近な方のアルに襲い掛かる。
素手の相手に剣を振り回すほど、アルも素人ではない。鍛えられた武芸を振るってよい時と、そうでない時の区別がつく程度には落ち着いていた。それだけの修羅場と地獄を越えて来た故の落ち着きということもあるが、冷静に体捌きのみでドーラン男の拳打をいなした。
「クソッ!!」
喧嘩慣れしていないのだろう。ドーラン男は、ただがむしゃらに拳を振り回している。フェイントも何もない、ただの空打に当たってやるほどアルはお人よしではなく、ひょいひょいと躱しつつ、周りを隙無く窺っていた。
尚、薄情にも手伝いすらしないヤントには若干の意趣返しとして、ふらつきだしたドーラン男を押し付けておいたが。薄情男の服に、べっとりとドーランが付く。
「止めて!! その人たちは、私を助けてくれたのよ!!」
物騒な雰囲気を霧散させたのは、劇場までヤント達を案内してきた女性だった。これで止めなければ何かの陰謀かと疑っていたところだったが、流石にそういうことも無かったらしい。
「どういうことだ、エルザ」
「だから、この人たちは、私が変な人たちに乱暴されそうになったところを、助けてくれたの。それでここまで送ってくれたのよ」
「何!!」
エルザというらしい件の女性の言葉で、周りの雰囲気が変わる。
「そうだったのか、済まない。てっきり……」
「詳しいことは私が話するけど、その前に、着替えてきて良い?」
「ああ」
ぼろ切れと服の中間に成り下がっている布を茶褐色の肌の上にまとい、借りた上着で辛うじて最低限の被覆を取り繕っていた女性が、奥へと入っていく。
「とりあえず、エルザの恩人というなら、持て成さんわけにはいかん。両人、こっちへ来てくれ」
先ほどの危なそうな雰囲気から、困惑と胡乱げな雰囲気に変わっている連中の中を、ジロジロと見られつつアルとヤントは進む。
通されたのは、幾つもの鏡が置かれた部屋。鏡と言っても、合金を丁寧に磨き上げた金属鏡であるが、自分の顔はしっかり見える。
化粧品に詳しくない二人には何が置いてあるかは不明だが、刷毛やらカツラやら服やらが雑多に置かれていて、見慣れない感じの部屋ではあった。
その部屋の中に、何処からかテーブルを持ち出し、折り畳みの椅子が用意される。新人従士二人が座ったところで、テーブルを挟んで向かい側に髭もじゃ男が座る。
「まず、先ほどのことを詫びよう。俺はエルザの義父で、ブーラン劇団の団長、ゴファ=ブーラン。さっきの連中はうちの劇団員で、家族みたいなものだ」
「モルテールン家従士、アーラッチ=アフーノフと言います」
「同じく、ヤント=アイドリハッパだ」
ひげもじゃの大男は、エルザの養父を名乗った。親子にしては似ていないと思っていたヤントなどは、それを聞いて強く納得した。髪の色、肌の色、目の色、顔の各種パーツまで、全然似ていなかったのだから、実の親子と言われた方が驚いたに違いない。
ゴファの方も、二人の名乗りを聞いて驚く。具体的には、モルテールン家の人間であったという点に。だが、今はそれよりも優先すべきことがある。
「それで、一体何があったと?」
「実は……」
かくかくしかじか。説明はすぐに終わる。
モルテールン家には屈強な男も多い。厳つい大人たちにはかなり免疫のある二人だけに、大男の娘に起きていた事件のあらましを、落ち着いた様子で詳細に語る。
自分たちが王都に来ていた事情から、裏町をうろついていた理由、エルザの声を聴いて助けに入った経緯から、その時の様子まで。事細かに語ったことで、ゴファの顔つきも変わる。
「おい」
「はい、団長」
「今聞いた内容を、騎士団の詰め所まで行って伝えてきてくれ。盛りの付いたごろつきのことだ。似たようなことをやらかすに違いないからな」
「はい、早速」
人を動かすことに慣れた様子で、団員と思しき若い男へ指示を飛ばす髭男。
指示を受けた方も、何がしか思うところがあるのか、妙に張り切って部屋を出て行った。
他にも細々と何人かに指示を飛ばした後、改めてゴファは若い二人に向き合う。
「改めて、娘を助けてもらって感謝する。しかし、お前さんたち……いや、失礼、貴方方が、高名なモルテールン家の家人であったとは」
「えっと……俺達、いや、私たちもまだ駆け出しの見習いでして」
「ははは、口調は崩してもらって構いませんよ。モルテールン家といえば、王都でも有名でしてね。その家人の方々であれば、我々としてもお近づきになりたい相手です」
「それならば遠慮なく」
貴族に仕える従士となれば、平民階級より立場は上。別に丁寧に会話する必要もないのだが、やはり見た目にも風格のある大人相手に無遠慮な対応を取るのは憚られた。二週間ほど前であれば無意味にツッパッていそうなものだが、元々二人とも親が従士ということもあって育ちがよろしい。小さい時からの癖のようなものは、中々抜けきらないものだ。
他愛のない世間話をしつつ、色々と話をして打ち解けて来た頃合い。
着替えを済ませてきたのか、少女が部屋に入って来た。悪漢に乱暴されかけた直後だというのに気丈に振る舞っている様子を見れば、彼女が芯の強い女性だと分かる。
「エルザ、大丈夫なのか?」
「ええ。みんなの顔を見たら安心したわ」
「そうか」
多くを語らず、娘を抱擁する父親。
その姿を見れば、娘も愛情深く育てられてきたであろうことが察せられる。
だからこそ、ヤントには解せない。不用意に、危ない地域に若い女性が単独で居たことが。これほどまでに大切にされていたのなら、危ないところに近づかないように教わっているはずである。ある意味で箱入り娘。暴漢がつるんで出歩くような裏路地に、育ちのしっかりとした女性が居ることの不自然さ。
一人で出歩いていたというなら、何やら事情がありそうに思えた。
だからだろう、ついその疑問が口をついて出てしまう。
厄介ごとにわざわざ首を突っ込んでいくような真似は、幼馴染の影響が大であろう。
「それで、何であんなところに一人で居たんだ?」
「それは……」
やはり何か事情があるのか、途端に女性の顔色が曇る。
精神的にショックを受けたばかりであろう女性に対し、更なる追い打ちを掛けるような真似になりかねない。そう、咄嗟に気付いたのは、横に居たアルだった。
同じように顔色を変えている髭男に対して、慌てて変えた話題を振る。
「それにしても、皆さんはどういう仕事をされている方々なんですか?」
「我々は、劇団員ですよ」
「劇団員?」
「演劇をして、観客を楽しませるのが仕事です。今は、とある方が出資してくださった演目を準備中でして」
「へえ」
ゴファも、話題を変えてくれるのは望ましかったのだろう。髭顔を分かりやすくアルに向けて、やや早口気味に自分たちのことを語りだした。
「演劇に興味がありますか?」
「今、そういう仕事があると初めて知ったので。儲かるものですかね?」
「時によりけりでしょうね。我々の仕事で、お金をもらう相手は主に二通り。劇を見た方から貰うか、劇を見ない方から貰うかです」
観客から代金を徴収して稼ぎとする、というのは何となくアルやヤントにも想像できた。
だが、劇を見ずに劇に金を払う人間が居るというのはどういうことかと、首をかしげる。
「劇を見ないのにお金を払う人間が居るんですか?」
「ええ。先にあげた、劇を見て頂いて、対価としてお金をもらうのが一番わかりやすいことなんですが、これはとても不安定です。良い劇でもお客さんが見てくれるとは限りませんし、同じものを何度もやっていれば飽きられる。天候次第で客足が左右されますし、演者の人気にも影響される。お客の大半はある程度裕福な平民でしょう。それに比べると、と言ってはおかしいかもしれませんが、劇を見ずにお金を出す方というのは、主に貴族の方々です。ある程度の自由を拘束される代わりに、劇団そのものにお金を出していただける。お客の多い少ないに寄らずとも収入が安定するわけですよ」
「自由の拘束?」
「演目を指示されたり、団員の配役を指定されたり、演じる時間や日時を決められてしまったり、といった具合ですよ」
「ああ、なるほど。要は後援者か」
「そうです」
古今東西、権力者や富豪が芸術の庇護者となるケースは多い。
神王国では、極々一部の例外を除いて、金持ちとは貴族である。そして、権力者は例外なく貴族だ。
つまり、芸術のパトロンもまた、貴族であることは自然なことと言える。
自分の権力や財力を誇示する為に芸術を利用する者、お気に入りの役者や芸術家を囲いたがる者、純粋に芸術を好んで自分好みに楽しみたいもの。理由は色々だが、貴族の後援を得ることが出来れば、劇団などは経営が著しい安定をみる。旅芸人達が貴族に呼ばれ、気に入られてお抱えになる、などというのはよくありがちなサクセスストーリーだ。
モルテールン家でも、ペイスの魔法を喧伝する狙いから風景画家に絵を描かせていたりする。画家が自由に描いた絵を買うのではなく、金銭を援助して指定の絵を描かせる。パトロンとしては一般的だろう。自由の代償は経済的安定だ。
似たような話はあちこちにあり、演劇もまた同じ。
などと話をしていて、頭の回転の速いアルが、ふと気付いた。
「王都の劇場に居るってことは、もしかして皆さんも貴族の後援がある?」
王都の、それも王立の劇場は、言うまでもなく神王国で一番いい劇場だ。立地といい設備といい格式といい、申し分ない。国一番の巨大劇場だ。一つの劇場で演目が一つということもなく、幾つかの舞台で同時に演劇が行われるはず。
しかし、だからと言って簡単に場所をおさえられるとも思えない。権力と財力の双方が無ければ、こんな一等地の最上級の場所で演じることなど出来ないはず。というアルの予想に、ゴファは首肯した。
「そうですね。実は最近、大口の後援が付きまして、その方のお陰で我々もこの劇場で演じられることになったのです。まあもっとも、その代わりに劇の内容は指定されてしまいましたが」
「へえ」
「おおそうだ、お二人にも是非練習しているところを見てもらいましょう。と言っても、今はまだ戯曲も手を入れているところですし、配役も決まっていないのですが、劇のあらすじだけでも、お二人には格別の興味を持っていただけるはずです」
「そうですか。折角ですからチラッとだけ」
アルとヤントの二人は、エルザの案内を受けて舞台の袖まで移動する。
そこで、劇の内容について数人がああだこうだと言い合いながら、ストーリーや演出を組み立てているらしい現場を目撃した。
紙の台本など存在しない世界で、ストーリーやセリフは各人が覚えるしかない。また、即興の要素が非常に強く、それだけに劇の骨子はしっかりとしておかねばならないのだ。
その為、入念な打ち合わせがベテラン勢で討議された後、配役を決めて練習に入る、という流れになる。
などという説明を、エルザはしっかりと説明した。綺麗な、聞きやすい声だったのは、幸いだったのだろう。彼女が、劇の題名とあらすじを説明してくれた部分を、聞き逃すことが無かったのだから。
「劇の題名は『モルテールン海神英雄伝』。隣国との戦争で大活躍したモルテールン家の活躍とレーテシュ伯爵家との友情を描く一大冒険活劇、だそうです。レーテシュ伯爵様直々に、物凄く援助してくださっている演目ですね」
ヤントとアルは、思わずお互いの顔を見合わせた。