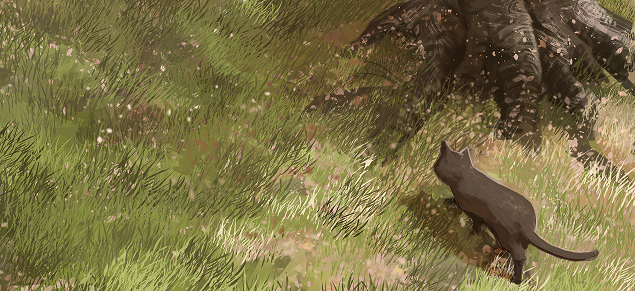じつはねこになれる
初冬のある日の昼下がり。
許可がおりたので、ぼくと彼女はひさしぶりに、朝の散歩をすることにした。
山の木々はすっかり色づいていた。
道がみえなくなるほど、黄色い葉っぱを惜しげもなく降り積もらせていて、彼女とふたりでそれを奇麗だねと笑った。
短く切りそろえた髪のせいで、彼女のきれいなうなじを、ぼくはたっぷりと見つめることができた。
時間がそこから立ち去るのを惜しむように、ゆっくりとすぎていくように感じた。
「あ。ねこだ」
と、彼女が道のわきを指さした。
一匹の三毛が、のんびりと日向に寝そべっている。暖かそうだ。
「ね。いままで、だまっていたけど」
と、積もっていく落ち葉を見ながら、今思いついたように彼女は言った。
澄んだ声をしていた。
「わたしね。じつは猫になれるんだ」
へえ、とぼくは答えた。そいつはすごいね。と。
ぼくの声は、震えてはいなかったと思う。
「あら、信じてないでしょう。本当なのよ」
彼女はすこし、さみしそうに笑った。
☆
初雪が降った日の朝だった。
ふと見ると、ベランダのすみっこで、子猫が一匹ふるえていた。
生後半年くらいの、真っ黒い猫だった。
「みい」
子猫は窓ガラス越しに鳴いた。
両手で、ガラスをかりかりと掻く。
「入れてほしいのか」
ぼくがベランダをあけてやると、黒猫はするりと入ってきた。
さむそうにぶるぶると体をゆすり、大粒の雪を振り落とす。
ぼくが手を伸ばすと、するりと逃げた。
我が物顔で、部屋をうろつき、そこらじゅうを嗅ぎまわる。
そしてすぐ、本棚のすぐそばの、彼女の指定席にすわりこんで、安心したように丸くなった。
「おいおい」
ぼくは、思わず笑った。
「まさか、きみ。ほんとうに、ねこになってしまったのかい」
子猫は答えなかった。
ただ、ぼくのほうを見て、なにか言いたげに、すん、と鼻をならした。
☆
すごく冷える夜だった。
ストーブの火をおとすと、彼女は不満そうにみゃーみゃーと鳴いて、ぼくのふとんに入ってきた。
「こらこら」
彼女がふとんの中であばれるので、ぼくは彼女をだきしめた。
ねむくなったのか、彼女はもがくのをやめて、ぼくの腕のなかで静かになった。
呼吸の音が近くではっきりと聞こえた。
人よりも高い体温が、とてもあたたかかった。
☆
春が来た。
獣医師にすすめられて、彼女を去勢することにした。
しかたがない。飼い猫にとって、これは必要なことなのだ。
彼女は出かける先が苦手な病院だと知って、絶望的な顔をしていた。
「よくがんばったね」
ひさしぶりに家に帰ってきた彼女は、ぐったりとしていた。しばらく、定位置にだらしなく座って、ふてくされていた。
週末、おわびをかねて、桜を見にいった。
彼女はこんどこそ機嫌をなおしてくれたようだった。
☆
夏になった。
彼女といっしょに、遠出をして、海にいくことにした。
はじめて海を見た彼女は、おそるおそる波に喧嘩を売った。そしてかなわないとみるや、その場から脱兎のごとく走り去った。
「たははは」
あわてて追いかけると、彼女はパラソルの日陰で、心からイヤそうに前足を舐めていた。
そのあと、いくら水をのませても、キャットフードをあたえても、彼女はずっと塩からそうにしていた。
ぼくは帰りの車の中で、たくさん不満を言われた。
来年きたときには、海の幸をたくさん食べさせてやるからと、ぼくは彼女に約束をした。
☆
彼女は相変わらず雷が苦手だった。
ゴロゴロ、と空が鳴ると、体を固くして、一目散にクローゼットへ走っていく。
そうして、一番下の衣類の中にもぐりこんで、しばらくじっと息をひそめるのだった。
雷がやむと出てきて、ぼくに文句を言う。ぼくに言われても、どうしようもないというのに。
「にぼし食べる?」
彼女は文句を言いながら、器用ににぼしを食べた。
☆
秋になった。
きらいだったはずのサンマを、彼女はついに克服したらしい。
すききらいがないのは、いいことだ。もっとも、彼女は嫌いなものも増えたのだけど。
「にゃーう」
最近では、カニカマがお気に入りらしく、冷蔵庫をあけるとよくねだってくる。
カキフライは作らなくなった。彼女が食べられないからだ。
街路樹の落ち葉はあの日とおんなじくらい、たくさん積もった。
☆
冬になった。
彼女はまた、ふとんに入ってくるようになった。
「なあ」
ある夜、ぼくは思わず、布団の中で口に出した。
「さみしいよ。きみが猫になってしまったから、すごくさみしいんだ」
なにか急に、ずっと長い間抱えつづけてきた、とても大きくてだいじなものが、少しずつこぼれて消えてしまうようだった。
つらい気持ちが瞼からあふれて、ぼくは寝巻の袖でそれをぬぐった。
ぼくのうでの中で、彼女はただ「みい」とだけいって、ぼくのほっぺたを舐めた。
☆
今年も、雪が積もった。
彼女はまるで初めてその景色を目にしたように、おそるおそる前足を伸ばして、情けない顔でぼくを見た。
「雪だよ。雪」
指をさして教えると、ちょっと真面目そうな顔をして、彼女は雪を舐めはじめた。
「あんまり食べるなよ」
美味しそうに食べるので、ぼくは思わず注意をした。
彼女はあんまり食べなかった。
すぐに飽きたのか、まもなく家の中にひっこんで、いつもの場所で丸くなった。
☆
灯油配達のトラックは、去年と比べて百円ほど高くなったようだった。
せっかくだからと、七輪を出してきて、炭で餅とスルメを焼いた。
焼き餅は、海苔と醤油。
彼女は焼いたスルメのことが気に入らない様子だった。かわりに、ぼくのぶんの焼き海苔を、一枚奪われた。
ケーキは小さめのものにした。彼女のぶんは、当然ながら七面鳥ではなく、ささみ。
☆
遠くの除夜の鐘を、二人で聞いた。
☆
春がきた。
ぼくは彼女を連れて、また桜を見にいくことにした。去年、彼女が桜のことを気に入った様子だったから。
彼女はご機嫌だった。
散っていく花びらを目で追いかけ、土に落ちると喜んで前足で踏みにいく。
「あ、ねこ」
お昼時の公園には何組かの家族がいて、子供たちが彼女を見ては、そうはやし立てた。
彼女は耳をぴくぴくとさせて、愛想よくしっぽをふった。
おいで、と、ぼくが彼女の名前を呼ぶと、
「にゃあ」
こちらを見て、彼女は幸せそうに鳴いた。
「ああ。きれいだね」
ぼくは彼女といっしょに、桜を見上げた。
もう満開を過ぎて、数日もすれば葉桜になっているだろう。まだ冷たい春の風が、青空にのぼっていく。
「ふうん」
ふいに、ぼくのすぐそばで、そんな風に声がした。
「じゃあわたし、次は桜になろうかな」
なつかしい響きだった。何度も耳にした、忘れられない、澄んだ声。ずっと聞きたいと思っていた声。
びっくりして、ぼくはあたりを見渡した。
近くには、誰もいない。
かわりに、黒猫が一匹、ぼくのすぐそばでぼくを見ている。
ぼくは彼女を抱き上げた。
「にゃあ」
黒猫は鳴いた。
空耳ではなかったはずだと思った。まだはっきりと、耳の奥に声が残っている。
のどの奥から、まるであふれ出すように、おかしさがこみあげてきた。
「困るな。桜になんて、なられてしまったら……」
ぼくは彼女に、そう文句を言った。
こみあげるおかしさを抑えきれず、言葉のなかほどで、思わず声にだして笑ってしまった。
おかしくておかしくて、仕方がなかった。夢中で、彼女の小さなからだを、めいっぱい抱きしめた。
「にい」
腕の中の彼女は一言だけ小さく鳴いて、ぼくのほっぺたを丁寧に舐めた。
少しだけ、痛かった。
どうしようもないものが、ぼくの喉を伝って、ぼろぼろと、大きな声になってこぼれた。
了