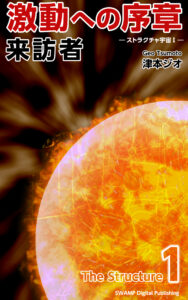全球凍結の惑星、地球 ―CE(共通歴)二四八九年―
機体の外部点検で冷え切った手をデフロスターで温めながら、僕は相棒が来るのを待っていた。
長距離クルーズ用のオプションをフル装備した無骨な《センチネル》。そのパイロットシートに縮こまり、効きの悪い暖房装置に呪いの言葉を吐きながら……。
八歳くらいのころ、基礎学校の講義で「太陽系事変後の寒冷化・初期」というタイトルのアーカイブを見たことがある。
アクティブ可変翼で優雅に風をつかみ、氷原の上空を美しく舞う純白の飛翔体から映像は始まった。
テロップによると、当時の最新多目的宇宙艇で、《レイ》級一番艇マンタレイという小型艇だ。
艇の全長と同じほどの細い尾をなびかせ……タグを開くと、これは大気圏航行用の補助可変尾翼だそうだ。
それは、吹き荒れる極北のブリザードの中を、主翼をはためかせ大空を泳ぐかのように優雅に飛翔していた。
何だろう? 以前この光景を見たことがある気がする。艇の名前に聞き覚えは無いけれど……。
奇妙な懐かしさ、胸が締め付けられるような、切ない不思議な感覚に、僕の心は揺れた。
なぜか、寒さに凍える今このとき、ふとそのことを思い出していた。
僕は基礎学校を卒業して、予定通り応用学校に入学した。
フルタイムの基礎学校とは違って応用学校は午前中だけの授業だ。十二歳になると直接脳に記憶を転写するニューログラフが使えるからだ。
数十分、電磁暗室に入って転写処置を受ける。そして残りの時間に座学や実技を行い記憶を定着させて一日の授業は終了だ。
僕は二年前から、旧時代のインターシップから派生したアドミニ・プラクティカムに参加している。
これは、午後の自由時間を遊んで過ごすのではなく、行政機関で報酬をもらいながら働くプログラムだ。今の時代は積極的に働く意思のある人材は子供でも重要だからね。
あまり人気のあるプログラムではないけれど……。同学年で参加しているのは僕を除けば一人だけだ。
その一人は、僕の幼馴染のトールだ。彼は保全管理課で見習い整備士として働いている。
周りの子供たちは、働きながら学校に通う僕たち二人を不思議そうな顔で見ている。
そりゃ遊びたい年ごろだけどさ。でも、僕にはどうしても叶えたい願いがあるんだ。トールだってきっとそうだろう。
今日も勤務先の調査課に出勤したが、どうも様子が慌ただしい。
「何かあったの?」守衛のおじさんに聞く。
「おう、見習い坊主か。実はな……」
守衛のおじさんが言うには、宇宙探査網との接続拠点、通称《通信塔》が応答しないそうだ。
だが、調査課の氷原行動隊は別件で全て出払っている。さて、どうしたものかと相談していたらしい。
「ありがとう、オフィスで詳しく聞いてみるよ」何はともあれオフィスに急がなくちゃ。
駆け足で調査課のオフィスに向かう。
オフィスに飛び込むと同時に声を掛けられる。
「やあ、ジーン。待っていたよ。これを見てどう思う?」課長がディスプレイを指さし聞いてくる。面倒見のいい人なんだけど、どうにも胡散臭い。
「こんにちは課長、通信塔と連絡が取れなくなったそうですね」ディスプレイを覗き込みながら返事をする。
画面には三チームの氷原行動隊の位置と任務内容が表示されていた。
アルファチームは北太平洋、ブラヴォーはエドモントン跡地、チャーリーはロサンゼルス・シェルターだ。
「アルファは長距離潜航艇ですよね? これ帰還するだけで一か月はかかるんじゃないかな。チャーリーはロサンゼルスで発生した集団感染の医療補助任務に従事中。まあ、跡地調査のブラヴォーに任せるのがいいんじゃないですかね」
「そうなんだよね。早速任務変更の連絡を取ったんだけどね。高機動車ごと崩落に巻き込まれたらしくてね……」
「えっ、大丈夫なんですか?」
「怪我人はいないみたいだよ。でも高機動車が壊れて修理中だってさ」
「無事でよかったですね。それならチャーリーでしょね。ちょっと遠いけど」
「……それが、チャーリーも全員罹患しちゃってね。事前にワクチンを接種済みだから軽症で済んでるけど」
「軽症って言ってもあの病気ですよね。視神経に来るやつ」
「そうそう、視界がぼやけたり、視野狭窄しちゃったりとか。チャーリーも全員使い物にならないね」なんか雲行きが怪しくなってきたぞ。
「あ、シガ・シェルターに応援要請したらどうです? あそこはスペースプレーンを持ってましたよね?」
「うん、聞いてみたよ。でも、あれは先日の事故で修理中だってさ……」ああ、シガ・シェルターで小さな爆発事故があったな。あれに巻き込まれていたのか。
「打つ手なし……ですか」
「そこで、ジーン君。君は氷原行動隊志望だったよね!」課長……顔は笑ってるけど目が笑ってない。ここら辺が胡散臭いんだよ。
「はい……去年、氷原行動課程を履修しました」何かいい具合に誘導されてる気がしちゃうんだよな。
「科学部長に相談したらジーンがいるだろと言われたんだ。君の保護者、いや、相棒のアルファ君と一緒に行ってくれないか? 氷原デビューだ!」
ちゃっかり、アルも引き込んでいるらしい。そういうところだよ!
こうして、見習い調査員である僕が調査責任者として抜擢されたのだ。
でも、これはチャンスかも知れない。僕にはみんなには秘密の目的があるんだから。
今回の派遣が決定した直後、万能自動工場《豊穣の角》のデータバンクからダウンロードした《マンタレイ》の設計資料を持ちこみ、科学部長のドナルド爺を説得しに行ったときのことを思い出す。
「大気圏飛行対応のMPSSか。今の太陽系じゃ重力推進なんぞ使えんぞ? ……ジーン、お前また趣味が入っているな?」
科学部長のドナルド・ササキが苦い顔で言った。
ちっ、やはり渋ってきたか。
「大体、お前は《豊穣の角》をおもちゃ工場か何かと勘違いしとらんか?」
実はちょっと思っているので何も言い返せない。
「この機体を製作するのに、どれほどの希少素材が必要か分かっとるのか? ノーザンエンド維持のための保守部材に換算したら五年分だぞ。却下だ却下。必要十分な性能の車両をすでに用意してある。出発までにシミュレータで訓練しておけ」
くそっ、駄目で元々とまずは提案してみたものの、やはり良い返事はもらえなかった。ドナルド爺は相変わらずのケチ野郎だ。
万能の自動工場、通称《豊穣の角》。原材料と相応のエネルギーさえ与えてやれば、大抵のものは産みだす機械である。まあ、データバンクに設計資料があるものに限られるんだけどね。
星系外へ移民していった人々にこそ必要なものだったと思うんだけど、地球に残留する僕たちのために全部を残していってくれたんだ。感謝しかない。
その魔法のような生産能力のおかげで、ノーザンエンド大規模セツルメントに住む僕たちは、曲がりなりにも文化的な生活を享受している。
ゆっくりと氷に埋まっていく《地球》という名の惑星の上で。