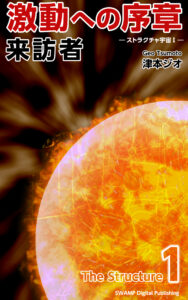ポイント・ズールーへ 3
「弾薬を再装填。弾種はそのままでいい」
「分かった……。アル」呼吸が浅い。
「深呼吸しろ、ジーン。ポイント・ズールーまで休憩は無しだ。気を抜くな」
厳しいことを言ったが、ここで気を抜くと後悔と自責の念に捕らわれるのは目に見えている。
少し時間を置いて見つめ直すべきだ。自身の経験から俺はそう考える。
「ふーはー、少し落ち着いたみたい……」
「ポイント・ズールーまで約二七〇キロ、少しペースを上げれば夕方には着く」
「いきなり実戦で実地訓練とか……ひどいよ、アル」
「そう言うな。おあつらえ向きに手ごろなハブ・ジャッカーが現れたからな」
「あれが手ごろなんだ……」
「今まで生き残ってきたんだ。あいつらにも手ごわい奴がいるぞ」
「なんか外は怖いね」
「全くだ。ところでさっきの戦闘、なぜアイス・プレーンを先に倒した? セオリーだと、より脅威度の高いフロスト・レンジャーを優先するはずだが」
誘導弾しか持たないアイス・プレーンはアクティブ防護で無力化できる上に、大きな進路変更ができない。
一方、フロスト・レンジャーは、センチネルにとって脅威となる20ミリ航空機関砲、ビースティンガーを装備していた。
このケースでの戦術は、アイス・プレーンはアクティブ防護で対処、フロスト・レンジャーを誘導弾で破壊。残ったアイス・プレーンも誘導弾で処理。これがセオリーだ。
「えっとね。あの時はとっさにこうした方がいいと思ったんだ。今思うと誘導弾を節約したかったのかも。先は長いし」
判断の正確さよりも迅速性を取るのは指揮官向きの資質だ。継戦能力を考えにいれた判断もいい。
「なるほどな。あとで判断の検証を忘れるな。重大な局面できっと役に立つ」
四年前、ジーンは自分の願いを俺に語った。
いつか、両親が行方不明になったセレスに行って自分の目で生死を確かめたいと。
ジーンの目標を聞き、それなら強くならないとなと言ったら、鍛えてくれと頼まれた。
俺は承諾して身体能力を強化するメニューを組んだ。その後、ジーンは一日も欠かさず鍛錬を続けている。
訓練は順調に進み、今では同年代の子供たちから頭一つ抜けた身体能力を身につけている。
ナルヴィとアリスが聞いたらどんな顔をするだろうな。
――ナルヴィとアリスが頭に浮かんだことをきっかけに再び回想に沈んでいく。
俺の脳には、異星種族製の補助電子脳がインプラントされている。損傷した小脳を補助するためだそうだ。
おかげで思わぬ能力を手に入れた。
機械狼への移植手術のあと、各種能力測定を受けたが、その中に短期記憶テストがあった。
高速で点滅しながら表示される数字を記憶して、指定された順番で答えるというものだ。
集中しなければ答えられない問題のはずだが、そのときの俺は別のことを考えながら回答していた。
測定員がつけている黒猫のカフスを目にして、ある存在が語ったジーンの出生に関する秘密を思い返していたのだ。
その間も目は数字を追い、余さず記憶して正確に回答を続ける。不思議な感じがした。
俺は、当たり前のように並列思考をしていたようだ。
そんな能力も、仕事をこなしながら回想に耽ることに費やしている気もするが……。
ナルヴィ、アリス、連れて帰れなくてすまなかった。あのセレスでの惨劇のあと、どれほど後悔したことか。
セレスで出会ったあの存在は、必ず二人を取り返す、十年待てば強力な援軍がやってくる。それまでは耐えてくれと言っていた。今は九年目、もうすぐだ。
しかし、あの化物相手に対抗できるのだろうか。