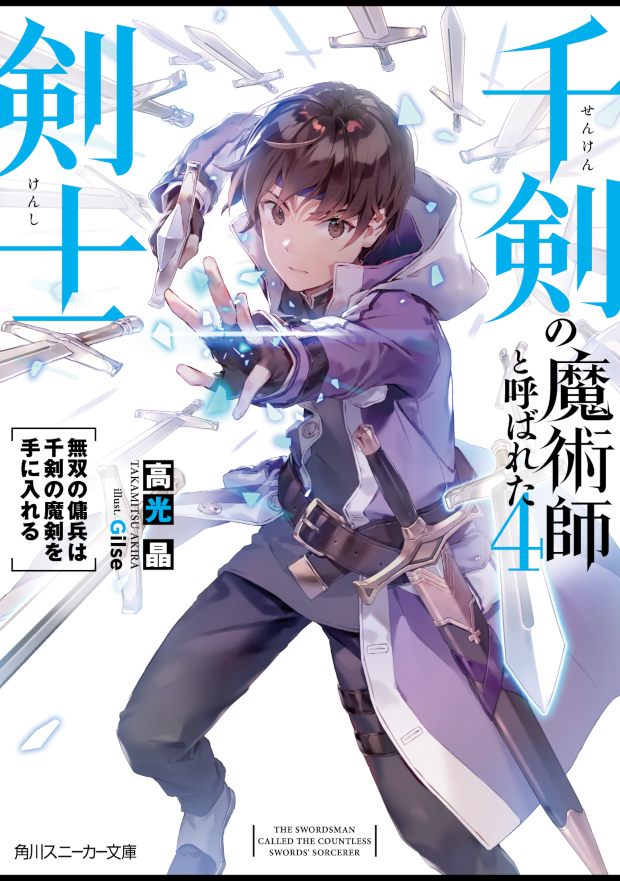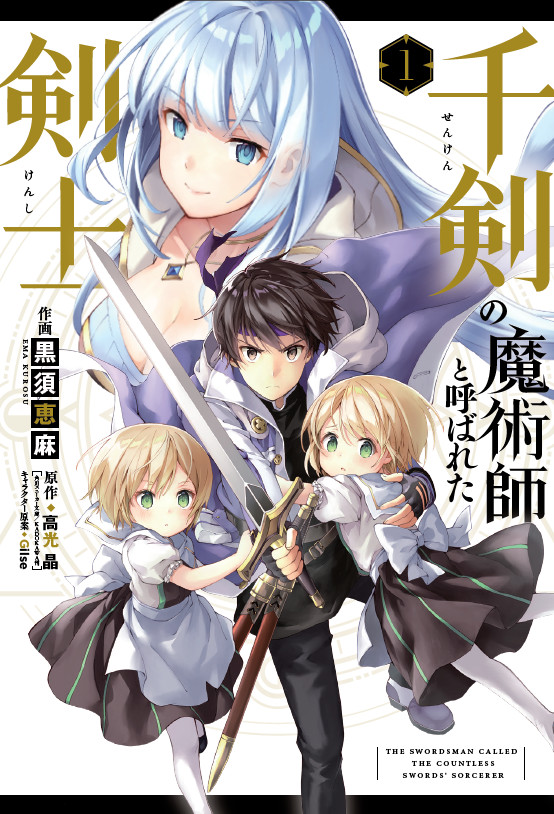第124話
両軍の先鋒同士が激突してから一時間。
中央部隊の後方に位置する王国軍の本陣へは、各部隊から次々と報告が届いていた。
「左翼部隊も敵右翼部隊と接触!」
「右翼部隊、敵左翼部隊を押し込みつつあり!」
「中央は戦力拮抗! 前進が止まりました!」
机上へ広げられた図面上には周囲の地形が描かれ、各部隊を表した模型が置かれている。報告にあわせて模型が動かされることで、将軍や参謀たちは戦場全体の情勢を本陣にいながら把握できた。
「勝てるのか?」
この場にいながら、図面を見ても戦場の状態を把握できていない唯一の人物が問いを口にする。
「はっ、殿下。戦力的に決して有利とは言えませんが、勝つための算段は立てております」
問いを発した主へ体ごと向き直って、副将を務めるオルトリヒ将軍が答えた。
副将の立場ではあるが、オルトリヒ将軍は実質的な最高指揮官である。彼が敬意をもって接する相手はこの軍にひとりしかいない。
それはつまり形式上の最高指揮官、ナグラス王家の第三王子その人である。
「敵の数はこちらよりずいぶん多いようだが……」
「それは否定いたしません。正面から消耗戦を挑めば先に崩れるのは我が軍です。ですがそうならないよう策を講じてありますので。おい、殿下にご説明を」
将軍はそばにいた参謀のひとりへと詳細の説明を指示する。
指示を受けた参謀が進み出た。第三王子の視線が妨げられないよう、机の脇に立って広げられた図面へと指示棒をのばす。
「現在我が軍は部隊を中央、左翼、右翼と分けております。帝国も同様に三方へ部隊を分けておりますので、いずれの部隊も正面から戦闘に突入しております」
第三王子が頷くのを見て参謀は説明を続けた。
「当然このままでは戦力に劣る我が軍が不利です。しかし我が国の密偵が敵の作戦情報を事前に入手しました」
「帝国の作戦情報を?」
「はい。そのため我が軍は敵の作戦情報を逆手にとって形成を逆転すべく罠を張っています。敵の作戦はこうです――」
密偵の掴んだ帝国の作戦情報。それは左翼部隊の後退で王国右翼部隊の突出を誘い、引き込まれた王国右翼部隊を背後から迂回させた部隊で側面から攻撃すると同時に欺瞞的後退をしていた帝国左翼部隊が反転するというものだ。
順調に作戦が成功すれば、元々数的に不利な王国右翼部隊は戦線を支えきれず崩壊するだろう。たとえ中央、左翼部隊が健闘しようとも、崩された右翼方面から本陣へ敵が流れ込んでくれば敗北は決定的である。
「しかも右翼部隊を側面から攻撃してくるのは、先の戦いで本陣を蹂躙した騎馬隊だそうです」
「南の大陸から送られてきた一軍とかいう、例のあれか」
「はい」
見慣れない獣に跨がった騎馬隊の正体をようやく王国側もつかみつつある。
その戦力はいまだに明らかとなっていないが、前哨戦での活躍ぶりを考える限り侮っていい相手ではないだろう。
「あの騎兵を追加で投入してくるというわけか……」
「ですからそれを利用します。騎兵が突撃してくるとわかっていれば、対策の打ちようもあるというもの。右翼部隊へは対騎兵用の装備を多く振り分けてあります」
参謀が具体的な作戦の説明をはじめる。
「敵の左翼部隊が欺瞞的後退をした際、それに引きずられぬよう追撃は控えさせます」
図上に配置された敵左翼部隊の模型を後方に動かし、その後ろから敵騎馬隊の模型を王国右翼部隊の前に移動させる。
「我が軍の右翼部隊は防御隊形にて敵の騎馬隊を迎え撃ち、盾と長槍で打撃を与えます。同時に戦力温存していた中央部隊主力と――」
王国中央部隊の模型を右翼部隊側に差し向け、敵騎馬隊の側面を突かせる。
続いて王国右翼部隊の後ろに置いてあった小さな模型を手にし、右翼部隊の右側を回り込ませて敵騎馬隊の側面にぶつける。
「右翼部隊後方に控えさせている我が軍の騎兵が左右から包囲して殲滅する、というのが作戦の骨子です。後退によって距離が離れた敵の左翼部隊が援護に戻ろうとしても間に合いません。例の騎馬隊さえ仕留めてしまえば、あとは勢いにまかせて敵の左翼部隊を屠ることも容易なことです」
三方の一角が崩れてしまえば戦線を保てないのは敵も味方も同じこと。
敵の策を逆に利用して帝国左翼部隊を破り、その勢いのまま本陣を突く。それが王国軍の立てた作戦だった。
「なるほど。左翼部隊が積極的な攻勢に出ていないのはそのためか?」
「お気付きでしたか。ご慧眼、感服いたします。左翼部隊の役目は陽動です。相手にこちらの意図を悟られぬ程度に攻めよ、と指示をだしております」
領軍や王都軍は敵の騎兵と左翼部隊にぶつけるため、王国側の右翼部隊と途中で転進させる中央部隊へ重点的に配置してある。
左翼部隊は民兵を中心に編成されている。その中にはトリア領軍も含まれていた。
あまりにも兵質が悪すぎては作戦の意図が漏れる可能性もあるとして、何処かの領軍が左翼部隊に配置されるのは当然としても、まさかトリア領軍の指揮官がそれを申し出るとは誰も思わなかった。
積極的な攻勢に出る予定のない左翼は安全と言えば聞こえはいいが、逆に言えば功績を立てる機会もない。
敵の作戦情報を入手し、それを利用することで勝機を見出していた各領軍の指揮官たちはトリア領軍指揮官の考えを計りかねた。
参謀部としてはトリア領軍を中央部隊か右翼部隊へ配置したいところだったが、他に左翼部隊への配置を望む者がいないのでは仕方ない。
やむを得ずトリア領軍を左翼へ配置し、それ以外の領軍を全て右翼と中央の主力部隊に振り分けた。
「だが中央部隊の先鋒は左翼と違ってずいぶん強引に攻めているのだな。敵も陣を固くして待ち受けているとのことだったが」
「さすがに左翼と中央の両方が消極的では敵も不審に思うでしょう。中央先鋒には全力で敵を突破せよと命じてあります」
「……損害は度外視でか?」
王子がその表情へ釈然としない感情を浮かべる。
「中央先鋒は傭兵部隊です。我が軍の兵士たちが消耗するわけではありません」
「しかし傭兵といえど我が国の民だろう?」
「恐れながら殿下。傭兵は国に対する忠誠などございません。我が軍に集まった傭兵すべてが我が国に住まう者ではありませんし、現に平時は王国へ居を構えながら今回の戦いでは帝国へ参じた者も多数おります。傭兵にそのようなご温情をお掛けになる必要はないかと」
「そういうものか……」
納得したわけではないだろうが、王子はそれ以上の言及を避けた。
作戦上有効な選択が道義上賞賛される選択とは限らない。
むしろ逆であることの方が多いだろう。
それを理解し、飲み込めるほどには聡い人物であった。
ここで王子が余計な口出しをしたところで現場にただ混乱を招くだけだ。
王子の価値観や気持ちなどお構いなしに戦況は刻一刻と変化しているのだから。
それを証明するように本陣へ伝令があわただしく駆け込んでくる。
「伝令! 右翼部隊が敵の左翼部隊を打ち破って敗走させつつあり!」
報告を受けてザワリと周囲の空気に雑音が走る。
この一戦において、王国へ勝利を引き寄せるため待ちに待っていた報告であったからだ。
それはつまり、今この瞬間が勝敗を分ける分水嶺であるという意味でもある。
オルトリヒ将軍は重々しく頷くと、すぐさま参謀たちに指示を出す。
「騎馬隊と中央部隊主力に伝令を出せ! 作戦通りの行動を開始せよと!」
「はっ!」
参謀たちの目に熱がこもる。
幾人かが伝令要員を呼びつけはじめ、忙しなく動きはじめた陣内において取り残されていた王子が将軍に向けて声をかけた。
「将軍、これはつまり――」
言葉の続きを無言で投げかけた王子に向けて、将軍は真摯な表情で答えた。
「はい。予定通りの展開です」
「狙い通りの展開だな」
ところ変わって帝国軍の指揮官が身を置く本陣。
王国同様に机上へ戦場を描いた図面が広げられ、その左右を挟むように士官が並んでいた。
士官の視線を一身に受けながら声を発したのは、帝国侵攻軍の指揮官である大将軍だ。
その年齢が三十代と若いながらもこれほど大規模な軍の指揮を任されているのは、本人が帝国内で有力な貴族の当主であるからだろう。
加えて、三代前に皇女が降嫁した家柄である。皇室の血縁ということで現皇帝から厚い信任を得ているという理由もあった。
「かかりましたな」
大将軍の言葉を受けて、左右に並んだ士官のうち最も近くに座る男が頷く。
「これでようやく肩の荷が下りる。エサに食いついてもらわねば、なんのためにここで王国軍を待ち受けていたのかわからなくなる」
「左様です。逸る兵どもを抑えて陣地構築に従事させた甲斐があったというものです」
王国の残存戦力を徹底的に叩きつぶし、阻む者がいなくなったところを王都まで進撃し、城下の盟を押しつける。それが帝国の狙いであった。
過去戦場で王国に勝利しながらも、結局帝都からの長い距離が障害となって撤収せざるを得なかったという苦い経験が帝国には幾度もある。
だが今回は同じ轍を踏まないよう、目標は徹底的に明確化されていた。
領土の占領ではなく、なによりも敵戦力の殲滅を優先することが開戦前から定められている。
そのために撒いたエサ。それが帝国左翼部隊を起点に展開する作戦情報だった。
「敵の右翼は我が軍の左翼部隊後退に乗じず、距離を置いているようです。流した偽情報に踊らされ、こちらを罠にはめたつもりなのでしょう」
この報告をもたらした末席の士官が発言する。
士官の言う通り、王国軍は帝国左翼部隊の欺瞞行動に対して距離を取っていた。
こちらの動きを逆手にとって罠を仕掛けるつもりだろうが、それこそが帝国の仕向けた罠である。
無論、王国軍がエサに食いつかなかったとしても何ら問題はない。
その場合は流した作戦情報通りにサンロジェル君主国の騎馬隊と左翼部隊で攻勢に出て、王国軍の右翼へ打撃を与えればいい。
決着まで時間はかかるだろうが、正面からぶつかれば数の多い帝国軍が有利であることに変わりはない。
ただその場合は、たとえ戦いに勝ったとしても敗残兵の多くを討ちもらしてしまう可能性があった。
だからこそ帝国軍は一計を案じ、王国軍の戦力へ決定的な打撃を与えられるようエサ付きの罠を仕掛け、事前に長い時間をかけて網を張っておいたのだ。
かくて王国軍はエサに食いついた。
勝ちの目を拾おうとして、手を出してはならないところに引き寄せられてしまったのだ。
帝国左翼部隊と距離を置いた王国右翼部隊は、おそらく騎馬隊の突撃に備えて守りを固めているところだろう。
だがそれが無駄な備えであることを帝国の士官たちは知っていた。
サンロジェル君主国の騎馬隊、彼らが駆る『飛馬』という生き物が帝国軍上層部の度肝を抜いたのはまだ記憶に新しい。
今度は同じ驚きを王国軍が味わう番だろう。
「王国将兵の驚く顔が目に浮かぶようだな」
士官たちの顔をひと通り見回した後、大将軍は端正な顔に人の悪そうな笑みを浮かべた。
2019/07/30 誤字修正 例え → たとえ