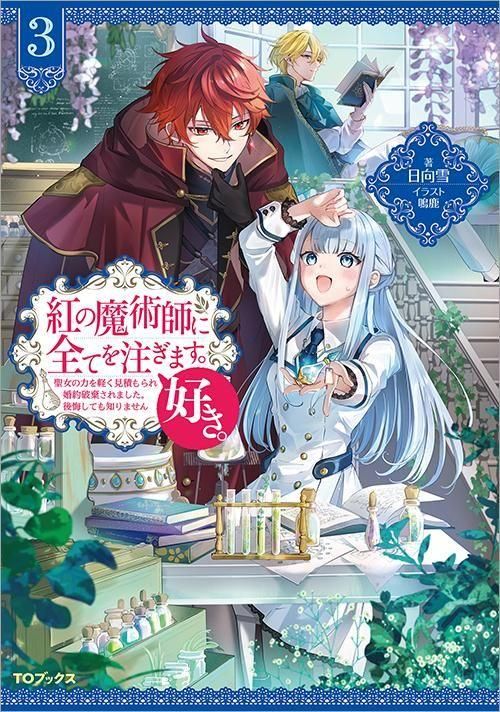422【20】『妖精の国の物語』
妖精の国というのは、やはりこう温かくて、淡いお花が咲き誇っていて、いつでも春のような陽気といいますか、そんなほわほわとしたイメージありますよね。
「シリル様、妖精の世界には七つの国がありまして、その国それぞれに守りの色を持っているんですよ?」
「へー……」
そんな遠い目をしなくとも? これはもちろんアクランド王国の成り立ちがベースになっている。
自国の物語のお茶だと思うと愛着が湧きませんか?
身近に感じるというか?
神話のようなお伽噺のような、そういうもの達に乗せて。
その上、健康茶という部分も欠かせない。
なんせ纏め掛けとはいえ、リフレッシュが添加されているのですから。
薄ーく。限りなく薄ーいリフレッシュがお茶で抽出出来ると考えると、大きな付加価値になる。
私は学生の頃に参加していた『雪の月、ハンドベル演奏会』を思い出していた。
あのベルを演奏する季節は決まっていつも寒い。年の終わりに教会が催すイベントだ。
学生聖女と現役聖女が集まって、ハンドベルを奏でるのだが、これはもちろん純粋な演奏会ではない。
只で施すこのイベントの一番の売りは、そのハンドベルの音に乗せて、聖魔法を奏でるところにある。
リフレッシュではなく、治癒の聖魔法を奏でる。
というのも、このハンドベルの演奏会に来る人は、庶民がメインで、庶民の為に施していると言っても過言ではない。そして庶民が欲しているのは大概治癒魔法の恵みだから。
治癒の聖魔法は神が聖女に託したものと言われている。
だから神の愛する子供達に、神に替わって聖女が聖魔法を施さなければならない。
スギナ茶に添加する魔術はリフレッシュだが、桑茶などは治癒魔術にしても良いかも?
効能が違うところがまた粋ではないか?
私は辺り一体に広がる貧しい土地を眺める。
貧しい土地。
それは神の振るサイコロのようなもの。
偶然の割り振り。
豊かな土地もあれば、貧しい土地もある。
けれど、人にとっては一生ものなのだ。
離れることのない、自分自身の一部のような、永続的なもの。
領民たちにもお茶を配りたいな?
彼らは貧しく、お茶など買えないから、何か正統な言い訳が欲しい。
無節操に上げては無くなってしまうし、けれど値段を付けたら誰も手に出来ない。
ほんの少しの努力で届く見返りのようなもの。
誰もが出来るようなものがいい。
貧しいばかりの領地でも、シトリー領らしい特典があったら嬉しいじゃないかと思う。
「うちの領は貧しいよ? だけどお茶だけは絶品だ」なんて領民が言ってくれたら素敵じゃないか。
実際、私は侍女で、魔法省の準官吏で、聖女なので薬草の世話もある。
なので大量のスギナを摘んだり、乾燥させたりという作業を常時出来ない。
そもそも領民のサイドビジネスにしたいのだから。
領民には乾燥スギナを領主館に持ってくるように言おう。
お金がないからお金では払えない。
だから、お代はリフレッシュ済みのお茶で払う。
十キロ持って来たら一キロのお茶に代えて。
軌道に乗るまでは、どうせ手元に金はない。それは致し方ない。
その条件で納得してくれる人だけで、細々と。子供のお手伝いくらいの感じで。
最初だけ魔法を掛ける場面を見せるのだ。
そうしたら、若干恭しい感が出る。
聖魔法ブレンドにしたよ? 家族全員で飲んでね? と一言添えて。
ちょっとやり過ぎ感があるかもしれないが、プラシーボ効果も出そうだし。
実際偽薬ではない訳なんだけど。免疫系の力というのは思い込みにも左右される。
効く効くと思った方が、疑うよりは効果が高い。相乗効果だ。
一キロ持ってきてくれたら百グラムか……。
子供ならそれくらいの量が丁度良いかな?
となれば各地の村長を呼ばなければ。
そして村長会で、土産としてスギナ茶を持たせよう。
村に帰ったら、お茶会を開いてもらい、村人に試飲してもらうのだ。
その上で乾燥スギナを一キロ持って来たら、このお茶百グラムと交換すると伝えて貰う。
領主館には秤と添加済みのお茶を置いて、交換台を作る。
良いじゃないか?
これ。
私は早速、今思い付いたばかりの案をルーシュ様とシリル様に伝える。
何か必要で何が必要じゃないかは机上でしか分からないから、やりながら試行錯誤してみよう。
きっとソフィリアの街の薬草店でも取り扱ってくれる。
最初の特約店はソフィリアの薬草店。
あと『魔術師達が集うお茶会の庭』
「シリル様? スギナの王子は王冠は外せませんよね?」
「……王冠」
「はい。色とりどりの精霊石が嵌められていて、きらきらきらきらしていて、お茶が美味しそうな王冠ですっ」
「……お茶が美味しそうな王冠???」
「そうです」
「そうなんだ」
「ぜひ」
「……うん」
ちょっとピンと来ていなさそうなシリル様にペンを取ってもらい、ルーシュ様の意見も聞きながら、私達は草地に座りながら、真剣に絵を描き始める。
何かこの絵こそがこのお茶の成否の要になるような気がして、私達三人は真剣に考え続けたのだ。