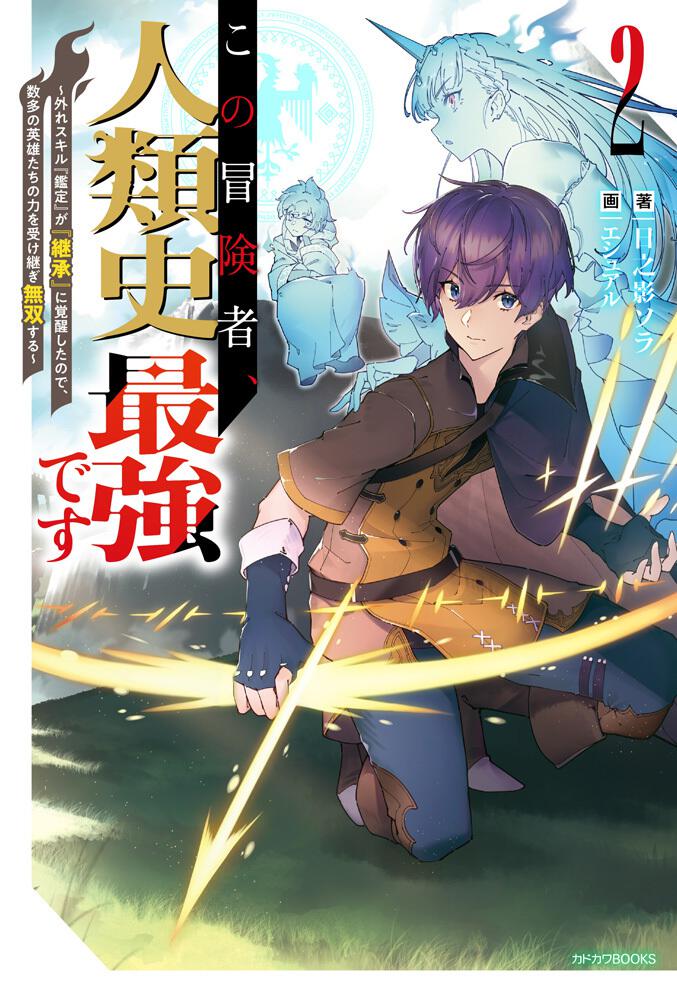4.決別と旅立ち
久しぶりに、私は実家に足を運んだ。
聖堂に入ってからは、生活のほとんどを王城の敷地内で過ごしていて、外に出る機会は限られていた。
良くも悪くも守られていて自由はなかった。
特に私の場合は、家にも居場所がなくて、帰る理由もなかったから。
だから素直に驚いた。
急に帰って来いなんて、言われるとは予想していなかった。
とは言え丁度良いとも思った。
地方への派遣まで一か月を切った。
そして私にも、専属の騎士が一人現れたのだから。
「やぁ、レナリタリー」
「アウグスト様?」
実家の屋敷に入ると、最初に出迎えてくれたのは両親でも妹でもなく、さわやかな笑顔を見せる金髪の美男子だった。
彼の名前は、アウグスト・シーベル。
上級貴族の中でも特に権力をもつ、五大貴族の一角シーベル家。
その次男にして、私の許嫁……今は婚約者。
「久しぶりだね。元気にしていたかい」
「はい。アウグスト様は、どうしてここに? もしかして、アウグスト様も招待されたのですか?」
「いいや、違うよ」
彼は首を横に振る。
「君を呼んだのは君のご両親じゃない。僕なんだ」
「え?」
「話したいことがあってね。ああ、ご両親なら不在だよ。貴族同士の会合に向われて、明日まで戻ってこないそうだ」
彼は淡々と話を続ける。
疑問に疑問が上乗せされて、話についていけない。
ただふと思い出す。
そういえば、屋敷の敷地に入ってすぐ停まっているはずの馬車がなかった。
あれはお父様たちが出かける時に使われるもので、つまりそういうことだった。
疑問へさらに、違和感も重なる。
私は不審に思いながら、彼に恐る恐る尋ねる。
「お話というのは……何でしょう?」
「ああ、大切な話だ」
「大切な……」
「そう。僕と君の、将来に関わることなんだ」
将来。
その一言だけで十分だった。
彼が私に何を言いたいのか……それを察するには。
「レナリタリー、君との婚約を解消したいんだ」
「え……」
驚くような声が出た。
自分の表情は見えないけど、たぶん悲しんでいる。
薄々わかっていたことでも、実際に突きつけられたら驚くらしい。
そんな風に考えられる程度には冷静で、思わず声や表情に漏れてしまうほどには、ショックを受けていた。
「すまない。本当は……こんなことを言いたくなかった。だが仕方がないんだ。だって君は、もうすぐこの地を去るのだろう?」
「それは……」
「聖女の務めを果たすために、君の行く場所はとても遠い。僕はこの国の貴族で、いずれ王政の一端を担う者だ。その僕が、統治もされてない辺境で過ごすことは出来ない」
尤もらしい理由を口にした。
申し訳なさそうに眉を下げ、悔いるように唇を紡いている。
だけどそれは、全て真実ではないと知っている。
口にしたことだけが理由ではないと。
とっくの昔に彼の心が、私から離れてしまっていると。
彼が私のことを、『レナ』と呼んでくれなくなった日に、誰と笑い合っていたのか。
私は見て、知っている。
その相手は――
「ごきげんよう、お姉さま」
「ラトラ……」
私の妹だった。
彼女はひらりと豪華なドレスに身を包み歩み寄る。
私の元ではなく、彼の隣に。
まるで、ここが自分のいるべき場所だと、私に見せびらかす様に。
「ご心配なさらないでくださいお姉さま。家のことも、アウグスト様のことも、私にお任せください」
「……」
ラトラはニッコリと微笑む。
無邪気に、天使のように。
その笑顔に、一体何人の男たちが騙されたのだろう。
内面は悪魔のように冷たくて、計画的で策略的で、私から色んなものを奪っていった。
容姿も、表向きな性格も、勉学の才能も、貴族としての気品も。
全て、何一つをとっても、私より優れてる彼女は、両親はもちろん周囲からも好かれ、期待されていた。
アウグスト様が彼女と親しくなっていることなんて、すぐにわかった。
「お姉さまは聖女として、立派に役目を果たしてきてくださいね」
「ああ。僕も期待しているよ」
やめて、そんなこと言わないで。
期待なんてしていない癖に。
その笑顔だって、何も詰まっていない空っぽだとわかっているから。
でも私には、文句を言う資格もない。
返せる言葉は一つだけ。
「はい」
ただ、身を引くしかない。
「話は……これだけですか?」
「ああ、そうだ」
「わかりました。それでは……失礼します」
まるで他人の家から去るように、私は二人に頭を下げる。
ここは私が生まれた場所で、私の家なのに。
今は何だか、知らない場所にさえ思えてしまう。
屋敷を出て、身体から何かがすーっと抜け落ちたような感覚に襲われて、ようやく私は気づいた。
私のことを縛っていた鎖が、繋いでいた縄が途切れたんだと。
そして同時に思う。
直感的に、あるいは確信をもって。
「さようなら」
私はもう、この屋敷に戻ってくることはないのだろうと。
それから一か月弱。
王城の聖堂で過ごす時間はあっという間に過ぎていった。
私は毎日のようにユーリと話しをして、一緒に練習を重ねて。
結局、何一つ上達はしなかったけど、少しだけ勇気を貰えた気がする。
「準備は出来てるか?」
「うん」
「忘れ物は?」
「ないと思う」
馬車に荷物を運び終え、私も一緒に残りこむ。
後からユーリが乗りこんで、馬に繋がった手綱を手に取る。
「あいさつしておく人は……大丈夫か?」
「うん、大丈夫」
そんなに気を遣わなくても良いよと、私は精一杯微笑んで返した。
「そっか。じゃあ、行こう」
「よろしくお願いします」
パチンと、ユーリが馬を手綱で打ち付ける。
馬は声もあげずに歩き出し、ゆっくりと一歩ずつ、確実に王城から離れていく。
私もユーリも、それから一度も振り返らなかった。
目指すは辺境の小さな町アトランタ。
私はそこで、聖女としての役割を果たしていく。