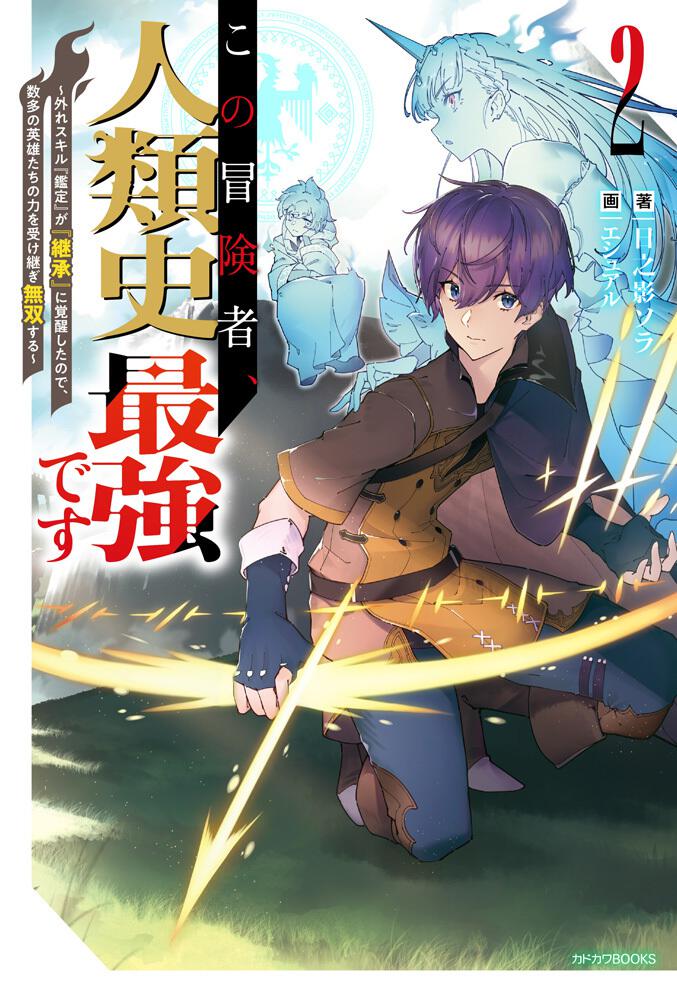3.専属騎士
騎士団の養成所には、将来騎士になるため集まった若い男女が、騎士としての立ち振る舞いや剣技を学ぶ場所だ。
最短で一年、長くても三年かけて見習い過程を終了したのち、騎士団へ正式に加入する。
条件はさほど厳しくない。
ほとんどが貴族の家柄か、元々騎士の家系に生まれた者が多い中、辺境の田舎暮らしの村人でも、素質があれば入ることが出来る。
彼、ユーリもその一人だった。
養成所でも聖堂でも、ここで身分は関係ない。
だけど、それはあくまで表面上だけのことで、実際には身分格差がある。
ユーリは諦めたように小さくため息をついて言う。
「タイミングも……悪かったんだろうな。今はちょうど俺しか田舎者がいなかったから、余計に悪目立ちしてさ」
「そう……なんだ」
彼の話を最後まで聞いて思う。
経緯は違うけど、私と彼はよく似ている、と。
大聖堂に居場所がない私と、養成所に居場所がない彼。
無個性の聖女と馬鹿にされている私と、辺境の田舎育ちだからと哀れな目で見られている彼。
言葉を並べると違いがあるように思えるけど、置かれている状況に大きな違いはない。
私も、彼も……一人ぼっちだから。
「無個性の聖女……か」
彼は思い出すかのようにぼそりと呟く。
「……はい」
「俺はそんなに詳しくないけど、その個性がないって珍しいことなのか?」
「えっと、今まで一度もいなかったみたいですよ」
「そっか」
一言に聖女と言っても、個人の特性や性格によって与えられた力は異なる。
祈りの形、と言い変えても良い。
その祈りが、何を司っているのか。
自然なのか、思想なのか、高位なのか。
あるいは概念や目に見えない心なんて場合もある。
聖女にとって個性は、力を増幅し強化するための起爆剤。
環境要因や、他者に与える加護の性質に関わる。
それがないという時点で、私は他の聖女たちに比べ一歩も二歩も遅れている。
「それに、そうでなくても私の力は弱くて、他のみんなに笑われてばかりで。もうすぐ聖堂を出るのに、専属騎士さんにも立候補者がいないですし……」
「ああ、専属の護衛騎士か。その、あれって立候補者がいない場合はどうなるんだ?」
「その場合は、当日に誰か配置されるはず。だから別に、立候補者がいなくても働ける。働けるけど……」
どうせ選ばれたその人も、ハズレくじを引いた気持ちになると思う。
私の成績で配置されるとしたら、間違いなく辺境の田舎。
誰も望んで行きたがらないような僻地だから。
穢れは人の多い場所でより強く現れる。
だから、強い力を持つ聖女は人口が多く発展した街へ派遣され、そうでない者は穢れの出現率が弱い場所に派遣される。
人口の少ない遠く離れた街で、見ず知らずの人と一緒に暮らす。
想像しただけで心がどんより暗くなる。
「知らない人となんて、絶対上手くやれない……」
不意に弱音が口に出ていた。
相手も似た境遇だったから、無意識に感情が漏れた。
私は膝を抱えて蹲る。
「じゃあ、俺が立候補しようか?」
「え?」
そんな私に、彼は思わぬ一言をかけてくれた。
驚いて顔をあげると、彼と目が合う。
「聖女の護衛。あれって君が派遣される時点で正規の騎士だったら問題ないんだよね?」
「そ、そうだけど」
「俺もちょうど同じ時期に養成所を卒業するんだ。一応配属先は決まってるけど、今ならまだ変更が効くはずだし」
「ま、待って、本当に?」
「ああ」
彼はまじめな顔で答え、こくりと頷いた。
その表情は嘘をついていないように見える。
だけど私は信じられなくて、確かめるように続けて聞く。
「わ、私が配置される場所は辺境ですよ? 一番成績悪いし、ずっと遠くの場所ですよ?」
「それは別に構わないよ。俺の生まれだって似たような場所だし」
「配属先が決まってるんですよね?」
「うん。だけど、たぶん騎士団に入っても、今みたいな扱いが続く」
「あ……」
その寂しそうな目が、全てを物語っている。
彼は続けて言う。
「騎士になったのは憧れだった。小さい頃に助けられて、自分も誰かを助けられるようになりたいって。その目標に場所は関係ない。それに……」
「それに?」
彼は私の顔を見て、恥ずかしそうに笑う。
数回目を逸らしながら、羞恥を乗り越えて口にする。
「ここで出会ったのは、運命なんじゃないかって思った」
「運……命?」
「そう。自分以外いなかった場所で、似たような境遇の人と出会えた。これを単なる偶然だとは思えない……いや、思いたくないのかもしれない」
偶然か、運命か。
私も、同じことを考えていた気がする。
初めて会うのに自然体で話が出来て、私のことを笑わないでいてくれた。
「何というか、上手く言葉に出来なくてごめん」
「ううん、私も……そう思う」
偶然じゃなくて、運命のほうだと。
「レナリタリー」
「レナでいいよ。呼びにくいでしょ?」
「じゃあレナ、改めて……俺が専属騎士に立候補しても良いかな?」
「……うん。私のほうこそお願いします。ユーリ君」
その日のうちに、彼は私の専属騎士に立候補してくれた。
私に立候補者が出たことはたちまち広がって、聖堂でも噂になる。
そしてその噂は、私の家にまで届いた。