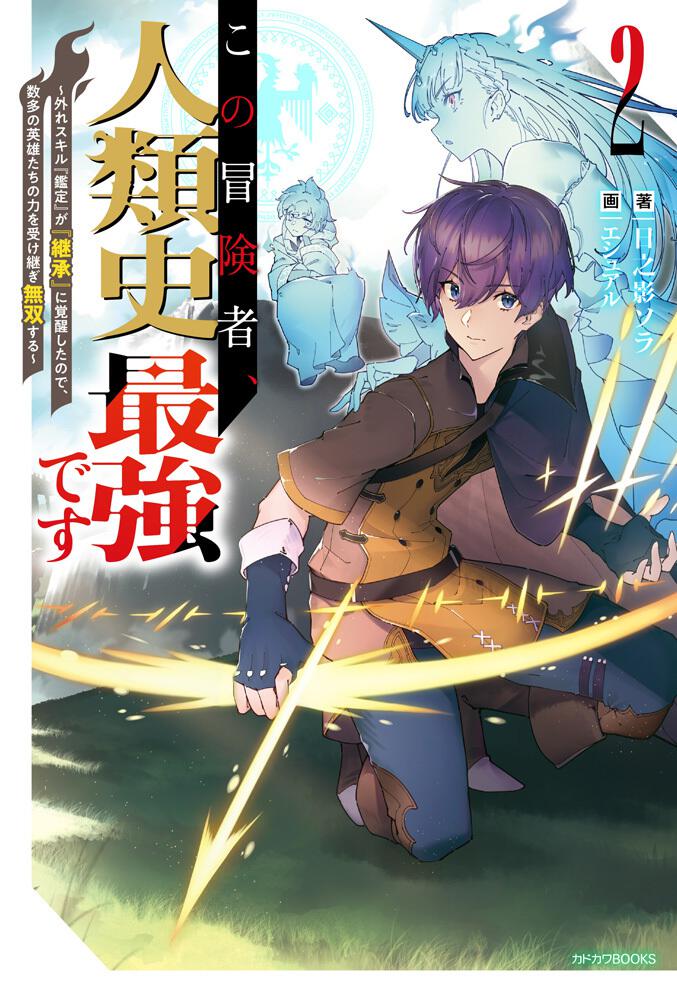11.嬉しい嘘
昼間だというのに森は薄暗い。
背の高い木々が多く、日光の大半を遮ってしまうせいだ。
その影響か、地面には草花はあまり生えていない。
ほどよくジメジメして、足元を冷ややかな風が吹き抜ける。
「寒くないか? レナ」
「大丈夫だよ。最近はとくに暖かくなってきたし」
「そう言う時こそ風邪をひくんだぞ。って、聖女って風邪とか引かないんだっけ」
「ううん、別に絶対じゃないよ。普通の人よりも病とかに強いだけで、疲れたり聖女の力が弱いと風邪も引くよ」
レナリタリーは続けて昔の話をした。
自分は聖女の力が弱かったから熱を出して寝込んだこともあると、恥ずかしそうに笑いながら。
辛い過去の話も、今は少しだけ軽い気持ちで話すことが出来るようだ。
そんな二人の間に、ジェクトが強引に割って入る。
「ねぇねぇーレナリタリーちゃん! ちょっと聞きたいことあるんだけど良い?」
「は、はい? 何でしょう?」
「いやさ? これからオレたち魔物と戦うかもしれないんだけど、それがもし穢れの影響だったら、オレたちには倒せないの?」
「いいえ。魔物が穢れに犯されている場合なら、魔物を倒せば穢れも散ります。散った穢れを祓うのは私たちの役目ですし、もしも穢れそのものが相手ならユーリしか倒せません」
説明しながら、レナレタリーはユーリに目配せをする。
小さく頷いたユーリ。
その様子が気に入らないジェクトは、図々しくもさらに質問を続ける。
「聖女と、聖女の加護を持つ者しか穢れは見えないし倒せない……か」
「はい」
「だったらさ! その加護をオレにもくれよ!」
「へ?」
レナリタリーは呆気にとられ、ユーリは表情は変えないままピクリと反応する。
不躾な要望だと感じるロイドとアリサは、不安げに様子を見守る。
「ほらほら、どうせ穢れと戦うかもしれないんだったらさ? そっちのほうが良くない? 今後にも繋がると思うんだよねぇ」
「そ、それは……すみません。その、私はまだ未熟で、加護は一人にしか授けられないんです」
申し訳なさそうな顔で断ろうとするレナリタリー。
事実、彼女は一人しか加護を付与できない。
ユーリに加護を与えている以上、他の第三者に加護を与える場合は一度解かなくてはならない。
「なら今だけのお試しでさ? オレに加護を移してよ」
「え、え?」
「出来るでしょ? オレのほうがこの森を知ってるし、騎士君も守りに専念できるじゃん? 何なら戦いの腕も上だと思うんだよね」
あからさまな挑発だった。
ユーリもそれに気づくが、毅然とした態度を崩さない。
一方のレナリタリーは、彼の下心なんて知りもせず、善意で言ってくれていると勘違いしていた。
その所為で断り辛く感じ、どうすればと慌ててしまう。
見守っていた二人もしびれを切らし、ジェクトを注意しようと動く。
「それは無理ですよ」
それよりも一歩早く、否定したのはユーリだった。
全員の視線が彼に向けられる。
「ユーリ?」
「……無理って?」
ジェクトは威圧的で睨むような視線でユーリを見る。
対するユーリは毅然と構え、ジェクトに答える。
「聖女には個性があります。彼女の個性は『絆』、加護を与えた者との信頼関係によって力が増幅されるんです。その性質上、一度加護を与えると変えられません」
「……へぇ、そうなんだ」
「ええ。ですよね? 聖女様」
「え、あ、はい! そうなんです」
それは紛れもない嘘だった。
ただ、この場で嘘だと気づけたのは、言い放った本人とレナリタリーだけ。
レナリタリーもユーリの嘘に合わせた。
困っている自分を助けるためについた嘘だとわかったからだ。
言われてしまえば仕方がない。
ジェクトは引き下がり、二人と距離をとるように下がる。
「ありがと、ユーリ」
「どういたしまして」
「で、でも嘘はよくないよ?」
「わかってるよ」
小声でのやり取りは、二人の間でしか聞こえない。
それでも、端から見て良い関係性だということが伝わる距離感にある。
「ちっ、何だよ」
「だから言ったでしょ? あんたには無理だって」
「ま、まだわかんないだろ! 穢れだか知らねぇーけど、魔物が出たら見せつけてやるよ。あんなヒョロヒョロよりオレのほうが強いってな」
「まだやる気なのね……」
呆れるアリサ。
ロイドはそんなアリサの肩を叩く。
「ロイドからも言ってよ」
「また迷惑かけそうなら止めるよ。でもたぶん、必要ないんじゃないかな?」
ロイドはそう言って前を歩く騎士と聖女を見る。
肩と肩が当たりそうなほど近い距離。
意識しているのか、していないのかはわからないが、二人の後姿に微笑ましさを感じていた。
「あの二人は、見ていて何だか安心するね」
「そうね。ちょっとまだ初々しいし、騎士君のほうはぎこちないけど」
「だからかな。応援したくもなる」
「ええ。それにくらべてこっちは……」
じろっと視線を向けた先には、一人やる気に燃えるジェクトの姿が。
「見てろよ~ つーかさっさと出て来いよ魔物!」
「駄目ね」
「はははは……」
呑気に進む面々だったが、まだ気づいていなかった。
すでに魔物のテリトリーへ足を踏み入れていたことに。