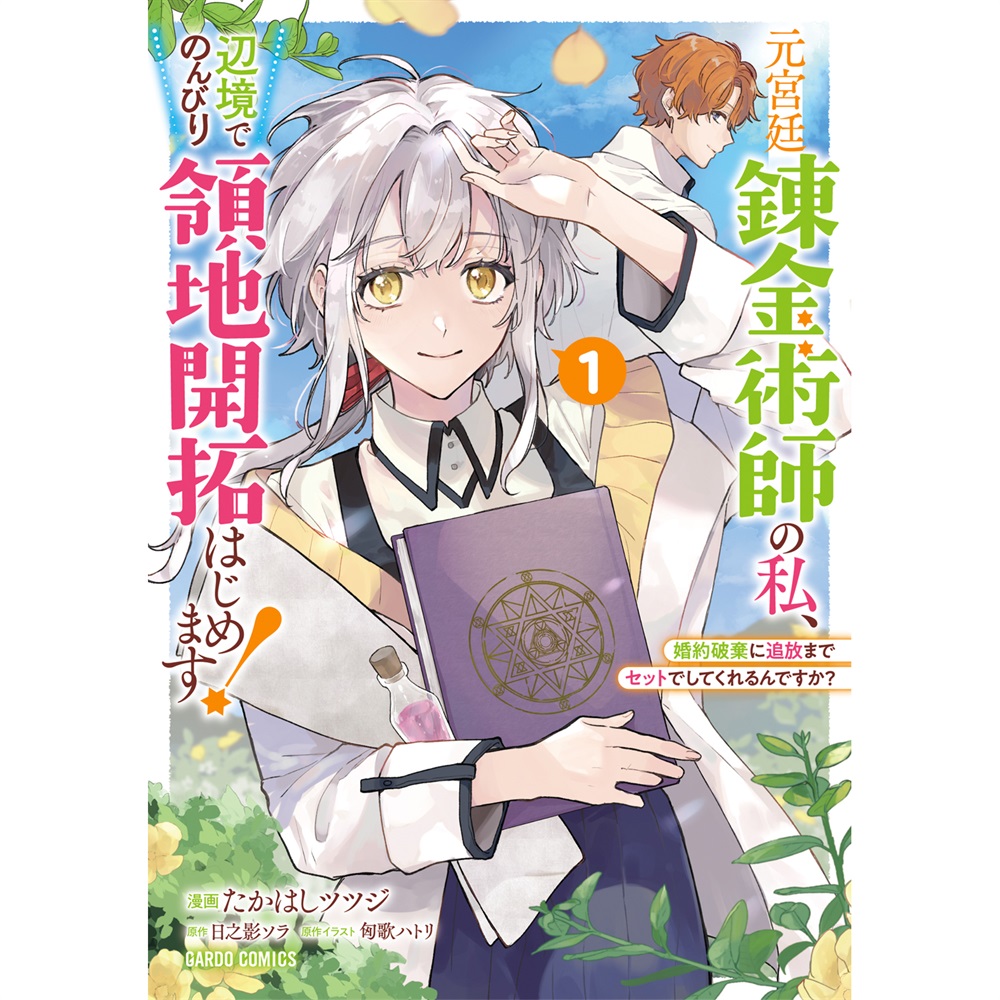勘違い勇者様が今日も求婚してくるので困っています
最近、とても困っていることがあります。
私一人の力じゃどうにもならないので、皆さんも一緒に考えてください。
時間は西の空に夕日が沈むころ。
東側の空はすでに夜へと変化し、西の空を暗く染めていく。
私は屋敷のベランダで、沈んでいく夕日を眺めながら、小さなため息をこぼす。
「はぁ……そろそろかな」
夕日がゆっくりと沈んでゆく。
オレンジ色の光が完全に消えて、夜空には星々と月が輝く。
昼と夜が切り替わる時間に、彼はやってくる。
沈んだはずの太陽がまた昇ったのかと錯覚するようなまばゆい光を放ち、私の前に降り立った。
「こんばんは! 愛しい僕のお姫様!」
「……またいらっしゃったのですか? 勇者アレス様」
「何度でも足を運ぶさ。君に会うためならね」
「……」
そう言って彼はニコリと微笑む。
さわやかな笑顔をみせられたら、どんな女性もたちまち恋に落ちてしまうだろう。
勇者アレスにはそういう魅力がある。
パーティーに参加すればたちまち女性で囲まれ、婚約の話を迫られるほどに。
そんな彼が……。
「今日こそ『はい』と言って貰うよ! アネーシャ、僕の婚約者になってほしい」
私みたいな男爵令嬢に求婚してくるなんて、一体誰が想像できるでしょうか。
一番驚いているのは私自身だった。
これで何度目だろう?
彼の求婚を聞き、それを……。
「お断りします」
断るのは。
十回目あたりで数えるのは止めてしまった。
求婚を断ると、アレス様は決まってガクッと膝から崩れて落ち込んでしまう。
「またダメなのか……」
「何度もお伝えしているはずです。何度求婚されようと、私はアレス様と婚約するつもりはないのです」
「どうして? 僕のことがそんなにも気に入らないのかい?」
「そうではありません。あなたは優れたお方です。それは私に限った話ではなく、世界中の人々が、そして……女神様も認めていらっしゃいます」
この世界で勇者に選ばれるということは、聖剣を抜く資格を持つことを意味する。
聖剣を抜く資格は女神によって、もっともふさわしく、愛おしい人間に渡されるとされていた。
彼は選ばれた。
聖剣に、すなわち女神に。
人類を守る最後の砦、守護者として。
彼はすでに、二度の魔王討伐を終えている。
どちらもたった一年足らずで旅を終え、見事魔王に勝利して世界を救った。
紛れもなく、彼は英雄である。
そんな彼のことを、快く思わない人間などいないだろう。
少なくとも善人であれば皆、彼のことを尊敬しているし、女性ならば迷わず好意を抱くはずだ。
けれど私は……いや、だからこを私は彼を拒絶する。
「嫌いではないのなら、理由を聞かせてくれないかい?」
「……それも何度もお伝えしているはずですが」
求婚を断り、この流れになるのも普段通りだった。
彼は膝をついたまま、物欲しそうな表情で私を見上げている。
話してくれるまで退かないと、強い意思すら感じた。
だから私のほうが折れて、何度したかわからない理由を彼に説明する。
「私では、アレス様と釣り合わないからです」
「そんなことはないさ! 君は素晴らしい人だと、僕は知っているよ」
「……ありがとうございます。アレス様にそう言って頂けるのは光栄です。ですが、そう思ってくださっているのは、アレス様だけなのです」
私は、世間一般で言うところの不遇な令嬢だった。
自分でそう思うのもおかしな話ではあるけど、事実そういう扱いを受けている。
私はこれまでの道程をなぞるように、アレス様に説明を続ける。
「私がいるロートラス家は男爵家です。貴族の中でも位は一番低い……王都に居を構える家柄の中なら、もっと相応しい名家があるはずです」
「地位に興味はないからね。僕だって、生まれは一般家庭、遠い田舎の出身者だ」
「アレス様は勇者という誉有る地位を獲得していらっしゃいます。その地位は、貴族の地位すら霞むほど大きなものです」
「僕は地位が欲しくて勇者になったわけじゃないよ」
「わかっております。アレス様は常に、人々の未来を考えている。だからこそ、尊敬されるべきお方なのです」
勇者に選ばれるということは、その者の善性を保証されていることを示す。
彼は悪にはなりえない。
地位や権力に固執し、利用しようとするなど考えられない。
そういう人間だとわかっているからこそ、誰もが彼と友好的な関係を築こうとする。
かくいう私が属するロートラス家もその一つ。
貴族としての地位が低いからこそ、勇者様と懇意になることで、他の貴族たちより優位に立とうと考えているのが、当主であるお父様の考え方だ。
そういう意味では、私はアレス様との婚約は、ロートラス家としても喜ばしいことだろう。
もっとも、なんの確執もなければ……。
「そこまで僕のことを評価してくれるなら、意地を張らず婚約してくれないかな?」
「意地ではありません。アレス様もすでにご存じのはずです。私が……ロートラス家の正式な令嬢ではないことを」
「妾の子という噂のことかい? あんなの気にしていなかったよ」
「……それはアレス様だけでしょう」
私は小さくため息をこぼす。
ロートラス家には二人の令嬢がいる。
私ともう一人、姉であるライカ・ロートラス。
対外的には姉妹だけど、私たちは本当の姉妹ではない。
五年前、私はロートラス家に養子として迎え入れられた。
一般家庭の生まれでありながら、突然貴族の家に引き取られるなど、相応の理由がある。
理由は単純だった。
私は、現当主のお父様と不倫相手との間に出来てしまった子供だった。
お母様はそのことを隠して生活していたけど、精神的に不安定になり、縋るようにお父様に自身の子供であることを告白した。
平民と関係を持ち、子供まで持ったなど大きなスキャンダルだ。
お父様はお母様から私を引き取ると、お母様との関係を完全に遮断した。
今となってはお母様がどこで何をしているのかも、私は知らない。
私はあくまで、養子として迎え入れられた子供、ということになっている。
ただし、貴族間の情報網は恐ろしく広く、早かった。
お父様は隠そうとしたけど、簡単に知られてしまい、噂は広まった。
以来、私はこの屋敷で腫物のように扱われている。
「位が低いだけでなく、望まれずに生まれた子と婚約など、貴族や王族だけでなく世間も認めてはしないでしょう」
「周囲の目がそこまで気になるのかい?」
「勇者の伴侶となれば、嫌でも注目されてしまいますので」
どんな目で見られるかなんて、考えるまでもない。
不遇な令嬢が勇者と婚約すれば、確実によくない波が押し寄せる。
環境が改善されることはなく、余計に悪化する未来が待っているだろう。
世間の目は優しくない。
人々の憧れ、平和の象徴が選んだ女性が、私のような誰からも愛されない令嬢では誰も納得しない。
よくて憐れまれるのが関の山だ。
私はそんなこと……望んでいない。
「関係ないさ。君にふりかかる障害は、僕が必ず取り除く」
「アレス様……」
彼はまっすぐに私のことを見つめてくる。
その瞳は煌めき、迷いは感じない。
なんて清らかな心の人なのだろうか。
勇者に選ばれるのもわかる。
でも、だからこそ、私が汚してはならない。
特に私のように、誰にも言えない秘密を抱えている人間は……。
「お気持ちは嬉しいですが、やはり私では不釣り合いです。私にはアレス様と釣り合うものが何一つありません。平凡以下の私に、勇者の妻は似合いません」
「そんなことはないだろう? 君にはあるじゃないか。優れた才能が」
「――! それは……」
「僕もいろんな場所を旅して、たくさんの人と会ってきた。中々いないよ? 精霊と心を通わせる人間は」
そう、彼は私の秘密を知っている。
精霊と意思疎通を図り、その力を行使することができる『精霊使い』であること。
貴族たちはもちろん、屋敷の人間すら知らない事実を、彼だけは知っていた。
「初めて会った時は驚いたよ。君がたくさんの精霊に囲まれているところ見た時はね」
「……私も驚きました」
遡ること、一か月前。
その日は、王城で開催される一年で一番大きなパーティーが開催された。
◆◆◆
「ライカ、明日には大事なパーティーが開かれる。名のある貴族、そして王族が参加される催しだ」
「はい。わかっておりますわ、お父様」
「うむ。ライカも今年で成人となった。そろそろ婚約者を見つけていい歳だ。このパーティーでよき出会いがあることを期待しよう」
「私も楽しみですわ」
明日に開かれるパーティーの話で、夕食の場は盛り上がる。
話しているのはお父様とお姉様だけだ。
私も参加することにはなっているけど、一切話題はふられない。
このまま無視されているほうが平和だから、早く食べ終わって席を外したかった。
「アネーシャ」
「――! はい」
お父様が私の名前を呼んだ。
久しぶりだった。
お父様に名を呼ばれるのは……数か月ぶりだろう。
自分で声をかけておきながら、お父様は嫌そうな表情をみせる。
「不本意ではあるが、此度のパーティーはお前も参加してもらう」
「私も……ですか」
「文句があるのか?」
「い、いえ……ありません」
大事なパーティーなのに、私を参加させていいのだろうか?
頭の中で浮かんだ疑問に応えるように、お父様は大きくため息をこぼして続ける。
「はぁ……本来ならば参加させる意味はない。だが此度のパーティでは、成人する歳の子は参加するようにと言われている。古い習わしだ」
そんな条件があったのか。
毎年あったのに、今年だけ私も参加するのはそういう理由だったのか。
私の年齢はライカお姉様と同じ、十六歳ということになっている。
実際の誕生日や年齢は、私たちにはわからない。
それを知っているお母様はどこかへ消え、お父様もその話に触れないから。
「いいか? くれぐれも目立つようなことをするな。お前はただ黙ってじっとしていればいい」
「はい」
「せめてライカの引き立て役にはなってもらうぞ」
「……はい」
「あまりアネーシャをイジメては可哀想ですわ、お父様」
「そうか。ライカは優しい子だ」
私は罵倒され、お姉様は簡単に褒められる。
優しいわけじゃない。
今だって、笑いながらこっちを見て、いい気味ねという心の声が聞こえてくる。
ライカお姉様は私のことを見下していた。
当然だろう。
この屋敷の誰もが、私のことを哀れな平民の娘として見ているのだから。
「お父様、お母様はどうされるのですか?」
「彼女は不参加だ。体調が優れないようなのでな」
「そうですか……残念です」
「ああ、まったくだ。誰かが現れなければ、彼女が病弱になることもなかっただろうに」
誰か、とは私のことを示している。
私の存在が知られてから、ライカの母親は体長を崩すようになった。
元々強くはなかったらしく、精神的に病んでしまったことが原因で、頻回に体調不良を引き起こすようになってしまったらしい。
お父様は私のせいだと言っているけど、これに関しては文句も言いたい。
最初に関係をもったのは自分なのに、それを忘れているのだろうか?
ともかく憂鬱な気分になりながら、私は翌日のパーティーに参加した。
会場は多くの参加者でにぎわっていた。
誰が誰なのかはわからない。
王都に居を構える貴族以外にも、他国の要人も参加しているらしい。
知り合いを見つけては談笑したり、挨拶をしたりする光景を見て、私は居心地が悪くなる。
「今年は特に多いな。誰か珍しい人でも参加されているのか?」
「お父様、あっちに人混みがあります」
「うむ。行ってみよう」
二人は人ごみに向かって歩き出す。
地位の低い家系であるがゆえに、こういう社交場での交友は必要不可欠となる。
二人とも表情には見せないが必死だった。
私のことなんて忘れて、そそくさと人ごみに消えてしまうほどに。
「……どうしよう」
置いていかれてはぐれてしまった私は、知り合いのいない中ポツンと会場に立っている。
誰も私のことなんて見ていない。
気づくことすらない。
二人も私がいないことなんて、パーティーが終わるまで気づかないだろう。
仕方ない。
どこか一人になれる場所で時間を潰そう。
そう思った私は、パーティー会場の外へと足を運んだ。
パーティー会場の外は、王城の私有地である庭だ。
今は会場内に人が集中して、外には誰もいなかった。
空気も悪くないし、ここなら落ち着くまで時間を潰すにはもってこいだろう。
私は目についたベンチに腰をおろす。
「隣いいかな? お嬢さん」
「どう、え?」
気づかなかった。
一人だと思っていた私は、聞き覚えのない声に答えかけて振り向く。
さっきまで誰もいなかったはずなのに、いつの間にか隣に男性が立っていた。
「あれ? ダメだったかな?」
「あなたは……!」
その顔を、腰に携えた剣を知らぬ者など、この王都には存在しない。
私は一目で悟った。
彼が名だたる貴族の名すら霞む存在、人類の希望……勇者アレスであると。
「申し訳ございません、アレス様! すぐに退きますので」
「いや、退かなくていいよ。一緒に座ろう。といか、僕のことを知っているんだね?」
「もちろんでございます」
知らない人間がここにいるなんてありえない。
むしろ意外だった。
なぜ勇者である彼がこんな場所に?
彼は年の大部分を、王都の外で活動している。
魔王や魔物の出現を察知すると、人々を守るために戦いに赴く。
帰還すれば大々的に報じられ、人々に祝福される。
いつ旅から戻ったのだろう。
そんな話は聞いていなかったけど……。
「お戻りになられていたのですね」
「うん、昨日戻ったところだよ」
「昨日……」
だからまだ発表されていないのか。
「なぜこちらに?」
「パーティーに参加してほしいと言われてね? あまり好きじゃないんだけど、王様がどうしてもっていうから参加したんだ」
「会場は……中です」
「知ってる。でも人が多すぎて、すぐ囲まれちゃって疲れたから逃げてきた。やっぱり参加するんじゃなかったよ」
彼は小さくため息をこぼす。
もしかして、二人が見つけた人混みは彼がいたから?
お父様が例年より参加者が多いと話していたのも、勇者様が参加されると知っていたからかもしれない。
「でも参加してよかったかな? 君みたいな綺麗な人と、お近づきになれたし」
「え……私……ですか?」
「君が以外にいないだろう?」
「わ、私の容姿など……褒めていただけるほどでは……」
「容姿もそうだけど、それ以外もだよ。キラキラして綺麗だなぁ」
「――!」
驚愕した。
後から考えれば自然かもしれない。
聖剣に選ばれるような人に、見えないはずがないだろう。
私の周りに集まる精霊の輝きが、彼には見えていた。
「君の周りにいるのは精霊だろう? そんな数が集まるなんて、よほど精霊に好かれているんだね」
「……そ、それは……」
「あれ? 違ったかな? 君は精霊使いだろう?」
「……はい」
隠していた秘密が知られてしまった。
これはよくない。
お父様やお姉様も知らない秘密が、よりによって勇者様にバレるなんて。
「わ、私はこれで失礼します」
「もう行くの? せっかくなら少し話さないかい? 中は騒がしいし、ここにいたほうが落ち着くと思うけどな」
「で、ですが私も……参加者なので」
「参加者なのに一人でこんな場所にいる。何か事情があるんでしょう?」
「――! それは……」
「僕は君に興味があるんだ。教えてくれないか?」
彼は私の手を握っている。
強くはないが、これはもう逃げられない。
悟った私は、彼と自己紹介と、精霊のことを隠している話を伝えた。
これが始まりだった。
彼と私の……不釣り合いな日々の……。
◆◆◆
「あの日から君のことばかり考えている。初めてだよ。心からこの人だと思ったのは!」
ハッキリと後悔する。
あの日、私はパーティーに参加するべきではなかった。
勇者が参加すると知っていたら、仮病でも使って参加を辞退していただろう。
予想外の事態だ。
一番予想外だったのは、勇者様が私に好意を示すようになったことだ。
「これでもたくさんの人と関わった。たくさん見てきた。その中で、君は一番美しい。姿も、心も他にない美しさがある」
「心なんて……見えないではありませんか」
「そうだね。でも君は、そんなにも精霊に好かれている。僕は勇者だから精霊が見えるし、関わることもできる。だから知っているんだ。精霊たちが好むのは、心が純粋で清らかな人だけだとね」
「……そうじゃない精霊も、いるかもしれませんよ」
少なくとも私は当てはまらないだろう。
彼は大きな勘違いをしている。
精霊の力を借りることができるのは、私が純粋なこの世界の人間ではなく、遠い世界の生まれ変わりだからだろう。
そうでなければ私が精霊に好かれるわけがない。
私の心は……ひどく汚れているのに……。
「精霊は本質を見抜くからね。どう取り繕っても悪人には懐かないように、悪い悪いと思っていても、根が善人なら好かれるのさ。だから僕は自分の目を、精霊たちを信じる」
「……」
「もう一度よく考えてほしんだ。僕は君に、本心から惹かれている。この一月君と話して、君がどういう人間なのかを肌で感じて、より強く思うようになったよ。君を救いたいとね」
「救い……たい?」
彼は笑う。
優しく、見透かすように。
「私は、救ってほしいなんて思ってはいません」
「本当にそうかい? 君は、今の自分に満足しているのかな?」
「……」
「君はいつも寂しそうな顔をしている。僕が来ると知りながら、夕暮れにベランダへやってくるのも、本当は孤独が嫌いだからじゃないのかな?」
「違います」
「強がらなくていいよ」
強がりなんかじゃない。
寂しさなんて感じないし、孤独を辛いとも思わない。
私がここにいるのは、ちゃんとした目的があるからだ。
彼がまだ気づいていないもう一つの秘密……。
知られるわけにはいかない。
特に、勇者である彼には。
「何度お願いされようと、私の意志は変わりません。正式な跡継ぎであるお姉様ならともかく、私との婚約など誰も認められないでしょう」
「関係ないよ。僕が婚約したいと思っている。あとは君の意思次第だ」
「無理をおっしゃらないでください……」
「無理ではないと思うけど、まぁいいさ。これ以上は困らせてしまうから帰るよ」
もう十分に困っています。
「また来るよ。それまで何度か、僕のことを考えてほしい」
「……」
ずっと考えていますよ。
あなたのことを。
いつ、どこで、何をしているのか。
何が得意で、何が好きで、弱点はあるのか……。
無敵の勇者様を――
殺せるのか。
「……はぁ、今日も無理だった」
殺せなかった。
手が届くほど近くにいたのに、殺す隙がなかった。
さすが人類の代表、最強の勇者だ。
そんな人を殺せるのだろうか?
甚だ疑問だけど、やるしかない。
それが私に下された……任務なのだから。
自室に戻った私は、準備をする。
食事?
お風呂?
明日の洋服?
否、暗殺のための準備だ。
「……この屋敷ともお別れになるかもしれないな」
私は普通の人間じゃない。
幼い頃から暗殺者の先生に鍛えられ、権力者たちの命令に従い、他人の命を奪う者。
この屋敷に潜り込んだのも、貴族の中に入り込み、彼らの情報を手に入れやすくするため。
そして、警戒されにくくするためだ。
依頼主は誰も、私が暗殺者であることを知らない。
依頼は全て先生の元に届き、その後で私に命令が下る。
故に誰も私の正体を知らない。
「ロートラス男爵も気の毒だ。損な役回りだね」
この家は、王都に居を構える貴族にしては目立たず、地位も低い。
故に隠れ蓑として最適だった。
ロートラス男爵は女遊びを影でしていたから、子供ができたと嘘をつき、利用するのは簡単だった。
もうわかると思うけど、関係を持ったというのは嘘で、先生がロートラス男爵を騙しただけだ。
私は誰の子供でもない。
本当の両親なんて、どこにいるのかも、生きているかさえわからない。
私はただ、命令されるままに人を殺す。
落ちているナイフと同じだ。
だから……。
「ごめんなさい。勇者様」
ナイフに意思はない。
あなたが選ばれた。
次のターゲットは、勇者アレス様だった。
一体誰が依頼したのだろう。
勇者を殺してほしいなんて、無理難題を押し付けてくる。
先生も意地悪だ。
私が勇者と関わりを持ったことを報告すると、この依頼の話をされた。
以前からあったのか、新しく現れたのか。
勇者が邪魔だと思っている人間が、この国にもいるらしい。
せっかく人類を救っているのに、恨まれるなんてかわいそうな人だ。
同情はするけど、任務は任務だから。
準備ができた私は、窓から外へ出る。
期限は勇者が次の旅に出てしまうまで。
これまでの周期を考えて、おそらく残り数日しかない。
もはや時間がなかった。
失敗すれば、私が不良品として処理される。
そういう世界だ。
死にたくないなら、殺すしかない。
今夜がラストチャンスだろう。
小さな精霊を一体、勇者アレスにつけてある。
彼がどこで何をしているかは、精霊が教えてくれる。
殺しに精霊を活用している私の心が綺麗?
「……そんなわけない」
誰より汚れているはずだ。
勇者の目も、精霊の目も節穴だと思う。
たどり着いたのは、勇者が寝泊まりしている宿屋だった。
おかしなことに、彼は今も宿屋を借りて寝泊まりしているらしい。
王城より、庶民的な暮らしのほうが楽なのだとか。
おかげで警備もいない。
私自身の気配も、精霊の力を行使して消している。
誰にも気づかれず、私は彼が眠る部屋に入った。
「やぁ、君から来てくれるなんて嬉しいなぁ」
「――!」
音も気配もなかったのに、気づかれた。
部屋に入った瞬間、勇者と目が合ってしまう。
すぐにナイフを取り出し殺そうとするが、戦闘力で勇者に勝てる人間など存在しないだろう。
難なく捕まり、私はベッドに押し倒される。
「ここまでかな?」
「……そうですね」
わかっていた。
こうなることは最初から……。
「僕に精霊が見える時点で、君の偽装は通じない。わかっていはずだ。それでも来たのは……なぜ?」
「……どちらにしても、失敗すれば死ぬだけですから」
もういいと思った。
何人も殺した。
悪人ばかりじゃない。
依頼されたら、善人だって殺さないといけない。
善悪なんて、依頼がくれば関係なかった。
殺せば慣れる。
先生はそう言っていたけど……。
「慣れなかった。全然、この手に残る感触は……消えてくれない」
人を殺した。
他人の一生をこの手で終わらせたという事実が、いくつも私の背に乗っている。
消えてくれない。
毎日毎日、殺した人間に殺される夢を見る。
もう、うんざりだ。
いい機会だと思った。
殺されるなら……。
「僕になら、殺されてもいいと思ってくれたのかな?」
「……かも、しれません」
「光栄だけど、残念。僕は君を殺さないよ」
「――! なぜ? 私はあなたを――」
殺そうとしたのに。
彼は笑う。
「言っただろう? 君を救いたいんだ」
「――!」
まさかあれは、令嬢としての境遇ではなく、暗殺者としての私に向けて?
つまり彼は、最初から気づいていた。
私が暗殺者で、自身の命を狙っていることを。
知った上で、毎日のように求婚してきたというの?
「どうかしている」
「それだけ本気だってことだよ。君が何者でも、僕が惹かれた事実に変わりはない。暗殺者なのに殺しを躊躇し、後悔する。そんな君の心が汚れているわけがないよ」
「――それでも……」
許されてはいけない。
「後悔があるなら、これからの行いで示せばいい。わからないなら、僕も手伝うよ」
「……」
あなたはどこまでも、肯定してくれる。
初めだ。
こんなにも、私個人を見てくれる人は……いなかった。
先生も、偽物の家族も……。
「アネーシャ、僕と一緒に来てほしい」
「それはできません。だって私は……」
ただ、あなたは知らない。
見えているようで、見えていないことがある。
私は絶対に、あなたの手を取れない。
最後の秘密を、初めて明かす。
「――俺は男ですから」
「――!」
嘘ではない。
正真正銘、私……いいや、俺は男の子だ。
女装しているのは、令嬢のふりをして相手を油断させるため。
顔つきが整っていて、女装するのに向いていたから、先生が普段からそうしていろと言った。
実際、女性だと思われると相手は油断してくれる。
「わかりましたか? 俺は男なので、」
「ふふっ、そんなことか」
「……は? そんなことって……」
「大丈夫だよ」
大丈夫って何?
まさか勇者様ってそっちの趣味があ……。
勇者に手をとられ、彼の胸に俺の手が触れる。
モニュッと柔らかい。
柔らか……柔らかい!?
「ま、まさか……」
「僕も、女の子だからね」
「なっ!」
驚き過ぎて腰が抜けそうになった。
ありえるのか?
知っているのか?
誰が想像できる?
勇ましき男として、人々から愛されている。
そんな人が……実は女性だったなんて。
「これでもう、障害はないでしょ?」
「……いや」
それは本当に……困ります。
【作者からのお願い】
新作投稿しました!
自信作です!
タイトルは――
『偽者に奪われた聖女の地位、なんとしても取り返さ……なくていっか! ~奪ってくれてありがとう。これから私は自由に生きます~』
ページ下部にもリンクを用意してありますので、ぜひぜひ読んでみてください!
リンクから飛べない場合は、以下のアドレスをコピーしてください。
https://ncode.syosetu.com/n8335il/