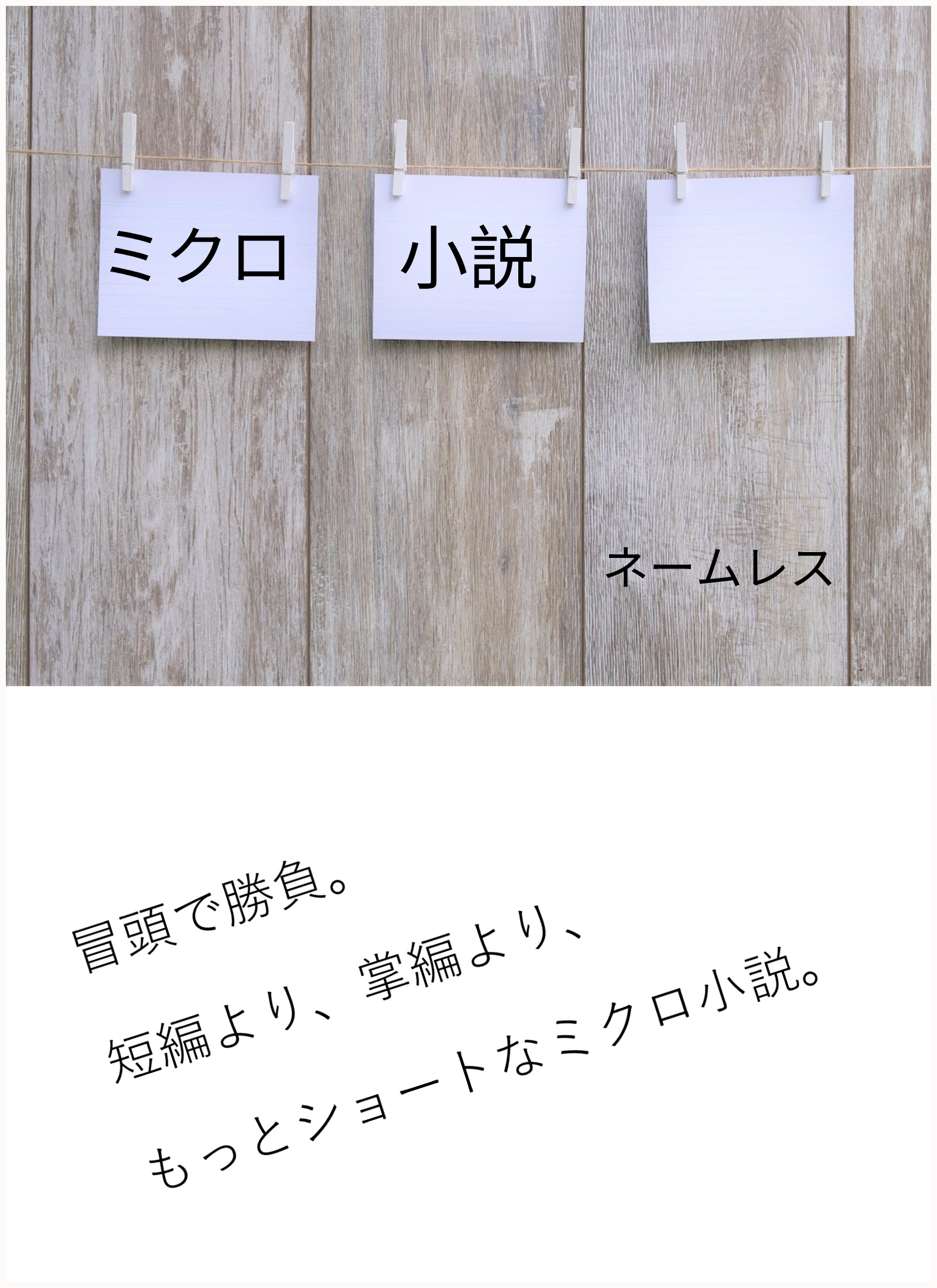第8話 6月8日 月曜日⑧
「えっと、まずは」
僕がそういったそばから彼女は体を小刻みに震わせ体半分で笑っていた。
とりあえずその態勢をなんとかしてほしい。
「いったん外に出てよ?」
「うん。わかった」
どのみち僕らは大人じゃない。
とはいえ高校生ふたりだ。
それだと電話ボックスには入れない。
入ったところでぎゅうぎゅうになっておそらく受話器も上げられないだろう。
となると彼女が公衆電話の前に立ち、僕がドアを押さえてうしろから指示するのがベスト。
彼女は大人しく電話ボックスから出てきた。
彼女はまずもって公衆電話の初心者だ。
さっきまでの不思議な行動の数々、まあドアに挟まって笑うのを抜きにしてだけれど……。
あれは「てへぺろ」ってわけじゃないし「ドジっ娘」ってわけでもない。
いたって大真面目にやっていたこと。
本当に公衆電話の使いかたがわからなかったんだ。
うん、わかるよ、その気持ち。
僕だって最初はぜんぜん使いかたがわからなかったから。
ただゆいいつ僕には最初から使いかたを教えてくれる人がいたから見様見真似でスムーズにできた。
まさか僕が誰かに公衆電話の使いかたを教える日がくるなんて思わなかった。
僕は片手でドアを押さえて――どうぞ、と彼女を電話ボックスの中へ誘導した。
「まずはその電話の受話器を持って。えっとその紐がついてるさきの部分のことね」
本当に公衆電話を知らないなら受話器さえわからないと思ったから前もって説明しておく。
「さすがにそれはわかりますよ~」
なぜか丁寧語で返してきた。
彼女は受話器をとって耳に当てる。
耳にあてる部分と会話する口元の部分が逆だったなんてことはない。
それをやったらさすがに狙ってるってわかってしまうから。
しかも受話器を逆に持った場合は構造上紐が邪魔になって使いづらい。
ここで僕はやっぱり彼女は本当に公衆電話の使いかたがわからなかったんだなーと思う。
それでいながらこの公衆電話を使いたがっているのは本当だ。
受話器を手にしてからあとの使いかたは彼女ひとりでもなんとなくわかるかもしれない。
「じゃあ。まずお金入れて」
「了解しました」
なぜだかすごくニコニコしている。
「誰かと話せるっていいね」
やっと電話ができる見込みがついて笑顔になったみたいだ。
連絡をとりたい相手に連絡をとれるっていうのはやっぱり嬉しいはず。
彼女は公衆電話の上にスクールバッグを置きバッグの中からカラフルな花柄がプリントされた「がま口」の財布をだした。
「がま口」の財布を使う高校もめずらしい。
失礼かと思ったけれど、それS町の大型スーパーの百均にも売ってた気がする。
彼女は「がま口財布」の「がま口」の上で密着していた球体と球体を指で弾いて財布を開いた。
財布の中で窮屈そうに四つ折りになっていた千円札を手にするとテレホンカードのところに挿入れようとしている。
お、たしかにそういう発想もあるかもしれない。
やっぱり公衆電話の初心者だと確信する。
「あれ? 入らない。そっか広げないとだめか~」
紙幣を広げても折ってもどんな形に変えても意味はないから、彼女が千円札を広げて試す前に止めないと。
「いや、あの、その電話に千円札は使えないんだ」
「え?! そうなの。でもこの薄い隙間なら絶対入るでしょ?」
う~ん、そういわれればあながち間違いじゃなかもと思ってしまう。
けれどテレホンカードは紙だろうか? 硬貨じゃない点でいえば紙の部類かもしれない。
でもあれは磁気だ。
形状でいえば薄くて平なのは一緒だけどよくわからない。
なんにせよ物理的に入るか入らないかは別として、そのテレホンカードを入れるところに紙幣は入らない。
だって公衆電話とはそういう構造だから。
と、思いながら僕も試したことはない。
じっさいやってみたらスルっと電話の中に入っていったらどうしよう? まあ、そのときはそのときで素直に謝ろう。
「ちょっと貸して」
僕は体を前のめりにして電話ボックスにすこしだけ割り込んだ。
試しに千円札を入れてみる。
物理的に千円札のさきは入ったけれどやっぱりなにもおこらなかった。
だよね。
「ほら?」
「本当だ」
「ちなみに五千円も一万円も入らないから」
これは知人にきいたことがあるから知っている。
五千円札と一万円札が無理なら、やっぱり千円札が入る確率も低いだろう。
「二千円は?」
え!?
その存在さえ忘れていた。
「いやそれ」
僕がつぎの「は」を言おうとしたときだった。
「入るわけないよね。千円も五千円も一万円も入らないのにさ。冗談」