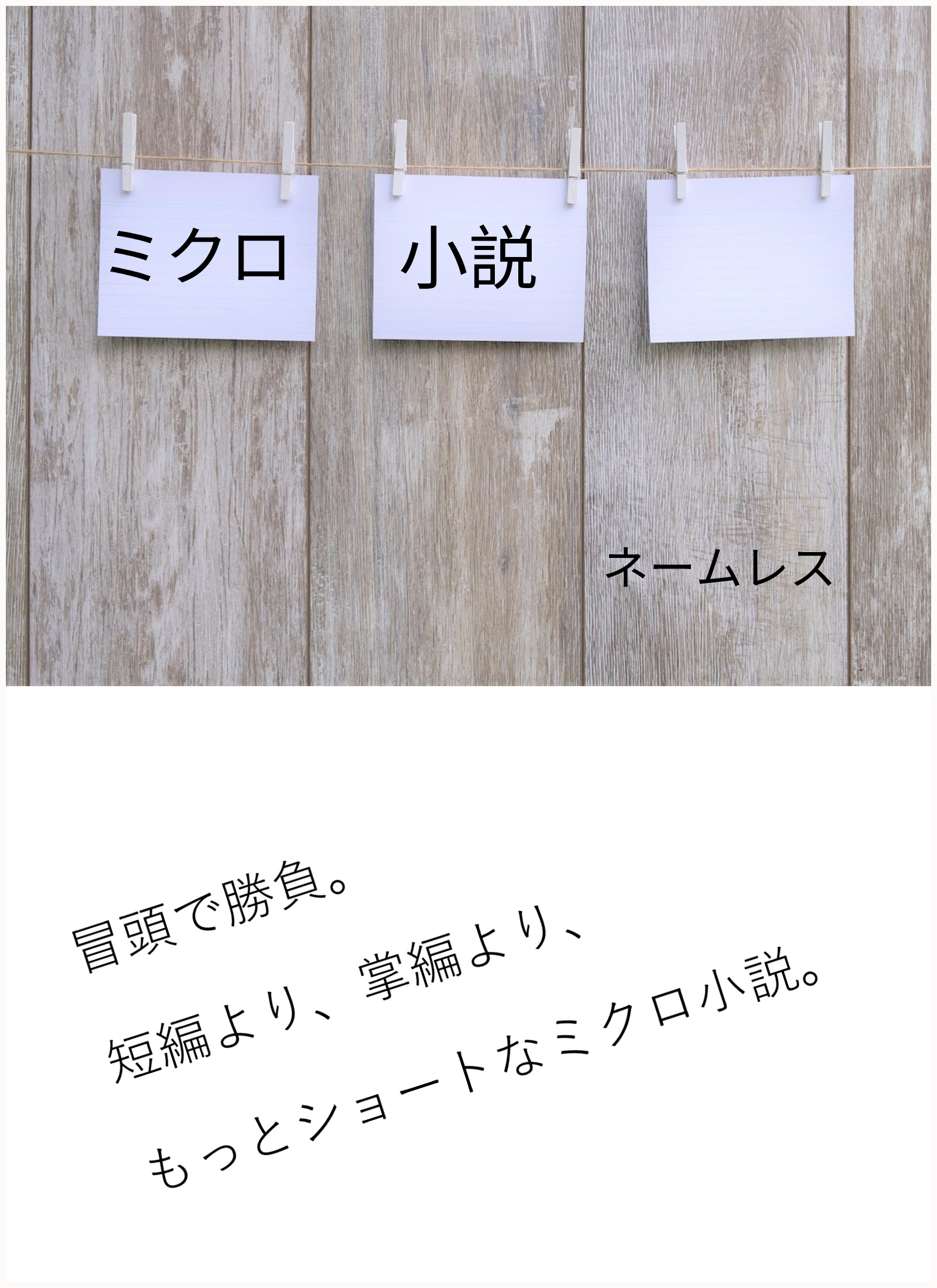最終話 6月30日 火曜日④
「そういえば山村さんスマホ持ってるけどまだテレカも持ってる?」
「そりゃあ。持ってるわさ」
わさ? これもなにかのキャラかな。
「おお、ちょうどいい。公衆電話って災害時には通信規制の対象外で優先回線になるし。停電してても使えるから肌身離さずに持ってたほうがいいよ」
「へー!! 目から鱗」
目から鱗で当然だと思った。
「まあ、そのときは無料で使えるんだけどね」
「目から鱗。でもテレカ関係ないじゃん」
「まあね。山村さん。この公衆電話からときどき山村さんのスマホに電話してもいい?」
こんなこと思ってないのに口のほうがさきに動いていた、ってことは思ってるってことだ。
もう、きみと連絡がとれなくなるのは嫌なんだ。
不意に口をついて出たテレカの話題もそういうことなんだろう。
彼女は首を傾げて考えこんだ。
「まあ。ときどきなら、ね」
でも、いいみたいだ。
「明日の電話はときどきになるかな?」
「う~ん。今日晩ご飯食べるから”ときどき”かな」
夕飯を一回食べると”ときどき”にワンカウントしてくれるらしい。
「そう。じゃあ明日、ときどき電話する」
僕は日本にない言葉をしゃべっていた。
「しょうがないな。私の電話番号教えておくね」
彼女はTwitterのアプリを閉じてスマホの設定からそのスマホの電話番号を表示させた。
「うん」
きみの番号なら菊池さんの十一桁よりも早く覚えられる気がする。
僕はスクールバッグから筆記用具をとり出して僕の生徒手帳のメモ欄を開いた。
「ここに書いて」
「私ね、頑張ってまた学校に行ってみようと思うんだ」
彼女は生徒手帳に数字を書きながら流すようにそう言った。
梅木さんもきみの諸事情を知ってるし、今ならいじめだってちゃんと刑事事件として捜査してくれるから大丈夫だと思う。
「応援するよ」
僕はわかってた。
だってきみは休学中なのにいつだって制服とスクールバッグ姿だったから。
きみが学校好きなこと知ってたよ。
S町の「X-Y=+3」の流入数「X」にならなくたっていい。
電話番号も教えてもらたったし、きみがまたふつうの高校生に戻るならU町に帰ったっていい。
「私は私の人生を取り戻してもいいんだよね?」
「うん。いいんだよ。お父さんはお父さん。きみはきみ」
母さんは母さん。僕は僕。
「うん」
僕は彼女から生徒手帳とペンを受け取りスクールバッグのなかから一昨日もらったLudeの漣プロデュースの試供品のシャンプーとリンスをとり出した。
いつかを信じて持ち歩いていた甲斐があった。
「あと、これきみに」
「なに?」
「Ludeの漣って人がプロデュースした試供品」
でも、あまり喜んではくれなかった。
なんでだろう? マウントレーニアのバニラモカのほうがよかったかな? やっぱり僕には女子高生の心はわからない、かも。
「山村さん、好きなんだよね? Lude?」
「Ludeの好きは曲が好きっていう部類」
彼女はそこで言葉をいったん切った。
そしてまた――で、といってもう一度、言葉を区切った。
僕は電話ボックスの中でいまだ宙吊りになっている受話器に気づいた。
あ、あとで菊池さんに謝らなきゃ。
あれからほったらかしだし。
とっくに電話は切れているだろう。
菊池さんの声はもう聞こえてこなかった。
僕が公衆電話からまた彼女に視線を戻すと彼女はLudeのシャンプーとリンスを指差しながら――本物の好きはこっちじゃなくてと言った。
どういうことだろう? 彼女の指先がシャンプーとリンスからわずかに逸れた。
ん? なに? まあ、いっか。
僕は諸事情で彼女にあえて訊かなったことがある。
それはあの白い封筒のお金ことだ。
いまだに家に保管してあるけどいつかまとめて返そうと思っている。
本当のところあの白い封筒は慰謝料とかそういうのじゃなくて山村さんが僕に山村さんを見つださせるためのヒントだったんじゃないか? まさか何ヶ月もずっとお金を入れつづけて僕がそのままなにもしないでいるとは思わないだろう。
――気づいて。
親のこともあるけどそんなふうに僕に助けを求めてくれていたんだとしたら嬉しい……まあ、勘違いか。
僕は強くもないし頼りにもならない。
「110」にも「119」にもなれない。
でもこれからもきみが僕を選んでくれたらいいなと思う。
そうなれるように努力する。
だって僕にはどうしても叶えたい夢ができたから。
明日から七月。
北海道の多くの高校生の制服が夏服に変わる。
この電話ボックスに微かな夏の匂いが流れてきた。
六月の半ばに感じた風だって、夏至のときに吹いていた風だって黙々と季節を進めていたんだ。
心機一転、僕らもまたふつうの高校生に戻るとき。
グラハム・ベルが発明した電話によって僕も彼女も傷つけられたけど、その分救われもした。
光ケーブルが主流にはなってきてはいるけど、かつてインターネットをするのに電話線は必要不可欠だった。
それこそブログをするのだって、Twitterなんかのスマホのアプリを使うのだってそうだ。
僕はグラハム・ベルの功罪を感じながら彼女の電話番号が書かれた生徒手帳を制服の内ポケットにしまった。
「ねえ。マウント。レーニア。飲みに。行こ。う。よ」
彼女はまた何かのキャラの真似をした。
ん……? この独特な言葉の区切りって。
そっか時報のときの女の人の口真似だ。
彼女は僕が彼女と出逢った6月8日とはまるで別人のように晴れやかな顔で笑っている。
僕の未定になっていた僕の進むべき路も拓けてきた。
進学とは違う進路。
僕はインターネット系の犯罪を少しでも減らせるように、サイバー犯罪対策課のサイバー捜査官になろうと思う。
それが新たな夢だ。
僕もまた明日から学級の中で止まっていた、いや自分自身で止めてしまっていた時間を動かすんだ。
北海道の短い夏の始まりとともに。
END