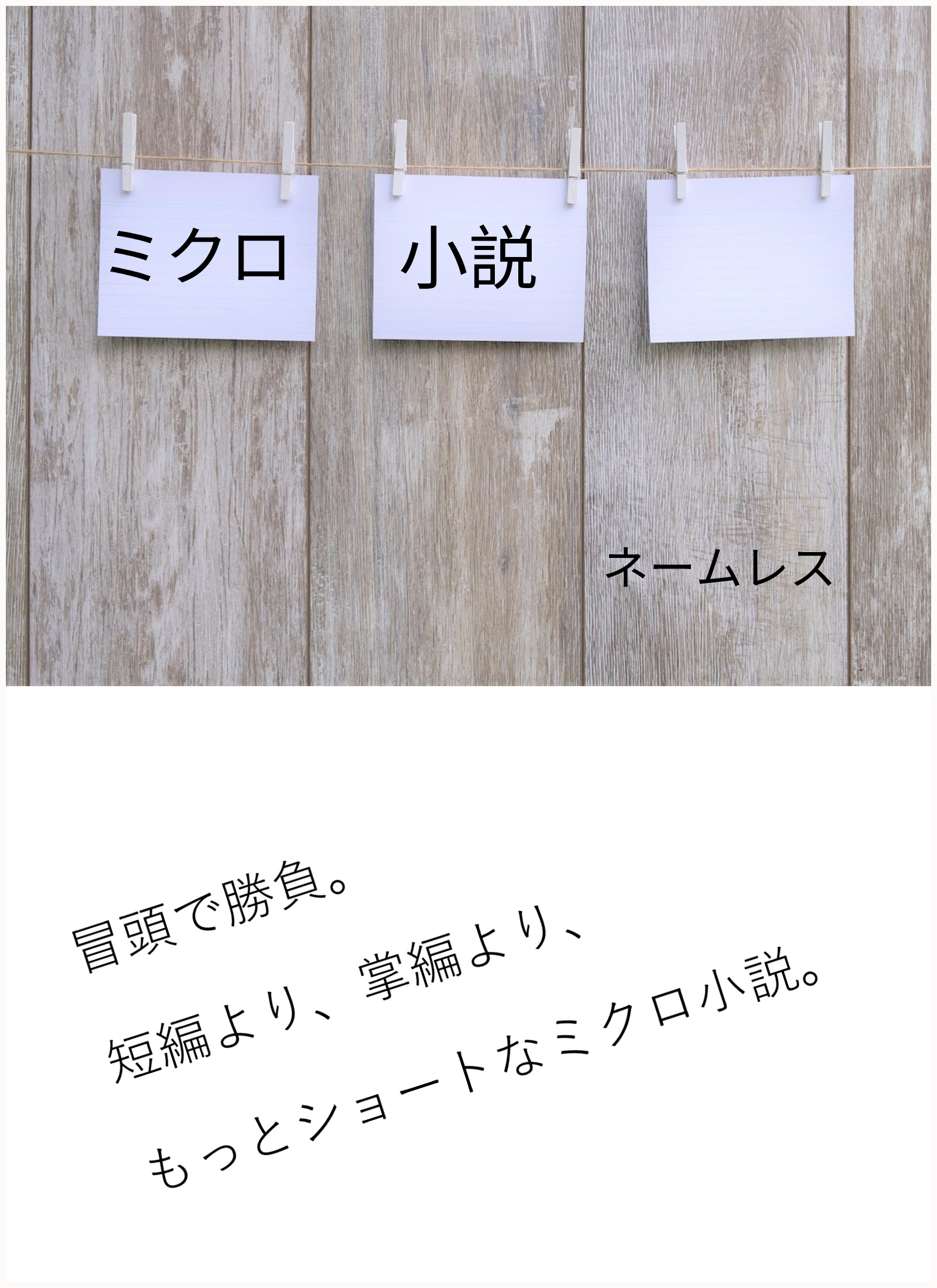第30話 6月10日 水曜日⑥
彼女はまた「へー」とか「ほー」と言っていた。
「117」に関しては昨日電話かけたし、で終わった。
これで昨日、僕が彼女に頼まれた約束は果たした。
でも考えようによっては明日会う理由がなくなった、ともいえる。
約束の力がないとすこしだけ不安になる。
「よし。じゃあ私の1パワーで111にかけてみよう」
怖いっていってたわりには乗り気だ。
さっきの都市伝説で逆に興味を持たせてしまったかもしれない。
まあ、「111」は人工的な機械のシステムだから。
「1パワーでたりるかな?」
僕もすこしだけ話に乗ってみる。
「たりなかったら私のテレホンカードの2パワーでも3パワーでも使っていいよ」
あ、僕は今日まだ菊池さんに電話をかけてなかった。
いつの間にか僕はこの瞬間を楽しんでいた。
いつ以来だろう? 時間を忘れて楽しいなんて思ったのは。
「ごめん。諸事情でちょっと電話かけなきゃ」
「あ、そうだね。うん。いいよ」
僕は制服の内ポケットから生徒手帳を出して中に挟んであった残り「10」パワーのテレホンカードを出した。
「……にしかわたくみ……S町の?」
彼女に突然名前を呼ばれて驚いた。
「えっと、そうだけど」
なんで知ってるんだろうと思ったけど僕自身が僕の名前が載っている生徒手帳の表紙裏のページを開いているのが理由だった。
「東西南北の西に難しくないほうの川。拓海は手偏に石と海で西川拓海。だけどそれが?」
「へ~」
彼女の声のトーンが弱まった。
「家ってこのへん?」
「ここからでも屋根だけ見えるよ。ほらあの青い屋根の家」
つい答えてしまった。
「……」
彼女はまた沈黙した。
「ここから屋根が見えてるのに電話ボックスで電話するなんてやっぱり諸事情だね?」
「え、あ、うん。ま、まあ、ね」
昨日の前言撤回をさらに撤回する。
諸事情は便利だ。
僕の複雑な事情を言わなくていいから。
「じゃあ、電話してくる」
「うん」
電話ボックスに半分入っていた彼女は彼女のものではないけどドアを開いてそのドアを僕に渡してくれた。
いつもどおり菊池さんに電話する。
今日も母さんの状態はあまりよくなかった。
でも、いつもこんなときは心がドンと沈むのに今日は違う。
僕は菊池さんと空っぽの話をしていた。
電話ボックスから五メートルくらい離れた歩道で石ころを蹴っている彼女をなるべく待たせたくなかった。
彼女といってもそれは三人称の「彼女」のこと。
うわのそらで話しを終えたテレホンカードの残りのパワーは「9」になっていた。
公衆電話から出てきたテレホンカードの「10」の右側に新しい穴がある。
いよいよ百円をきったか。
電話を終えて彼女のところに行くと彼女は僕を笑顔で迎えてくれた。
「もう行かなきゃ。じゃあ、また……」
読んでいた本のつぎのページが突然なくなったような急な反応に思えた。
気のせい? 本当なら僕が電話しているあいだに帰っていてもいいはずなのに。
でも電話が終わるまで待っていてくれた……。
考えすぎか?
彼女にも都合があるだろうし。
それに、たしかにまたって言った……。
彼女はまた明日もU町からここにくるんだろうか? 彼女はまた道の駅へのほうへと歩いていった。
その背中がすこしづつ遠ざかっていく。
「また」は約束なのだろうか?
そういや彼女は僕の名前を知っているけど僕は彼女の名前を知らない。
U町の女子高生なのは確かだと思うけれど……。
知りたいけど不躾な詮索はしない。
僕があとひとつ彼女のことで知っているとすればLudeが好きということだ。
僕は「9パワー」を使って「117」の時報に電話をした。
今の時刻は四時三十五分。
家に戻って大納言のアルバイトに行かないと。