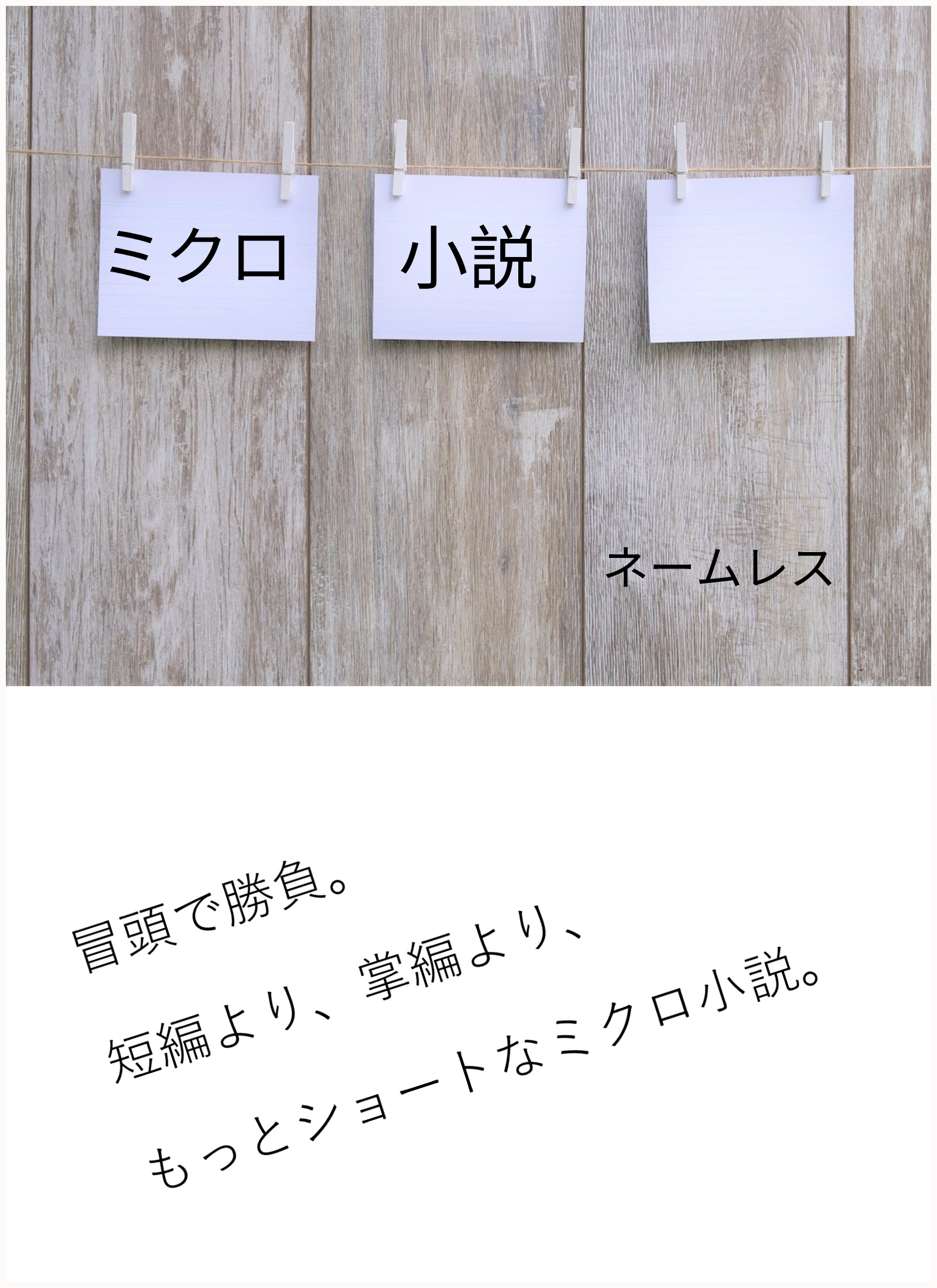第29話 6月10日 水曜日⑤
五時間目、六時間目の授業を終えてさらにホームルームのあと教室の掃除をしてから校門を出た。
今日、理髪店は休みだった。
登校時間のときはまだ理髪店の営業時間外で気づかなかった。
定休日じゃなくても休む日もあるか。
左側の新築のアパートの工事現場では作業員の人たちが足場の上で一生懸命に働いていた。
休む人がいれば働く人もいる、長い人生、多少は休んだっていいのかな? その問いの答えは僕にはわからない。
今日はコンビニ寄らず学校から「ブランデンタルクリニック」のところまで一直線に進んだ。
そこで右折して調剤薬局のところ行くと、あの娘がすでに電話ボックスにいるのがわかった。
心が高揚んだ。
もうどこかに電話をかけたあとだろうか? 彼女は僕が電話ボックスに近づいていくのに合わせて彼女も電話ボックスのドアをすこしづつ開いた。
ちょうど僕が電話ボックスの前についたと同時に彼女はまた電話ボックスのドアに挟まった。
「やっぱり誰かと話せるっていいね?」
誰かと話し終えたあとか? もう公衆電話には慣れたみたいだ。
「使いかた覚えたんだ? んで、昨日言ってたこと今日学校で調べてきたよ」
「お?! 仕事早いね~」
僕はなんだか”できる人”みたいに思われて嬉しくなった。
「まずは11のあとの1ね」
「うんうん」
そううなずく彼女のスクールバッグには「L」というアルファベットのキーホルダーがあった。
今まで見落としていたけれど、そのロゴ、Ludeのキーホルダーだったんだ? 秋山さんがいっていたように流行に敏感な女子ならLudeを先取りするのかもしれない。
彼女もやっぱりふつうの女子高生なんだ。
たぶん僕が最初に会ったときもこのキーホルダーをつけていたんだろう。
そもそも僕がLudeの存在を知らなかったからな。
「つまり111の電話番号のことね」
僕が身振り手振りで伝えると彼女は僕の一挙手一投足を真剣に見てくれた。
「うん」
「111は折り返しの番号」
「折り返しって?」
彼女はきょとんとして目を丸くした。
「111にかけると自動で折り返し電話がかかってくるんだって」
「怖っ?! わ、私それ系苦手なのよ」
怖い話が苦手って? 意外ってわけでもないか? なんとなく僕の心がまたそわそわした。
彼女にだって怖いものがあって……いや、やめておこう。
「そういう機械的なシステムなんだよ。幽霊とかじゃないから」
きみは知らないかもしれなけど心をなくした人間より怖いものなんてないよ。
「おっとぉ」
彼女は――おっとの”と”の語尾を上げた。
「ならいいよ。つづけて、つづけて」
いわれた僕は順番に「112」「113」「114」がどこに繋がるのかを伝えた。
彼女は「ほー」とか「おー」とかリアクションをとる。
なかでも電話機が壊れてるのかどうかがわかる「113」に感心し目から鱗を落とした。
「んで115は電報ね」
「電報ってあの結婚式とかの?」
「そうそう」
「結婚ってさ……」
彼女はそこでいい淀んだ。
「いや、ううん、いいや」
なに?って訊こうと思ったけれど僕は冷静に諸事情で収めた。
「そういや111の怖い話もあったな」
僕はさっき隠していた「111」にまつわる別の都市伝説も引っ張り出してみた。
話題を変えるのにこの選択は間違いだったかもしれない。
「ガ、ガクブル」
言葉でガクブルといわれてもいまいち怖がっているようには思えない。
でも、上手くこの場の空気を変えられた気がした。
本当に怖い都市伝説を披露するつもりはないから軽めの話で抑える。
彼女を怖がらせたいわけじゃないんだ。
ただ、すこしだけ距離が近くならないかな?とかの淡い期待だった。
クラスの男子が夏場に女子を集めて怖い話をしてたけれどこういう感覚なんだろうか? リアクションが嬉しい、みたいな。
彼女は”結婚”という言葉になにを隠したんだろう? そしてまた電報の「115」から後半の番号の「116」「117」「118」「119」までを教える。