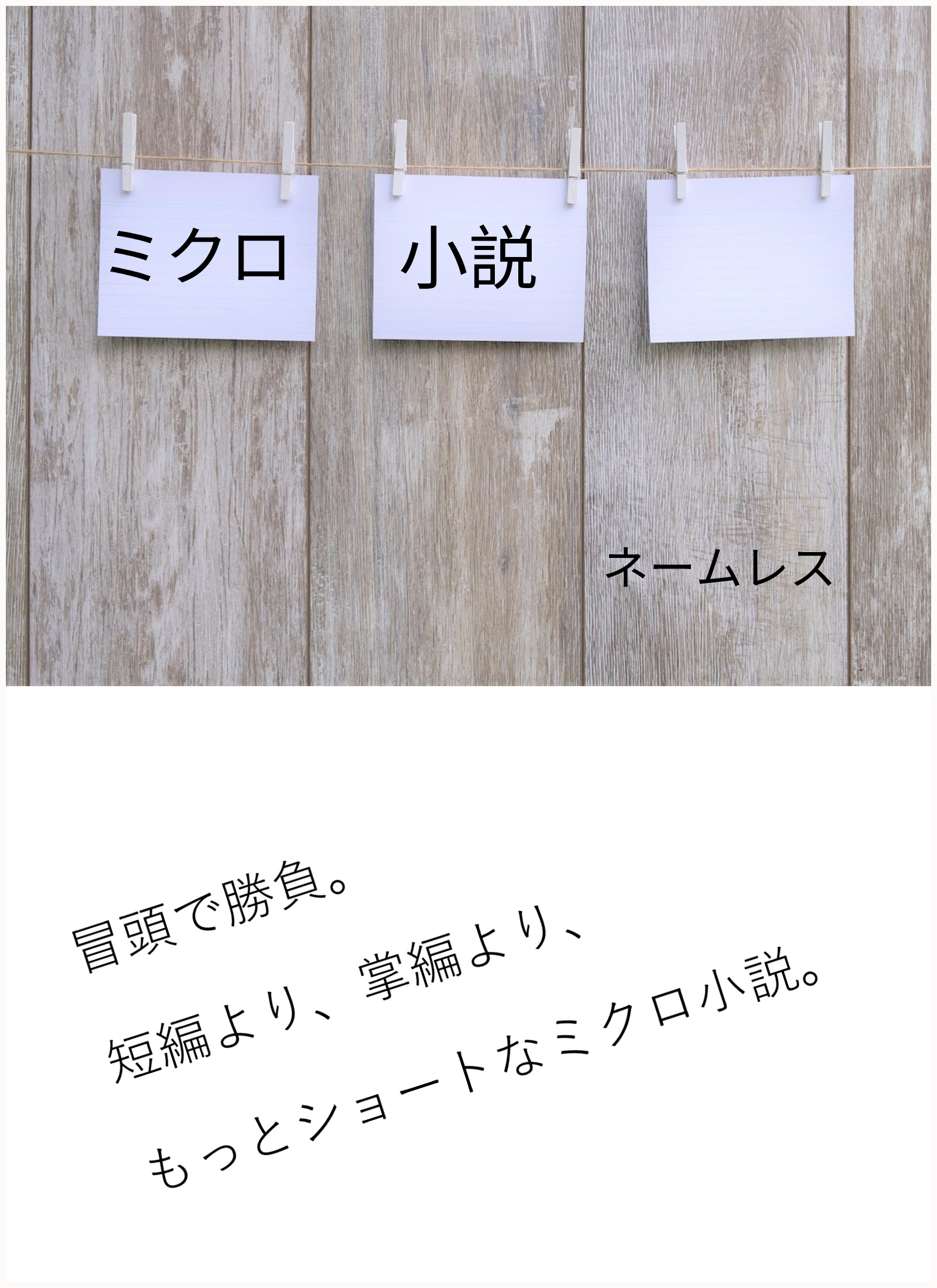第20話 6月9日 火曜日④
「それに電話の使いかたを教えてもらったから。授業料」
人はときどき人がなにかに騙されたとき――授業料だと思ってあきらめなさいと言うことがある。
それってつまり騙す人の存在を認めてるってことだ。
勉強を教える人はきっと良い人なんだろう。
だって勉強させてくれるんだから。
僕は二度ほど彼女の好意を断ったけど彼女は――ほれほれとまだカップを押しつけてくる。
もう一度断ると今度は僕の頬にマウントレーニアを押し当ててきた。
「っ冷たっ?!」
反射的に声を出してしまった。
「どう。受けとる気になった?」
「わかったよ。じゃあ遠慮なく。ありがとう」
せっかくだからもらっておこう、か。
「ところで。きみはなんでここから電話してるの?」
それはこっちのセリフだよ。
しかも「きみ」っていわれてるし。
「いろいろとね」
それは言えないから濁しておく。
言ったところで僕の重すぎる人生は誰にも受け止められない。
「諸事情か。うんうん。あるある」
彼女は――私も諸事情よって感じでうなずいていた。
「聞かれちゃマズい話ってもんよね? だから諸事情、諸事情。諸事情って言葉使うよね~」
彼女の話しかたはころころと変わった。
どこか自問自答のように言い聞かせているような気もするけれど? そういえば昨日もそんな瞬間があった気がする。
この諸事情という言葉は便利だ。
諸事情であれば中身なんてなんでもいいわけだから。
「そっか。明日もここくるの?」
諸事情を盾にしながらも僕に探りを入れてきてるみたいだった。
「僕には諸事情があるからね」
「私にも諸事情があるから明日もくるよ」
「そう。ところできみもなんでわざわざS町にくるの? その制服ってU町の公立高校のだよね?」
「おお!! めざといね」
たしかにS町から南に三十キロは離れてるけど
うちの高校とも部活やなんかで交流もあるし。
「でも私がここにいる理由は諸事情だよ」
前言撤回。
諸事情って言葉は不便だ。
大雑把すぎて検討がつかない。
「U町にだって公衆電話くらいあるでしょ? 学校終わってからこの町にきてるの?」
「それに近いかな。なんて、ね」
……それはおかしい。
高校が終わってから三十キロの移動だ。
車で移動しても三十分はかかる。
バスでも四十五分くらい? 今この時間にここにいるっていうなら車で移動してきても今から三十分前にU町を出ていないと無理だ。
通話時間がどれくらいかわからないけれど、すでに公衆電話での電話も終えている。
そのあたりが諸事情か……。
U高校は昨日と今日、短縮授業だった可能性もあるし。
よって僕は彼女に訊くことをやめた。
直感だけど、たぶん訊いてもなにも答えてくれないと思う。
「諸事情」って言葉は答えたくないことを答えなくていいように誰かが作ってくれた魔法の言葉なのかもしれないし。
こんな僕だってそのあたりの空気は読める。
なにせ僕も答えたくないから諸事情を使ってるわけだし。
僕は興味なさげに、ふ~んとだけ返しておいた。
「ねえ。せっかくだもん、飲みなよ」
「え、ああ、うん」
マウントレーニアのカップの横のストローをとって上蓋からストローを挿した。
「ねえ。117は時報なんでしょ?」
「いただきます。そうだけど」
甘みがほどよく、美味しい。
「110は警察、119は消防だよね?」
「そうそう。だから本当に必要じゃないとかけちゃだめだよ」
「わかってるよ。じゃあ1と2と3と4と、それに5と6と8は?」
彼女は指折り数えていった。
……ん? ああ、それって111、112、113、114、115、116、118はどこに繋がるのかってことか? まったくもって考えつかなかった発想だ。
ぜんぜんわからない。
でも、それぞれの番号にも割り当てがあるに違いない。
今のところ僕にはその知識はないけど。
「どこに繋がるんだろうね? 僕も知らない」
「知らないんだ~」
「ごめん。今度学校のPCで調べておくよ」
「お願いね~」
とんだ安請け合いをしてしまった、かも? これって調べた結果を彼女に報告する義務が生じたんじゃないかな? っとその前に僕自身の用を済ませないと。
「っとごめん。僕もそろそろ電話をしないと」
「あ。こっちこそごめん」