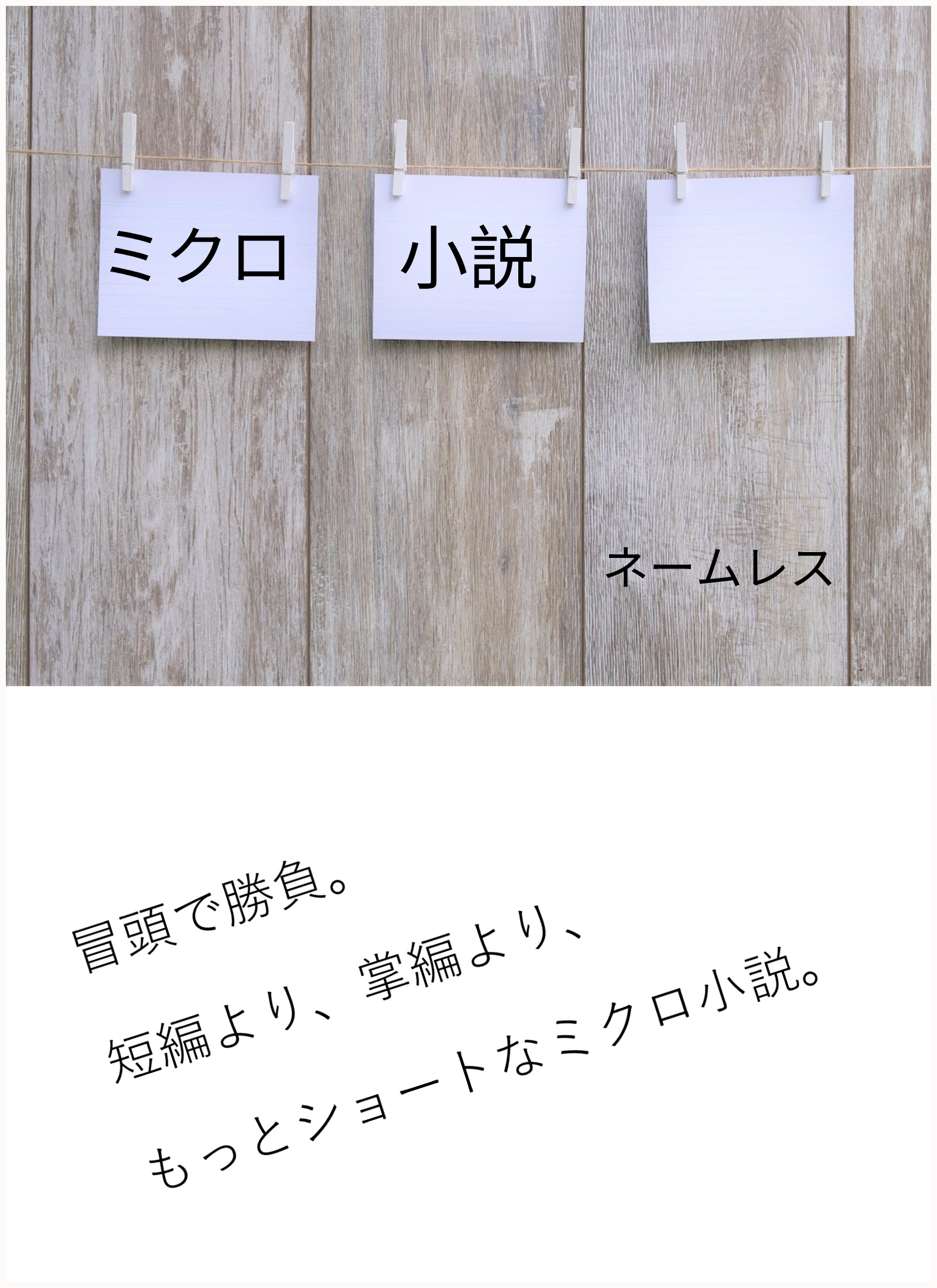第19話 6月9日 火曜日③
彼女は僕を見つけると一度悪そうな顔をしてから、わざと電話ボックスに半分挟まった。
ここで引き返すのも新人に場所をとられたみたいで嫌だな。
なんせ僕には電話ボックスで絶対に電話をしなきゃいけない理由がある。
僕が近づいていくあいだも彼女はずっと電話ボックスに挟まりっぱなしだった。
「いちばん強いの買ったよ」
え? 開口一番なにを言ってるんだろう。
「つ、強い、とは?」
「だから強いの。百五、ど。度、でいいの? 度なんてふつうは角度か温度だよね?」
「ああ、テレホンカードのことね」
「いまいち単位がわからないから、いちばん強いのくださいっていったの。んで、おまけつきの百五度」
「というか今は、テレホンカードって五十度と百五度の二種類しか売ってないから。でも百五度のテレホンカードは強弱でいうなら”強”なのは間違いないと思う」
ということで今日、僕が買ったテレホンカードは”弱”ということになる。
「そうなの~? てっきりもっとたくさん種類があるのかと思ったのに。目から鱗」
今日は鱗が落ちるの早いな。
「んで、きみはそんな体勢でなにしてるの?」
「いや~。上手く電話できたから師匠にご報告」
師匠? まあ、昨日、僕も心の中でひっそりとメンターとかって思ってたから言い返せない。
「公衆電話から無事に電話できたってことでしょ?」
「そうなるわな」
彼女はアニメかなにかの物真似をした。
たしかそんな口調のキャラがいたような気がする。
彼女は電話ボックスから出ると昨日のようにけらけらと笑っていた。
「昨日ジュースおごってあげるっていったから。約束」
彼女はスクールバッグを開くと――ほいとマウントレーニアのバニラモカをとりだした。
スクールバッグについているキーホルダーが揺れている。
「いや、べつにいいのに」
「でも1パワー使わせてもらったから」
1パワーというのはきっと僕のテレホンカードが「12」から「11」になったことだ。
単純計算でも「1」は十円。
マウントレーニアはコンビニなら定価に近いはずだから百六十円くらい? スーパーなら税抜きで百三十円くらいかな? 彼女はまるでアルバイト先の常連さんみたいに利子をつけてくれた。
ただ僕はそこまで大それたことはしていない。
正直、僕はこの世界にある昔噺的な恩返しにだって期待はしない。
吹雪に晒さらされているお地蔵様に手ぬぐいを被せても見返りなんて求めない。
この世界では良いことをすると良いことが返ってくるわけでもない。
悪いことをしても絶対に天罰が下るわけじゃない。