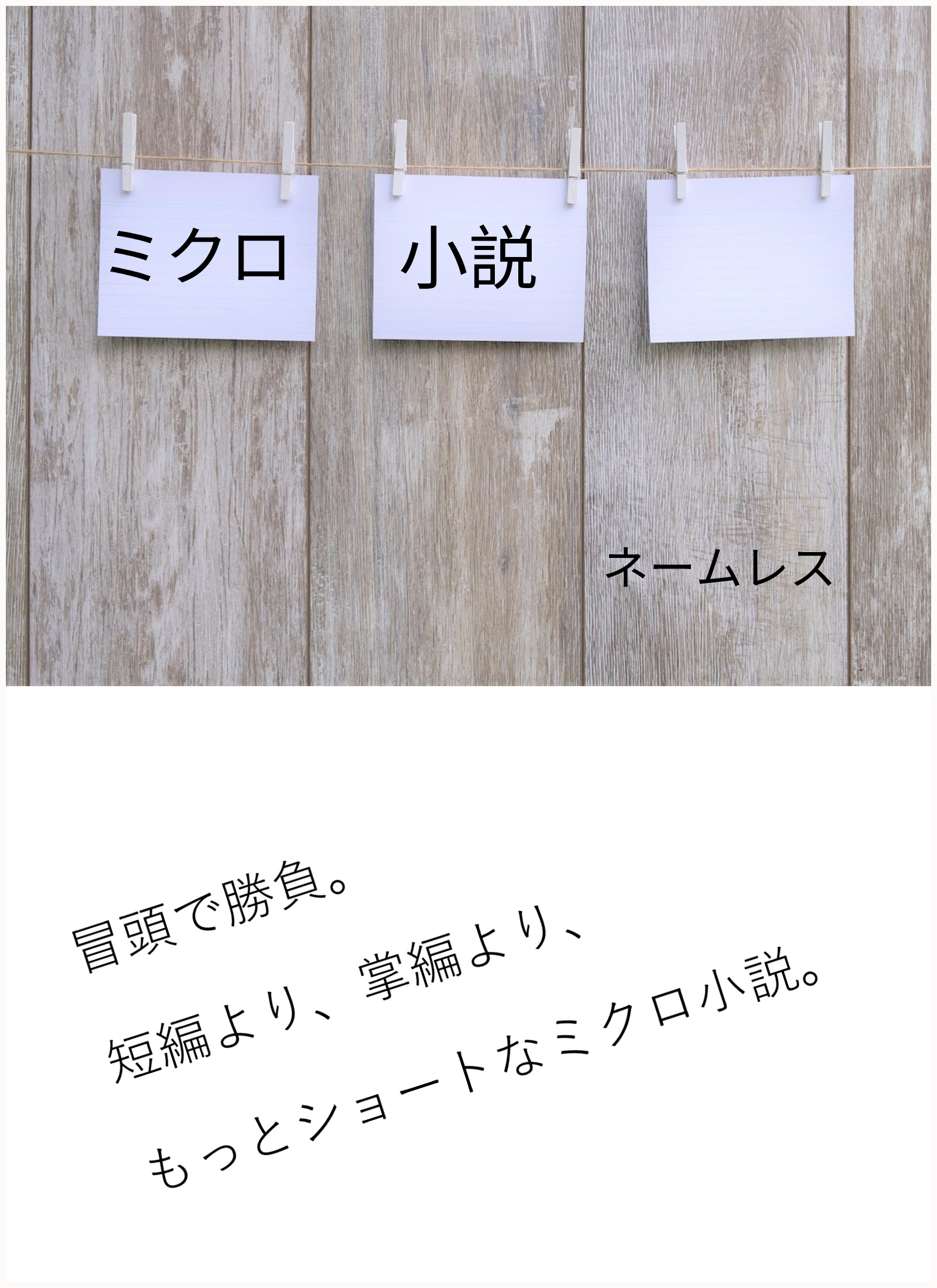第16話 6月8日 月曜日⑯
その日のアルバイトを終え賄いの餃子定食を食べてから家に着いたのは夜の十時過ぎだった。
僕は手にしていた小さなペンライトでポストを開きルーティーンでなかを確認をした。
ポストのなかにはなにも入っていない。
三月の下旬くらいまでは夕刊をとっていたけれど今は辞めてしまった。
意外と新聞を読むのが好きだったけどあれは嗜好品でありライフラインではない。
なければないで死ぬこともない。
ネットとはなにかが違っていて、読みつづけていれば視野が広がるだろうなとは思った。
あ、そっか? ネットなら自分の読みたいところしかクリックしないけど新聞なら最初からさまざまなジャンルの記事を読めるからだ。
僕はそんなことを思いながら鍵を回して玄関の扉を開けた、――ただいまと同時に扉がしゃんと音を立てた。
僕の右腕に小さな衝撃が走る。
あ、鍵を閉め忘れてバイトに行ってたのか。
しまった。
今後は気をつけないと。
僕はまた鍵を回し、再度――ただいまと言いながら扉を開く。
まだ電気は点かないかな?
「うわっ?!」
こんなときの人の思い込みは侮れない。
まさか暗闇に人がいるなんて思わないから。
だってうちに誰かがいるなんてことは通常はない。
「おお?!」
光に照らされている僕の声と誰かの声が家の中で衝突した。
「拓海くんかい?」
「はい。菊池さん、で、すか?」
「そうそう」
菊池さんは手に持っていたLEDの懐中電灯を僕から逸らし、まったく別の角度を照らした。
LEDの光というのは本当に強力だ。
菊池さんが壁側に光をずらしてくれたから僕の目もすこし闇に慣れてきた。
僕の持っているペンライトなんて比べ物にならないくらい明るいな。
「ごめんね。さっきコンビニで電気代を払ってきたから」
「あ、そうだったんですか? てっきり昨日のうちに……」
「さっきの電話で言えばよかったんだけど支払い用紙を家に忘れてしまってね。だからまた車で支払いに行ってきたんだ」
「すみません。そんな手間までかけさせてしまって。それに母さんのことも」
「いやいや。いいって、いいって」
「ありがとうございます」
菊池さんは車を走らせてどこまで行ったんだろう? すくなくとも国道の十字路交差点のコンビニじゃないな。
橋を渡ったところのコンビニかな? あとは町外れのところのコンビニ? むしろS町外のコンビニかもしれない。
菊池さんは持っていたLEDの懐中電灯を右側に何度か捻じってそれをスッと引き上げた。
LEDの懐中電灯は見事にLEDランタンに変形した。
今はこんな便利な懐中電灯があるんだ? つぎにアルバイトの給料が入ったら買おうかな。
これが無駄遣いと言われればそうかもしれない。
ただ、防犯に役立つとなればそれは必需品だ。
「電気がつくかどうか確認したけどまだだったみたい」
「みたいですね」
「うん」
僕は菊池さんにいったんリビングまで戻ってもらうように言った。
「なんでも今じゃインターネットでも電気の復旧手続きができるみたいだけど僕じゃついていけなかったよ」
「へー。ぜんぶネットできるんですね?」
「そうみたい」
僕の家系と菊池さんとは遠縁で菊池さんはそのむかしペンキと刷毛だけで看板を書いていた職人さんだ。
うちの母さんよりも十歳以上は上かな? 今はK市の総合病院の警備員をしていて僕が毎日、公衆電話から電話をかけている相手だ。
菊池さんは僕の祖父母の会社から独立した人で僕が小さいころから親しかった。
その恩があるとかで今でも僕によくしてくれる。
この家の鍵だって菊池さんに預けていて僕の世話係まで引き受けてくれている。
電気が点かないこの家に上がり込んでいたのも、電気を止められた未成年の僕を心配してのことだ。
電話ボックスの公衆電話の使いかたを教えてくれたのも、この菊池さんだった。
僕はアルバイトに行く前に沸かしたポットのお湯でお菊池さんにお茶を淹れた。
あれからけっこう時間が経っているけど保温効果のあるポットだからまだ温かいはずだ。
「どうぞ」
「ああ、すまないね」
「いえ」
「お母さんのこと気になってるとは思うけど」
「はい」
「今日はすこし調子悪そうだったね」
「そうですか」
「まあ、発作だから」
「ですよね。別にここが悪いっていう場所があるわけじゃないですし」
「それが逆に厄介なんだろうね?」
「ですね」
もっと簡単に人の記憶を消せたらいいのに、バイトのときと同じ感情が湧いてきた。
それにポットのお湯はもう一回沸かすべきだったとも思った。
保温効果があるといってもけっこう温くなっていた。
それでも僕はお茶を飲みながら菊池さんの持っていたLEDの懐中電灯のことを訊ねた。