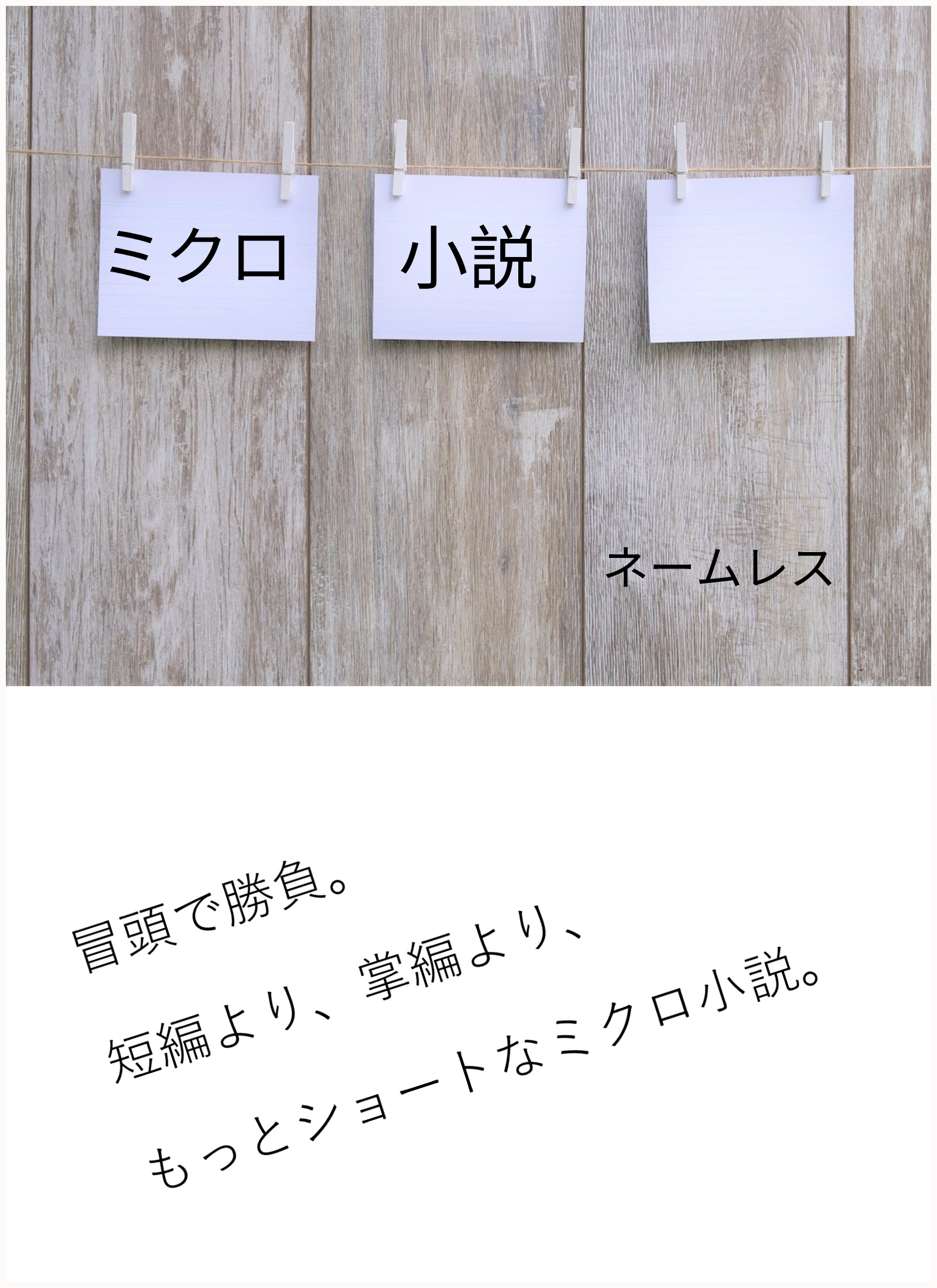第15話 6月8日 月曜日⑮
「大将。ツケといて」
奥座敷にいた常連さんのひとりがそう言いながら足早にフロアにでてきた。
大将は腕をあげて合図したけれど、テレビの中の力士が負けるとその手はすぐに下がった。
ただ大将は数秒も経たず焼き餃子を焼くためフライパンに腕を伸ばした。
常連さんはカウンター前を素通りするように横切っていき両開きのドアを開いて何事もなかったように出ていった。
秋山さんは今、奥座敷の別のガラステーブルを拭いている。
大納言の常連さんたちは店が混んでくると自分たちで席を移動して店の不利にならないようにしてくれる。
自発的にそんなことができるもの大将との関係性だろう。
だから「常連さん」になれるのかもしれないけれど。
今度は僕が奥座敷にいって常連さんの食器を下げてくる。
瓶ビールの大瓶一本と中瓶一本、それに大納言のいちばん人気、味噌バターチャーシュー麺と焼き餃子二人前を注文していた。
だいたいの金額を暗算で計算してみる。
合計二千六百十円にプラス消費税だから二千八百七十円くらい? 仮にそれが払われなければ大納言はそれだけの損だ。
でも大納言はツケの利く店でそれは大将と常連さんの信頼以外のなにものでもない。
「ラーメン大納言」の先代が店をだしてからツケOKで四半世紀近くやっているそうだ。
ツケのお客はほとんどがS町の人だし、大将の同級生や同じ町内会なんかの知人ばかり。
まさに性善説の世界だ。
僕を採用したのだってプラスαはあったけれどS町で生まれて義務教育の小中学校を卒業し、いちおうは受験でS町の公立高校に入学したからだ。
店の入り口から見てコの字型カウンターのいちばん右の奥の席で新聞を広げて読んでいたお客さんがバサっと新聞を閉じポケットから一万円札をだしてカウンターに置いた。
「大将。ごちそうさま」
「まいどー」
大将はそれを手にとると大袈裟なくらい、がしゃーんと音のするレジの中入れた。
その常連さんは満足げに暖簾をくぐっていった。
「ありがとうございましたー」
僕も声で見送る。
秋山さんが僕に目で合図をしたと同時に、秋山さんはすでにお盆を持って空いた席に向かっていた。
僕と秋山さんのコンビネーションもなかなかだと思う。
僕はツケ伝票の整理をする。
なんとなく気になって今のお客さんが前回一万円を置いていってから今日までに食べたメニューの合計を調べてみることにした。
えっと、ああ、そっか。
ないんだった。
また癖がでてしまった。
そう簡単に直らないか。
僕はレジの横に置いてあるカシオの計算機を手にそれぞれの伝票の合計を足していく。
計、九千二百六十円。
七百四十円のプラス。
いや、飲食店は通常の支払いで絶対に儲けが出る値段設定にしている。
じゃなければ店を経営することはできない。
たぶん七百四十円はツケの迷惑料みたいなものか? あるいは利子のようなものかもしれない。
なんにせよ常連さんたちは一定の時期がくるとカウンターに一万円を置いていく。
そんな自然発生のルールができあがっていた。
支払いが遅れるとか、そういったたぐいの揉め事はいっさい聞いたことがない。
常連さんは一万円に対して釣り銭を要求することもないし大将が釣りを払うこともない。
ちょうどいい時期にツケを清算してまたツケで食べていく。
その関係が崩れるときはすべてが終わるときだろう。
でも、見えない絆みたいなものは強固だと思う。
あるとき常連さんのひとりが長期入院したとき、その奥さんがやってきて一万円を置いていった。
大将は「待ちな」と声をかけて店の名前入りの封筒をとって乱雑な文字で「見舞い」と書いてぶっきらぼうに突き返していた。
――治ったらまたきなって伝えといてくれ。でも今度は味噌バターチャーシュー麺頼んでもチャーシューなし。油なしのマズいラーメンしかださないけどな。
口は悪いかもしれない。
でも大将はそういう性格の人だ。
むしろ人当たり良くしていて人を騙すよりはよっぽどいい。
奥さんは自分で持ってきた無地の封筒に「見舞い」と書かれた封筒を手に頭を下げて帰っていった。
その三日後に卸業者の人が入院していた常連さん名前を告げ、ビールの大瓶、五ケースを店の裏に置いていった。
思いやりには思いやりで返す。
そんなことを学んだ。
すべての人にそんな心があれば世界はもっと平和なのかもしれない。
店の窓から外の景色をながめるともう暗くなってきてるのがわかった。
僕は外に出てスタンド看板の灯りを点灯させた。
真っ赤な看板の中に「ラーメン大納言」の文字が一際目立っている。
都会だと黒板式のおしゃれなスタンド看板なんかを使っているけど大納言は電気スタンドの看板。
なんたってこの電気スタンドの看板ならけっこう距離の離れた車からでも目に入るから。
黒板式のスタンドじゃそうはいかない。
この電気スタンドを見て、ふと食べに寄っていくかと思う人がいるかもしれない。