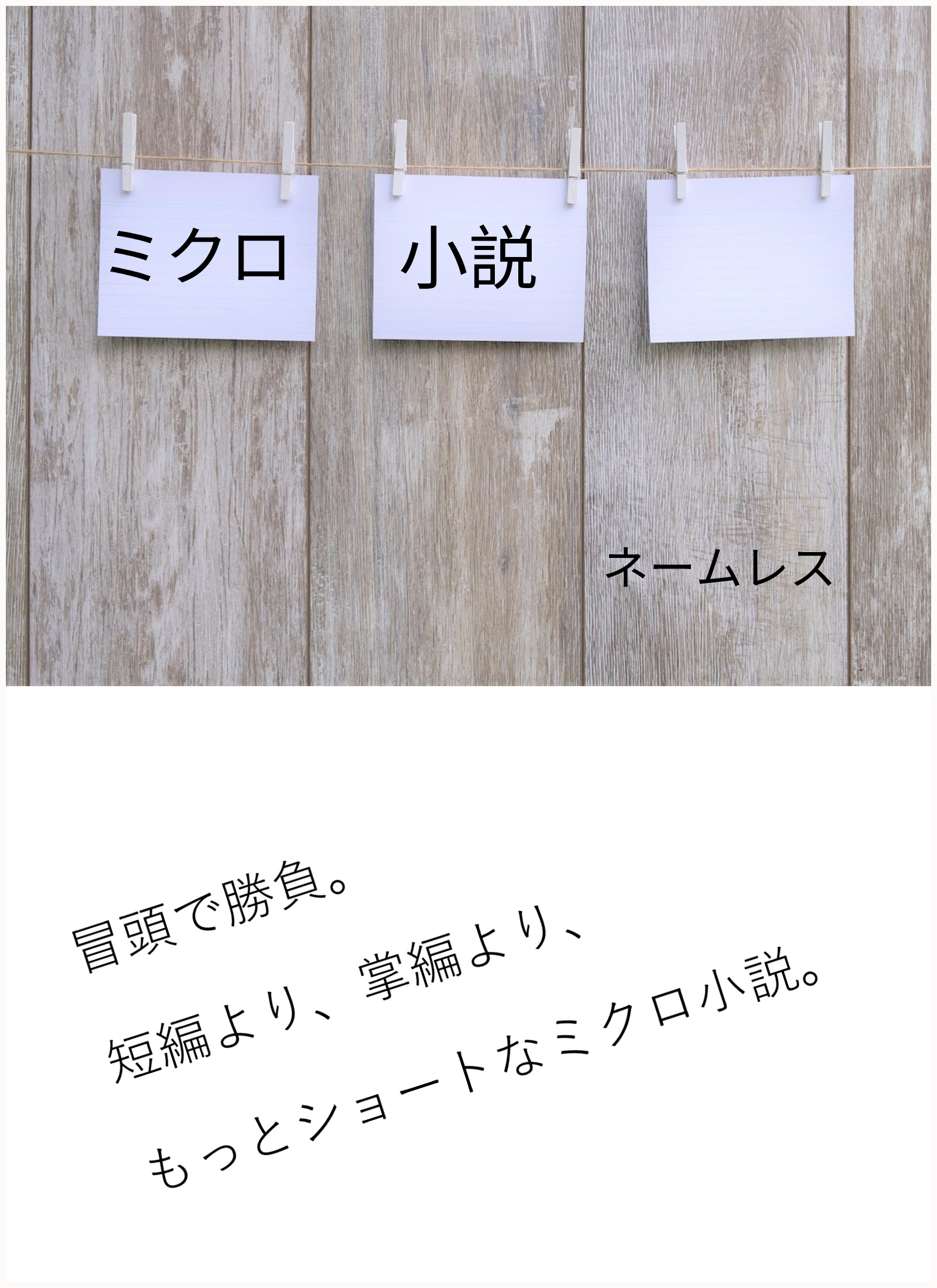第14話 6月8日 月曜日⑭
秋山さんがお盆の上に食器類とガラスのコップ、それに割箸と丸まったテイッシュ、それとは別に爪楊枝が突き刺さっているテイッシュまで乗せて奥の座敷から戻ってきた。
これはついさっきまで食事していた家族連れのお客さんのものだ。
常連さんのひとりが秋山さんとすれ違うようにしてレジの前にある飲み物の冷蔵庫を勝手に開けて大瓶の瓶ビールを持っていった。
秋山さんはそれを横目で確認すると栓抜きを片手に意気揚々とそのお客さんのところへと向かった。
僕は秋山さんから受けとったお盆を手にして、ラーメンどんぶりとレンゲ、それに餃子の皿とタレの入った小皿、コップのすべてをいったん水で濯いでから専用の洗い桶に入れた。
ものすごい泡立ちだから今、この洗い桶の中にいったいいくつの食器が入っているのかわからない。
食器を手探りで探してはつぎからつぎへとスポンジでこすっていく。
洗い物を終えてからはお盆の上にまだ残っていた割箸を束ねて専用の紙箱に捨てる。
テイッシュに刺さったまま爪楊枝もテイッシュからとって割箸と同じ紙箱に入れた。
ティッシュはそのまま燃えるごみの袋行きだ。
僕は自分の手元と秋山さんの動きを交互に見返す。
つぎに席を立つ人がいたら秋山さんにアイコンタクトで知らせるためだ。
秋山さんが向かった常連さんのカウンターでは、もうすでに割箸入れの横で栓抜きとビールの蓋が転がっていた。
秋山さんは常連さんと笑いあっている。
ふと、今日会ったあの娘ならその栓抜きでまたなにか面白い発想をするんじゃないかと思う。
僕は食器類の水を大雑把に切ってから、さらに乾燥させるため別の水切りかごの上に置いた。
もうひとりの常連さんもさっきの常連さんに感化されたようでレジ前の冷蔵庫に歩み寄っていった。
こういう食堂の冷蔵庫は中がぜんぶ見えるようになっていて飲み物を選びやすい。
お客さんはついつい同じ行動をとりたくなるのかもしれない。
意外と人の心理を利用した販売方法だったりして? コンビニのガラスケースの飲み物もそうだしあの冷凍食品もそうだった。
本当なら口頭でビールを注文されれば僕らのようなアルバイトが栓を抜いてビールを持っていくのに、お客さん自らセルフでビールを持っていくのは店としてもメリットだと思う。
そのあいだ僕らは違う仕事ができるわけだし、一石二鳥。
本当に効率がいい、もしかしたら三羽目の鳥だって獲れるかもしれない。
でもこれは大将が狙ってしたことではなくて「ラーメン大納言」限定の小さなルール。
偶然の産物だ。
僕は割箸と爪楊枝でいっぱいになった木材専用の紙箱を店専用の資源ごみのところ捨てにいく。
帰りにきちんと替えの紙箱をだして元の位置に置く。
栓抜きを持っていった秋山さんは別の常連さんにビールを注いでいた。
小上がりにいる別の常連さんはビールを片手にもう何色かもわからない壁の手書きメニューから「焼き餃子」を注文した。
ほかにも汚れて読みづらいメニューはたくさんある。
高校の前にあるあの古いアパートの看板みたいだ。
僕は前に大将にメニュー表を書き直したらどうかと提案したことがある。
大将はなにがなんでも首を縦には振らなかった。
メニュー表だけを新しくしても浮いてしまうからだそうだ。
タオルやスポンジにつけて壁をこすっただけで新品のようになるすごい洗剤で掃除をすればいいといったけれどダメだった。
今、僕の左斜め上で回転している油でギトギトな換気扇だって新品のごとくきれいになるはずなんだけど。
――きれいすぎたらお客さんが入りづらいだろ?
いやいやそれはない、と、思う僕のほうが愚かだった。
じっさいに店内をきれいに改築したのに客が減った実例を大将が教えてくれた。
町のラーメン屋や中華屋ではそういうことが多いらしい。
最近はやりの町中華もそんな感じか。
人は慣れた場所が変化することを嫌うそうだ。
たしかにそうかもしれない。
僕も母さんと一緒にやってきた十七年が急に変わってしまったんだから。