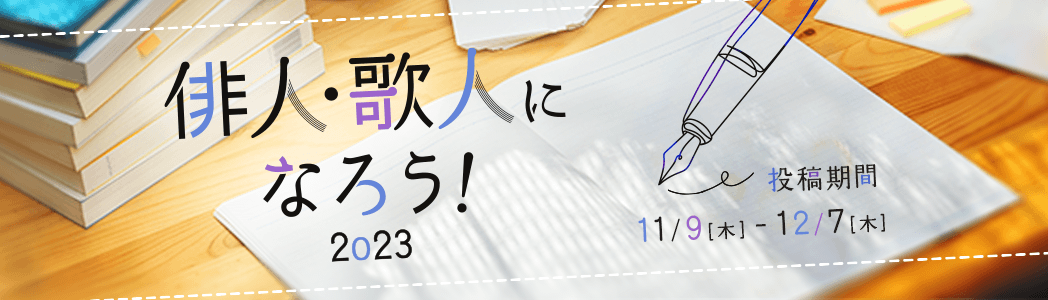和歌りますか? 短歌と俳句はどこが違う?
公式企画で『俳人・歌人になろう!2023 』が開催されています。
自由な形式でかけるもので、私も投稿しました。
が、『短歌』『俳句』『川柳』の違いについて、私自身が勘違いがありました。
これらの違いをまとめてみました。
■短歌とは
和歌の形式の一つで、五七五七七の音で成り立つ。
奈良時代から歌われるようになりました。
それとは別に長歌というものもありました。
こちらは五七五七を何度も繰り返し、最後は七七で終わります。
長歌は平安時代以降はあまり歌われなくなりました。
ちなみに切れのいい言葉を発することを『タンカを切る』と言います。
こちらはタンがからんだ状態からスッキリするような意味で、短歌とは無関係です。
■連歌と俳諧
連歌は複数の歌人によって、五七五、七七、五七五、とつなげて長い歌を作るもの。
平安時代から、貴族の間で歌われるようになりました。
これが庶民にも俳諧という歌遊びになりました。
最初の五七五を『発句』といいます。
■俳句とは
和歌の形式の一つで、五七五の音で成り立つ。
江戸時代から歌われるようになりました。
前述の俳諧で、五七五の発句だけで完結させる作品を作る人がでてきました。
松尾芭蕉などがその代表者です。
明治になって、五七五だけの歌を俳句と呼ぶようになりました。
基本的に、季語が入ります。
俳句は自然をテーマにしたものが多く、短歌は恋をテーマにしたものが多いようです。
■川柳とは
和歌の形式の一つで、五七五の音で成り立つ。
江戸時代から歌われるようになりました。
季語は不要。社会に対する風刺やギャグを入れています。
五七五七七で社会に対する風刺やギャグを入れたものが狂歌です。
江戸時代に、短歌の下の句(最後の七七)をお題にして、上の句(最初の五七五)を考える遊びが流行しました。
そこから上の句だけで完結する歌を柄井川柳さんという人がまとめて歌集を作りました。
そこから、五七五の社会風刺の歌を川柳と呼ぶようになりました。
■和歌のリズム
和歌の、五七五または五七五七七も実は四拍子です。
応援や締めで使われる三三七拍子も、実は四拍子です。
日本人はいろいろな場面で四拍子をつかいます。
『俳人・歌人になろう!2023 』へ投稿した筆者アホリアの作品『百葉楽歌(短歌集)』はこの下のリンクから見られます。