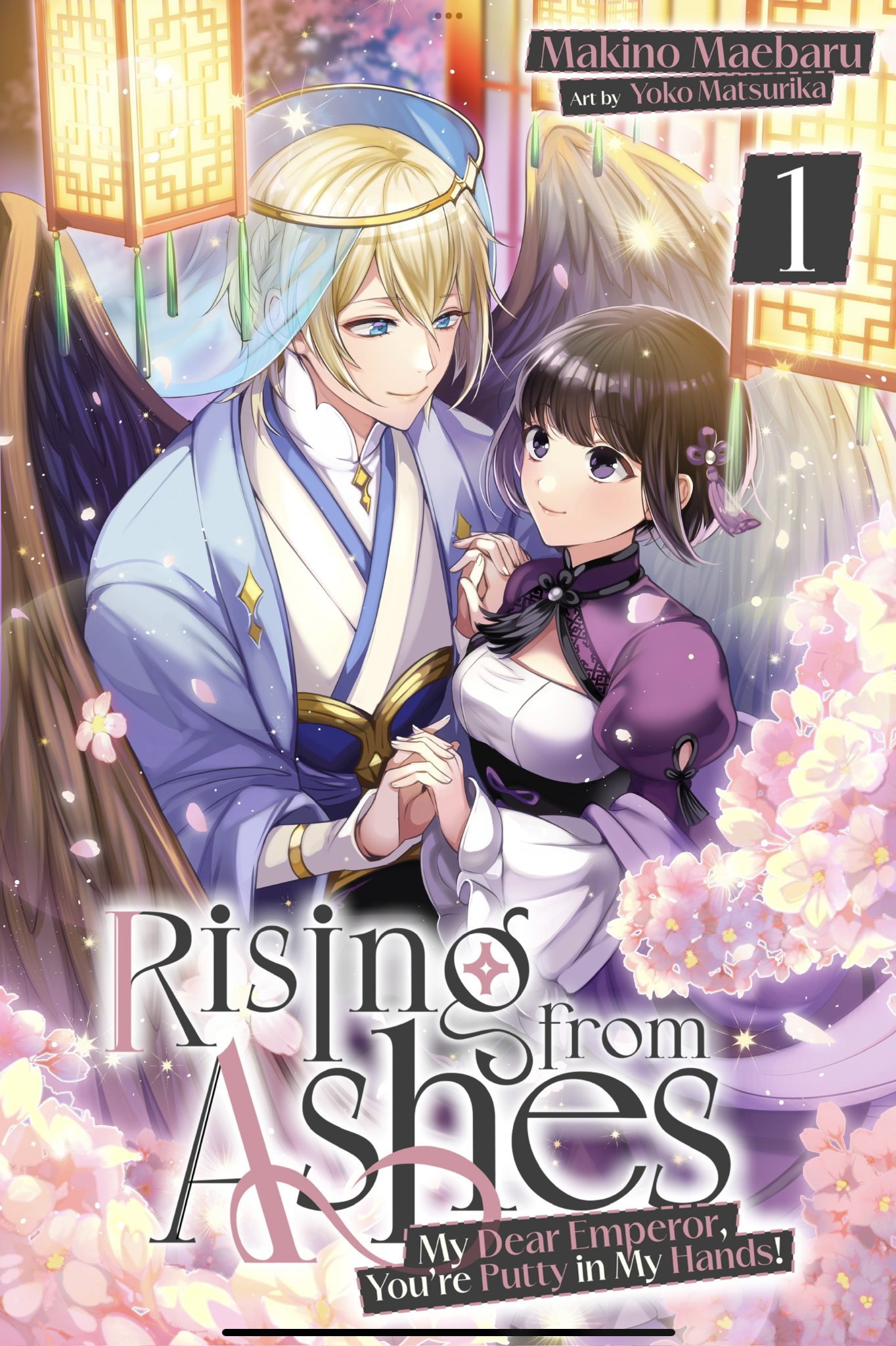39.お茶会にはパンケーキを添えて。
鶺鴒の巫女の朝は早い。
まだ深夜とも言えるような早朝の時間、私は牛車にて錫色と侍女、そして護衛を伴って、商人らの懇意とする茶屋街へと向かった。
錫色は無邪気でかしこくて可愛いだけでなく、実家が太い。
「お茶会ですね! そういうことなら! この錫色にお任せください! ええ!」
錫色の実家、竜花家は中央の薬種問屋の御三家の一つだ。
彼女と彼女の実家の縁により商人階級の女性たちとのお茶会の機会を設けることができた。
故郷、中央国での移動は馬車もしくはロバが主流だったが、東方国では首都内の交通手段は輿もしくは牛車が奨励されていた。
牛車の構造はお雛様についている牛車そのままだ。馬でも牛でも、どちらも可愛い。
日が昇る前から、商人たちはきびきびと仕事をしている。
今朝は涼しく、簾を乱さない程度に心地よい風も吹いている。絶好の牛車日和だ。
こうして街に降りて見物してみると、市街地は宮廷ドラマで観たような景色が続いている。ただ、通りを歩く人達の服装や市場で売られる食事はどことなく和を感じさせる。
「……遣唐使が廃止されなかったら、こんな感じの文化になっていたのかしら」
「けんとうしってなんですか? 斎さま」
「ええと……遠い世界のお話です」
少し恥ずかしく思いながら、私は前世の記憶を言葉にした。
「ある島国では、海を越えた先にある大陸の先進文化を学ぶため、使節を定期的に派遣していました。その使節の事を、大陸の国名を用いて遣唐使や遣隋使と呼んでいたのです」
「そうなんですね! サイ様は何でもご存知ですね! ……そうか、そうですね」
錫色は急に納得した顔をして、簾の向こうに広がる町並みに目を向けた。牛車はちょうど橋を渡るところだ。
「東方国の文字や着物や食文化も、海の向こうからやってきた『天鷲神』様、えっとつまり、陛下のご先祖様が伝えてくださったと言われています!」
「そうなんですね」
「ええ! なので私達の文化も、その物語とよく似ていますね」
「……なるほど、たしかに」
細い水路の向こうには、船で運んできた積荷を運ぶ人足たちの姿が見えた。水路は大河に続き、その下流には海が広がる。錫色はその景色に思いを馳せてるのだろう。
この世界も、海の向こうには東方国とよく似た文化の国があるのかもしれない。
---
私達の牛車は茶屋街に入り、最も目立つ大きな茶館へと連れて行かれた。
宮廷の一角なのかと錯覚するような大きな茶館だ。
茶館に入って錫色と侍女にあれこれと指示をだして準備をしていると、あっという間に時間が過ぎる。
太陽が昇ってやわらかな午前の光が窓から降り注ぐ時間になった頃、錫色の母親――竜花家の女将が商家の婦人たちを伴って茶館へと訪れた。
婦人がたの人数は総勢20名ほど。それにそれぞれ侍女や従者も付いているのでとんでもない人数だ。
錫色の母は黒髪の美しい女性だった。
「はじめまして斎さま。竜花家の女将、淡藤と申します。『鶺鴒の巫女』殿とこうしてお会いでき光栄です」
「こちらこそ、お忙しい中ご足労いただき、誠にありがとうございます」
「いつも錫色がお世話になっております」
にこり、と控えめに微笑む姿はまるで、山にひっそりと咲く一輪の百合のように儚い。目元は似ていないものの、灰色の瞳と額の形が錫色と瓜二つだ。
他に並んだ女性は見るからに女将といった覇気を感じる方々ばかりなだけに、目の前の彼女が薬問屋御三家・竜花家の女将というのがとても意外だ。
しかしこの方の一声でこれだけの商家の婦人が集まるのだから、すごい人に間違いない。
首都の商家の女性陣として錚々たる顔ぶれは『鶺鴒の巫女』を前に、一様に華やかでありながら凛とした格式の高い装束に身を包んでいる。
「お忙しい中ご足労いただき、誠にありがとうございます」
彼女たちの挨拶を受け、私は『鶺鴒の巫女』として求められる振る舞いを意識した。背筋を伸ばし、落ち着いて。陛下が招いた巫女であり、彼女たちの声を陛下に直接届けられる立場として、『鶺鴒の巫女』に失敗は許されない。
彼女たちとの茶会に用意したのは、茶館の本館から庭を通った離れだった。こじんまりとした建物だが、庭の新緑と池の輝きが室内にきらきらと反射する、晴れの日に心地の良い部屋だ。
給仕の女性がお茶と茶菓子を運んできた。
茶はこの店のチョイスで、彼女たちそれぞれの好みに合わせたものをお願いしている。
茶を淹れる姿で目を楽しませる横で、錫色の手によって菓子が運ばれてきた。
「あら、珍しい茶菓子。中央の焼き菓子ね?」
さすが商家の御婦人がた、情報が早い。私は頷いた。
「中央国の焼菓子です。お口に合うとよいのですが」
彼女たちの前に出されたのは、楊枝で食べられる大きさに小さく焼いた焼菓子だ。
離れには本館とは別の厨房が用意されている。来訪客が気に入りの職人に作らせるための特別の厨房だろう。
私はそこの厨房を借り、朝から婦人がたに振る舞う中央国の菓子を作っていたのだった。
舟形の皿に並べるように乗せて、生クリームとあんこを添えている。粒あんとこしあんも、しっかり事前に好みをリサーチしておいた。
焼き菓子自体は中央国の甘味として一般的で、東方国でも材料が揃えやすい。ただその作り方と盛り付け方は、前世の記憶を元にした。
慣れた職人の力なしに生クリームを作るのは多少難儀したが、金具で前世用いた泡立て器に似たものを造り、それに魔力を与えて電動ミキサーにした。
火力の調節なども、前世見たレシピの見様見真似だ。庶民でも誰でも職人の美味しいレシピを気軽に学べる前世、よい時代だった。
そして貸し切りの厨房なので、遠慮なく魔力をチートさせてもらったという訳だ。
「おいしそう。どうやっていただくのがおすすめですの?」
「普段のお茶請けのようにご賞味ください。味のお好みがありますので、一度素でお召し上がりの後、添えた練牛乳や餡をつけてどうぞ。他にも、お好みで蜂蜜ときなこもご用意しております」
私の言葉に合わせ、錫色が手押台の傍で礼をする。
甘味を前に盛り上がる女将の方々の様子にほっとする。
「少し濃い目に入れた緑茶によく合いますね」
「中央国のお菓子って初めて口にしましたけど、これは確かに甘くて美味しいですね」
好評で嬉しい。実は本来の中央国のレシピより、油と甘みは抑えめだ。東方国の薄味に慣れた婦人がたにとっては、自分で甘みを加減できるくらいがちょうどいいと思ったのだ。
「鶺鴒の巫女様は、もしかして厨房でお勤めだったのですか?」
「そういう訳ではありませんが……」
「このお味でしたら十分商売になりますよ。私好きだわ」
「ありがとうございます」
――正直、前世の知識に頼りすぎた調理法なので、褒められすぎるとじわじわと罪悪感が湧いてくる。この世界にない知識なのだから、目新しくて美味しくて当然だ。
恐縮しながらも、私は彼女たちの雰囲気を読み、会話の流れを意識しながら場を乗り切っていった。
その後も様々に話題は花開き、彼女たちは珍しいお菓子と会話を楽しんでくれていた。
彼女たちのあいだでも、春果陛下は大人気のようだ。そして同時に陛下の母――皇太后陛下も、評判が良い女性のようだ。
「皇太后陛下は何度もお会いしたことがありますわ。後宮からご実家の錐屋家に帰られてからは、災害に被災して苦しむ人たちの為に慈善事業を行われたり、私達商人の婦人と交流して私達の声を聞いてくださったりしましたの」
「そうなのですね……」
その時の情報が、春果陛下即位後の治世に影響を与えているのだろう。息子の時代になったときの事を考慮した行動をなさっていた皇太后陛下に頭が下がる思いだ。
「皇太后陛下は本当にお美しい方でしたわ。皇帝陛下の御尊顔は拝見したことないのだけれど、きっと似ていらっしゃるのでしょうね」
ちょうど話題が陛下の話にうつったのを見計らって、私は少し切り込んでみた。
「陛下もまるで女性のように麗しいですよね、御尊顔ではなく、その……物腰とか」
「ああ、その手の話はよくありますよ。陛下が女性だとか」
「え、」
私はどきりとする。
しかし、続いた話題は意外な方向性だった。
「うちも娘がいるのですが、女の子って紅一点の恋愛作品が好きじゃないですか。いわゆる男装物のお話で、陛下が女性だったらという想定の本は出ているんですよ」
「そ……そうなのですか?」
「結構人気よね。女性陛下と双翼の三角関係ものとか」
「陛下が男性で、双翼が女性の作品も見たことあるわ」
彼女たちは口々に様々な書籍の内容を教えてくれる。
意外すぎる展開だ。
「中央国での文化がどのようなものか存じ上げませんが、東方国は文芸に緩やかなのですよ。よほど酷いものでなければ皇帝陛下を題材にした作品や、宮廷の物語はよく出ております」
「そうなんですね……」
確かに、前世の世界でも、源氏物語を始めとして現実の人物をベースに置いた文学作品は数多い。男性ほど外に出られない女性にとって、屋内で楽しめる娯楽は親しまれやすいのも当然だ。
そして後宮が黒歴史なら、自然とラブロマンスを書こうとすれば宮廷の男性を女体化した作品が増えてもしかるべきだ。
「ところで、この国の女性の識字率はとても高いのですね」
「下働きの娘だとしても、多少の読み書きができないと仕事になりませんからね」
「お使いなどで薬を間違えられたら困りますし、記憶には頼らないのが基本です」
「男子は特に古典から鍛えられますよ。なにせ、物語を知らなければ売薬の行商もはかどりませんし」
「薬の知識だけではないのですね」
「もちろんです」
口々に返してくれる彼女たちは、じつに誇らしそうだ。
「でも、実際の陛下に関する話題って何も聞かないんですよ。だから想像が膨らむんですよね」
一人の婦人が、頬に手を当て口にすると、「そうそう」と他の婦人が同意するように頷いた。
「男たちも、行事以外ではほとんど見たことないっていうしね」
「先程お話した宮廷文芸も、だいたいは後宮時代の話を元にしているんです」
――後宮。
ぽろりと溢れた言葉に、和やかな場の空気がざらり、と変わった。一様に親しげだった彼女たちの態度に僅かなズレが生じてくる。嫌な顔をする者、目を輝かせる者。
「そういえば、後宮を新しく作るご予定はあるのかしら、陛下は」
「あのときは本当に大変な騒ぎだったけれど……」
「鶺鴒宮の設置や祭儀の復興でお忙しいのでは?」
「でも……」
ぽつぽつと話題に出しながら、彼女たちは私の様子を伺っているようだ。
情報を得たいのは私だけではない、彼女たちもまた、今後の宮廷の動向を少しでも知りたいのだ。私は小さく肩をすくめ、誰か一人ではなく全体に通るように意識して言う。
「私の知る限りではありますが、後宮を再興するというお話は今の所はきいていません。後宮に使っていた殿をそのまま鶺鴒宮にしていただきましたし、少なくとも……数年内にすぐ、以前と同じ後宮制度を実施するということは考えられないと思います」
言葉を選びながら、私は彼女たちの期待する情報を口にした。
その言葉にほっとするような人と、残念そうにする人がいる。
顔は笑顔でも、どこかしらの湿度というか、物腰のぎこちなさで見えてくる。
(おそらく、後宮に関する感じ方は同じ商家の婦人でも人それぞれなのね。ここは適度なところで切り上げたほうがよさそうね……)
話題を変えたいとおもった、ちょうどその時。
廊下と部屋を隔てる玉簾の向こうから錫色が顔を出す。
「斎さま、準備が出来ました!」
彼女に向かって小さく頷き、私は立ち上がった。
「ところで、皆様に是非見ていただきたいものがあるのですが、隣の部屋にいかがでしょうか?」
ご評価、ブックマーク、ご感想いつもありがとうございます。更新の糧です!
お読みいただきありがとうございました。m(_ _)m