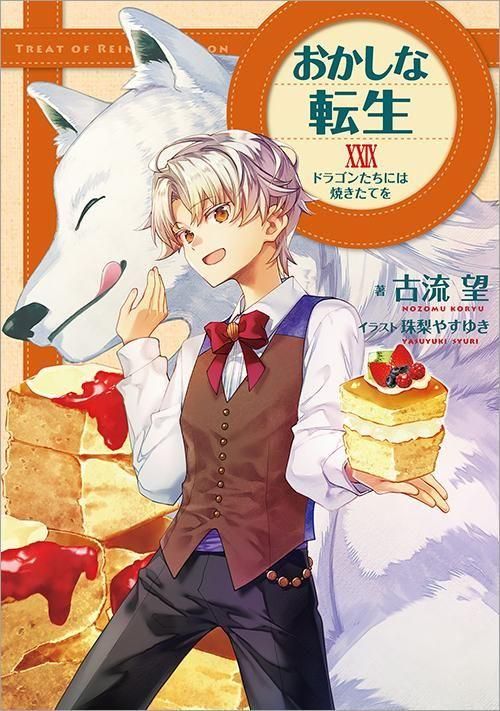052話 かぼちゃ
冬至にはかぼちゃがおすすめです。
「ふむ、これが……」
「ええ、立派なものでしょう」
「坊が威張ることでもねえでしょう。運んできたデココが自慢するならまだしも」
本村の領主館。執務室の中に、デンと置かれた緑の物体。数にして四つほど。人の頭ほどありそうなごつごつとしたそれは、衆人環視の只中に積まれていた。
緑黄色野菜の代表格であり、江戸時代には女性が好きな食べ物の常識として、芋やタコと並べられたもの。
かぼちゃ。
神王国のみならず、南大陸では得体の知れないものとして扱われており、物珍しさから遠くの異国商人から買った者が、更に別の場所で他の異国商人に売りつけ、巡り巡って船で運ばれた物を、行商人デココが買い付け、たどり着いた先がモルテールン家の執務室であったのだ。
長旅の疲れもあったのだろう。どこか渇いた風情で、くたびれた様子すら見せるかぼちゃではあるが、それが何かを知るのはこの場にただ一人。父親からは神から知恵を授かったと評される少年。ペイストリーである。
「これは食い物なのか?」
四十前の偉丈夫、カセロールが呟いた疑問。それは、一人を除いた全員が思っていた事だろう。
わざわざ大金を積んで買い取り、手間暇をかけてモルテールン領まで運んだデココや、その弟子のデトマールなども、これが野菜らしいという曖昧なことしか知らない。
食えるのか、と聞かれても恐らくとしか答えようがないのだ。
「勿論です。茹でて食べてよし、蒸かして食べてよし、焼いて食べてよし。栄養満点で皮から種まで食べられる、万能の野菜です!!」
父親の疑問に答えたのは、勿論銀髪の少年。自信満々で、輝くような笑顔で応えている。
自然な甘みのある野菜には、イチゴやメロンやスイカといった、フルーツに分類されそうなものも含まれる。かぼちゃもまた同じく甘味のある野菜で、スイーツ材料としてはごく一般的なものだ。
ペイスからすれば、これが領内で栽培できるようになれば、また一歩夢に近づくわけで、やたらとハイテンションになっているのはその為である。
パンプキンタルトやパンプキンパイ、かぼちゃプリンにパンプキンマフィンと、作りたかったスイーツは片手では足りない。
「毎度毎度、思う事なんですがね。何で坊はそうやって他人が知らないことを教えもしてないのに知っているんですかね?」
「それは僕にも答えられませんね。知っているから知っている。人が生まれながらに呼吸の仕方を知っていたとて、何故呼吸が出来るのかと聞かれて答えられることも無いでしょう。何故か知っているものを、問われて答えるのも難しいのです」
「ああ、うちの息子の非常識は今更だ。それをとやかく言っても意味がない。今は、これが食べられる野菜なのが分かればそれで良い」
シイツの疑問も尤もであったが、それを今論じても始まらないというカセロールの判断も合理的であった。
目の前に鎮座ましましている物体の正体が分かるのなら、その手段は何でも良いという現実的な意見もまた道理である。
「それで、ペイスはこれの食い方を知っているのか?」
「ええ。基本は芋と同じと思えば良いのです。少々皮が分厚くてごつくて不格好ですが、中の身は火を通せば柔らかくなります。甘いので、お菓子作りにも使えます。早速作って来て良いですか? 良いですよね?」
「待たんか。何でお前はお菓子作りにだけ目の色を変える。少しは落ち着きなさい」
今にも厨房に駆けだしそうな少年を、父親は窘めた。
窘められた方も、頭では分かっているものの、今まで作りたくても作れなかったスイーツがまた一つ作れるようになるかと思うと、気が急いて仕方がない。
「これが食い物で、食べ方が分かっているなら、後はこれを増やせるかどうかだ。珍しい食べ物であるのは間違いがないから、上手く育てられればうちの輸出品目に加えられるかもしれん」
「おお、カセロール殿。その際には是非私にお声掛け下さい」
「考えておこう。で、これの育て方や、育つ条件に詳しいものは居ないか?」
「そりゃ坊以外に居ないでしょうよ」
商人は、本来なら自分では商品を作らない。人が作った品を、右から左に捌くことで利ザヤを稼ぐのが商人だ。
かぼちゃをモルテールン領で作る。珍しい物であることは間違いがないから、それを独占的かつ安定的に扱えるなら、これほど美味しい商品も無いだろう。デココなどは、きょとんとしている弟子をしり目に、少々興奮気味である。
「乾燥にも強く、やせ地でも育てやすい野菜ですね。ただ、寒さには弱かったはず。特に、霜や雪には極端に弱くて、寒冷な地域で育てるのは難しいはずです」
「うちで育ててくださいって言わんばかりの野菜じゃねえっすか。都合がよすぎるでしょうよ」
「これも、神のご加護かもしれん。なんにせよ、当家でも育てられるとなれば、後は実践あるのみだな。そういえば、種まきの時期はいつになるんだ?」
「実が秋に生っているわけですから、逆算すれば春ぐらいでしょう。春先から夏頃に時期をずらしつつ播いてみて、一番いい種まきの時期を探るのが良いかと思います」
ペイス自身、かぼちゃの種まきの時期などは流石に知らない。知っている人間が居るとしたら、かぼちゃを育てたことがある人間ぐらいだろうし、それは日本でも少数派になるだろう。ペイスは無論多数派の方だ。
ただ、かぼちゃの旬は、芋や栗と同じようにスイーツ材料として取り扱っていたこともあるので知っていた。そこから大体の逆算をするのならば、種まきの時期も目安が出来る。
まさか栗のように、育って実が出来るまで三年掛かるということも無いだろう。
「なら、これの栽培条件の研究は、ペイスに一任するとしよう。皆、それで良いか?」
「異議なし」
「分かりました」
結局、正体不明だった物体は、新たなモルテールン領の特産となる可能性を秘めているということでペイス預かりの案件になった。
この家で良く分からない事があれば、とりあえず彼の少年に任せてみるというのが、最近は一つのルーチンになりつつある。
「よし、それではペイスはこれを持ってどこかに保管しておくように。お前に任せたのだから、成果を出せるのならば好きにして良い。さっきから腰が落ち着かない様子だし、何かをこしらえたいなら退席してよろしい」
「はい、それでは失礼します。デトマール、ちょっと運ぶのを手伝ってください」
「分かりましたペイストリー様。お持ちします」
大の大人でも二つも持てば重たいと感じるような大きさだ。子供のような年の二人で、何とか運びだす。
良い鍛錬になるだろうと、カセロールやシイツは笑ってその背を見送った。
それをよい息抜きがてらだと気を抜いたのち、執務室の面々は改めて硬い表情を作る。
「さて、あれをうちで買い取るのは決定事項だが、そうなってくると後は値段だな」
「私としては、かなりのリスクを負っていたということをご承知おき願いたいです」
子供たちが去った執務室では、大人たちが交渉事を始める。
お互いに信頼関係があるとはいえ、お金のやり取りは真剣にやらねば双方ともに困ることになるのだ。
「正直なところ、全くの未知な作物の値段など見当がつかん。相場も存在しようがないだろう。そこで、あえて聞く。あれの原価は幾らだ?」
「四つ合わせて八十レット。運搬に掛かった費用は抜いて、買い取った値段がそれです」
「何とも、よくもまあそんな博打をしたもんだ」
「そこは商人としての決断です。ここに持って来れば、売れると確信しておりましたから」
レーテシュ金貨八十枚。これは相当な大金だ。一枚で農家が半年から一年弱は暮らせる金額なのだから、文字通り、一生遊んで暮らせるだけの大金だ。
二十年培った信頼。商人としての目。カセロールと、その陰に居るペイスが欲しがる珍しい商品。売れなかった時や途中で荷が腐る危険性。手持ちの財産。それらを全て含めての決断であろう。
行商人として、店を持つために貯めてきた財産を、ほとんどつぎ込むような一大決心をしたわけであり、破産する危険性を背負って運んできたことになる。軽く扱う事は出来ない。
奇妙な取引のやり取りは、お互いがお互いの気質をよく知る為。虚飾や嘘を嫌うカセロールと、それを知って正直に事情を話すデココ。
ぶっちゃけた原価を聞くカセロールもカセロールだが、それに嘘偽りなく応えるデココも大概に商売の原則から外れている。
弟子には見せられないやり方だ。
「普通ならば、商品に利益を載せるのは三割から五割が相場だが……今回の、特殊な事情も勘案して、倍で買い取るというのはどうだ?」
「正直、もう少し載せて貰いたいところではありますが、今後もあの商品。かぼちゃと言いましたか。あれを私に扱わせて頂けるのなら、倍で結構です」
流石にデココもそれなりに経験を積んだ商人としてのしたたかさがある。
仮に今、四つのかぼちゃの取引で多少の利益の上積みを図るより、今後も珍しい商品を扱うことで得られる利益の方がでかいと踏んだ。
商売は専門外ながら相応に経験のあるカセロールも、分かっていながら苦笑して頷いた。
「良いだろう。どのみち“かぼちゃ”の取引は直ぐに始まるものでは無い。早くとも来年以降になるわけだから、それでデココが良いなら、問題は無い」
「ありがとうございます」
「いっそ、大儲けしてくれれば、うちとしても株が上がるがね」
「是非そうなりたいものです」
カセロールとデココはお互いに握手を交わす。
とりあえずはこれで取引妥結だ。しかし、だからと言って大量の金貨が直ぐに用意できるわけでも無い。特に今回は予定にも無かった取引だ。
部下として、シイツが金貨を用意する間、カセロールとデココは、豆茶を啜りながら世間話をする。
「珍しい材料で珍しい料理が出来れば、それはそれで色々と使い道は多そうですね。特に、料理法を広めて頂けるなら、材料を取り扱う側としても売りやすくなると思うわけです。私には政治は良く分かりませんが、噂ではタルトなんとかの作り方をレーテシュ伯との取引材料にしたとか。今回のかぼちゃも、それに倣うと面白そうです」
「ふむ、確かにそれもそうだな。まだ栽培も上手くいくか分からん状況で話をするのも気が早いかとは思うが、何処にどう売りつけるか、戦略を練っておく必要があるかもしれん」
領地貴族とは、政治家でもある。
自分の領地を如何に富ませ、自分の家を如何に盛り立てていくか。その過程には、どうしても多分に政治的要素が絡む。
ペイスがタルトタタンのレシピを取引材料に使った時。正味な価値を金貨で測れば、今回のかぼちゃ程度は軽く見積もれる。
王都の市場で売っているような果物の料理でそれだ。元の材料からして特別な料理ともなれば、その価値は計り知れない。
まさしくペイストリーの知識は、モルテールン家にとっては至高の福音であり大いなる富であると、カセロールはデココに親馬鹿をぶちまける。
デココとしても否定しようがないのだが、かといって傍目に親馬鹿としか見えない息子賛美には多少の含みのある笑顔になるのも仕方がなかった。
「私は商売人ですから、どうしても商売のタネとして見てしまいますが、それで言えば、間違いなく他に無いと言える商品。これは、高く売りつけようと思えば幾らでも方策があるでしょう。ただ、その場合は売り先の選定が重要でしょうね。下手な所に売りつけると、ぼったくりだと騒がれたり、支払いが理由で相手方が傾いたりと、騒動の種にもなりやすい」
「なるほど、商人らしいが、貴重な意見だ」
「商売は、一時に金を取れるだけ取るより、恩を売って細く長く取る方が良いことも多いです。珍しい品が手に入った時、私などは高値で売りつけることよりも、より多くの恩を売れることを基準に売り先を決めます」
「今回のかぼちゃもそれか?」
「大変な苦労をして、相当な危険を抱え込んで手に入れましたから、是非とも恩にきて欲しいですね。私としましては」
二人は笑った。
胸襟を開いて会話できる関係とは、貴重なものだ。お互いに腹の中を探り合うよりかは、望んでいるものをはっきりさせておく方が好ましい、というカセロールの嗜好を、行商人はよく知悉していた。
「恩を売れるとしたら、何処になるだろうな」
「そうですね……」
他愛のない世間話。
もしも、かぼちゃ料理のレシピで恩を売るとしたら、何処が良いか、等と言う話だ。
まだかぼちゃがモルテールン領で作れるようになると決まったわけでも無く、今後の課題が山盛りであるなかで、夢のある話だ。
宝くじが当たったらどうしたいか、という雑談と大して変わらない。
ああでもない、こうでもないと言い合う中、シイツが金貨の山を持って戻ってくる。
生憎と皮袋を切らしていた為に、ザルのような、浅い籠状のものに金貨を積んで持ってくるという、見る人が見れば卒倒しそうな状況だったが。
金貨をデココが入念に数える中、世間話の続きがカセロールとシイツの間で交わされる。
「お前なら、何処に恩を売りつけに行く?」
「俺なら、そうですね。やっぱり一番の天辺に売りつけに行くべきでしょうよ」
「天辺?」
「そう。王様のところに、出来るだけ恩着せがましく持っていく。上手くすりゃあ、また大将が位を上げて貰えるかもしれませんぜ。目指せ伯爵」
冗談めかして笑い合うのは、仲の良さだろう。
そこへ丁度金貨の枚数を数え終わったデココも、会話に混ざってきた。
「その際は、是非ともお引き立てのほどを。ああそうそう、国王陛下の所と言えば、こんな噂をご存知ですか?」
「あん?」
「国王陛下の御令息。王子様が、いよいよ御妃をお迎えになろうとしていると」
「む、それは噂では無いな。事実だ。先ごろの舞踏会でもそれらしい動きがあったし、殿下におかれては年も頃合。もう既に候補の絞り込みが進んでいるだろうな」
先だって行われた、公爵家主催、王家協賛の舞踏会。ここでは王子の嫁取りの熾烈な争いが水面下で、いや、水上での激しいバトルとして行われていた。
この時の戦いの結果、ある程度の候補は既に絞り込まれたと見る貴族は多かった。王子が声を掛けた上で二度程踊った相手が何人か居て、その中の誰かが本命だろうと言われていたのだ。
ルンスバッジ男爵令嬢、エンツェンスベルガー辺境伯令嬢、アスロウム子爵令嬢、ジーベルト侯爵令嬢などが有力な候補。誰にしたところで、家柄も後ろ盾も本人の器量も言うことが無い。無論、個性としてそれぞれに違いはあるにしても、誰が選ばれたところで不思議はない。
「ほう、それはまたよいお耳をお持ちで。カセロール殿の御令嬢は候補には挙がらなかったので?」
「ジョゼか? しがない準男爵家のうちの娘が王妃になどなれんよ。第一、あのじゃじゃ馬娘が、王妃などになれる柄だと思うか?」
「思わねえっすね。まだまだ嫁入り前に覚えにゃならんことがあるでしょうよ」
男たちが笑う中、屋敷の裁縫室の中で、一人の少女が盛大にくしゃみをするのだった。