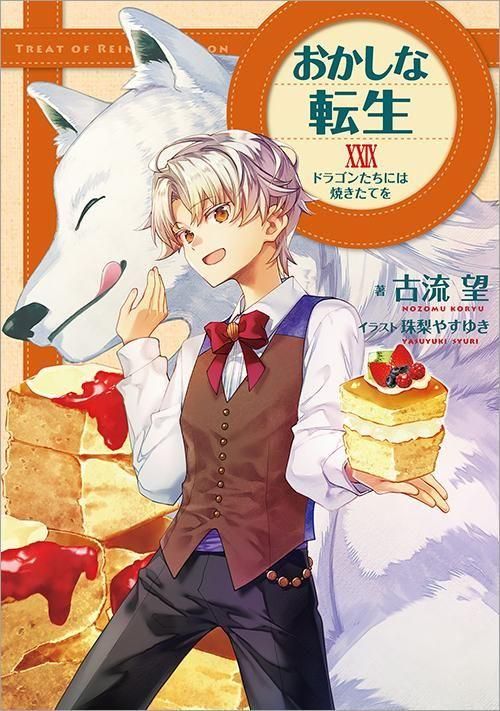495話 看破
北から隣国が攻め込んできたとの一報を受けてすぐのこと。
ザースデンの領主館執務室には、主要な面々が集まっていた。コアントローが急ぎで知らせてきた内容を皆に伝える為である。
父カセロールの出征に伴い情報収集強化中のモルテールン家では、集まってくる情報を精査していた。
「戦争の状況は? 推移を教えてください」
ペイスの問いに、まず答えたのはコアントローだ。
モルテールン家の情報機関を取りまとめる重鎮であり、シイツ従士長をカセロールの右腕とするなら、コアントローは左腕である。
領地開拓初期からカセロールの部下として付き従って来た古株であると同時に、苦楽を共にしてきた仲間。清濁併せのめる器量を見込まれて、モルテールン家の裏側まで任せられている人物だ。
どこか軽薄さがあってチャラチャラとした雰囲気を無くさない従士長に対して、厳めしい風貌と見た目通りに厳格な性格であり、若手たちにとってはモルテールン家の厳しさ担当とされる。
彼の言葉は、ペイスの部下たちも背筋を正して拝聴する。
「当初は先手を取られたことで、劣勢にありました。前々から怪しい動きが有ったとはいえ不意を突いた形になりますので、兵力差の不利もあって押し込まれる形になりました」
「まあ、例えエンツェンスベルガー辺境伯がどれほどの名将であっても、後手に回れば受け太刀になりますか」
「はい」
戦いというのは、有利不利を取れる要素が幾つか存在する。
兵の数の多少は言うに及ばず。兵の質の優劣や兵種の相性、疲労の度合いや士気の高低。地形の状況や防衛設備の有無なども戦いの要素としては大きい。指揮官の質や天候なども大きな要素だろう。
総じて言えるのは、戦いとは主導権を握った方が強いということ。
相手の行動を制約し、誘導することが出来れば、最終的に勝利をもぎ取ることは確実。
仮に兵力差で劣っていようと、或いは兵の質で劣っていようと、はたまた全てが劣っていようと、先に相手の弱い所を付ければどんな時でも勝ち目は生まれる。
主導権を握るなら、やはり先手を打つのが一番いい。
神王国側としては、一番困ることだ。
「辺境伯は防衛線を七つ作っていた模様。そのうちの最前線は、開戦と同時に破られました」
「ふむ」
ペイスが助言したこともあり、エンツェンスベルガー辺境伯は、モルテールン家に対しては割と防衛準備の内実を教えてくれていた。
コアントローが説明役をしているのも、事前の準備について知る機会が多かったからだ。
防衛線をどのように敷いているかなど、本来ならば他家に漏れるはずの無い情報である。
「その後、態勢を整えて防備に回ったエンツェンスベルガー辺境伯は、各防衛線の守りを固め、王都に対して縁軍を要請しました」
「妥当な判断でしょうね」
広大な領地を持つ大国にとって、辺境の保持というのはとても微妙なバランス感覚が求められる。
仮に、中央からの目が届きにくい所に、強大な軍事力や経済力と、殆ど制限の無い独自裁量権を持った貴族が居た場合。この貴族がほんの少し野心を持つだけで、あっという間に離反の上で独立勢力を作ってしまう。大陸の歴史上そうやって生まれた国家は多いし、大国の宿命でもある。
かといって、辺境の独立を警戒するあまりに軍事力に制限を掛け過ぎてしまえば、いざ敵から攻められた時にあっさり呑み込まれてしまう。弱肉強食の世界、弱い所を見逃してくれるようなお人よしは生きていけない。あっという間に食いちぎられるのがオチだ。
大きすぎず、かといって小さすぎない権力と軍事力。とても微妙なバランスで辺境というものは成り立つ。情報伝達に著しい制約が有る為、どうしても仕方のないことだ。
エンツェンスベルガー辺境伯領では、攻勢の為の戦力を殆ど持たないことで中央に対して恭順をアピールしていた。その分防衛戦力は手厚くしていて、守りという点では国内屈指の戦力が整っている。
これは、元より専守防衛を基本戦略とし、反転攻勢には他の戦力を当てにしているということでもあった。
王都に対して迅速に援軍を求めるのは、防衛戦略としては極々当たり前の行動である。
何ら不自然なところは無いはず。
ペイスがじっと考え込んでいなければ、部下たちも全く気にせずスルーしていただろう。
「続けて下さい」
「はい。戦線が一旦膠着すると、ナヌーテックは、約半数同士で軍を別けました。本隊が防衛線への攻撃を続ける一方で、別動隊と思われる一隊が防衛線を迂回する動きを見せています。現状、恐らくギュラ大湖の辺りを大回りしているようです」
「敵は軍を半分に分けた。一方は攻撃を続けていて、もう一方は天然の要害を迂回しようとしている?」
「その通りです」
ペイスが、コアントローの言ったことをじっくりと整理する。
何かを考えながら、咀嚼するようにして状況を口にしていた。
「防衛線を攻めている方は、別に砦を取り返されたりはされていないんですね?」
「はい。むしろ兵の数は減りながらもじわじわと防衛線を削りつつあるようです」
「負けている訳でも無い……ちょっと待ってくださいね」
「はい」
ペイスの目の前に、現状の戦況図が【転写】されていく。
国が持っているものよりもはるかに正確な地図。いや“航空写真”を元に、兵力の配置が示されるのだ。
軍事機密などどこの話か。“今現在”の両軍の配置と、動きが丸裸になる。
「何か……おかしい?」
「何がですかい?」
「微妙な違和感があるといいますか……何かが微かに引っかかるんですよ」
「……坊の勘ですかい?」
「勘というより、おさまりの悪さですかね」
ペイスは、見た目は線の細い美少年である。しかし、外見には全然似合わないほどに戦歴を重ねた勇士でもある。
戦いにおいて経験を重ね、また生来頭の良いペイスが、何かに気づいた。
こういう時の違和感というものを疎かにしてはいけないと、戦場の勘が従士長にも警鐘を鳴らす。
「戦況は五分。まだ若干ナヌーテックが有利」
「はい」
「やはりおかしい。いきなり準備万端攻めてきたのなら、もっと圧倒的になってもおかしくないのに、何故こんな牛歩のような戦いをするのでしょう」
「そりゃ、辺境伯が上手くあしらってるからじゃねえですかい?」
「いいえ。辺境伯が上手く対応したというのなら、これほどまでに防衛線を後退させるのもおかしい。経緯を見ても、辺境伯が下手とは思いませんが、妙手をうっている訳でも無い」
「そりゃ厳しい意見で」
ペイスのエンツェンスベルガー辺境伯評は、割と厳しめ。
勿論、国境を守るには十分な能力を持っているのだ。間違っても無能ではない。
しかし、事前に怪しい北の動きを察知しながら、既に幾度も防衛線を引き直している以上、際立って有能とも思えない。
ほどほどに優秀。
ナヌーテックは国の総力をあげていると思われる。ならば、エンツェンスベルガー辺境伯よりも智謀に優れた人間、指揮の上手い人間が居て当然だ。
一地方領と大国一国とでは、人材の質と量の差は大きくあるはずなのだから。
事前にたっぷりと準備できたはずの敵。小さな砦を幾つか落としただけでは満足できるはずも無い政治状況。優秀な将兵を揃えられているはずの相手。
圧倒的優勢になっていなければおかしい状況で、ほどほどに有利。
ここに違和感の大元が有る。
「そもそも、何故今なのでしょう。不意を突くというのなら、もっと油断していたり、適切に攻められるタイミングを見計らっていてもおかしくないはずなのに」
「そりゃぁ……あれ? 確かに、なんで今攻めてきたってなあ妙ですぜ」
「タイミング的に、今でなくてはならない理由があった。これは間違いない……」
圧倒的有利になるまで辛抱するでなく、神王国が隙を晒したタイミングを見計らうでもなく、しっかりと警戒している時に攻める。
ここはどうにもおかしい。何故今なのか。今でなければならなかったのか。
国内の政治事情だろうか。権力争いだろうか。一番可能性が高いものとしてはナヌーテックの事情なのだろうが、ペイスは納得できずに首をひねる。
「仮にナヌーテックのお国の事情だとすれば、これほどの戦力を動員できるのは何故? 勝ち目が有ると確信しなければ、ここまで総力を挙げて軍を動かすことなど出来るはずが無い」
「まあ、そうでしょう」
「第一、戦線がこうしてじわじわ動くような戦況となれば、ましてや辺境伯側が押し込まれる事態になれば、神王国側も国軍が介入することぐらい、織り込んでいるはずですよね?」
「向こうさんが馬鹿でも無けりゃ、援軍が大挙して来ることは計算づくでしょうよ」
ナヌーテックが仮に防衛線をじわじわ攻めていたとしても、圧倒的な優勢でもない限りは神王国軍の介入が有った時点で敗色濃厚になる。
ナヌーテックも攻め込む前から理解しているはずだとペイスは言う。
シイツや他の部下にしても、それは確かにその通りと頷く。
余程の阿呆でもない限りは、援軍が来るであろうことは分かり切っている。
「つまり、援軍が来ても勝てると思っている。勝てる策が有る?」
「そりゃ一体どんな策で?」
「僕が知る訳ないじゃないですか」
「そりゃまあそうです。しかし、予想は付いてるんでしょう?」
「推測を重ねるなら……幾つかは」
「流石は坊。それで、どんな策を?」
「内通者を用意する。伏兵を置く。諸外国に介入させる……いや、まてよ? 前提が間違っている? 辺境伯領の領土を一部でも切り取り、国軍が介入してきたところで神王国を混乱させられれば……今見えているものが全て囮? 本命は見えていないところ。狙いは北ではない? 西部は勝手に混乱させられる。とすれば狙いは南部か東部。或いは両方? 北を押さえつつ東も南も同時に混乱させられれば、戦局はごっそりナヌーテック有利になる? そんな都合の良い駒がある?」
ぶつぶつと呟き始めるペイス。
思考の深みにハマり、何処までも遠くまで見通す。ペイスの智謀を知るものは、黙って待つだけだ。
「読めました。一手で全てをひっくり返せる。既に後手に回っています」
「どういうことで?」
「戦線をあえてじり貧で膠着させ、兵を北に集める。敵の動きは明らかに国軍を誘う動きです」
「ふむ」
辺境伯軍がジリジリと押されているなら、必ず国軍の援護が後詰でやってくる。分かっていながらあえてやっているのは、国軍に来て欲しいからだと考えると納得がいく。
「本来ならば、神王国軍をわざわざ集めるなど愚策ですが、敵の狙いが兵力の撃破では無いとすれば自然な動きになる」
「撃破が狙いではない?」
「兵站です。敵は、我々を空腹にさせ、矢も無いまま戦わせようとしている」
「なんでそう言えるんです?」
「あえてギリギリ攻める戦力に調整しているからです。圧倒的に攻め込んでしまえば、ナヌーテック側の兵站にも負担が掛かってしまう。出来るだけナヌーテックに近い所に、出来るだけ多くの兵力を集めたいのだと考えれば、不可解な兵力分散やゆっくりとした侵攻も納得できる。兵站を狙うのは、初歩の奇襲です」
「ふむ」
ペイスは、地図の上で駒を動かしていく。
言われてみれば、確かに神王国側の兵站線は北に行くほど伸びる。大軍で助けに行けば、更に兵站への負担は増す。
「そうしておいて、我が国の兵站の根本を荒す。兵站が滞れば、大軍であるほど一気に干上がる」
「……つまり、南部が狙い」
「ええ。それも、南部街道を両方抱えていて、食料産出が豊富であり、海運の拠点となり、更には食糧庫たるレーテシュ領と王都との間にある領地……ボンビーノ領。ここが、この戦いにおいて兵站のボトルネック。結節点になっている。ボンビーノ家を大きく混乱させられれば、我が国の兵站は一時的にでもかなり大きく乱れる。そしてその乱れは、今次の戦争において致命的急所になり得る」
「やべえ状況っての分かりますが……国軍も馬鹿じゃねえでしょう。そう簡単に後方を攪乱できるとも思えねえし、備えも有るでしょう。大将だっているんだ」
「確かに。普通ならば兵站にもそれなりに備えをしているはず。しかし、誰もが見落としている、不確定な確定要素が有る」
「不確定な確定要素?」
「このタイミング。ボンビーノ家には、とても大きな弱点が産まれてしまった。中央軍も、盲点になっている“今まで存在していなかった急所”が突然現れたんです。神王国側にとって完全に意識の外側。間違いなく狙われる」
「ってえと……もしかして」
従士たちが、はっとして有ることに気づく。
「敵の狙いはスプレです!!」
ペイスの発言に、一同は騒めきだった。