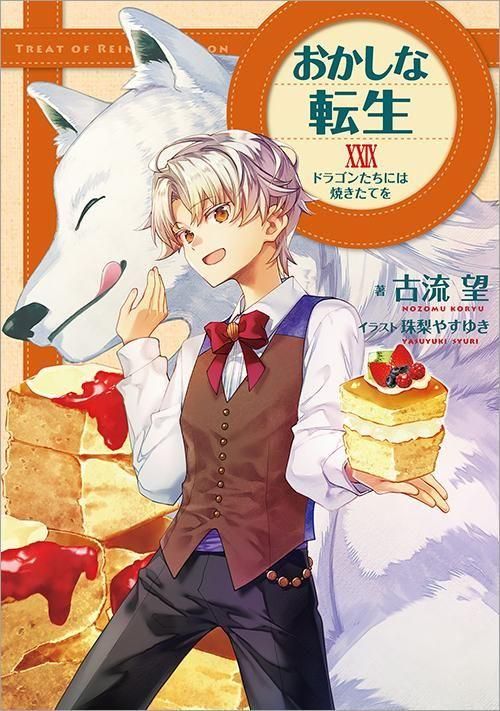223話 陰謀の続き
神王国に於いて、数ある貴族家の派閥を色分けする場合、最も大きな区分として、大よそ三色に分けられる。内務、軍務、外務の三つだ。内務は内政全般を指し、軍務は軍事全般を指す。そして、外務は外交全般を担う。
何故この三権を分けるかといえば、それは戦争における役割が、大よそこの三つだったから。つまり、歴史的な伝統だ。
都市国家を興りとする騎士の国。今は神王国と呼ぶこの国が大きくなる過程で、主権者とも呼ぶべき騎士たちの軍事制度や指揮命令系統が、そのまま政治体制になるのは極自然なことだった。
軍隊が大きくなり、部隊が分けられ、攻め取った占領地を一部の部隊に任せる。占領が長引けば、統治という概念が生まれる。そして、部隊の大きさの違いがそのまま爵位制度に繋がり、貴族制度になっていった。三権も、勿論この過程で色分けされたもの。
後方支援や補給。戦いでは無くてはならない仕事だが、これを担当していたのが内務貴族と呼ばれる者達だ。食料を安定的に生産するための農務、運ぶための道路整備などは工務、買い付けを行うならば財務。物資の調達や管理がそのまま内政と結びついていくのは自然なことだろう。
戦いが終わって戦後処理が行われる時、戦時にこれら後方を担当していた者が、そのまま役割を引き継ぐのは極自然の成り行きであり、更にそのまま平時となっても仕事が変わらず継続し、各担当分野が各々の職位となって内務貴族となっていった。
前線での戦い。馬に乗り、剣を振るい、命を懸けて勝利を得るのは、戦いにおいては花形だ。より強力な力を持つ者や、より巧みに兵を操る人間がこれを担当する。実戦力を持つ者は、そのまま軍務貴族となっていく。
後方を担当する者は、前線を支え、物資を生産する重要な役割。緻密で堅実な精神を持つ者は、そのまま内務貴族となっていく。
では外務貴族は何を担当していたか。これは、戦いの始まりと終わりを告げるのが仕事だった。戦争を始める時に敵に宣戦を告げに行く使者として、或いは敵に負けを認めさせる使者として。或いは、自分たちが降伏するときの使者として。
弁舌巧みな人間が、敵地に乗り込んで辣腕を振るう。これは、戦場で敵を殺すこととは違う勇気が求められる。敵の使者を首だけにして返事にする、などといった蛮行もいまだに残っているわけで、文字通り命がけで行う仕事だ。並みの度胸では務まらないし、また阿呆では仕事にならない。
何より、忠誠心も欠かせない要素だ。相手との交渉を一手に任されるということは、その気になれば自分だけ良い目を見ることも出来る。こっそり賄賂や接待を受けることで交渉に手心を加える、などということはありがちな話。自分の欲ではなく、あくまで職務に忠実足らんとする忠誠心。時に敵を騙し、或いは事実を隠蔽し、詭弁を駆使しつつも、高い道徳心を持つという、矛盾を常に抱え込まねばやっていけない。
度胸があって弁舌が巧みで交渉上手な人材。つまり、専門家が強く求められるのだ。お前たちをぶっ殺すと喧嘩を売りに行くのが仕事であり、これぐらいで勘弁してやってもいいと片を付けるのが仕事。そして時には、許してくださいと億面なく頭を下げ、靴の裏を舐めるのが仕事。
外務が無くては、戦いの終わりは敵の皆殺しか自分たちの全滅かという極端な話になってしまう訳で、最初と最後の欠かせない締めを担うわけだ。
戦いが終われば、彼らはそのまま仲裁役としての仕事に就く。一度手打ちにした内容が守られているかの監視であったり、何かしらの誤解やトラブルが生じた際、間に入って解決に尽力したりもする。これは、戦いの幕引きの経緯を最もよく知る人間が行うべきであり、それがそのまま平時における外務貴族となっていった。
内務、軍務、外務は、どれも無くてはならない仕事であるが、それぞれ戦時における役割は違う。そして、求められる能力も違う。堅実細緻な内務、剛健屈強な軍務、機転鋭利な外務。
真面目な人間は内務に向いていて、強い人間は軍務に向いている。頭の回転が速いならば外務に向く。勿論、軍務貴族は内務が全く出来ないという訳でも無いし、賢い人間が必ず外務を担当すると決まっているわけでもない。内務貴族にも不真面目な人間は居るし、軍務貴族にもヘタレのへなちょこは居る。あくまで、向き不向きの傾向の話であり、中には全部苦手というものも居れば、何でもこなせるという人間も居るのだ。
この、三権で国政を担う伝統は今尚根強く残っていて、基本的に神王国は三権が互いに牽制し合うことでバランスを保って来た。どこかが突出すれば、他の人間は頭を押さえに掛かる。それを延々と繰り返すのだ。
不毛と言ってはいけない。権力を集中させ過ぎることなく、かつ分散しすぎることも無い。三派閥の抗争は、適度な自浄作用を産むのだ。
少なくとも、今まではそうだった。
「……実に拙いな」
コウェンバール伯爵邸。外務閥の重鎮であり、国内でも上から数えた方が早い
程の資産家でもあるコウェンバール伯爵の住まう邸宅である。
その中の一室で、屋敷の主である伯爵が呟いた。
「何を、でしょう」
部下が、伯爵のつぶやきを拾う。
こういう囁くような呟きこそ、主が構って欲しい話題であると知っているからだ。外務貴族というのは賢いと同時にひねくれ者であることが多く、この主も又典型的な外務貴族。人に聞いて欲しいことに限って小さい声で言うという、仕える方としてはなんとも困るひねくれ方をしている。
案の定、聞き返して欲しくて準備していましたといった素早さで、伯爵は部下の言葉に反応した。
「これを見てみろ」
伯爵が、羊皮紙を部下に渡す。
羊皮紙には担当者が検閲を行った印があった。つまり、公文書ということになる。しかし、これは伯爵家の文章ではない。
「寄宿士官学校の卒業生の任官先一覧ですか。毎年のことではないですか」
寄宿士官学校から正式に報告される報告書の一種。しかし、王家の印が無いことから、報告前であることが分かる。正式な報告書の、報告前の姿。それが、伯爵の手にあるものの正体だ。
王宮に上げられるであろう正式な報告であるのだが、内容を事前に見られるのは伯爵の権力故である。
現在の寄宿士官学校は、コウェンバール伯爵とも縁の深い外務閥の人間が校長を務めている。それ故、校長の知る情報を、王宮よりも先に知ることが出来る。この情報を使って利得を得るのは、校長という地位に付随する伝統的な利権の一つだ。
個人情報保護法など影すらない世界であるし、そもそも個人の情報を漏えいしてはならないというモラルすらないのが普通。地位にある者は、その地位を利用して得た情報を権力や利益に置換する。この世界、少なくとも神王国とその周辺国では極々当たり前のことだ。
卒業生の卒業後の進路もその一つ。
例えばかつての日本で卒業アルバム内の名簿が売り買いされて利用される事件があったように、寄宿士官学校卒業生という情報と、個人情報が結びつくと利用価値が生まれる。
とりわけ、成績優秀者の情報は利用価値が高い。他家に雇われた成績上位者などは、上手く利用して取り込むことが出来れば、実に使い勝手のいいパイプとなるからだ。
成績優秀者は、まず大概の場合雇われた家で出世し、それ相応の権限を持つようになる。寄宿士官学校に入る時点で篩いにかけられ、更に四年をかけて多くを学び、鍛え、同じように才能ある連中と競い合った上結果を残した人間が、成績上位者と呼ばれるのだから。ランダムに選んだ人間が出世する確率よりは、遥かに高い。出世した、或いは出世すると見込まれる人間とパイプが繋がれば、美味しい思いも出来る。
何も無理に賄賂などで懐柔する必要は無い。仲の良かった人間や、同じ教官に教わった顔なじみなどを通せばそれで事足りる。まさか、旧友が訪ねてきたものを話も聞かずに追い返す無情者も居まい。門前払いを受ける心配もなく、高い確率で話を聞いてもらえるというだけでも、大きなメリットだ。
そして、情があれば、それを取っ掛かりに妥協を引き出すことも可能。友達から懇願されて、それでもなお突っぱねる毅然とした対応を、誰もが取れるとは限らないのだ。例え僅かな差でも有利になるというなら価値はある。
仲の良かった友達や身内からお願いと頼まれるのと、赤の他人から勧誘されるのと。例えば保険に入るならどちらがより選ばれやすいか、子供でも分かる。
保険よりも直接的に利益をやり取りする貴族であれば、無視できるものでもないわけだ。
つまり、成績上位者の就職先は、見過ごせないものといえる。
「良く見ろ。今年の首席を始め、上位陣がごっそり一カ所に取られてしまっているだろう」
外交を主任務とする外務閥は、人付き合いやコネクションは財産。個人情報が利益を産むと何処よりも知っている人種だ。
そんな伯爵は、今年のある傾向が気になった。
遅れて、部下も何を言いたいのか理解する。特定の一カ所に、上位卒業の学生が集中しているのだ。
王宮や国軍に集中するというなら、毎年のことだ。元々がその為の学校なわけで、国軍が人材をごっそり持って行ったり、官僚としてまとめて採用したりするのはよくあること。しかし、今回の場合は貴族家に雇われている。
貴族に雇われるというのは本来イレギュラーな雇用先なのだが、そこはそれ。大貴族などは常に優秀な人材を欲しているわけで、寄宿士官学校の上位卒業生に食指を伸ばすことは珍しくない。
だが、今年の場合は最も多く卒業生を確保した家は大貴族と言い難いところであった。
「本当ですね。一体どこの家です? カドレチェク家あたりですか? ……え? モルテールン?」
「驚くだろう」
「驚くも何も、どういうことです? 訳が分かりません」
部下は、驚愕の想いを隠せなかった。
軍家閥の筆頭であるカドレチェク家辺りが卒業生を掻っ攫っていくなら話は分かる。軍人の、それも士官教育を受けた優秀な人材だ。軍人の取りまとめ役であるカドレチェク家からすれば使い勝手も良く、利用価値の非常に高い有為な人材と評価する。
雇われる側も、軍人として出世するのにカドレチェク家に囲われるのは悪くない。国軍の人事権を左右できる人間の下で働くのだ。上手くすれば、隊長格のポストすら融通してもらえるかもしれない。
だが、モルテールン家というのは少々解せない。
勿論、このモルテールン家も軍家閥の重要人物であることは間違いない。部下もその点はよく知悉している。
有名か無名かと問われれば、間違いなく国内屈指の有名人と言える。そして先ごろ中央軍の大隊長に就任したこともあり、就職先として悪いとは言い難い。
だが、大量の人材が殺到するほど魅力的かといえば、疑問符が付く。中央軍の大隊長が左右できるポストなど、良くて小隊長、精々が班長程度だ。寄宿士官学校の上位卒業生ならば、もっと上を目指せる。
「ここ最近、軍務閥が伸張著しい。東部や南部の地域閥も、景気が良い。その起点となっているのが、モルテールン家らしい、というのは知っているな」
「ええ。それで閣下が一計を案じたと伺っていますが」
一計というのは、他ならぬペイスに対する措置だ。目の届かないところで動き回られるより、自分たちの目も手も多い王都に呼びつけた上で、大人しくさせておこうと企んだ。
企んだのは、他ならぬコウェンバール伯爵である。
「そうだ。モルテールンの倅を王都に呼び、慣れぬ仕事を与えて大人しくさせる目論見だった。我々の手の中に息子を匿うことで、父親に対する人質としての意味もあったし、モルテールンの倅が優秀ならば、我々の下で成果を上げて貰えば利用できるという思惑もあった。知っているな」
「上手くいった、という報告を聞いていましたが」
伯爵の企ては、当初非常に上手くいった。伸張著しい南部辺境に釘を刺し、他派閥をけん制しつつ自派閥の利益の為に利用し、それでいて自分達は一切費用負担もしていない。策謀に点数をつけるとするなら、満点をつけても良い位だ。
そう、伯爵は自賛する。いや、していた。
「ああ、上手くいった。寄宿士官学校の内部に巣食っていた理屈倒れ共は一掃され、校長の権威は新任でありながら高まった。学生の質も著しく向上したと聞いている。モルテールンの倅も領地を離れたことで、南部閥の急伸長も一先ず落ち着いたという報告も受けた」
「なら、結果は最上では?」
伯爵の狙いは、その殆どを完遂している。ペイスの働きにより、寄宿士官学校の中に根強く残る前校長派、つまりは内務系の影響力を削ぎ落すこととなった。更には卒業生の実力も近年になく上出来の部類であり、ひいてはそれを為した現校長の権威と名声は高まった。そして、ペイスの居なくなった神王国南部、特にモルテールン地域一帯では、一気に安定度合いを増したのだ。
狙っていた目的を、全て果たしたというなら、大成功の部類である。狙った獲物が狙った通りの動きをして、何が問題なのか。部下にはそれが分からない。
「……結果は上々。しかし、成果は酷いものだ」
「成果? それは?」
「寄宿士官学校で得られる成果など、優秀な学生以外の何があるのかね?」
「はあ」
伯爵は、憂鬱な気持ちを押し込めるのに大変な労力を要した。
狙った獲物が狙った通りに動いたのだが、狙った結果にならなかった。つまり、獲物の力量が想定外だったと認めるのが辛かったのだ。自分の目が曇っていたということなのだから。
魚を罠に追い込み、思った通りに罠に入ったにも関わらず、魚を得ることが出来なかったとすれば、何が悪かったのか。罠がお粗末だったとしか考えられない。
つまりは、それを用意した漁師の腕が悪い。目利きが甘い。
伯爵としては手前の腕がお粗末だと言われているようで、実に気分が悪い報告である。
「我々は、形式上最良の結果を得た。策は上手く嵌り、外務閥の権威は上がり、学内の権力も掌握し、優秀な学生を育てたという結果を得たのだ。しかし、その成果、実利を得たのは我々ではない。優秀な学生がごっそり持っていかれ、目ぼしいものからモルテールン家に強い縁故を持つ家が浚っていった。我々はどうだ。まともな人材確保が殆ど出来なかった。交渉術に強みを持つ我々が、だ。これでは、寄宿士官学校の校長職の旨味は半減だ」
寄宿士官学校の校長職の一番の旨味は、卒業生に強い影響力を行使できる点だ。有形無形の影響力は無視できるものではない。校長や教官から勧められた仕官先が、別に忌避するものでなければ、そのまま受け入れられる。
担任の先生から、顧問の部活に勧誘されるようなものだ。元より希望がしっかりしているような場合を除けば、惰性で流されるケースも多い。そして、流される先は大抵が校長の息が掛かったところだ。
しかし、今年度のフリーな卒業生は、校長の勧誘を断っている。つまり、校長よりも優先される権威が学内に存在したことになる。
これは、由々しき事態だ。
「直接釘を刺してみますか?」
部下に、伯爵は首を振った。
大きな力に対し、より大きな力で対抗しようとするのは自分たちの流儀ではないという、確固たる信念からだ。大きな力と大きな力がぶつかり合えば、生まれるのは破壊と衝撃である。物を壊し、命を奪うのが仕事の血生臭い軍務閥や、争い事がド下手な内務閥と、自分達はそもそも違う。見ている目線が違う。伯爵は、そう教わって来た。故に、信念に従って行動するまで。
「……いや、止めておこう。モルテールンの倅は、思っていた以上に出来る。ならば、敵にせずに味方にするのが我々のやり方だ。幸い、人事権を校長が持っている今ならば、打てる手もある」
「学内の再配置……ですか」
「そうだ。しかし、閑職に追いやるという訳にもいかない。表向きは我々に協力的な人間を冷遇すれば、悪影響は大きい」
自分たちに協力的で友好的な人間を露骨に冷遇すればどうなるか。他の協力的な人間や、友好的な人間が、自分たちの心情を疑い始める。仲の良かった友達さえイジメるような人間に、誰が親しく近づこうとするだろうか。人間性まで疑われかねない。そうなると、まともで誠実な人間や、有能な人間ほど距離を取る。
特に人付き合いが重要な外務の人間としては、これは致命的ともいえるダメージだ。
一度友好的な顔を見せたのなら、相手に非が無い限りは友好的な態度を取るべき。少なくとも、その振りは見せるべき。
「ならば、気付かれぬような足かせを嵌めるしかありませんな」
「うむ。学校の新任教官という程度では不足だった。もう少し、強力な足かせが必要か……」
伯爵は、更なる企てに知恵を絞るのだった。