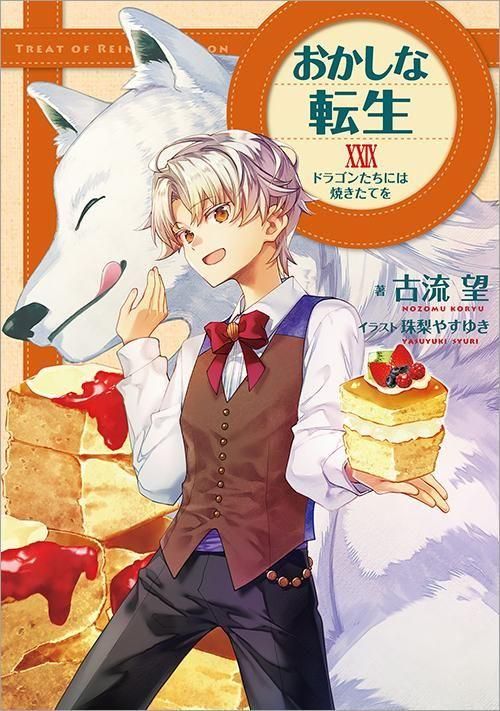221話 現状把握
藍上月初旬、神王国モルテールン男爵領には、初々しい若人たちの姿があった。寄宿士官学校の卒業生たちで、首席を筆頭に上位卒業(全体三分の一以上の席次)ばかりが十六名というエリート集団。
彼らは卒業間際に色々とトラブルに見舞われたものの、無事にモルテールン家に雇用されて従士となった者達であり、目下のところ新人教育の真っ最中である。希望と不安と期待を胸に、一人前の稼ぎ手となる晴れ晴れしいスタートの為に目を輝かす。
彼らの前には、中年男が一人。子供が生まれたばかりのモルテールン家従士長である。
「うっし、今日はうちの叙勲立家から現在まで、順を追って成長過程を説明してくぞ。分かんねえことがあればすぐ言え。後からまとめて聞かれても、答えられねえかもしれねえしな」
寄宿士官学校上位卒業者。つまりは神王国中から選りすぐりの原石を集め、四年をかけて研磨し、良質のものだけをより分けたような十六人である。頭の悪い人間は一人も居ない。それだけに新人教育も生半可な人間には務まらない。
最初は去年と同じように適当にと言う話だったのだが、若手を始め古参の人間まで嫌がった為、結局シイツとペイスが教師役となっている。それもそうだろう。例えるなら、町工場のように細々とやっていた会社に、東大卒や京大卒の新卒がどっと入社してきたようなものだ。下手をすれば、今いる人間よりも優秀かもしれない。教える方も気後れしてしまうのは当たり前だ。責任のたらい回しが行われた結果、最後に責任を取るのは責任者の仕事、と相成った次第である。
今はペイスが政務の山を片づけており、その一方でシイツが、モルテールン家の成立から現在までの歴史と経済状況について教えているところだ。
基本的に、貴族と言うのは自分たちの歴史を大事にする。貴族家としてのアイデンティティになっていることも多い。貴族が貴族として特権を享受する理由は、大前提として初代が貴族位を叙勲したことから始まるからだ。例外は王家だけである。
ご先祖様が素晴らしい功績を立て、今なお輝いているのだ。と、多くの貴族家では考えている。これを無視しては、そもそもの存在意義が揺らぎかねない。初代の功績や歴代当主の功績が大したことがないと仮定した場合、ならば何故貴族なんだ、という矛盾を産む。貴族のアイデンティティとして、大前提が先人の偉業なのだ。
故に、貴族は誰しもが“自分の家の歴史”を学ぶ。
手柄、功績、貢献、能力などを認められて叙勲され、それを代々の当主が受け継いできた。だからこそ貴族は特権を持つ。これは貴族の基本概念だ。
自分たちは凄い。何故なら、偉い人の子孫だから。こう考えるのが貴族というもの。
自分たちは特別だという特権意識の温床では有るものの、同時に貴族としての誇りを持つ根源でもある。
先祖に恥じぬ人間になれ。貴族として生まれたものは、大なり小なりこの言葉を聞かされて育つ。
そして、貴族家に仕える人間にも同じことが言える。
今日の健康状態を正確に知ろうとすれば昨日のご飯が何だったかを知らねばならないし、ここ最近の運動状況を知っておいた方が良い。同じように、今の主家がどういう状態なのかを正しく理解しようとするなら、過去がどういうものであって、何をしてきたかを知らねば話にならない。
自分たちが仕え、忠誠を捧げる家がどういう家なのか。知らずにいるなどあり得ない話だ。何を為して貴族となったのか。今までどのようにして家を守ってきたのか。何を役目としている家なのか。今どういう状況なのか。知らずにいい仕事が出来るわけがない。
十六人の新人達は、至極真面目に従士長シイツの話を聞く。
「あ~ここにいる奴は当然知ってるたあ思うが、うちはまだ家を立てて日が浅え。うちの大将……カセロール=モルテールン卿が叙勲して二十五年? 二十六年? 三十年には足りねえと思うが、まあそんなとこだ。歴史っつってもさほど長いわけじゃあねえ。他所に比べりゃ、爪の先ぐらいなもんだろうよ。しかし、内容は濃い。覚悟しとけよ」
シイツの脅しとも取れる言葉に、新人達は居住まいを正す。シイツはお行儀の良い若者を一瞥すると、昔を語りだした。
「ありゃあ王都防衛戦の時だったか。王様が若くして亡くなったってんで、周り中が敵になって戦争になったことがある。お前ぇらがまだ生まれる前の話だ。ここら辺は学校で習ったろうが、俺や大将もその戦争に居た。酷え戦争だったぜ。当時は王子だった今の王様の側でよ。こっちは千もいるかどうかって敗残兵。敵さんは万を超す大軍。当時の俺は傭兵、カセロールの奴は実家の居候。負けを覚悟した戦でよ。傭兵仲間と、どうやって逃げるかを真剣に話し合ってたな」
昔を語ると饒舌になるのは、年を食った男の共通する特技のようなものである。若かりし頃の武勇伝を語るのは、先達の特権だ。シイツも語り方が堂に入っており、口調も実に滑らかだ。
「そんな中、カセロールがやってきてよ。勝てる方法がある。自分に手を貸して欲しいって言いだした。俺ぁあん時はカセロールを心底馬鹿にしたよ。この状況で何が出来るんだ馬鹿野郎ってな。死にたいなら手前ぇだけで死ねやって話よ。しかし、奴さんがあんまり真剣だったんで、俺の魔法……【遠見】を使って、敵の指揮官を探してやった。勝利の前祝いで飲んでる輩も居たんで、そのまま教えてやったよ。そしたらあいつが自分の魔法で、敵の指揮官を根こそぎ斬りに乗り込みやがった。俺らも驚いたが、既に勝った気でいたあちらさんはもっと驚いたろう。そりゃもう敵は大混乱よ。気が付いたら俺達が勝ってた。あんときはもう無我夢中でよ。何をやったかも覚えてねえ。とにかく勝ったってのは分かった。周りの連中が、泣いてたからな。嬉しくて泣いたんじゃねえ。生き残ったことに安堵して泣くんだ。死にたくねえ、死にたくねえって戦って、死なずに済んだとほっとして。……ま、つまりだ。誰が見ても、うちの大将が一等の手柄だよな」
圧倒的に不利な状況下、滅亡の瀬戸際まで追い込まれた。そこからの大逆転劇の立役者となれば、何も事情を知らない人間から見ても大手柄である。
歴史に名を遺す偉業。このあたりの武勇伝は、吟遊詩人が幾つもの歌を作って歌い、数多くの劇団がこぞって演じた内容であるため、知らない者など居ない。少なくとも、新人達は全員が知っている。
「それで、従士だったカセロールを貴族にって話になるわけだが……この時も色々あってな。俺も同じころに誘われて部下になったわけだが、貴族ってのは汚え連中だと思ったぜ。戦争が終わってから、自分はどこそこを守っていただの、なにがしと戦っていただの、胡散臭え話をしてよ。カセロールの手柄も、運がよかっただけだの何だのと、足を引っ張る連中が腐るほどいた。何度剣を抜きかけたことか……いや、実際に抜いたこともあったか」
貴族にとって、自分の家を守ることは神王国の存亡よりも優先される。必要とあれば、神王国を見限って他国の臣下となってでも家を守る。そう考えた人間は多かった。
例えるなら会社が明らかに倒産寸前の時、社員は自分の家族を最優先に考え、必要とあれば待遇が悪くなってでも他社に転職しよう、と考えるようなものだ。最後まで会社を支えようと考える人間は稀だろうし、ましてや私財を投じてまで立て直そうと考える人間はいない。
だからこそ最後の最後まで神王国の為に尽くし、自分だけなら容易に逃げられたはずなのに、魔力的に限りのある【瞬間移動】を、仲間や家族を逃がす為でなく、王家の為に使ったカセロールは美談として語られるのだ。
しかし、カセロールが美談として語られれば語られるほど、王家が無くなることを見越して動いていた連中は悪し様に映る。国が立ち直った時、王からしてみれば、逃げようとしていた連中など裏切り者にしか見えなかったはずだ。英雄譚の大好きな民衆にとっても、自分たちの利益のみに終始した連中は矮小に映る。
自己保身は貴族の得意分野。戦後に裏切りが明らかになった者、明らかにクロだった者は粛清の対象となったわけだが、日和見的な灰色な対応をとっていた者も多かった。
援軍も出さずに領地に籠っていた者は、自分たちは領地を守るという職責を果たしていたのだと訴えたし、敵側につこうと準備をしていた者も、あれは王家救援の為の準備だったと言い張る。
それはもう、ありとあらゆる言い訳が飛び交い、嘘や隠蔽工作が横行した。つまり、保身を考える人間の汚い面が一気に集まった、と言うべきなのだろう。
当然、自分たちの保身のために、カセロールを貶める工作も行われた。一番の功績が大したことが無いとなれば、自分たちに大した功績が無くとも目立たなくなるからだ。素晴らしく飛び抜けた存在が上にあるから、下の連中との落差が目立つ。ならば、飛び抜けた杭を下げてやれと考える人間は数え切れないぐらい居た。何せ、当時のカセロールは勢力的にも弱小も弱小。庇護者も居ないカモでしかなかったのだから。
「結局、カセロールは騎士爵になった。本来ならいきなり男爵位をって話もあったんだが、足を引っ張る連中が躍起になっててな。流石に無理だろうってことになったわけよ。その時に拝領した土地がここ、モルテールン地域だった。家名もそこから付けたんだぜ?」
「モルテールン地域のように広い土地を拝領したのなら、かなりの厚遇なのでは?」
新人から質問が飛んだ。これにはシイツも苦笑いである。
モルテールン地域は、広さだけなら国内でも指折りの広さがある。ただし、可住地域は恐ろしく狭い。元々地域一帯が高い山に囲まれた土地で、雨に乏しいからだ。
水分を含んだ空気が一定の高さを持つ山脈を越える際、雨を降らせてから山を越えることになる状況は、現代であれば広く知られている。雨陰と呼ばれる現象で、世界中あちらこちらで見られる。四方を山脈に囲まれることで、森の多い土地から、山一つ越えただけで乾燥地帯という、モルテールン地域の気候が誕生したわけだ。極々短い雨期を除き、モルテールン地域は年中乾燥している。
「今でこそ、そこそこ人が住めるようになってるがな。昔は草も生えねえような土地だったんだよ。手つかずになってる土地もあるから、今度見せてやる。砂漠と大差ねえから驚くなよ。見渡す限りの砂と岩ってやつでね。っても、まあ、なもんだから、最初にここに来たときは、総人口が四人だった。鼻たれのガキも入れたら五人か」
「え?」
「人が一人として住めない土地だったんだよ。盗賊すらいやしねえ。大将、俺、爺さんにコアン。ついでに爺さんの息子。まずやったことは水を探すことだったっけか。二ヶ月ぐらいかけて貰った領内をくまなく探したが、一滴もねえのよ。知ってるか? 人間ってなあ喉が渇きすぎると小便も出なくなるんだぜ? 大将の魔法が無けりゃ、俺らは干上がってただろうよ」
シイツの言う言葉は、真実である。総人口が五人。嘘偽りなく、カセロール達以外には人が居なかったのだ。過酷な環境であったことも要因だが、隣国との緩衝地域であったことも理由にある。戦争に勝ったからこそ下賜出来たが、そうでなければ隣国に気を使って、今でも名目上王家直轄のまま放置されていたことだろう。
人跡未踏の不毛の大地。それがモルテールン地域だった。
「一応、領地と一緒に金も結構貰ったんだが、井戸掘りやら何やらですぐに消えた。まともに農作物が作れるようになるまで、三年以上かかった」
「そんなにかかったなんて……」
新人達は、モルテールン領の悪い噂は聞いていた。しかし、噂を鵜呑みにするほど考え無しな人間は一人も居ないわけで、自分の目で見てから判断する者ばかりだ。彼らの目には、モルテールン領はそこそこ豊かな領地に見えた。
ハリエンジュを基本の植生とする森があり、立派な貯水池があり、それなりに収量の有る畑が広がり、東部地域では牧畜も行われていて、製糖産業や製菓産業といった地域特色にも恵まれる。
流石に、交易拠点となる立地であったり、王都近郊といった豊領・富領とは比べ物にならないが、貧しいと自虐するほどでも無い。
だからこそ、彼らにはモルテールン領がカラッカラのド貧乏領だったことに実感が湧かないのだ。シイツの話を聞いて、改めて驚いている。
「当然、領地運営は赤字だ。毎年十クラウンぐらい赤字でよ。大将が傭兵紛いなことをやって赤字を補填してたんだぜ? こんな苦労するなら、貴族にならずに傭兵にでもなってた方が贅沢に暮らせたんじゃねえかって笑ってたぜ」
「へえ」
まだシイツもカセロールも若かった頃の話である。
貴族の常識的に、比類なき大功を挙げた英雄を野放しにするのはあり得ない話であり、貴族たちはなんとかカセロールを自分達が利用できるようにしたかった。
そこで、まともに開発すれば金が湯水のごとく必要な土地に縛り付けた上で、呼び水として纏まった金を与えたのだ。
貴族の策謀に疎かった当時のカセロール達は、陰謀に気付かず、貴族になれたと喜び、土地を貰ったと奮起し、一生遊んで暮らせるほどの大金を貰って笑い、夢と希望を胸に開発資金を投じた。そう遠くない時期に農地も出来て、暮らしも安定するだろうという希望的観測の元に。
だが、現実は甘くない。文字通り砂漠に水を撒くような状況。結果として金が足らなくなり、金を見返りとして他家の貴族に良いように利用され、飼い殺しにされてしまった。
どこかで諦めても良かったのだろう。土地を返上し、王都なりの都会に家を買い、出稼ぎで稼いだ金でそこそこに暮らす。職位無しの宮廷貴族のような立場だ。出来なくは無かっただろう。しかし、それに気付くころには、投じた開発資金が膨大になり過ぎていた。損切りを決断できずにずるずると損を膨らませる。投資初心者にはありがちな失敗だろう。
少なくとも若かりし頃のカセロール達が、投資という言葉すら知らず、領地経営についても素人な人間であったことは間違いない。
「ところが、だ」
ふと、シイツの声色が変わる。
「うちの坊……ペイストリー様が産まれてから、流れが変わった。特に、坊が喋り出したあたりから、もう驚きの連続だぜ?」
「喋り出した頃?」
「おう。二歳か三歳ぐらいだったか? 自分で家の裏を耕して実験しだしてよ。最初は、変わった遊びをするって笑ってたわけよ。それが四つになるころには豆を作れば畑の土が良くなるって言いだした。誰の目にも明らかな実験結果のおまけつきで。信じられるか? まだ歩き出したばかりのガキがだぞ?」
「そんな、まさか」
「だろ? そう思うよな? だが、事実でよ。大将も『どうせ何をやっても駄目なら、息子の好きなようにさせてみる。駄目で元々だし、いっそ諦めもつく』ってよ。そしたらこれが大当たり。豆の収益だけじゃねえ。麦の収穫も倍ぐれえに増えやがった。俺も驚いた。いや、驚かなかった奴は居なかったんじゃねえか?」
「私たちも驚いてます」
新人達にとっても、耳を疑う内容だった。まともに言葉を喋ることすら怪しい年ごろで、既に大人顔負けの農業改革を主導していたとは、誰が信じるのか。普通の常識があれば、荒唐無稽な話だと一笑に付す。
新人達も、ペイスの非常識さを寄宿士官学校で実感していなければ、こうして直に体験談を聞いても信じられなかっただろう。
「坊の出鱈目さは、枚挙に暇がねえ。子供だけを率いて五歳で狼を撃退。七つで聖別して魔法を授かる。同じ年には、伯爵家の正規軍すら跳ね除けた百人の盗賊相手に大立ち回り。似顔絵で一財産築いたかと思やあ、それを元手にあっさりと森を作っちまう。砂糖をうちで作れるようにしたのも坊だし、砂糖をただ作るだけに飽き足らず、製菓事業も立ち上げて大成功ってなもんよ。ああ、酒も造ったな。俺ぁ、色んな経験してきたし、色んな奴を見てきたが、坊だけは予測ってもんが付かねえ」
「ほへえ……」
いよいよもって、新人達の顔がぽかんとした呆け顔になった。
ペイス当人は、たった一つの目的の為に当たり前のことを当たり前にしているだけだというのだが、功績を並べてみれば狂人のそれである。おおよそ、まともな人間の為すことだとは思えない。
「その甲斐もあって、三年程前からうちの経営は通年の黒字になってんだよ。経営規模の拡大率は、ここ五年平均だと年十割三分だ」
「じゅ、十割? 五年で十割ってことは、一年で二割増しってことですか?」
一年で二割も収入が増える。それが毎年というなら、驚くべき数字だ。新人達はそう思った。しかし、シイツは首を横に振る。
「違えよ。毎年十割近く伸びてんだよ。五年平均でそれだからな。ここ三年に絞ると、もっと高い」
「うひゃあ!!」
新人の一人が、素っ頓狂な声をあげた。経済に明るい人間だったのだろう。毎年の領地の経営規模が十割増しになる意味に気付いて驚いたのだ。領地の経営規模、すなわち経済規模が倍増している。元々がド貧乏という点を差っ引いても、驚いて当然なのだろう。
現代の国の経済規模は、GDPやGNPという指標で表される。指標的にはこれに近しい。GDPの伸び率が100%を超えているような話というのも現代では想像もつかないだろう。
しかし、これにもちゃんとした事情がある。モルテールン地域より農業に向く旧リプタウアー領の併呑であったり、各種の産業政策が当たりに当たった結果がこれなのだ。
ただでさえ希少で付加価値の高い砂糖を領内で生産し、それを使ってお菓子を生産して付加価値を付け、おまけにブランド化して付加価値を付け、運搬はローコストな魔法がありと、付加価値が三乗にも四乗にもなる産業が、今のモルテールンの主産業である。
ペイスに曰く、伸びている現状が凄いのではなく、伸びる前の惨状が酷過ぎたのだとか。
「ま、そんな急激な伸びも、そろそろ終わりだろうと思ってる。これ以上のことは、幾ら坊でも難しいだろう。本人もそう言ってたからな。よほどのことが無い限り、これからは安定的な成長になる。なら、大事なのは突飛な才能じゃねえ。ミスの少ない手堅い優等生だろうよ。つまり、お前さんらの力が必要になるってことだな」
新人達への状況説明が続く。シイツにしてもモルテールン領の現状と、それに至る経緯を細かく説明していく。税の現状、今後の計画、軍備についてなども、ざっくりとした説明があった。時折笑いが混じるのは、シイツの人生経験から来る話術の賜物だろう。
そんな説明が大よそ終わるころ。説明役の交代にと、ペイスがやって来た。
「皆さん、やってますね」
「お、坊。もうそんな時間でしたかい」
部屋にノックもせずに入って来たペイスは、いつも通りニコニコとした笑顔だ。外見だけなら、大人しい良家のお坊ちゃんという雰囲気である。年も十を超え、段々と背も伸びてきて顔つきも精悍になって来た、とは親馬鹿たるカセロールの評価だ。
「よっす、シイツのおっちゃんも大変だな、見学に来たぜ」
そして、ペイスの傍には更に二人の若者が居た。元気に挨拶したのは男であり、その横には男装した女性が佇む。
「一応、全員に紹介しておきましょう。私兵団副団長コアントロー=ドロバの息子マルカルロと、工務担当責任者グラサージュ=アイドリハッパの娘ルミニートです」
ペイスに紹介されたのは、モルテールン領悪戯トリオの面々。マルクことマルカルロと、ルミことルミニートの二人。これにペイスを加えた三人が、お纏めお買い得セットになって悪戯トリオだの悪ガキトリオだの言われる。
幼い時から、散々に大人たちを困らせてきた悪童。勿論、言わずもがな悪ガキの大将はペイスであるが、二人も中々に素晴らしい経歴の持ち主である。
大人たちの目を盗んで真剣を振り回すことなど序の口で、投石に熱中するあまりに当ててはいけないものに対してクリティカルヒットをかましたり、弱い者いじめをする者を見つけて十人以上を巻き込む大喧嘩になったこともある。
獰猛な野獣相手に子供たちだけで立ち向かったこともあったし、村に来た怪しい連中を捕まえると張り切って、本物の犯罪者と鉢合わせたこともあった。
大けがをしたことも幾たびか。盗賊に攫われるだの、決闘騒動をやらかすだの、大人達を困らせることに関しては、モルテールン領屈指の悪ガキである。
その上、盗み食いや建造物侵入の常習犯である。ペイスのお菓子がいつの間にか消えていたら、十中八九犯人は二人のうちのどちらかだ。年々そのテクニックが巧妙になっていると、これまたモルテールン家の首脳陣が頭を痛めていた。
「よろしくなっ」
そんな二人ではあるが、褒めるべきところもある。モルテールン家に対する親愛の情は間違いなく本物であるし、身内を守ろうとする正義感も確かなものを持っている。この点は、モルテールン家の上層部全員が認める美点だ。郷土愛も、他所からの移住組に比べれば高い。
つまり、短所もあれど長所も大きい。ならば、後は使い方と育て方次第。斯様な意見が上層部にあり、これからの成長が期待されている。
ちなみに、人材育成と獲得が大きな課題となっているモルテールン家の特殊事情を鑑み、彼らも既に聖別の儀を行っている。一応は家中の重鎮の子弟ということで本聖別を受けたが、魔法は授かっていない。これは、確率論的にも当然のことだろう。
マルクは自分も魔法が使えるようになることをかなり真剣に望んでいたのだが、この世界で魔法を使える人間は本当に希少だ。魔法使いにならない方が普通なのである。
「マルク、一応ここにいるのはお前よりも遥かに上等な連中だからな。敬語を話せたあ言わねえが、舐めた態度を取ってると痛い目見るぞ」
頭の後ろで手を組みながら雑に立って挨拶するマルクに、従士長は苦言を呈する。礼儀正しくお上品にしろなどというのは、モルテールン家の家風にあわない。故に上下関係が緩くても、それは構わない。しかし、上下関係を弁えた上で緩めるのと、上下関係の弁え方を知らないのとでは意味が違う。
マルクの場合は、後者である。
「そうなのか? ま、関係ぇねえよ。俺だって、結構やるし。あんたらはあんたらで頑張りゃいいんじゃねえか?」
「けっ、良く言うぜ。マルクの腕なんて、俺以下だろ」
「あんだと!! ルミなんか、この間俺とやって泣きべそかいてただろうが」
「ばっ、ふざけんなっ!! いつ俺が泣きべそかいたよ。泣き虫野郎はマルクの方だろうが!!」
そして、ルミとマルクがやいのやいのと言い合いを始める。中々に白熱した罵り合いの様相を呈してくる。
そんな様子に戸惑うのは、新しく雇われた若者たちだ。
「……あれ、良いんですか?」
代表者的な立ち位置にあるプローホルが、ペイスに尋ねた。
「良いです。いつものことですから」
そして、ペイスは極自然な表情で応える。
ルミとマルクが口喧嘩でヒートアップするのは、小さい時からの習慣のようなものだと、彼は知っている。喧嘩するほど何とやら。いい加減、そろそろ進展があっても良い二人なのだが、犬も食わないものに手出しするほど、ペイスは野暮では無いのだ。
「仲良しこよしの二人は放っておくとして。これから皆を連れて領内を案内しましょうか」
誰が仲良しだ、という二人の反論の声は、実に息の合ったものだった。