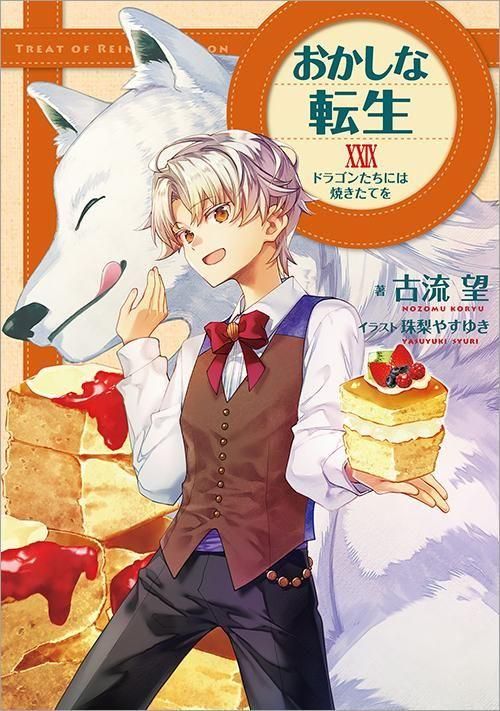217話 近づくその日
ペイスが教官になってから半年。
その力量は、誰の目にも明らかとなっていた。バッツィエン教官の模擬戦に端を発し、その後の学生見学からの噂の広がり。今や学校の名物教官となりつつあった。
元より、普通にしていても目立つのがペイスだ。学内を歩いているだけでも、あれは誰だ、何で子供がいると話題になる。そしてあれこそ噂の少年教官だと訳知り顔で語る輩が出るまでがワンセット。
噂は噂を呼び、物は試しと模擬戦を申し込まれ、ペイスに直接叩きのめされることもあれば、学生同士が戦うこともある。所属学生は勝ち星を積み、そしてその度に大きく成長していった。
先進的かつ合理的な講義を聞き、訓練で体に覚え込み、模擬戦などで実際に試し、反省点を洗い出して次に活かす。目に見えて、という言葉があるように、五人の学生たちがそれぞれに急成長を重ねていった。
寮生活を共にする同級生も居る。劣等生だったはずの連中が、並み居る優等生たちを凌駕し、自信を付けていくのだ。話題にならないはずがない。
オマケに、ペイスは聴講や見学も自由にさせている。講義を聞きたい、或いは聞いて目のうろこが落ちた、蒙を啓かれたという学生の数も増えていく。
卒業を控えた上級生でこれだ。現状で伸び悩みを感じている学生などにとっては、まさに救世主のようなものである。
「今日は、長期間の行軍と補給における注意点について講義します」
「「はい、教官」」
講義室に座る五人の学生が返事をする。そしてその後ろには、数えるのが面倒になるほどの数で見学者が並んでいた。
ちなみに、見学の時に見学しやすい場所を確保するために、朝から順番待ちが起きるという事象まで起き、流石に問題があると教官会議で取り上げられたこともあるほどである。
尚、その時はペイスを批判する声もあったのだが、ペイスが「他の教官が無能のせい」で「自分が被害者」だと暗に匂わせる反論をして、完璧に論破してしまう場面もあったのだが、甚だ余談である。
校長などはペイスの行動を手放しで称賛している。何せ「今まで何を教えていたんだ」という批判は、そのまま校長の権威を向上させることに繋がるからだ。今まで偉そうにしていた教官達が、顔を赤くしたり青くしたりと、カラフルなカラーひよこになっていたのは大したことではない。
「……今日もまた、見学が多いですね。皆さん、担当教官には今日ここに来ることを伝えていますか?」
「はい」
「ならば結構。他の教官方も素晴らしい講義をされていますから、そちらもしっかりと勉強するように」
一体どの口で言うのだろうか、という批判もあろうが、元々ペイス自身は他の教官を貶すつもりなど一切ないのだ。実際、ペイスとは違ったアプローチでありながら、素晴らしい講義をする教官も居る。特に海戦などはペイスは門外漢であるし、専門家の解説などはペイスをして一聴の価値があると言わしめた。
「さて、本題ですね」
ガタガタと、大きな物体がペイスの手によって運ばれる。
木枠で誂えられた、大きな黒板である。見学者が段々増えていったことで、出来るだけ見やすいようにとペイスが用意した。こんな些細なことであっても、学生たちにとっては色々と新鮮な驚きがあるもので、中には黒板とチョークのセットを売ってくれとせがむものまで居るとか居ないとか。
「我々は軍人です。命令があれば、どのような場所にでも出向いて、戦わねばなりません。そして、戦いの多くは長期間の行軍を伴います。むしろ、それが推奨されることもある。何故だか分かりますか? ……そうですね、デジデリオ、分かりますか?」
「は、はい。えっと……せ、戦争において、戦場は敵地であることが望ましいから……で、でしょうか」
「そうです。前の講義を良く覚えていましたね。戦闘行為を行えば、その周囲は否応なく荒れることになります。気の立った兵士の傍に寝泊まりしたいと好む、普通の住人というのも変な話ですから。好んで兵士の傍に来るのは、商売人か敵の間諜です。また、経済活動も阻害されますし、徴発や略奪行為も頻発する。ならば、出来るだけ敵の土地で戦争するのが正解です。自分の家の中で喧嘩するより、外に出て喧嘩しろ、と怒る母親みたいなものですね」
ペイスの言葉に、教室内に軽い笑いが起きた。
「一方において、戦争では物資の消費は著しいものになります。物価の高騰や物資の払底は言うまでもなく不利益です。しかし、物を運ぶというのも限度があり、補給線は短ければ短い程好ましい。さて……これはどうすればいいでしょう。フリーダ、答えてみて下さい」
経済活動の面から見ても妥当な意見だろう。経済活動が阻害される行動は、自分たちの根拠地より離れている方が良い。他方、軍事行動をより優位に進めるならば、根拠地に近い方が有利である。
戦うなら遠い方が良いが、補給するなら近い方が良い。
しかし、ならばどちらをより優先すべきか。ペイスの講義を受けてきていない見学者などは、言われてみてこの矛盾に気付いたらしい。メモ書きをしている連中なども、答えを書きとる為に顔を上げている。
このメモ書きについてはペイスが特に禁止もしなかった為に、闇売買的なルートが産まれており、ペイスを良く思っていない教官の学生や、講義の欠席を許されない学生などにプレミア価格で販売されている。それだけ、ペイスの講義内容を知りたい人間が多いのだ。
特に、初期の講義内容は高値が付いているとか。デジデリオなどは商売っ気には聡いようで、最初期にペイスから受けていた講義の内容についての覚書を小分けにして売り、ちょっとした小金持ちになっていたりもする。
「戦場は敵地を選び、補給も敵地で行う……というのはどうでしょうか」
フリーダが、しばらく考えて出した答え。
中々に面白い意見だった。学生自身が考えて出した答えは、ペイスにとっても望ましい答えだったのだろう。笑顔で頷き、フリーダを褒める。
「正解です。よく分かりましたね。古人に曰く、智将は務めて敵に食む、です。相手の食料を頂戴することが出来れば、これは敵に負担を強いると同時に、自分達の負担を著しく軽くすることになる。何も食料だけに限ったことではなく、必要なものを相手から貰うというのは、合理的な方法です。如何に相手の力を利用するか。この視点は、非常に重要ですので、頭に置いておくように」
「はい」
一斉に、ペンを走らせる音が響く。
答えを聞けばなんだそういうことかと思うだろうが、こういう問題は一番最初にノーヒントで考えた人間が凄いのだ。つまり、フリーダだ。
ペイスの講義内容はいちいち実践的で、それでいて合理的。それだけに、実学を旨とする肉体派も、理論を旨とする知性派も、どちらにも納得しやすい。だからこそ、人気が衰えそうにない。
「しかし、敵の物資のみを当てにするのは下策ですね。敵が焦土戦術を用いることもありますし、元より不確かなものですから。相手に行動を利用されやすい欠点もありますので、やはり補給の体制は整えておく必要があります。これが補給における注意点です。覚えておくように」
「「はい、教官」」
カリカリと書いている学生がまだいるが、ペイスは黒板の文字を布巾で消す。ああ、という悲しそうな声が見学者から聞こえたが、ペイスは彼らに対して講義しているわけでもないので、気にしない。
講義内容を売っているデジデリオからマージンを貰っていることは、関係ないはずだ。
「補給が十全である、という仮定が、とりあえず成り立ったとします。この場合の行軍における注意点とは何か。大事なのは、まず速さです。兵士の数が多くとも、ノロマな行軍ではそれだけ弱体化する。補給の負担が余計にかかるというのもそうですが、相手により多くの時間を与えるというだけでも、主導権を相手に取られがちです。主導権を取られてしまえば、勝てるものも勝てなくなる。仮に、戦う兵士が全て弓騎兵で、補給どころか生活丸ごとを移動させることが出来、遠慮なく略奪する軍隊、なんてものがあれば、世界一の大帝国を作れることでしょう」
ペイスは歴史を知る。それも、今の世界と、他の世界の両方の歴史を。
仮に、遊牧で常に移動する騎馬民族が、強力な武器を持った時にどうなるか、その答えまで知っていたりもする。
現代人なら、ユーラシア大陸に歴史上最大の帝国を作り上げた故事を思い起こせることだろう。
「速さですか」
「更に、地形も重要です。基本的には高さ。高い位置にいるというだけで、有利です。山あいを行軍するとき、高いところに向かっていって戦うような真似は避けなければならない。平地を行軍するときも、出来るだけ高いところに位置するよう心掛けること。馬鹿と煙は高いところが好き、等と言いますが、軍に置いて、馬鹿は低い方を好む」
「はい」
「さて、それでは今日の話を含めて、実践例を紹介します」
ペイスは、何処からか大きな羊皮紙を取り出した。一枚切りのとても大きな羊皮紙だ。
書かれているのは、地形図。等高線やら記号やらで地形が示してあり、更には色も塗ってあるのでとても分かりやすい地図になっていた。等高線もペイスが初めて士官学校に持ち込んだ概念で、平面図で立体を表せることから、今では他の教官も真似をするほどである。
地図の上に、赤と青で色分けされた駒が幾つか置かれた。駒の数は、赤色の方が多いようで、どちらも色ごとに固まっている。
一見するとボードゲームの遊びのようにも見えるが、これは駒を兵に模したもので、机上演習にも使われるもの。学生達には、割と馴染みがあるものだ。
駒一つがどれぐらいの兵力かは時によって違うが、兵の動きを視覚化出来る為分かりやすいと、昔から使われている伝統的な手法である。
「三十年前の、実際にあった戦いの例です。まず、こちらが某伯爵家。兵数は五千程。騎兵も歩兵も弓兵も、全てが混合された、混成軍です。練度はごく一般的なものだったようで、頻繁に休憩を取っていた為に疲労はあまりなかった。対するこちらが、某子爵家。兵数は千程だったそうで、ほぼ全てが騎兵でした。さて、勝ったのはどちらか……順を追ってみます」
かつんかつんと、ペイスが駒を動かす。
赤駒が、地図上の平野部に置かれる。綺麗に並んで置かれていて、それ相応に陣形は整っていたことを表していた。
「最初、伯爵軍はこのように動きました。混成軍が足並みをそろえる為、動きやすい地形を選んで進軍したと思われます。事実、彼らはこのように険しい斜面を避け、広くて視界の広いところを選んで進んだ。対し、子爵軍はこのように動きます。偵察も密に行っていたのでしょうね。伯爵家の進行方向から逸れる形で、このように丘の上に進んだ」
等高線で表される丘の上。地図上のそこに、青い駒が固まった。
「そして、お互いに視認したところで開戦です。この時点、恐らく伯爵は自分が圧倒的に有利と思っていたことでしょう。兵数は五倍。疲労は無い。弓もある。視界も良好で距離もある。伏兵などあり得ない見晴らしの良さです。そこで、伯爵は隊を二手に分け、挟み撃ちを狙いました。こんな感じです」
「おお」
学生たちは、自分が指揮官になったつもりでペイスの説明に聞き入る。
兵数は五倍。仮に自分が伯爵の立場でも、これなら勝ったと思うに違いない。そう、誰もが感じていた。
「対する子爵家は、この動きを待ち受けました。小高い丘の上に陣取って、しばらくは待ちの姿勢を取ったのです。そして、伯爵家の軍の片方がここら辺にまで来たとき、一気にそれに向かって駆け下りた。結果、この伯爵家の軍はまずこちらがこのように負けました。子爵家側は高い位置から駆け下りる騎兵の突撃ですし、伯爵家側は弓を射かけるにも上に向かって撃つ為に威力も減退しました。つまり、効果的な迎撃が出来なかった。丘を駆け上ったことで、疲労が一気に高まったというのもあったでしょう。もしこの疲労度合いを知りたい人が居たら、坂道ダッシュをプレゼントします。要りますか?」
「「遠慮します!!」」
ペイスなりの冗談なのだろうが、仮にこれに頷けば、本気で坂道を走り込むような特訓をしかねない。ペイスの非常識さとスパルタっぷりは、最早学生の間では常識とされていた。
「かくして、一対五の戦力比は覆されました。歴史上に実際にあった、実例です。参考になると思います。この勝因、敗因は幾つかあると思いますが、高い位置に位置どる重要性や、行軍時の高さ意識の重要性、そして速さの重要性も理解できると思います。さて、今日の宿題です。伯爵家は、どうすれば勝てたか。また、この戦いを自分が率いていたらどうするか。注意点は何か。赤青の双方でそれぞれに考えて来なさい。では、今日はここまで」
「ありがとうございました」
今日の講義内容も濃かった。
そう、満足げに頷く学生達。彼らは、これから食事だ。どうせド級に不味い飯を食うわけだが、空腹は最高の調味料である。
ペイスが一足先に部屋を出たところで、引き止める声があった。最近では、割と良くあることだ。恐らく、自分の教官の講義が早く終わった学生が、ペイスの出待ちをしていたのだろう。
「モルテールン教官、是非私も教えて下さい」
また一人、ペイスの元に学生が直訴に来た。若い学生、と言っても殆どが該当するのだが、若者の中でも更に低年齢の部類に入る学生という意味だ。
この学生は優秀な成績で入学し、将来の首席候補の一人と目される二年次生。ペイスの噂を聞き、講義内容のごく一部を漏れ聞いたところで内容に衝撃を受け、是非とも所属を変えたいと訴えているのだ。こんなことが最近は増えていた。
しかし、学年が始まってすぐならいざ知らず、現状ではそう簡単には許されない事情がある。
「駄目です。ヴァンデン教官からくれぐれも学生を引き抜かないでくれと言われていますので、先にそちらを説得してからにしなさい」
一考の余地もなく断るペイス。今まで、一度も頷いたことは無い。
ペイスの講義が素晴らしいとしても、他の教官だって今まで成果を出してきている。得意不得意は有るかもしれないが、彼らにもプライドがあるし、学生たちに用意した教育プランだってあった。
元々ペイスに紹介の有った五人は、将来の見込みがない、或いは現在の教官と致命的に合わないと思われたからこそ移籍出来たのだ。
優秀な学生。見込みの有りそうな学生。教育内容が合っている学生。これらは、他の教官にとっては自分の成果でもある。引き抜きを看過されるようなものでもない。
肩を落とす学生。それもそうだろう。ペイスに教えられた学生が目に見えて成長しているのだから。自分もそうなれるはずと思えばこそ、残念でならない。
若者は、断られたことで気を落とし、とぼとぼと廊下を歩く。
すると、物陰から声を掛けられた。
「君、少し良いかな」
「はい、何でしょう」
声を掛けてきたのは、見覚えのある教官だった。自分の担当教官ではないが、それなりに優秀な学生を抱えているという噂のとある教官。
「モルテールン教官の教えを受けたいというなら、一つ良いことを教えてあげよう。私の手伝いをしてくれれば、来年度以降に所属を変われるようになるかもしれないぞ」
学生たちが将来の希望を胸に抱いて勉学に励む頃。
卒業試験は間近に迫っていた。