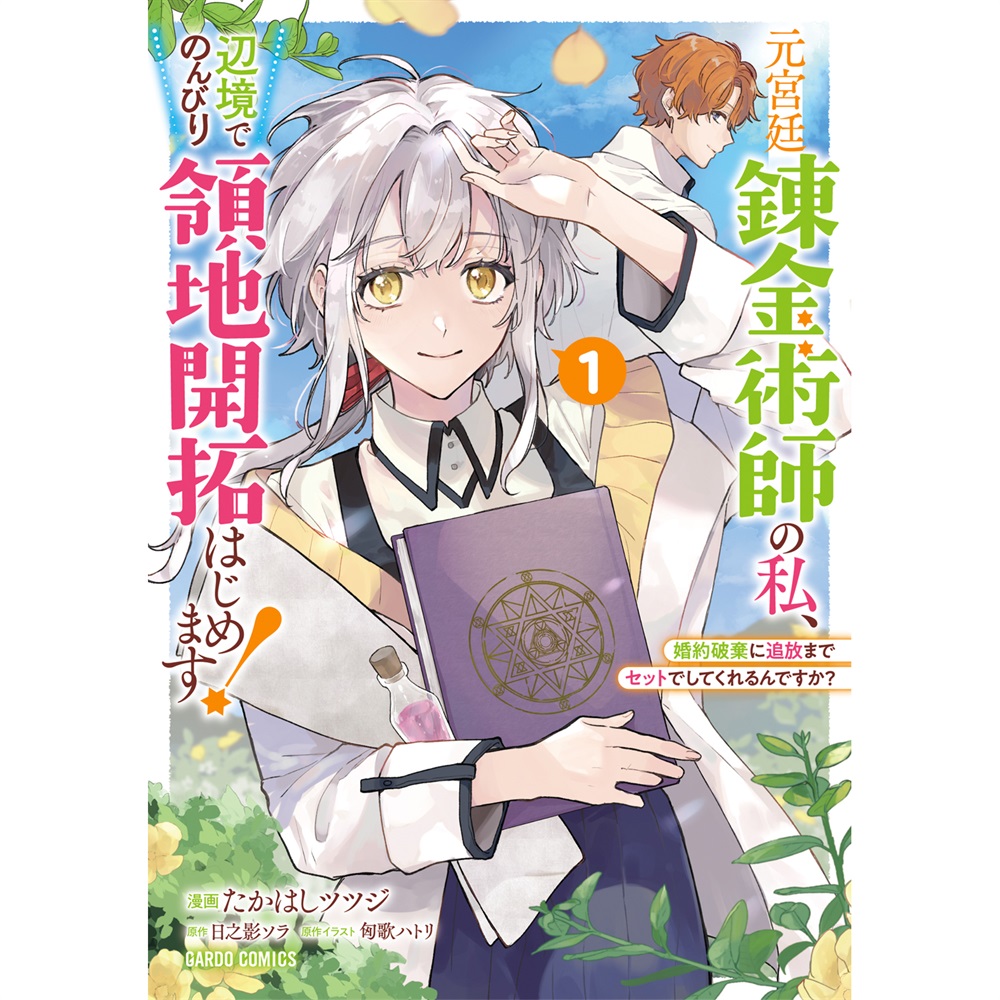王都でもお変わりなく①
世界各地に点在するアダムストの拠点。
そのうちの一つに、黒い騎士が帰還する。
「ただいま戻りました、姫」
「お帰りなさい。ラース」
薄暗い部屋に一人の少女が座っていた。
身体は小さく、色白で、ドレスを着た人形のような佇まい。
顔は部屋の灯りが少ないためハッキリとは見えず、口元が微かに覗ける。
「また随分と咎落ちを消費したみたいね」
「任務を果たすこともできず申し訳ございません。なんなりと処分はお受けします」
「ふふっ、私があなたにそんなことを求めていないのは知っているでしょう?」
「……」
「鎧、壊されたのは初めてよね?」
砕かれた鎧の一部から、赤い瞳が少女を見る。
「はい。目に余る失態です」
「ふふっ、そう思ってないでしょう? 嬉しそうな顔をしているわ」
「――!」
鎧の裏に隠れている表情を、少女は見抜いていた。
ラースは笑みを浮かべている。
無敵の鎧を身にまとい、一度も素顔を晒したことのなかった男が、自分よりはるかに力量で劣る者たちに砕かれた。
戦士としては屈辱である。
しかし、それ以上にあふれ出る充足。
「面白い人だったでしょう? 彼は」
「はい。姫様のおっしゃっていた通り、見どころのある男でした。レベルをあげ、経験を積めば……いずれ我々にとって最大の脅威となるかもしれません」
「脅威にはならないわ」
「……」
少女は微笑む。
「タクロウ……彼はいずれ、私の夫になる男よ。共に歩み、世界を壊すの。ラース、あの人を導いてあげて」
「……承知いたしました。イブ様」
彼女はアダムストの姫。
アダムスト……アダムは始まりの人間を表す言葉であり、その片割れはイブと呼ばれている。
アダムとイブ、二つの命が交わる時、人類は誕生した。
彼らは繰り返す。
世界の始まりと……終わりを。
◇◇◇
俺は夢を見ている。
それを自覚することがあるそうだ。
明晰夢というやつか。
でも、真っ暗で何もない。
自分の身体すら認識することができない暗黒の世界。
こんな場所で夢だと気づいても、何もできない。
――タクロウ。
ただ、誰かが俺の名前を呼んでいた。
「……ぅ……朝か……」
夢から目覚めた俺は、見慣れない天井に数秒だけ困惑する。
始まりの街の宿屋じゃない。
似ているけど、ジーナの屋敷でもない。
ここはどこだ?
心の中の問いに答えを出すように、もぞもぞっと俺の身体に抱き着く肌の温もりを感じる。
「うーん……タクロウ……」
俺の身体に抱き着いているのは、三人目の嫁となったラランだった。
彼女の幸せそうな寝顔を見て思い出す。
そうだ。
ここは俺たちの新しい拠点で、昨夜はラランと夜を過ごしたんだ。
ふと時計の針が時間を告げる。
「朝飯作らないと。ララン、もう朝だぞ?」
「う……朝ぁ?」
「そう、朝だ。みんなの分の朝食を作りに行かないと。だから起きてくれ」
「……! な、なな、なんでタクロウが私のベッドにいるんだよ!」
唐突に目が覚めたラランが飛び起きて、ベッドの上で距離を取る。
驚きはしない。
俺は呆れてため息をこぼす。
この後の流れも決まっている。
「はぁ……それ何度目だ? 一緒寝たからに決まってるだろ」
「な、なんで一緒に寝てるんだよ」
「だーかーら! 夫婦になったんだから当然だろ?」
「夫婦……そっか。そうだな。私たちは夫婦……だもんな。えへへへ」
ラランは幸せそうな声を出す。
だらしなく、愛おしい笑顔が見られるから、俺もこのやり取りに付き合っているけど……。
「さすがに三回目だぞ」
「悪い。なんか朝になると、全部夢だったんじゃないかって思っちゃうんだよ。こんな幸せなの……私の人生にはありえないからさ」
「その気持ちはわからなくもない」
「だろ? こんなに幸せでいいのかな……」
ラランはそう呟きながら、自分の身体を包むように両腕を握る。
ぼっち生活が長いと、誰かと一緒にいる幸福を感じすぎて、夢じゃないかと疑ってしまう。
俺も同類だから彼女の気持ちは理解できた。
要するに、幸せ過ぎて不安なのだ。
贅沢な悩みだと思いつつ、夫として妻の不安を解消するために行動する。
「いいんだよ、幸せで」
「タクロウ」
手を握る。
ラランは少し冷え性で、朝は手が冷たい。
彼女の手を温めるように、俺の手で包み込む。
「夢だと思うなら触って確かめてくれ。俺はここにいる」
「……温かいな」
彼女は俺の手から伝わる温もりを感じて、幸せそうに笑みをこぼす。
やっぱり彼女が一番寂しがり屋だ。
「さて、朝食の準備をしに行こうか」
「そうだな。私も手伝うよ」
「いつもありがとう」
「いいって! 好きでやってることなんだから」
自分で言いながら照れるララン。
彼女は三人の嫁の中で一番寂しがり屋で、そして一番初心だった。
しっかり目を覚ました俺とラランは、着替えてから寝室を出る。
他の三人はまだ寝ている時間だろう。
起こさないようにゆっくり階段を下り、キッチンへ向かった。
一般家庭のキッチンにしては大きい。
二人が並んでも、動き回れる十分なスペースがあって快適だ。
「キッチンが広いのはいいな」
「そうだな。こうやって一緒に料理してても邪魔にならないし」
「だな」
朝食の準備をしながら俺たちは話す。
あの日、ラランを救出してから俺たちの生活に新しい変化が訪れた。
変化の一つが、生活拠点だ。
ここは王都の貴族街の外れにある小さ目の屋敷。
元々はなんとかっていう貴族の別荘だったらしいけど、その家が没落してから空き家になっていた。
それをラランのポケットマネーで一括購入し、俺たちが使うことになって、現在に至る。
「ありがとな。家まで買って貰って」
「いいって。私にも必要だったし、ジーナの屋敷は使用人が多くて緊張するんだよ」
「俺もだ。執事とかメイドには憧れてたけど、いざずっと近くにいられると正直ストレスだよな」
「やっぱりタクロウもか」
「俺もちょっと前までぼっち生活だったから、その弊害だ」
「ははっ、私たちそういうところも似てるよな」
俺とラランは立場や生まれこそ違うが、感性はかなり近い。
人づきあいが苦手だったり、一人が得意だけど、孤独が好きというわけじゃない矛盾とか。
似た者同士だからこそ、夫婦になったことに必然性すら感じているほどだ。