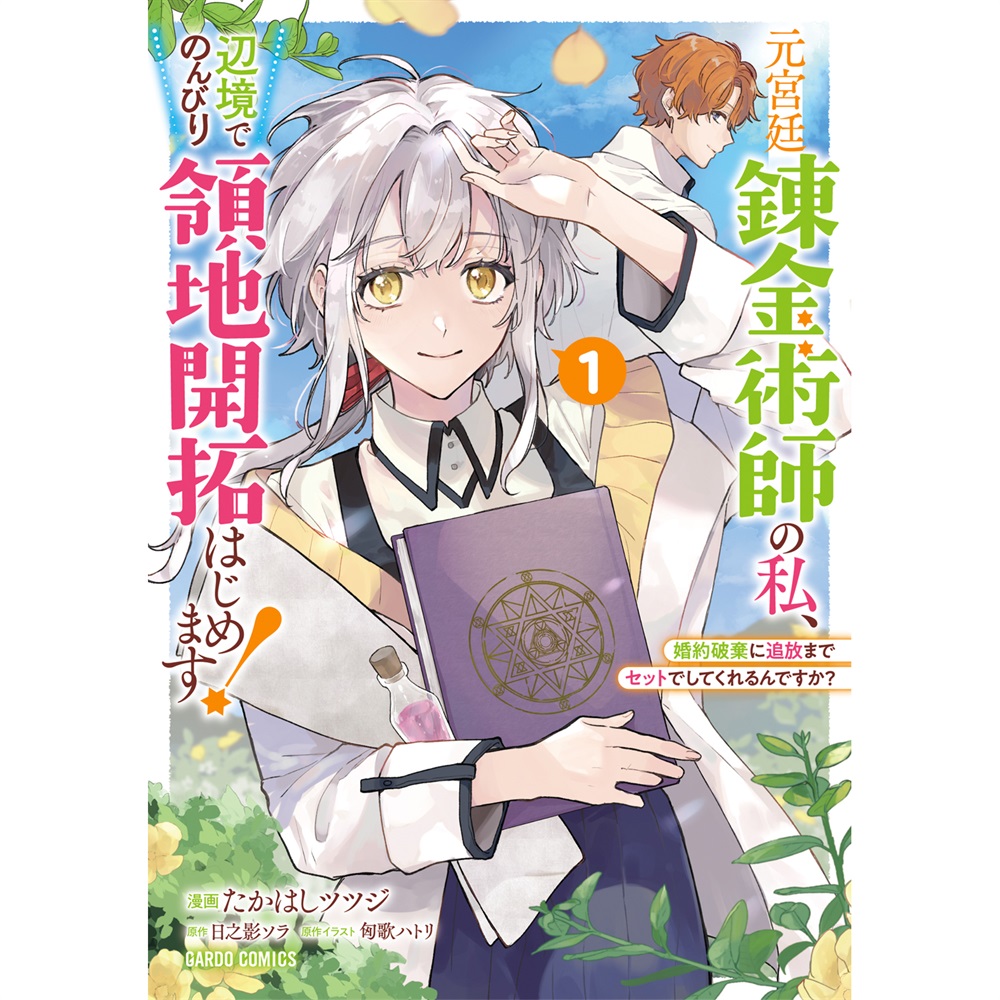孤独騎士の誘惑③
ラランの隠れ家に訪れ三日後の夕刻。
俺とラランは並んでキッチンに立っていた。
「そっちの野菜、皮剥いて適当なサイズに切っておいてくれ」
「了解。切ったら全部茹でればいいよな?」
「ああ、湯で終わったら教えて。あ、あとそっちの棚の皿も用意しておいて」
「もうしてあるよ」
「お、さすが」
ここ数日、ラランから料理を教わったり、俺からラランに料理を教えたり。
一緒に料理をしていたから、自然と食事の準備は二人でするようになっていた。
その様子を後ろから三人が眺めている。
「随分と仲良くなったようだな」
「もう夫婦みたいだよなー」
「このまま結婚しそうですね。するなら早くしてください」
外野がうるさいな……。
確かに仲良くはなったと思う。
料理以外でも話す機会が多く、この数日間ならカナタたちよりも一緒にいる時間は長いはずだ。
未だに色仕掛けは諦めていない様子で、風呂に乱入したり、夜の布団に入ろうとしたり。
結局そこから発展はせず、雑談して終わるのだが……。
ラランは積極的だけど初心だから、いざという時は引いてしまう。
エロいことがしたいけど、女の子を前にしたら緊張して何もできない童貞の思考にそっくりだ。
「おい、何か今失礼なこと考えてるだろ」
「気のせいじゃないか?」
「嘘つくな! どう見ても私のこと童貞思考だなとか思ってた顔だろ」
「……ラランはエスパーなのか?」
俺の思考を的確に射抜いてくるとは。
ラランはプンと怒りながら、トントントンと野菜を切る。
「お前はわかりやすいからな。見てれば何となく考えがわかるんだよ」
「初めて言われたな。見てればわかるか」
「ああ、思考タイプが似ているんだろうな」
「そういうことか」
考え方が似ていそうなのは、俺も密かに感じていた。
ひとえに気が合う。
話も合うし、友達として接するには長く一緒にいたいと思う相手だろう。
そう、友達なんだよ。
今のところ彼女に対する好意は恋愛のそれではなく、友人や知人に対する好意に留まっていた。
昔の俺ならとっくに好きになっていたはずなのに、結婚して身持ちが硬くなるとか真面目だな。
「惚気たこと考えてるだろ?」
「……本当に心読めてるわけじゃないですよね?」
「違うって、あ、もうできるぞ。仕上げ頼んだ」
「了解」
こうして話す分には、一番自然体の自分でいられる気がする。
何かあれば、きっかけさえあれば好意の種類も変わるだろうか。
ジーナの時とはまた少し違った感覚に、俺は戸惑いを感じていた。
夕食を食べた後は、順番に入浴する。
俺一人で入っているとラランが乱入するので、カナタとジーナどちらかが一緒に入るようしていた。
今日はカナタの番だった。
「どうだ? ラランのことは好きになれそうか?」
「うーん……」
「あれ? 微妙なのか? あんなに仲良さそうにしてるのに」
「好きは好きだな。けど友人としての好きというか、それ以上ではないんだよ」
風呂場は二人きりになれるから、こうして彼女たちに相談したり、近況を報告している。
「じゃあ結婚は難しそうなのか?」
「今のところはな。というか、俺よりラランのほうも同じなんじゃないかな?」
「あっちもタクロウのこと好きじゃないってこと?」
「たぶんな」
好意は……あると思っている。
まったく好意のない相手を誘惑したり、結婚を迫ったりはしない……よな?
ただそれも、騎士団を辞めたいという理由があるからだ。
この世界に打算的な結婚はない。
お互いに想い合い、愛を育まなければ女神は応えてくれない。
仮に俺の好意が愛に変化したとしても、一方的な愛は受け取ってもらえないだろう。
「きっかけが必要なのは、お互いなんだと思う」
「お互いかぁ」
カナタはジャパンと湯船のお湯で波を作り、二つの波をぶつけて遊んでいる。
ぶつかり混ざって一つの波になるように、俺とラランは互いを意識するきっかけが必要だ。
それを無理やり作る方法は一つある。
「デートすれば?」
「俺もそれは考えたんだけど……ラランは家から出たくないらしい」
「なんでだよ」
「そこはほら、出不精だからな」
気持ちはよくわかるよ。
引きこもり歴が長くなるとな?
外に出るのが億劫になり、最終的には外へ出ることにさえ勇気が必要になるんだ。
彼女も俺の同じタイプだろうことはわかっている。
無理やり外に連れ出しても、きっと楽しむことはできない。
「なんとかできないかなー」
「……」
カナタが俺の胸の中で、こっちをじーっと見つめていた。
それに気づいた俺が視線を合わせ、尋ねる。
「なんだ?」
「不思議だなぁーと思って。結婚はできないって言いながら、ラランのこと好きになる方法を真剣に考えてるのって、なんか面白いな!」
「――! 俺はほら? 百人と結婚しないと死ぬ定だからさ? 相手から結婚したいって言ってくれたらなんとかしたいって思うだろ」
「それだけなのか? 誰でもいいわじゃないんだろ?」
「……それはそうだ」
結婚はしたい。
しないと死んでしまうから。
でも、誰でもいいから結婚したい、とは思わない。
正確には、そう思わなくなった。
カナタやジーナと結婚して、本気で誰かを好きになる気持ちを教えてもらった。
思いが通じ合い、愛し合うのは心地よくて、尊い。
結婚とはそういうものだ。
それを知ってしまったら、誰でもいいなんて考えられないだろう。
「我ながら強欲だな」
「そんなことないだろ? 普通のことだよ。あたしだってタクロウがよくて結婚したんだ。だからタクロウも、自分が結婚したい相手とすればいいんだ」
「カナタ……」
「あたしは応援してるぞ! タクロウが幸せなら、あたしも幸せだからな!」
「カナタ!」
俺は思わずカナタを後ろから抱きしめた。
愛おしすぎて無理。
「おわっ! ビックリするなー」
「はぁ……もどかしい。ここが他人の家じゃなかったらこのままハッスルできるのにぃ」
「我慢我慢」
抱きしめた俺の腕をトントンと叩く。
少なくともあと数日で王都には戻れるんだ。
我慢するしかない。
カナタは平気みたい……?
「あたしも、我慢するからさ」
「――!」
カナタは抱きしめた俺の腕をぎゅっと握り、頬をすり寄せる。
俺だけじゃない。
この先の展開ができないことのストレスを、カナタも感じているみたいだった。
求め求められる関係……これこそが夫婦!
王都に戻ったらジーナの屋敷じゃなくて、どこか宿屋を探そう。
そんで思う存分ハッスルするぞ!