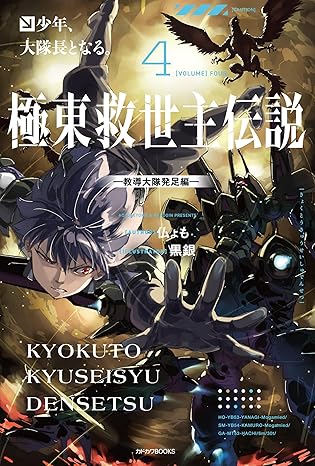9話。専用機
(うん。何度見てもおかしい)
とりあえず説明するから頭を上げろという整備士さんからの温かいお言葉に甘えて頭を上げれば、そこには相も変わらず俺の専用機となる混合型とやらの素体がデデンッと鎮座していた。
まぁ移動させてないからそこにあるのは当然なんだが。重要なのはそうではない。この混合型がおかしいのだ。
どこがおかしいかを指摘する前に、機体について簡単に説明しよう。
機体の正式名称や素材については説明したので飛ばすとして、まずはその種類から。
機体の種類は大きく分けて2種類ある。
まず一つ目が、標準型と呼ばれる人型を模した形をした機体である。日本では草薙型とも呼ばれている。
元となるのは、日本の場合は牛頭鬼や馬頭鬼に代表される鬼系の魔物であり、欧米ではミノタウロスやギガンテスなどの巨人系と呼ばれる魔物の死体だ。
この機体の最大の特徴は、人間の動きをトレースできるところにある。
両手に剣を装備することもできるし、盾を装備することもできる。もちろん重火器だって装備可能である。当然乗り手の習熟度合いによって戦闘力が跳ね上がるので、子供のころから武術を学んでいたり、重火器を使った経験がある人ほどこの型を好むと言われている。
次の二つ目が、獣型と呼ばれる型の機体である。こちらは日本では八房型と呼ばれている。
文字通り獣を模した機体であり、基本的には四足歩行なので、標準型と比べて体高が低い。
獣型の材料となるのは、主に大型の虎や熊、狼などが変異した魔物の死体となる。
機体の特徴としては、体高が低い上に前後にある足が支えとなるので、安定性と踏破性が高いことがあげられる。
標準型と比べて武器などの柔軟性はないが、元々備えてある牙や爪のほかに背中や肩に砲を積むこともできるので、標準型がたどり着けないような特殊な位置からの狙撃などが可能なため、火力という意味では標準型を凌ぐときもある。
また体高が低いので敵の索敵から逃れやすいうえ、標準型の元となっている魔物よりもしなやかさで優るため、防御性能は劣るものの、それを補って余りある回避性能を有しているのも獣型の特徴である。
ただし機体の大きさや砲が邪魔をするため、近い距離で複数を運用するのは難しい。
本物の狼のような連携は不可能……とまでは言わないが、相当な訓練が必要になる機体である。しかし武術の訓練を1からするよりは習熟が簡単ということもあって、適合率以外の才能がない機士はこちらを好むとされている。
纏めると、標準型は応用が利くうえに防御力が高い機体で、複数体での運用も訓練次第で可能となる。通常時はその防御力と殲滅力を見込まれているため、本隊や先発部隊に配備されることが多い。
また、土木工事や設営などの作業を行うこともできるので、応用の幅は極めて広い。
獣型は主に単独行動をする上では非常に有用な機体で、斥候や強襲、狙撃に向いている。最近増えてきたと言われている電波障害などを発生させる魔物が現れた際には命令の伝達役としても活躍するらしい。主に偵察部隊や先発隊に配備される。
ここまでが機体に対する常識と言われる知識となる。これ以上は受領する専用機の型に合わせた専門的な知識となるので、専用機を受領する前に学習しても意味がないと思い、調べていない。
ただ、こうして標準型と獣型の特徴を列挙していけば、おのずと一つの感想に思い至るだろう。
即ち『この機体のコンセプトってなんですか?』である。
上半身が標準型なので、人間と同じように武器や防具を持てる。それはわかる。だが武術に於いては上半身よりも下半身こそが重要だということは、少しでも武術を嗜んでいればわかるだろう。
翻ってこの、下半身で獣型特有の力強さとしなやかさを誇る四肢がめちゃくちゃ自己主張している機体はどうか。
(どう頑張っても俺が習得した技術は使えそうにねぇな)
この機体で俺が習得した技術を使おうとすれば、必ずラグが生じることになる。
だって俺は人間だもの。
上半身の使い方に頭を抱えたあとは下半身の使い方を考えてみよう。
獣型の特徴であるしなやかな動きをしようにも上半身が邪魔をするし、そもそも獣型の利点は体高が低いことだと何度も言っている。獣型は2~3メートルという高さだからこそしなやかな動きが活きるのである。
しかしながら俺の目の前にある機体はどうだ。
3メートルの下半身に3メートルの上半身を足した結果、標準型と同じくらいの高さなのである。
しかも標準型がその気になれば匍匐前進のような真似ができるのに対し、目の前のコレは接続部分が頑強に造られているせいで柔軟性がないため、上半身を丸めることすら難しい仕様になっている。
これだけ見れば、獣型が有する利点のほぼ全てを投げ捨てていると言っても過言ではない。
纏めるとこの混合型は、一見すれば標準型と獣型の悪いところを詰め合わせた機体なのである。
何も知らない者が一見すれば、だが。
当然俺には違う可能性が見えていた。
「この機体の特徴は、四足歩行の機動力を持ちながら通常型が装備可能な武器を装備できること、ですよね?」
「ほう、わかるか?」
「えぇ。おそらく通常型よりも重いのでしょう? 脚部だって上半身の重量がある分、かなりの補強をしてあるはず」
「ふっ。正解だ」
正解だ。じゃねぇよ。
「つまりこの機体のコンセプトは、通常型や獣型では反動が強すぎて使えない重さの砲を使った遠距離狙撃、ですか」
「その通りだ」
やっぱりな。というか、それしかないとも言える。
まず通常型の場合だと脚部は上半身や武装の重量を支えるための構造になっているので、砲撃によって生じる反動や振動に弱い。そのため一定の反動がある重火器が使えないという欠点がある。
獣型の場合はもっと単純で、通常型よりも軽いので大きな反動が発生する重砲は装備できないし、装備したとしても反動で狙いがブレてしまうので使い物にならない。
つまりこの混合型は、通常型や獣型では討伐できないような魔物を効率よく討伐するために造られた機体というわけだ。
付け加えるのであれば、機体であれば魔晶を流用することで砲塔を切り替えることが可能なので、砲塔が固定されている戦車や戦艦と違っていろんな種類の砲を使用させることができるようになる。
つまり狙撃や砲撃に限っては応用が利く。そんなところだろう。
コンセプトは理解した。使いづらいことは間違いないが、逆にニッチな点を突いているので需要という意味ではあるだろう。きちんと運用できるのであれば。
そう。きちんと運用できるか否か。
そこが一番重要なポイントだ。
「で、この機体の重さは?」
「……30トン。装備を含めれば35トン」
やっぱりな! こういう技術馬鹿には謙虚になるよりも直接ぶつかった方が良い。というか直接ぶつからないと変な方向に話を勧められてしまう。そう判断した俺は、これまで取り繕っていた敬意を取り払ってぶつかることにした。
「馬鹿ですか」
「なにぃ!?」
なにぃじゃねぇよ。
「標準型が15トン。獣型が10トンですよ? なんで両方をプラスしたのよりも重くなるんですか」
中戦車並みの重さじゃねぇか。
「お、大型を仕留めるレベルの威力を出す重砲の反動に耐えるにはこれくらいの重さが必要なんだよ!」
「そりゃそうなんでしょうけどねぇ」
それはわかる。履帯を履くことで大地との接地面を増やしている戦車と同等の攻撃力を求めるのであれば、戦車と同等の重さが必要になるってことくらいは俺にも理解できる。だが理解できることと納得することは別だ。
「これ、魔晶に入れたら35キロですよ? 俺は常に35キロの荷重を背負わなきゃいけないんですか?」
「……軍隊では40キロの機材を抱えて行軍することなんてざらにあることだろう?」
そうですね。なんて納得すると思ったか? 言っていることは正論だが、目が泳いでいるぞ。
「ですが彼らは休憩のときは荷物を下ろしますよね? 俺は下ろしていいんですか? 作戦行動中にいきなり機体が出現することになりますけど?」
「……」
機体はできるだけ魔晶の中に収納すべし。機士の常識だ。
例えば寝ている時だ。重いからと言って全高6メートルの機体を野ざらしにしていたら敵から狙い放題だろう? だから基本的に休息中は機体を魔晶に収納することを奨励している。
それ以外にも理由はある。それは機体には魔晶の中に収納されているときに、魔晶の中に満ちている謎の力で自己修復したり、他の魔物を討伐した際に得られる謎の力を体内に取り込んで成長する機能が備わっているからだ。
つまり機体にとって魔晶の中とはウィザード〇ィでいうところの宿屋に相当するのである。
宿屋に泊まることで機体は休息を行いつつ成長をする。ついでに魔晶の持ち主とのリンクが高まるという効果もあるらしい。
そういった事情があるので機体はできるだけ魔晶の中に収納するのが望ましいとされている。ただしガイダンスであったように、魔晶が持つアイテムボックス機能には明確なデメリットが存在する。それが収納した物品の重量の1/1000が魔晶の持ち主に襲い掛かるということだ。
そこで問おう。『常に35キロの荷重を背負わされている若者が休息できるのか?』と。
無理に決まっている。移動しているときも、車に乗っているときも、トイレに行っているときも、寝ているときも、常に35キロを背負う? 戦場に到着する前に疲労で倒れるわ。
かと言って専用のトレーラーなんかで運ぶのは手間がかかりすぎる。
そこまでやるなら普通の機体を使った方が早い。
「て、適合が進んで成長すれば半分くらいにはなるぞ!」
ほう。それは素晴らしい。
確かに半分くらいならなんとかなるだろう。
完璧だ。
不可能ってことを除けばな。
「それまで生きていられればいいですね」
「うっ」
うっ。じゃねぇよ。
レベルアップすれば最強ってのは言い換えればレベルアップしなければ雑魚ってことだろうが。
ゲームと違うんだぞ。どうやって一戦一戦が命がけの実戦で、常に35キロ背負って動いたせいで疲労した未熟な機士がレベルアップに必要な経験値を積むんだよ。生還するどころか、戦地に到着することすら難しいわ。
「しかも上半身が人型で下半身が四脚ですよ? 整備士さんは自分でこれを万全に動かすイメージが湧きますか?」
「ま、まぁ難しいかもな」
「かもな。じゃなくて難しいんですよ」
標準型であれば人として生きてきた経験で。獣型だけなら本能(ノリと勢い)でなんとかなるらしいが、合わせたら駄目だろ。
サイ〇ミュ搭載機みたいに脳量子波で動かせってか?
「……」
ついに無言になったか。そりゃな。いくらカタログスペックに秀でていても運用できなけりゃゴミだからな。
これまでいったいどれだけの兵器が選考段階で没になったかを考えろ。
パンジャンにはOKが出た? あれは連中が紅茶をキメていたからだ。それを当たり前だと思うな。
しかし、なんだ。散々悪し様に言っておきながらアレだが、俺的にはこの機体はアリだと思っている。
だってコンセプトが遠距離からの狙撃だろ?
つまり危険な前線から合法的に距離を置けるということだろ?
それに、荷重が35キロというのは大きいが、元々それなりに鍛えていることもあるし、戦場に出た場合はともかく、ハンガーに入れている間は重さを感じなくて済むしな。
もっと言えば荷重があるとはいえ所詮35キロ。
つまり妹様と同じようなもんだ。
それなら妹様を背負っていると思えば軽いもんよ。
実際俺が死ねばあいつが路頭に迷うことになるんだからな。
機体の重さ=俺が背負っている責任の重さと考えればむしろありがたい。
もしそれでもきついと言うのであれば、この学校にいる3年間で体を鍛えつつ、機体の成長……は無理だとしても、機体と俺との間で適合率を高めて荷重を減らしていけばいいのだ。最低でも3年は安全なところで給料をもらいながら訓練できるんだから文句を言うべきではない。
「……とりあえず乗りもしないのに文句を言ってもしょうがないですからね。シミュレーターをやってみましょうか」
「い、いいのか?」
「良いも悪いもありませんよ。いまさら交換はできないんですから。シミュレーターの準備をお願いしてもいいですか? マニュアルがあるならそれも見せて下さい」
「お、おう!」
そもそもの話だが、この学校に於ける俺の立場はテストパイロットだ。
テストを行う機体に良いも悪いもない。
これがテストパイロットである俺に割り当てられた機体である以上、しっかりとテストを行い、きちんとしたレポートを上げるべきだろう。
軍だって試作機に過大な期待はしていないだろうし、NOを突きつけるならちゃんとした理由がなければ駄目だろうからな。
(それにこの機体、一見すれば変態企業が造ったゲテモノだが、だからこそ化ける可能性は十分にある)
そう考えた俺は、機体の動かし方に関する構想を練りながら、半分申し訳なさそうな顔をしつつも、残りの半分は楽しそうな様子であることを隠そうともしない整備士さんの姿を横目に、機体について書かれた説明書を読み込むのであった。
風評被害?
なんのことやら。
ちなみに『35=妹様みたいなもんだから軽い』を口に出したら大変なことになるもよう。
なんなら口に出さなくても大変なことになるもよう。