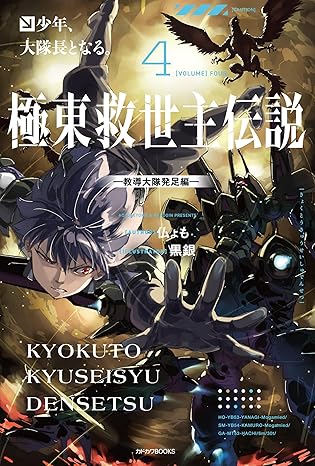11話。啓太、ベトナムに立つ。
短めです
ベトナム帝国。
19世紀の後半にフランスの植民地とされたものの、第二次世界大戦中に出征してきた日本軍と協力して植民地支配からの脱却を果たした国家であり、その際に中心的な活躍をしたバオ・ダイを祖とする、人口およそ2000万人の立憲君主制の国家である。
日本とは、大戦中だけでなく大戦後も行われたバオ・ダイに対する数々の支援や、各種インフラ整備への協力に加え、終戦に伴い日本軍が一度兵を引き上げてたところを突いてきた中華民国(現在の中華連邦)との戦い――第一次ベトナム戦争――や、その後に襲来して国土を荒らし回った魔族の軍勢に対して行われた解放戦争――第二次ベトナム戦争――で轡を並べて戦った関係上、強固な繋がりが存在している。
さらに言えば、ここ数年日本からの遠征軍が進駐していることもあって両国の関係は非常に良好なものである。
ただし、それはあくまで中央政府と日本の距離感の話であって、現地の人間が全員親日家というわけではない。
また、ベトナムに於いて行われた戦争の内容が啓太が知る前世に於いて行われたソレとは違うので、国内に存在する熱帯雨林は枯らされたりしていないし、散布剤を原因とした健康被害なども発生していない。良い言い方をすれば緑に溢れた国である。
そういう意味では第二次大戦後に独立することに成功した極々一般的な東南アジアの国と言えるだろう。
そんなベトナムの地に変態たちが足を踏み入れたのは、年末も近い12月下旬のことであった。
―――
年越しまであと一週間に迫ったとある日のこと、一部で【英雄】だとか【救世主】だとか【黒い変態】だとかと呼ばれ始めている少年こと川上啓太は、正真正銘筋金入りの変態である最上隆文らを伴ってベトナムはフエの地に上陸していた。
「これがベトナムか。事前に得ていた情報通り、12月だってのに暑いな」
「ですね」
暑いとはいっても12月のベトナムの平均気温はだいたい25度前後なので、ある意味では過ごしやすい温度と言えなくもない。
少なくとも、この時期【極寒】という言葉では足りないくらい寒くなる極東ロシアよりは過ごしやすいことは確かだ。
だが元々『冬は寒いモノ』と考えている啓太や隆文からすれば、この亜熱帯~熱帯地域にありがちな季節感の無さになんとも言い様のない違和感を覚えるのも仕方のないことかもしれない。
「ま、仕事する分にはこのくらい暖かい方がいい。寒いところで震えながら整備するよりはマシだからな」
「でしょうね」
微妙に淡泊に感じるかもしれないが、整備をして貰う立場の啓太からすればそうとしか言えないところである。
尤も、隆文としても特に意見を求めて発言したわけではないので、啓太の反応に不満を抱くようなことはなかった。
(これから熱帯仕様、いや、森林仕様に改造か。課題は多々あるが、最大の問題は武装だな。障害物が多いから平射は不利。近接も同じ理由で難しい。全部燃やすのは最終手段だから焼夷榴弾も使えない。となると、メイン武装は機関銃系か? まぁ最終手段である焼夷榴弾は絶対に積ませるが)
訂正しよう。仕事のことに没頭している隆文の耳には、啓太の相槌など初めから聞こえていなかったようだ。
聞こえていないのだから不満を抱くこともない。
不満を抱いていないのだから機体に誠実に向き合える。
これだけ見れば機士にとっては非常にありがたい整備士と言えるだろう。
ただし、隆文が誠実に向き合うのはあくまで自分が造った機体に対してだけなので、いざとなったら現地の人間が何と言おうと啓太に全てを焼き払わせるつもりだということを忘れてはいけない。
こういうところで容赦や配慮が無いのが隆文が隆文である所以とも言えるかもしれないが、実際にやらされる方からすれば堪ったものではないだろう。
何せ、ソレをやった後に叱責を受けるのは、ソレを実行した者なのだから。
そんな危険な思想を抱いている整備士が整備した機体に乗り、いざというときには周囲を焼き払ってでも生還することを強要される人間、つまり啓太はと言えば、こちらはこちらで既に覚悟はキめていた。
(最上さんがどんな仕様にするかはわからないけど、機体には嘘を吐かない人だからな。俺にとっても悪いことにはならない、と思いたい。まぁいざとなったら全部燃やすだけだしな。うん。絶対に焼夷榴弾は持たせてもらおう。現地の人がなんと言おうと、絶対にだ)
そう、穏やかな顔をしながら、こちらも最終的には焼き払う気満々であった。
というのも、啓太からすればいくら周囲が英雄だのなんだのと祭り上げようと、結局は自分が大事――個人的には『何をしたって死ぬときは死ぬだろ』と達観している部分はあるものの、今自分が死んだら妹の優菜が一人残されることになる――なので、本当にヤバいときは周囲に何を言われようとも躊躇するつもりなどないのである。
巻き込まれる人がいるかもしれない?
そりゃ戦闘区域にいたら巻き込まれるでしょ。
国民を避難させるのは国の仕事。俺は知らん。
機体の帰還と自身の生存。そこに至るまでの過程は違えど、結果的には同じところを見ている変態二人。これだけみれば実に理想的なメイン整備士と機士の関係と言えよう。
いざというときに発生すると思われる周囲に与える被害に目を瞑れば、だが。
そんな変態共が内心で抱いている危険な思想はさておくとして。
この日、啓太がベトナムに入国するにあたって教導大隊の面々と行動を共にしていないのは、彼女たちと啓太の間にある習熟度合いの差が原因ということになっている。
もう少し詳しく語ると、基本的に軍とは足が速い部隊と足が遅い部隊が分断されてしまうことを防ぐ意味もあって、部隊で動く際は一番遅い兵種に合わせて動くことを常としている。
それに鑑みた場合、啓太と他の面々は一緒に行動できるだろうか?
答えは当然、否。
将来的にはどうかは分からないが、少なくとも現時点の彼女たちは一人だけぴょんぴょんと飛び跳ねて移動できる啓太と行動を共にすることができるだけの技量を持っていない。
そうである以上、部隊運営の観点からすれば啓太が鈍足の面々に合わせて動くしかないのだが、それは軍が啓太という特記戦力を損失することを意味している。
そのため軍の上層部は、現時点に於いて啓太という戦力は教導大隊という部隊の一員として運用するよりも、一人で動かした方が戦力として有効であると考えた故に、軍は啓太には先んじて現地入りし、現地の様子を確認するとともに簡単な露払いをするよう命じたのである。
見方によってはなんのフォローもない場所に単独で放り出されたとも見えなくもないが、もちろんそんなことはない。
ベトナムという国自体が親日の国であるし、なによりこの地には国防軍の第四師団が派遣されているのだ。現地での補給や情報収集に問題はない。
付け加えれば、遠征軍として派遣されている第四師団の面々は紛れもない精鋭である。
その精鋭の支援を受けられることが確定している以上、啓太としても所属部隊を離れて単独で行動することに否はない。
むしろ同級生たちを護る必要がない分、気が楽になったとさえ考えているくらいだ。
(最上隆文? 考えるだけ無駄だろうな。そもそも危ないと判断したら勝手に逃げるだろうし)
信頼というには些か以上に投げやりな感じは否めないものの、実際にナニカあった際に一学生でしかない啓太が彼らに対してできることなど何もない。それどころか一般的には子供でしかない啓太の方が、社会的な立場を有した上で人生経験も積んでいる彼らに護ってもらう可能性の方が高い。
そう言った事情から、啓太に隆文らを心配する気持ちはない。
勿論何らかの事情があって彼らが逃げ遅れた場合などは助けるつもりではあるが、基本的に啓太は隆文ら大人を頼るつもりであった。
(差し当たっては……)
「ようこそベトナムへ。此度英雄殿の案内役を仰せつかった綾瀬勝成だ。娘が世話になっている」
「ご丁寧な挨拶痛み入ります大佐殿。第一師団教導大隊所属川上大尉であります。こちらこそ、娘さんにはお世話になっております」
前もって告知されていたこともあって滞りなく挨拶を行う啓太であったが、その内心はと言えば。
(第四師団から派遣された案内役にして、同級生の父親であるこの人を頼るとしようか)
と、中々に黒いことを考えていたとかいなかったとか。
大人を頼っていいぢゃない。だって子供だもの。
閲覧ありがとうございました。