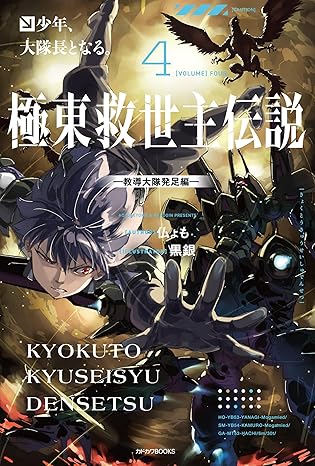10話。ブリーフィングという名の女子会
誤字報告ありがとうございます。
12月下旬。もしくはうら若き乙女たちに衝撃の告知が為されてから数日後のこと。
此度、自分が戦地に赴くことを知らされた少女たちが――28歳教員含む――文字通り死ぬ気で修練した結果、シミュレーター上のことではあるものの、ギリギリで【射撃】と呼べるような機体動作が可能となっていた。
これを受けて統合本部は、資格十分として軍学校所属の教導大隊に対して正式な命令として遠征軍への帯同を通告。
その通告を受けた少女たちは、自分が上層部に認められたことを純粋に喜んで……いなかった。
事実、現地へ赴く前に最終確認を行う場として設けられた一室の中には、悲痛な表情を浮かべて話し合う少女たちの姿があった。
「そうか。今まではあくまで内示だったのか。……なぁ、もしかして、なんだけどさ」
「なに?」
「もし私たちが今の段階まで成長できていなかったら、もしかして私たちは今回の遠征に参加しなくても良かったってことなんじゃないかな?」
ここ数日、強化外骨格の習熟よりもシミュレーターを優先してきた橋本夏希は溜息交じりにそう呟く。
(まぁ、ね)
確かにそれはその通りであった。
いくら第一師団の上層部が自分たちの影響力が及ぶ護衛を欲していたとしても、最低限の動作である【射撃】さえ満足にできない――言葉を飾らずに言えば肉壁にもならない――学生を護衛として欲することはない。
よって彼女たちが『習熟度合いが不足している』という名目で、今回の遠征に帯同することを避けられた可能性は極めて高かった。そういう意味では夏希の意見はなんら間違ったものではない。
誰だって戦地に赴くのは怖い。ましてそれが未だに満足に扱うことができない兵器に命を預けることを前提としているのであれば猶更だ。
一応言っておくと、夏希は「怖いから戦場に行きたくない」などと言っているのではない。彼女はあくまで『戦場に行くのは良いが、もう少し時間が欲しかった』と言っているのだ。
声を掛けられた翔子も、夏希がそう思う気持ちは理解できる。
自分だって似たような思いは抱いているのだから。
だが翔子は、今回の遠征を避けることが自分たちにとってプラスになるとは考えていなかった。
「その場合は単純に実戦を経験するのが遅くなるだけよ?」
「その時間でより修練を積めるのでは?」
「そりゃ、練習期間が延びたと考えればいいことかもしれないけど……」
「けど?」
「その場合、初陣が前の大攻勢みたいな死地になるかもしれませんよぉ?」
「そうなのよねぇ」
翔子は会話に割り込んできた那奈をちらりと見やりつつ、那奈が述べた意見に全面的に同意する。
そうなのだ。今回自分たちが赴く先は他国、つまり最悪の場合退くことができる場だ。
それに対し、先だって行われた大攻勢は自国の防衛、つまり退くことができない場である。
もちろん戦場で死ぬことを恥とは思わない。だが、初陣を飾るならどちらがいいか? と問われたならば、翔子は迷わず前者を選ぶ。
初陣が、誰も彼もが余裕のない戦場なんて御免被る。
誰だってそうだ。夏希だってそうだ。
なんなら部隊指揮官である静香だってそう思っている。
だからこそ翔子は自分たちの初陣が今回の遠征になることを悪いこととは思っていない。
さらにもう一つ。
「ついでに『落ちこぼれ』っていう烙印も押されるかも」
「押されるかも、じゃなくて押されんのよ。『役立たず』ってね」
那奈が語るのが実利についてであれば、茉莉が語るのは矜持の問題であった。
どう言い繕っても、武器とは戦場で使うものだ。軍から新型の機体や強化外骨格を預けられておきながら『習熟できませんでした』という理由で戦場に赴けないとなれば、それは文字通りの役立たずであろう。
尤も、新兵器の習熟に必要な時間を考えれば一方的に非難されるようなことではないかもしれないが、第一師団の上層部が自分たちに失望することは想像に難くない。
なにせ自分たちのすぐ傍には、自分用にカスタマイズされた専用機だろうが、誰でも扱える量産型だろうが、誰も実戦で試していなかった強化外骨格だろうが、なんでも縦横無尽に操り赫赫たる実績を挙げている一般家庭出身の変態がいるのだから。
「あぁ。そうか。それも嫌だな」
彼女たちはそれぞれが師団を代表する武門の家に生まれた武人であり、それなり以上の期待をかけられてこの学校に送り込まれてきた俊英だ。状況と比較対象が悪いとは言え、一方的に無能扱いされて面白いわけがない。
さらに言えば、彼女たちは望んでいたのだ。
同級生である変態が武勲を挙げて昇進していくのを目の当たりにして『自分だって』と『機会さえあれば』と。自分が戦場に立つことを。
その機会を与えられたのに文句を言うのは筋が通らない。
そして彼女たちは知っている。
その変態同級生こと啓太とて、初陣は自ら望んで戦場に赴いたわけではないことを。
周囲はできる限り万全の態勢を整えていたのかもしれないが、本人からすれば不意打ち以外のなにものでもなかったことを知っている。
で、あればこそ。
「初陣が怖いのは当然よ。私だって怖い。でもね」
「「「……」」」
「私は逃げない。絶対に」
初陣を前に緊張するのは当然のこととしたうえで、翔子は正式な命令として与えられた軍令に異を唱えるような真似はしない。
たとえ自分が扱うのが慣れ親しんだ草薙型ではなく、実戦での経験を一切積んでいない、それどころか扱った経験がある先人すらいない完全な新型の機体であったとしても。
たとえその機体を造った技術者たちが頭のネジが何本か外れた変態の集まりだったとしても。
たとえその機体の構造やら基本的な制動に関係する諸々のデータと言った、根元の部分を構築するのに使用したデータの全てが、変態が行い。変態によって精査され。変態が活用するために集められたものだとしても。
(……駄目かもしれない)
思い返せば不安に思うことも多々あれど、すでに翔子の中にあった(かもしれない)後退のネジは外されているのだから。
「うむ。よく吠えた。それでこそ武家の娘だ」
「「「中佐っ!?」」」
―――
「話は聞かせてもらった。貴様らの気持ちも、な」
聞きようによっては悲痛な覚悟の表明と言えるような翔子の言葉を耳にして静香が感じたのは【驚愕】ではなく【感謝】であった。
未熟な学生を戦場に連れて行くことを謝りたい。
未熟な学生に覚悟を決めさせたことを謝りたい。
つい先ほどまで教師としての静香はそう思っていた。
しかし、翔子の言葉を聞いて考えを改めた。
否、改めさせられた。
静香は翔子のことを『未熟な学生』と侮っていたことを謝りたいと思っていた。
何より自分以上に不安を覚えているであろう同級生を前に覚悟を表明してくれたことに感謝したいと思っていた。
だがしかし、悲しいかな今の静香は彼女たちの教師であり、上官であり、指揮官である。
故に静香の口から翔子に対して「自分を含め彼女たちの不安を和らげてくれてありがとう」とは口が裂けても言えない。むしろ不安を抱いているであろう面々を叱責しなくてはならない立場なのだから。
(代わり。というわけではないが、な)
こいつらは絶対に死なせない。
静香は何を利用してでも彼女たちを生還させることを自分の心に刻み込んだ。
まぁ、差し当たって利用されることが確定しているのは、どこぞの上層部の面々ではなく一般家庭出身の変態なのだが、彼としても同級生に死んでほしいとは思っていないので、この件で静香に利用されたところで文句を言うことはないはず――もちろん自身が生き残る可能性がない場面で彼女らを生かすために囮にされたり、意図的に殺すような命令を出した場合は容赦なく反逆するが――だ。
いろんな意味で一人だけ扱いが違う男子のことはさておくとして。
「我々が赴くのは戦場だ。一つのミスが死に至る場所だ」
「「「「……」」」」
「だがな。そもそもの話。我々は軍人だ。貴様らも学生とはいえ准尉待遇なのだから軍人と言って差し支えはあるまい?」
「……軍人なら命令に従って死ぬのも任務、ですか?」
「そうだ」
「「……」」
震える声で問いかけてきた夏希に対し、あえて強い口調で返す静香。
覚悟はしていたものの、改めて口に出されたことで衝撃を受けたのか、夏希だけでなく那奈と茉莉が表情を歪ませる。
「ただ、な」
しかしながら静香の話はまだ終わってはいない。
むしろこれからが本題だ。
「貴様らは重大な勘違いをしている」
「勘違い、ですか?」
「そうだ。命令に従って死ぬのは軍人の務め。それは事実だ。だがな、部下に死ねと命じるのはあくまで最悪の場合に限った話だぞ? そうそう簡単にそんな命令は出さんよ。その部下が殻も取れていないヒヨッコである貴様らであれば猶更そんな命令は出さんさ」
(ヒヨッコではない奴には遠慮なく命じるがな)
いざとなったら啓太に暴れてもらおうという何とも他力本願な思惑を内に秘め、あえて軽い口調で告げる静香。
「……あぁ。そうでした。そうでしたねぇ。少なくとも今回の遠征で死ぬような命令が出されることはありませんよねぇ」
そんな静香にヒヨッコ扱いされた那奈は怒るどころか、納得の表情を浮かべ。
「確かにそうですよねー。第一、危なくなったら一目散に逃げれば良いだけだし?」
茉莉も元々今回の遠征は逃げ場がある戦場であることを思い出し。
「さすがに一目散に逃げるのはどうかと思うけどね」
一番不安に苛まれていた夏希も、指揮官である静香から自分たちが死ぬのは最後。つまり最悪に最悪を重ねた状態にならない限りありえないと明言されたことでその不安を和らげることに成功し。
「必要ならわき目も振らずに逃げるべきでしょ。もし【逃げる】ってのが嫌なら後ろに向かって全力前進すればいいのよ。それなら立派な軍事行動でしょ?」
「中々うまいこと言いますねぇ」
「後ろに向かって、か。それはいい」
「それなら逃げてないもんねー」
元々後退のネジを外しているものの、当然無駄死にする心算などない翔子がそう纏めれば、一同は笑みを浮かべながら相槌を打つ。
(ふっ。うまく纏めたな)
彼女らの緊張が良い感じに解れたのを見て、適度な緊張は必要だが、悲痛な覚悟を決める必要はないと考えていた静香は、それを成した翔子への評価を再度高めつつ、この流れが失われないうちに本題に入ることにした。
本題、即ちブリーフィングである。
「納得したところで、出陣前のブリーフィングを始める。これが国内で行う最後のブリーフィングになるので、疑問に思った点や改善すべき点があれば今のうちに言っておけ」
「「「「はい!」」」」
如何に指揮官である静香から『そう簡単に死ぬようなことはない』と言われたとはいえ、これから行くのは戦場である。そこが、油断すれば即座に死ぬ場所であることは変わらない。
故に翔子らは静香から告げられる任務の内容を真剣に聞き、それに対して忌憚のない意見や質問を繰り返し行うこととなった。
――そうこうして語ること数時間。
「ふむ。こんなところか。他に聞きたいことはないか?」
「そうですねぇ。私は大丈夫です」
「私としても特にはないです」
「私もです。あとは現地でって感じですよね?」
「……え? これで終わり、ですか」
軍人としてだけでなく、武家の娘として、また、学生としての視点から様々な意見を出されたことで、指揮官としての知見を得ることができたと満足していた静香が話しを纏めようとするも、最初から覚悟をキめていたが故に確認以外の意見を口にすることがなかった翔子の口から疑問の声が上がる。
「どうした?」
何か問題でもあるのだろうか? そう考えた静香だが、翔子からすれば「何か問題が?」どころの話ではない。
「あの、アイツは?」
「「「あっ」」」
そう、この場には教導大隊の主力である啓太がいないのだ。
自分たちがどのよう意見を出そうと、実働部隊の隊長である啓太がNOと言えばNOとなる。それは指揮官である静香とて同じこと。
指揮官だからと言って実働部隊を軽んじることはできないし、軍事行動に於いては優秀な一人の人材とその他大勢による意見では優秀な人材の意見が通るものなのだから。
ましてその優秀さが机の上のことだけでなく、戦場での実績によって証明されているのだ。
誰だって実戦経験がない翔子らや、簡単な実戦しか経験したことのない静香の意見よりも、九州での防衛戦だけでなく国外でも戦ってきた経験を持つ啓太の意見を重んずるに決まっている。
翔子らとて、豊富――自分たちと比べて――な実戦経験を持つ啓太がNOと言ったことを強行するつもりは欠片もない。だからこそ啓太の意見は聞かなくて良いのか? と問いかけたのだが、それに対する静香の答えは是。
「かまわんよ」
「いや、え?」
別に静香が自分よりも若い啓太を軽んじているわけでもなければ、実績を持つ部下である啓太を疎んじているわけでもない。ことはもっと単純な話であった。
「大尉なら先に現地に入っているからな」
「「「「はい?」」」」
そう、啓太がこの場にいないのは、すでに現地に入っているから。
この場にいない人間がブリーフィングに参加できるはずがないし、参加できない以上意見を聞く必要はない。ただそれだけの話である。
閲覧ありがとうございました
ようやく遠征に行ける……かも。