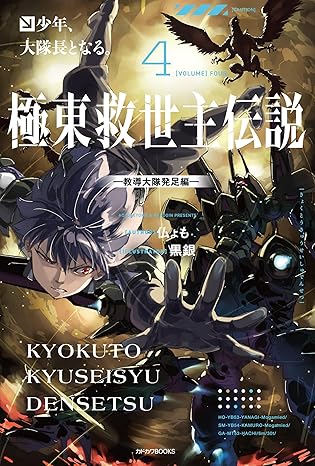16話。文化祭9
元々啓太は上から『遠距離狙撃は不可』と言われた時点でそれなりに苦戦することは覚悟していた。
故に最初啓太はこう考えた。『どうせ一瞬で片が付けられないのであればいっそのこと持久戦にしよう』と。
これは、魔族との戦闘を長引かせることで自分や整備士はもちろんのこと、これから量産型に乗る機士たちに対して『量産型の動かし方の参考になれば良い』という思惑と、後に似たようなことが発生してしまったときのための対処法を確立することができるかもしれないという思惑があってのことだ。
持久戦を行うにあたって自己の性能と同じくらい重要なのが、相手の性能である。
特に武器の種類や間合いに関しては一歩間違えれば自分が死ぬということもあり、かなり真剣、かつ余裕を持った回避を心掛けていた。
そのおかげ……と言えるかどうかは不明だが、少なくとも啓太は未だに無傷であった。
もちろんそれはアルバも同じなのだが、アルバと啓太の間にはいくつかの違いが存在する。
まず一つ目は、アルバが最初から啓太と量産型の性能調査を行うつもりで手を抜いている最中、啓太の方もまたアルバを観察していることを考慮に入れていなかった点である。
アルバは啓太が必死で自分を殺すための攻撃を行っていると考えていたが、そんなことはない。
啓太はアルバの行動を見るために連射できるところでも連射をせず、それどころかぶち抜ける隙があったときにさえもあえて放置――もちろん必ず殺せるという確信があればヤっていたが、その確信がなかったため――してまで観察を優先しており、そこから攻撃のタイミングや回避の癖など必要な情報を抜き取ることに成功していた。
次いで防御に関してだ。アルバだけでなくこの場にいる啓太以外の全員が気付いていないことだが、この一連の戦闘の中でアルバは、啓太が40mm機関銃を使う際には必ず正面に構えた盾によって啓太の攻撃を防いでいる。
しかして装甲に魔力をコーティングした盾は、啓太が放つ40mm機関銃の攻撃をものともせずに全てはじき返し、ノーダメージのまま啓太の攻撃を凌いでいた。
これだけならアルバも、アルバと啓太の戦いを見ていたルフィナも特に問題とは思わないだろう。
だが物事をより正確に言い表せば、啓太の狙いの一端がわかるはずだ。
アルバが必ず正面に構えた盾で攻撃を防ぐということは、即ち上下左右に飛び回る三次元機動を得意とするはずの啓太がそれを行わず、敢えて短めの跳躍だけを行い、アルバから見て前方からのみ攻撃を行ったということである。
つまるところアルバは、正面に構えた盾によって防御させられていたのだ。
それによって啓太は、アルバがばら撒かれた銃弾をどう防ぐか。盾はどのような角度で構えるのか。盾越しに衝撃は伝わるのか。攻撃を受けながら前進することはできるのか。等々、細やかな情報を得ていた。
啓太が得た情報はそれだけではない。
アルバは88mm滑腔砲から放たれる焼夷徹甲弾を必ず回避している。このことも貴重な情報だ。
何故なら、わざわざ攻撃を回避するということは、アルバ自身が己の操る魔物が防御に専念したとしても88mmの攻撃に耐えられない――もしくは防御したところで甚大な被害を受ける――と判断しているということを意味しているからだ。
極めつけは先ほど回避された80mm焼夷榴弾である。
魔力で熱を完全に遮断できるのであればわざわざ6メートルもの大きさがある体でバク転をしてまで距離を取る必要はない。にも拘わらず距離をとったということは、アルバは咄嗟の際に魔力で熱を遮断できない、もしくは爆風を防げないという可能性が浮かび上がってくる。
もちろん、この回避方法を選んだアルバがただの目立ちたがりという可能性もある。だが、これまで戦ってきた感覚から、啓太はアルバという魔族が40mm機関銃で焼夷榴弾を撃ち抜いた自分を前にして、無意識以外でそんな隙を晒すとは思えないと判断していた。
それらの情報を纏めればおのずと一つの結論が浮かび上がってくる。
それは『アルバは、一度負けイベントを経験してからでないと倒せないような理不尽さを備えた敵ではない。攻撃が当たればダメージを受ける。即ち、当たれば殺せるし殺せば死ぬ存在でしかない』という事実だ。
なにを当たり前のことを……と思うかもしれないが、忘れてはいけない。ここは悪魔がいる世界なのだ。
88mmが当たっても死なない存在。
殺しても死なない存在。
はたまた殺してからが本番になる存在がいないと誰が言い切れよう?
だが少なくともアルバはそうではない。
それが知れただけでも今の啓太にとっては十分であった。
『行くぞ』
―――
(……なんだ?)
外部スピーカーを切っているため啓太の宣言はアルバに聞こえていない。しかしながらアルバはその野生の勘ともいうべきもので、啓太の発する気配がこれまでのモノとは大きく変わったことを察知した。
(最後の奇襲を避けられてようやく命を捨てる覚悟をキめたか? 遅せぇ。遅すぎる。そんな覚悟くらい最初からキめてこいってんだ!)
問題はその変化がナニを齎すものかが理解できないことであったが、今のアルバにはそれを熟考するだけの精神的な余裕はない。
余裕がないといっても、別にアルバが追い詰められているわけではなく、あくまで戦闘と解放の興奮に溺れているため、他のことに考えを巡らせる余裕がないだけだ。
(さぁ、仕上げだ!)
具体的には、この戦闘に至るまで何度も子供の喧嘩にも劣る見世物を見せられ続け我慢を強いられていたことと、その子供どもと同い年ということで期待していなかった英雄とやらがそこそこ自分と戦えているという事実がアルバを興奮させているのである。
ましてアルバはその興奮が悪いものだとは思っていない。
人間を超越した存在となった自分が負けるとは考えてもいない。
むしろそれこそが戦闘を楽しむ為のスパイスだとさえ考えていた。
『今更何をキめたかは知らねぇが、所詮は悪あがき! 雑魚は雑魚らしく死ねぇ!』
アルバはすでに啓太が操る新型の性能を見切っていた。最後の奇襲には少し驚かされたが、それも回避に成功している。
故に彼は必殺の奇襲を回避されて意気消沈している啓太が絶対に避けられないであろう速度と威力を以て襲い掛かる。
(終わりだ!)
今までよりも段違いに早くそしてより深く踏み込んで行われたその振り下ろし攻撃は、一度でも当たれば啓太が操る機体を完膚なきまでに叩き潰すことができるだけの威力を内包していた。
回避をしようにも生半可な速度では間に合わず、もし回避されたとしてもこの状況から回避すれば体勢が崩れるのは必至。アルバはその間に二撃目、三撃目の追撃を繰り出してやればいい。
この攻撃はアルバにとって間違いなく『終わらせる一撃』であった。
だがしかし、そんな『当たれば終わる攻撃』を大人しく喰らってやるほど啓太は甘くない。
『甘い』
放たれた一撃を横に飛ぶことであっさり回避する啓太。
『なっ!?』
それもアルバや周囲の人間が予想していたようなギリギリの回避ではない。反応速度も違えば、飛んだ距離も違う。さらには回避の後に体勢が全く崩れていないというおまけつき。
誰がどう見ても余裕のある回避である。
『どういうことだ!』
自分の攻撃が完全によけられた――それも今までとは全く違う速度で――事に、疑問を抱くアルバ。だが、啓太が行ったのは回避だけではない。
『燃えろ』
啓太は置き土産と言わんばかりにばら撒いていた焼夷榴弾を撃ち抜き、アルバの進行方向に灼熱の地獄を造り出す。
『ぐっ! やってくれる! だがッ!』
テルミット反応によって生じた数千度の熱の中に自分から突っ込む形となったアルバは、即座に魔力を纏うことでダメージを軽減しようとする。だがその動きも啓太の予想の範疇である。
『そうだ。そうするだろう。そうするしかない』
魔力によってダメージを軽減しつつ、纏った魔力を以て熱を吹き飛ばそうとするアルバに、啓太は容赦なく40㎜の銃弾を叩きこむ。
『う、おぉぉぉぉぉぉ!』
高速で周囲を飛び回りながら放たれる銃弾を回避できるわけもなく、アルバが操る鬼体が徐々に削られていく。
『手前ぇ、今まで手ぇ抜いていやがったなぁぁぁぁ!』
だが、通常であればそれなりのダメージは免れなかったであろう攻撃も、熱を遮断するために纏っていた魔力に阻まれて大きなダメージにはなっていない。
しかもダメージを与えて初めてわかったことだが、魔族によって操られている鬼体は魔族が持つ魔力によって回復することが可能なようだ。
(……回復もするのか。まぁ機体も収納したときに回復するからな。大量の魔力を保有する魔族ならそういうこともできるだろうさ)
つまるところ40mmでアルバを仕留めるには回復が間に合わなくなるくらいの量をぶち込むか、コックピット部分を重点的にぶち抜くしかないということだ。
『ニンゲン風情が舐めやがって!』
それを知るからこそアルバも正面からの攻撃は重点的に防御していたのである。
一見すれば一連の攻撃はダメージを与えても回復されてしまうことを見せつけられただけの結果に終わったように見える。
『理解したか!? 手前ぇが何を隠していようと! いくら逃げようと俺様は殺せねぇんだよッ!』
事実アルバやこの戦闘を見ている者たちはそう考えていた。
静香や校長でさえ「どうやって殺せというのだ……」と絶望を覚えたくらいだ。
しかし、至近距離で回復をしていく敵の姿を観測している啓太は違う。
(魔力がある限り回復するなら魔力が無くなれば回復はできまい。さらに回復量もそんなに大きくない。つまり、このままでもいずれ勝てる)
冷徹な狩人の目はアルバが決して無敵の存在ではないことを確信していた。
『死ね!』
回復の様子を観測しているが故に動きが鈍っていた啓太に襲い掛かるアルバ。繰り出される攻撃は先ほどの大雑把なものとは違い、より単純に、より強力な魔力を纏った油断も慢心も除いた正しく必殺の一撃。
『当たらんよ』
しかし確実に当てるつもりで放った一撃も、既にアルバのモーションパターンを読み取っている啓太からすれば予備動作が丸見えのテレフォンパンチに他ならない。
さらに啓太が操るのは量産型バージョンとはいえ、機動力を強化する為に足を四脚備えている混合型だ。
その速度はアルバが操る鬼体のそれを大きく上回る。
加えて日々シミュレーターや訓練などで草薙型や中型の魔物との戦闘を経験している啓太と違い、アルバには――当たり前の話だが――上半身が人型で下半身が獣型というゲテモノとの戦闘経験がない。
よってアルバにとっては全ての攻撃が未知の攻撃である。これではモーションパターンを盗むどころの話ではない。
『……』
『あぁぁぁぁ! ちょこまかと跳ねやがって!』
周囲を飛び回る啓太にアルバの攻撃は届かず、隙を晒してしまったアルバには啓太の攻撃が当たる。
(このままじゃ負けはしねぇだろうが疲労はする。つーかこれ以上無様を晒せばルフィナ様に殺される!)
悪循環に嵌りつつあったアルバは、この戦闘を観覧しているであろう上司の存在を思い出し、ここで使う予定ではなかった切り札を切ることにした。
『おぁぁぁぁぁぁぁ!』
掛け声と同時に黒く輝く鬼体。
それは魔族にとっての切り札を使った証拠でもある。
この状態になった鬼体は体内に巡らせた魔力の影響で全ての能力が向上する上、体外に放出される魔力を操ることで全ての行動に大幅な補正がかかる状態となるのだ。
『はぁ。はぁ!』
使用した後にかなりの消耗をするというデメリットはあるものの、多少の不利程度であれば覆すことができるという、魔族にとって正真正銘の奥の手である。
『これで、終まい……『馬鹿が』……がぁ!』
普通なら見た目が変化したことに驚くのかもしれない。
普通なら膨れ上がった殺意に圧倒されるのかもしれない。
普通ならその勢いに呑まれてしまうのかもしれない。
だがしかし。アルバにとって残念なことに、啓太はあらゆる意味で普通ではない。
『無駄なことを』
啓太は一切動揺することなく、あえてアルバの変化が終わる間際を狙ってその頭と胴体部に88mmを叩きこんでいた。
『て、てめっ……』
『まだ生きていたか』
『ゴッ……』
アルバにとっての不幸は、元々啓太がアルバをただの獲物としか捉えていなかったことであり、アルバのようなタイプは奥の手を隠しているだろうと確信していたことであり、それを予想しつつ変身ヒーローの変身を待つような律儀さがなかったことであり、アルバ自身が奥の手を切る際に動きを止めなければならなかったことだろう。
『念のため』
啓大は倒れ伏す鬼にさらに二発ほど追撃を加える。
『……』
『……動きはない。どうやらただの肉塊のようだ』
こうして、つい先ほどまで圧倒的な圧力を放っていたはずの鬼体は、駄目押しと言わんばかりに放たれた88mm徹甲弾によって半分ほど原型を留めていた頭部を完全に吹き飛ばされただけでなく、ミンチより酷い状況になっていたであろうアルバの死体があった胸部にも大きな孔を開けられた上で放置されることとなった。
『こちら川上。対象、沈黙しました』
しっかりと止めを刺し対象が完全に動かなくなったことを確認した啓太は、己が肉塊へと加工した相手への警戒を解かぬまま粛々と状況終了の報告を行うのであった。
戦闘シーンは後で加筆するかも……(加筆するとは言っていない)
閲覧ありがとうございました