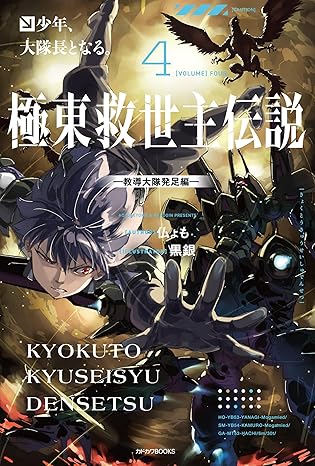24話。予期せぬ大攻勢(後)
時は少し遡る。
「し、少佐……」
「あぁ。これは無理だな」
芝野を中心とした指揮所の面々が頭を抱えていたころ、より近い位置で想定以上の魔物が上陸を果たそうとしているのを目の当たりにしていた機士たちの表情は、芝野たち以上に恐怖に歪んでいた。
当然だ。指揮官であるが故に直接魔物と接触することがない芝野と違い、直接魔物と戦闘を行ってきた彼らは魔物の怖さというものを誰よりもよく知っているのだから。
機士の常識として、大型に比べれば中型は弱いとされており、参謀部が出した戦力比は、20M級の大型1体に対して6M級の中型が10体とされている。
だが実戦を知る機士に『大型1体と中型10体のどちらが怖いか』と問うたなら、彼らは悩むことなく『後者の方が怖い』と答えるだろう。
戦いは数。数は力。けだし名言である。
ちなみに元々通常型と中型の撃墜対被撃墜比率は1:2であり、獣型と中型では2:1とされている。
これを好意的に捉えるのであれば、通常型は1機で2体の中型を倒せる。獣型は2機で1体の中型を倒せる。となる。だが逆に言えば中型の魔物は2体で1機の機体を倒すことができるし、獣型を相手にした場合は1体で2機を倒すことができるということになる。
翻って中型の魔物の数が133体いるのに対し、迎撃部隊が擁している機体は通常型が20機。獣型が40機だ。
数字だけで見れば迎撃部隊が討伐できる中型の魔物の数は通常型が40体。獣型が20体。合計で60体となる。
これでは元々確認されていた62体にすら及ばないのだが、エースと呼ばれる機士が数人いることと100人近い砲士による援護射撃があるので大型を含めてもギリギリ何とかなると考えられていた。
実際に上陸してきた魔物の数を見る前までは。
「10の大型だけでなく100体以上の中型が相手ではどうにもならん」
ランチェスターの二次法則を例に出すまでもなく、初期の戦力差はそのまま生存率に直結する。
つまり、62体の魔物と60機の機体が戦った場合は双方に被害が出る接戦となるが、133体の魔物と60機の機体がぶつかった場合、60機の方が一方的に潰されることになる。
このうえ大型もいるとなれば猶更だ。
もちろん戦い方や個人の技量。または連携によって敵に一定以上の被害を与えることは可能だろう。可能なのだが、迎撃部隊に甚大な被害が出ることは避けられない。
その場合、今回の戦いはまだしも、次回以降の防衛戦ができなくなってしまう。
(それを考えれば……撤退、だろうな。それも通常の戦車隊らを殿にして。その場合は芝野大佐も残る、か)
機士隊の隊長である佐藤泰明少佐は、全体指揮官である芝野の考えをトレースして、そう結論付けた。
数に劣るが故に勝てない、もしくは甚大な被害が出るというのであれば、一度退いて数を揃えてから再度挑めばいい。第二師団だけでは無理だが他の師団の力を借りれば可能なことだ。故に芝野らが選ぶのは『たとえ自分たちが全滅しようとも、反撃の中核となるであろう機士と機体だけは戦場から撤退させること』となる。
(その覚悟、無駄にはしません!)
『何があってもお前たちだけは必ず逃がす』
そんな芝野の気持ちがわかるからこそ、佐藤は一刻も早く戦場から撤退できるよう手配をするつもりであった。だが、司令部からの命令が下る前に撤退の準備をすることはできない。
自分一人が査問にかけられることで一人でも多くの部下を逃がすことができるというのであれば敵前逃亡の不名誉も甘んじて受け入れる所存ではあるが、何事にもタイミングというものがある。
今回で言えば、いち早く機士たちが撤退してしまえば殿として残された部隊が暴走する可能性が高いという点が挙げられる。そうなれば殿の部隊もろとも蹂躙されてしまうことになるだろう。
故に佐藤はタイミングを計るのだ。
殿にされた者たちが命を捨てる覚悟をするタイミングを。
機士たちが、命を捨てて自分たちを逃がそうとしてくれる友軍を見捨てて逃げる覚悟を決めるタイミングを。
(まだか。まだか)
『司令部より各員に告げる』
(来た!)
一分一秒も無駄にできない極限の状況でもじっと命令を待つ佐藤。
周囲が焦れる中、司令部からの命令が聞こえてきた。
ただし、その内容は佐藤が想定していたものとは大きく違っていたが。
『全軍、攻撃準備を急げ。戦車隊及び砲士は合図とともに一斉射撃。機士隊は反撃から砲士を護るよう、盾を用意』
「は?」
(全軍で攻撃? 機士は砲士を護る? 撤退ではないのか?)
砲士が撤退の援護射撃をするというのはわかる。できるだけ砲士の損害を無くしたいというのもわかる。だがそれでは機士が逃げる機会がなくなってしまうのでは?
「少佐!」
「どうした!」
混乱する佐藤を正気に戻したのは、副隊長である清田大尉だ。
「あちらをご覧ください!」
「あちら? ……むっ!」
清田大尉が指差す先を見れば、そこには肩に担いだ戦車砲のようなものを魔物の群れに放つ四脚の機体の姿があった。
『グォッ!』
放たれた砲弾は一直線に魔物の下に向かい、その先にいた大型の頭部をぶち抜いた。大型だろうがなんだろうが頭をぶち抜けば死ぬ。故にあの大型も間違いなく死んだはず。
「一撃? い、いや! そうじゃない! あれはどこの隊の奴だ!」
一撃で大型を仕留めたことに驚いた佐藤だが、即座にあの行為が『命令違反』であることに気が付き、その所属を誰何した。
もしあの機体に乗る機士が『命令があったのに拘わらず隊長が呆けていたので撃ちました』というのであれば、それでは仕方がない。と認める程度の器量はあるつもりだが、司令部からの命令はあくまで『合図と共に一斉射撃』だ。軍に所属する者として、一兵卒が勝手に判断して攻撃を行うなどあってはならないことである。
故に佐藤は怒気を放ったのだが、その怒気は司令部から流れてくる言葉が洗い流すこととなった。
『見ろ諸君! 我々が魔物の数に怖気づいている間に学生が先陣を切ったぞ!』
「は?」
(がくせい? 何を言っている?)
「あの、少佐。もしかして、あの機体は試験機として持ち込まれていた新型では?」
「新型? あの単騎で4体の大型を仕留めたという、あれか?」
「おそらくは。噂では今年軍学校に入学したばかりの生徒だけが動かせる機体で、獣型の下半身に通常型の上半身を載せた歪な機体とのことでしたが……」
「いや、あれはそんなものじゃないだろ」
確かに下半身は四脚だが、そこに獣型のような肉感やしなやかさはない。むしろ機械と蜘蛛の脚を足したような無機質さが目立つ。そこに載っている上半身の普通さがなんとも不気味さを助長している。
「あれは、なんだ?」
『ガァァァ!』
佐藤と清野が話をしている間にも、戦場ではなんとも形容しがたい機体がぴょんぴょんと飛びながら狙撃を繰り返し、大型の魔物を撃破していく。
『グギャ!』
『問おう。諸君らは子供に戦わせて敵に背を向けることができるか? 俺は無理だ!』
ワンショットワンキル、否、稀に二発撃っているがそれでも順調に大型を仕留めていくゲテモノ。
「少佐!」
「あ、あぁ!」
姿かたちはさておくとしても、間違いなく自分たちの味方であることは間違いない。
しかもそれを操る機士は噂が正しいのであれば軍学校の生徒、つまり子供だ。
そこまで思い至れば佐藤にも芝野の気持ちが理解できた。
戦略的撤退?
将来の為に逃げる?
目の前で戦う子供を見捨てて逃げるのか?
それで『自分は軍人だ』と胸を張って言えるのか?
機士としての誇りはないのか?
「確かに。確かにそうだ!」
芝野がああいう以上、例の機体を操る子供の行いは芝野も予期していなかったことなのだろう。
同時に、あの戦いぶりから子供が恐怖に負けて命令違反を犯したわけではないというのもわかる。
あれは確信がある動きだ。
それは一部のエースのみが持つ『俺はこんなところでは死なない』という確信だ。
『キャオラッ!』
撃てば死ぬ。反撃をしようにも次の瞬間にはその場にいない。
飛び跳ねながら一方的に魔物を殺していくその様は、正しく命を刈り取る死神のようで。
「総員戦闘準備! 学生一人に戦わせるな! ベテランの強さを見せつけるぞ!」
「「「「はっ!」」」」
『ガトォッ!』
「ただし勝手に動くな! 命令あるまで待機だぞ!」
「「「「了解です!!」」」」
下手に介入すれば彼のリズムを崩すことになる。それがわかるからこそ佐藤は司令部からの攻撃命令を待つことにした。
(待て。待つんだ!)
『ブバァッ!』
(まだか、まだかっ!)
新型機が大物を刈り取る姿を見ながら司令部からの命令を待つその姿は、先ほどまでの焦燥に塗れたものではなく、今にも戦場に駆け出そうとする己を抑えるが如く熱を帯びていた。