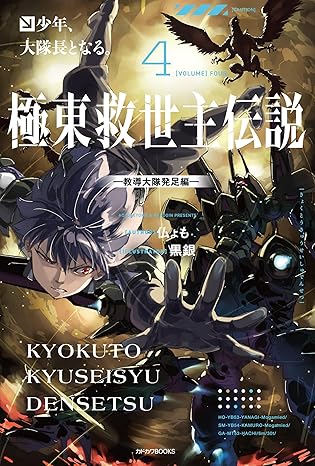22話。予期せぬ大攻勢(前)
魔物が日本を襲う理由については先述した通りなのだが、実は一つだけ説明をしていないものがある。
それは何か? 率直に言えば『口減らし』だ。
言うまでもないことだが、魔物は消費者である。もちろん魔族が命令をすれば畑を耕したりすることはできる。しかし農業や漁業や酪農と言った生産系の仕事に詳しい魔族は限りなく少ないし、何より魔族はそのような気の長い作業を嫌う傾向にある。故に魔族は、支配下に置いた地に住んでいた人間を農奴化して一次産業に当たらせている。
しかし、だ。いくら土地や資源が余っていようと、それは決して無限と同義ではない。
加えて、小型の魔物は野生動物と似た生態を持つ。
つまり小型の魔物は魔物同士で生殖し、増えるのだ。
さらに小型の魔物の食性は雑食であり、人間が作った農作物をつまみ食いしたり、人間そのものをつまんで食べたりするという、誰にとってもなんともありがたくない性質を持っている。
一応小型の魔物は中型以上の魔物にとっての餌になるので、そういう意味では彼らも生産者なのだが、ニンゲンと同じ知性を持つが故にニンゲンに似た嗜好を持つ魔族にとってみれば、小型の魔物など大した戦力にもならないのに餌だけを求める頭の悪いペットと変わらない。
同様に、中型の魔物や大型の魔物も生きている以上は食事をしなくてはならないのだが、彼らはその大きさに比例して大飯喰らいである。
いくら戦力になるとはいえ、一体で一日数十トンもの食料を必要とする大型の魔物を大量に維持することは難しい。
故に魔族は、配下の魔物の中で弱い者や食事量と働きが見合っていないものを選んで出撃させる。
途中で溺れ死んだらそれはそれ。海を渡ることに成功して無事日本に辿り着いたのであれば、迎撃に出てくるであろう国防軍に圧力を掛けつつ物資を使わせる。その上で国防軍の兵士に損害を与えることができれば尚良し、というわけだ。
もちろん魔物はそんな魔族の思いなど知らない。故に彼らは全力で泳ぐし、辿り着いた地に敵がいれば全力で戦うのである。
そうして上陸した彼らは基本的に全滅するため彼らが得た戦訓がフィードバックされることはない。魔族もそこまで期待していないため、行動に変化が出ることはない。
故にいつも同じように上陸し、同じように戦闘を行い、同じように死んでいく。
それが魔物の宿命であった。
……この日までは。
それは新しく生まれた魔族が、命令を受けて日本へと向かう魔物に対して疑問に思ったことを口に出したことから始まった。
曰く「なんでみんな単体で泳ぐの? それだとみんな疲れて溺れるだけでしょ? 大きいのはゆっくり泳いで、中くらいのと小さいのは大きなのに乗ったり引っ張ってもらえば体力の損耗を抑えられるじゃん」とのことであった。
別に命令されたわけではない。しかし上位種である魔族からの意見であるし、何より彼らの本能がそうすることで『より余力を維持したまま任務にあたることができる』と理解してしまった。
知性がないとはいえ、本能の部分で『無駄死にしたくない。命令通り戦いたい』と思っていたのだろう。
これ以降、それまで特大型にしか見られなかった移動戦術を大型の魔物たちも共有することになる。
それはまるで渡り鳥が隊列を組むことで気流を操り、全体の体力の消費を抑えるかの如き行いであった。
魔物たちがこの単純ながら効果的な移動方法を得たことが敵に何を齎すか。
それは数日後、対岸である日本の防衛ラインを維持していた第二師団が身を以て経験することになる。
―――
「馬鹿な! 多すぎるッ!」
司令部の一角からそんな声が発せられたのは、啓太が九州に到着してから3日後のこと。前日までに配置場所の確認やら武装の最終点検やらを終わらせ、万全の状態を保ったうえで魔物との戦闘を行おうとしていた矢先のことであった。
この世界は第二次大戦中に悪魔が召喚されたこともあり、啓太が知る世界では当たり前ともいえる存在であった人工衛星を使った監視体制などというものは存在しておらず、基本的に監視はレーダーを積んだ監視船による索敵や地上に設置された大型のレーダーによるものに頼っている状況だ。
ちなみに監視船とレーダーの比率は1:9くらいの割合である。
本当であれば軍としても、いくつもの船と優秀な監視員を使った監視部隊のようなものを組織したいところなのだが、海上で魔物に襲われた場合その船に乗っている船員たちは間違いなく死ぬことになるというのがネックになっていた。
まぁ、一度や二度の索敵で専門の教育を受けた船員を死なせるわけにもいかないのだから船員を必要とする監視船の数が絞られるのは当然と言えば当然の話と言える。
そのため軍はいくつかのポイントに使い捨てのレーダーを配置し、それが破壊された場所と時間を逆算することで魔物の侵攻方向と到達時間を察知するようにしていた。
この方法の欠点は、魔物が上陸する正確な場所や時間がわからないことと、敵の数がわからないことだ。
故に迎撃部隊は、魔物の進軍が確認された時点で魔物が上陸されると思われる地点に移動を開始し、魔物が来る前に展開を終わらせ、迎撃の準備を整えてから敵の数を探るようにしている。
上記のような順序で動いているため、魔物の数の確認が遅れるのはある意味では仕方のないことと言えよう。
また地上から魔物を探るために設置されている大型レーダーの索敵範囲は凡そ300キロほどなのだが、この索敵範囲の広さも敵の数を誤認する理由の一つとなっている。
というのも、魔物が300キロ泳ぐためには大体1日ほどかかるのだが、軍はその300キロを泳いでいる間にも一定数の魔物が溺れることを想定している(溺死する魔物の数はこれまでの経験から算出している)からだ。
この場合、当然海の状況によっては溺死率も低くなるので、最終的に『上陸に成功した魔物の数が思った以上に多い』ということもままあることと認識されていた。
よって、想定よりも多少魔物の数が多いからと言って、戦闘経験豊富な指揮官が声を荒げることなどないはずであった。――通常であれば。
「なんだあの数は! 一体どうなっている!」
迎撃部隊の指揮官である芝野雄平大佐は目視できる範囲に現れた魔物の数を見て声を荒げていた。
先述した理由から、魔物の数に多少の増減があるのは当たり前のことだ。それは芝野とて理解している。
理解できないのは、魔物の数が、多少どころではないほどに多い、否、むしろ増加していたからだ。
「減るのはわかる。だがなぜ増える!」
事前にレーダーで観測されていた魔物の数は、大型が15。中型が62。小型が200弱と合計でおよそ300体。
この時点でこれまで第二師団が観測してきた中で最大規模の数であった。
そのため芝野は敵の規模が判明した時点で他の部隊に応援を要請したし、休暇の予定だった兵まで招集した。加えて本来であれば後方で試験を行うはずだった試験機まで動員している。
まさしく猫の手を借りている状況であった。
そうして集められた迎撃部隊の内訳は、通常型の機体を使う機士が20。獣型の機体を使う機士が40。砲士(棺桶砲と言われる砲撃専用の砲を使う機士)が100程。
通常兵器では戦車400両、歩兵兼砲兵が4000人という、第二師団が有する戦力のおよそ50%。機士については第二師団が有する戦力のほぼ90%を動員している。
機士の数が少ないと思われるかもしれないが、そもそも機士という兵科が増やしづらい兵科なのだ。
確かに第二次救世主計画の影響で日本では魔晶の数や機士の数は増えている。しかしながらその数は、啓太が通う軍学校に入学した人数が示すように年間約100人程度でしかない。
第二次救世主計画が発動してから約50年。この計画によって一定の数が集まったと判断されたために行われた第一次反攻作戦から約30年しか経過していないことを考えれば、単純に考えて100人×30年で3000人となる。この中で通常型や獣型を使える程に魔晶との適合率が高いのは30%程度しかいない。つまり通常型や獣型を使う機士は900人。棺桶砲を使う砲士は2100人となる。
もちろん軍学校に通っていない下士官にも魔晶との適合率が高い人間はいるので機士も砲士も多少の増加はあるものの、それでも年間30人を上回ることはないのが実情であった。
結果として900人の機士と2100の砲兵は9つの師団で分散させて配備されているため、その数は単純計算で一つの師団に所属する機士が100人。砲士が230人となる。
尤も、九州や中国地方を守護する第二師団は他の師団に比べて多めに人材が配備されているので、実際に配備された機士の実数はもう少し多いのだが、近年に配備された機士の多くが遠征軍である三・四・五師団に優先して回されたし、なにより30年の間に年齢や怪我を負ったことを理由に除隊している機士や戦死している機士がいるので、現在第二師団に配属されている機士の数は、通常型と獣型を合わせても70人。砲士は130人となっている。
よって今回機士60人、砲兵100人の動員というのは、他の場所に上陸されたときのことを考えて予備に回された戦力を除いた限界ギリギリの数であった。
ただし、これだけの戦力を集めても大型15体、中型62体の相手は厳しいと言わざるを得ない。
(勝つことはできるだろう。だが反撃で相当数の砲士と機士を失うことになる)
芝野だけでなく第二師団の上層部の皆がそう思っていた。
しかし、魔物の上陸を前にして彼らは、特に芝野は絶望と共に自分たちの想定が間違っていたことを痛感させられることになる。
何故か? 前提となる数が違ったからだ。
それも観測員が肉眼(双眼鏡)で確認したところ、上陸に成功するであろう魔物の数は、大型が10体。中型が133体。小型が500体以上となっていたからだ。
「なぜだ!」
大型は減ったが、他が増えている。それも想定の倍近い数にまで増えている。
まさしく前例のない異常事態である。
「なぜここまでの齟齬が生じたっ!」
中型が100体を超えるという規模の群れなど、それこそ大陸で反攻作戦に当たっている第四師団や第五師団が稀に遭遇するくらいで、そうそうお目にかかれる状況ではない。
その第四・第五師団とて現地の軍勢と協力して当たっているが故にそれほど大きな被害を出すことなく対処できているのであって、これだけの規模になると本来一つの師団が単独で当たるような数ではない。
さらに大型の中には最大とされる30M級が複数いるというではないか。
「レーダーで観測したときは間違いなくここまでの数はいなかった。一方向から一つのレーダーで観測しただけではなく、複数の場所から複数のレーダーで観測したうえで算出された数値だからそれは間違いない。そしてこの大型の数と種類だ。30M級なんて今まで見たことがない。それが急に、しかも複数現れた……間違いない。悪魔や魔族がナニカしたな!」
魔物が増えた理由を考察する芝野。確かに、レーダーに異常が無いのであれば悪魔や魔族が魔力という不思議な力を使ってレーダーを誤魔化したと考えるのが最も自然な考え方である。
しかし芝野の考察は的を外している。
答えを言ってしまえば、別に悪魔や魔族が意識をして欺瞞工作を行ったわけではない。
増えた分の中型や小型は、単純に大型の上に載っていたため数に数えられていなかったものや、纏まって大型に引っ張られる形になっていた魔物たちが一体の魔物と誤認されただけの話である。
これまで見られなかった30Mがいるのも、魔物が互いに体力の損耗を抑えるようにして泳いできたため、今まではその大きさ故に疲労が激しく、途中で溺死していた個体が無事に辿り着けただけの話である。
「大佐!」
「くっ!」
とはいえ。どのような理由があろうと、目の前に魔物がいる。
そうである以上芝野は決断をしなくてはならない。
即ち、退くか、戦うか、を。
(どうする? どうしたらいい!)
迎撃部隊指令官芝野は決断を迫られていた。
閲覧ありがとうございます
読者様から頂けるポイントが作者にとっての燃料となります。
面白かった。続きが気になるという読者様がいらっしゃいましたら、ブックマークや下部の☆をクリックしてポイント評価をしてくださいますよう、何卒よろしくお願いします