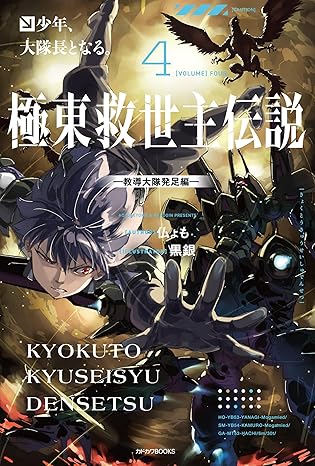13話。クラスメイトの思惑(前)
藤田一成
「巡嗣。例の話は聞いたか? 」
「無論だ」
「まさか入学から一か月と少しで特務少尉として戦場に出るとはな」
「それも中型を多数と大型を討伐したらしいぞ」
「大型……じゃあ卒業と同時に少尉、いや、特務中尉か?」
「さて。少なくとも少尉は確実だろうな」
「一年どころではないくらいに先を越されたな」
「あぁ」
通常軍学校を卒業したものは准尉として軍に配属される。そこで一年実務を経験させた後で少尉に昇進させるというのが通例となっている。
よって現時点で少尉となるであろう啓太は、その働きだけで『一年の実務』という期間を省略したことになるわけだ。
最初の一年だけといえるかもしれないが、その間の任務に大きな違いがあることを忘れてはいけない。
片や准尉として下積みをする者。片や少尉として戦場に出る者。どちらがより上に行きやすいかなど、語るまでもないことだろう。
もちろん、卒業後に軍の大学校に行く場合はまた少し違うのだが、どちらにせよスタートラインが違うのは変わらない事実である。
啓太の昇進のきっかけとなった戦果については、一成とて最初に話を聞いたときは「何を馬鹿なことを」と思ったものだ。しかし、試験中のこととはいえ彼が挙げた戦果は第二師団によって公式に認められているもの。そこに嘘や誇張はなかった。
「羨ましい、と思っては駄目なんだろうな」
「あぁ」
入学して一か月で戦場に出て、抜群の功績を立て昇進する。
これだけ見れば確かに羨ましいことこの上ない。
彼はどうやって戦場に出ることが許されたのか。
彼は戦場でどんなズルをしたのか。
Bクラスの生徒だけでなく、上級生の先輩たちまでもが彼に嫉妬と疑惑の目を向けているのも理解できる。一成とて彼の事情を知らなければ似たような感情を抱いただろう。
だが違うのだ。
彼は生まれた時から戦場での活躍を願われ、そのために鍛えられてきた我々とは根本からして違うのだ。
我々は、彼が戦争による被害者であることを知っている。
我々は、彼には伝手もコネもないことを知っている。
我々は、彼が妹との生活を護るために軍へ入隊したことを知っている。
我々は、彼に回された機体が混合型という、これまでにないコンセプトの機体だったことを知っている。
我々は、彼に与えられた機体が財閥系ではなく新規に参入してきた企業が造った新型だったからこそ失われても良いと判断されたことを知っている。
我々は、上層部から彼が死んでも惜しくない人材と見做されたからこそ、学生ながら戦場に出され、戦場での試験を行う許可が出たことを知っている。
つまり彼は、上層部の都合で戦場に行き、そこで死に物狂いで戦い、結果として功績を立てただけに過ぎないということを知っている。
それを羨む? ありえない。
そんな浅ましい感情で彼と向き合うべきではない。
「決めたぞ巡嗣」
「なにをだ?」
「俺は正直今まで距離感が掴めず曖昧な態度で接していた」
「……それは俺もだ」
通常自分たちのような人間が彼のような戦争被害者と顔を合わせることなどないから。
だから距離感を掴めず曖昧な態度になるのも仕方がない。
そう思っていたが、それは甘えでしかなかった。
それを自覚したからには変えなければ、変わらなければならない。
「金輪際、彼を被害者として見るのは止めにする」
「一成、それは……」
「いや、無論そのことを忘れるつもりはない。戒めとして覚えておくべきことだからな。だがそれとは別だ」
「というと?」
「生粋の武門の人間からすれば面白くはないかもしれんが、功績を上げた者を『武門の出ではないから』と言って認めないのは違うだろう? 故に彼はただのか弱き被害者ではなく、我々と共に戦場に立つ資格を持った同胞として扱うべきだ」
「……なるほど」
実際は上に立たれているが、な。
それでもすぐに追いついてやるさ。
「さしあたっては彼が使う機体を見せて貰うとしよう。勿論一方的に情報を搾取するのではなく、こちらもそれなりの情報を渡すつもりでな。当然お前にも協力してもらうぞ?」
「問題ない」
――こうして第七師団閥の若手を代表して軍学校に入学した二人は、啓太を一人の級友として認めるとともに、これまで意図して取っていた距離を詰めることを決意したのであった。
―――
武藤沙織
第七師団の二人が啓太との距離感について話し合っていたころのこと、主席として入学した武藤沙織を中心とした第三師団閥の面々もまた啓太のことについて話し合っていた。
「あの男が戦場に出ることができたのは偏にあの男に後ろ盾がなかったからに他なりません! 第二師団の連中はあの男を取り込むと同時に、我々を戦場に立たせない為にあの男を取り立てたのです!」
(そうなのでしょうか?)
「辰巳の意見は正しいだろう。実際アレが戦場に立ったことで、第二師団は『もう生徒を受け入れているので他の生徒の実習に付き合うことができない』という断り文句を得たからな」
(それは、たしかにそうかもしれませんけど)
5席として入学した笠原辰巳が声を荒げながら訴えれば、9席として入学した小畑健次郎は我が意を得たりと頷いている。
ちなみに5席の笠原よりも9席の小畑健次郎が偉そうなのは、偏にお互いの実家が持つ格の違いにある。
笠原家は第三師団閥の内で参謀や旅団長を輩出した名家なのだが、小畑の家はそれ以上の名家。即ち前第三師団の師団長、牟呂口廉次郎を輩出した牟呂口家の一員なのだ。具体的には牟呂口家の次男を入り婿として迎え入れたのが小畑家であり、健次郎はそこの次男であった。
つまり健次郎は第三師団閥の領袖であった牟呂口廉次郎の孫ということだ。
現在牟呂口家は、先年のインパール作戦に於いて当主であった廉次郎とその嫡子である伸昌。さらに小畑家に入った次男の裕司が死亡したため、当主不在の状態となっている。
一応伸昌の子、廉次郎からみて嫡孫である敬信は生きているが、彼は健次郎より一才年上の身。
つまりまだ学生であるため、武門の派閥を束ねる身として必要な武功を上げていない。
また軍部の中に於いてもそうだが、世間的にも牟呂口という名に対する忌避感が強いこともあり、今後数年以内に彼がまともな戦場に配備された上で周囲に認められるような戦果を挙げることは限りなく難しい状況にあると言わざるを得ない。
こういった事情があるため、牟呂口一族が健次郎にかける期待は大きくなっているのが現状である。
健次郎は健次郎で周囲からの期待とその内容を理解しており、何としても従兄弟である敬信よりも先に武功を立てたいという思いがあった。
故に健次郎は、まずこの軍学校で二年、もしくは一年雌伏した後、実習という形で出征し、そこで武功を立てて自分が本家を継ぎ牟呂口家を再興する。そんな大望を抱いていた。
こういった事情から、笠原辰巳は実家から小畑健次郎を支えるよう命令を受けている。つまり彼らは主従の関係にあるわけだ。
因みに沙織の実家である武藤家は、先代である彼女の父が第三師団の総参謀長を務めるなど第三師団閥に於いて牟呂口家も軽視できないほどの重鎮の家である。
とは言っても、彼らも遠征先で当主や多くの人材を亡くしたせいで他にかまけている余裕はない。
そのため現在水面下で行われている健次郎と敬信による家督争いには興味を抱いておらず、まずは自己の家の武名を取り戻すことを第一としていた。
なので武藤家は笠原家と違って沙織に対して健次郎をささえるような命令は出していない。
むしろ距離を取るよう指示を出しているくらいであった。
尤も生粋のお嬢様として育てられてきた彼女にとって辰巳も健次郎も距離を取りたい存在だったので、その指示はまさしく渡りに船だったのだが……。
(辰巳さんも健次郎さんも私のことを味方だと思っているみたいなんですよねぇ)
思わず溜息を吐きたくなる沙織であったが(ここで波風を立ててもしょうがないですよね)と黙って彼らの会話を聞くことに徹していた。
武藤家や沙織の思惑はさて置くとして。
自身こそが第三師団閥の正当な後継者と考えている健次郎としては、当然入学の成績で笠原辰巳や武藤沙織に負けたことに思うところもあった。しかし『自分は武官の中でも将として彼らを使う存在なのだ。だから魔晶との相性を第一とする試験で後塵を拝するのも仕方のないことだ』という理屈で己を納得させていた。
さらに一般人のくせに自分たちよりも成績が上だった小僧――しかも言うに事を欠いて第三師団が敗戦したせいで両親を失ったなどと被害者ぶった上で、挨拶にも来ないという不遜な態度をとる不届き者――に聞いたこともない会社が製造したゲテモノの機体が割り振られたことを知り、それを嘲笑うことで溜飲を下げていたのだ。
そうして無聊を託っているところに齎されたのが、啓太が自分たちを差し置いて戦場に出たという情報であり、そこで多大な戦果を挙げたという情報であった。
最初はその情報の真偽を疑った健次郎であったが、その情報が真実であると知って不快感を露わにした。いや、激昂したと言っても良い。
この場は、その様子を見た笠原が『この流れは良くない』と思い、健次郎を宥めつつ、健次郎が功績を挙げるためにどうするべきかを論じるために用意された場であった。
閑話休題。
重鎮の家の出であり、主席入学者である沙織に否定されず、主筋である健次郎が自分の意見を認めたことで調子に乗った辰巳は賢し気に言葉を紡ぐ。
「そうですね。それと、あの男が戦場に出ることができた最大の要因は派閥が関係していることに間違いありません。ですが、実際の口実として用意されたものは他にあります」
「……新型の試験だな?」
「ご明察です。あれがなければ如何に第二師団が口を挟もうと、我々を差し置いて一般人の子供を戦場に立たせるなどということはできませんでした!」
「確かに。この学園に、否、日本に一つしかない機体の試験となれば特例として許可が下りることもあるだろう。テストを行う機士が死んでもいい小僧なら猶更だな」
「えぇ。えぇ。その通りです。あの男が挙げたとされる戦果を見れば、アレは本来我々に割り当てられるべき機体であったということは明白です!」
「うむ。だが試験運転すら行われていない、つまり安全性が不確かなものを我々に回すわけにいかなかった。だからこそあの小僧が先に使うことになった。それだけだ」
「その通りです。あの小僧が挙げた戦果はあの機体があれば誰にでもできるものなのです!」
彼らの話し合いは、一成や巡嗣のように事実を事実と認識した上での話し合いではなく、感情に任せて語るだけのものであったが。少なくとも彼ら二人は真摯に話し合っているつもりであった。
(それは違うと思いますよ?)
黙って話を聞いていた沙織は、そんな二人の意見に懐疑的な思いを抱いていた。
まず機士としても優秀な沙織とて啓太が乗ったという混合型を動かせる自信はない。アレを動かせるというだけで啓太の有能さ――もしくは稀少さ――がわかるというものだ。
そもそも彼女が啓太に抱いている感情は、第七師団閥を率いる一成のそれに近い。
むしろ派閥の面目という理由で下駄を履かされて主席にされた自分よりも――もちろん大量の下駄を履かされておきながら9席にしかなれなかったどこぞのお坊ちゃんよりも――よっぽど優秀な人材だと思っているくらいだ。
(それに、ねぇ。現状第三師団の状態はよくないのですから、敵を作るのではなく味方を作るべきでは?)
彼女個人の意見もそうだが、第三師団閥の人間として見ても、現実問題として師団を再建する為には他の派閥の力を借りなければならないという問題が有る以上、他の師団に喧嘩を売るような真似は慎むべきだという思いもある。
まして啓太は後ろ盾のない一般人だ。今は第二師団が取り込みを行っているようだが、そんなものは政略結婚でもなんでもして身内にしてしまえば解決する問題ではないか。
彼自身に一族の誰かを嫁がせるもよし、彼の妹を嫁にするもよし。武功を立てたからこそ取り込むべきなのに、なぜわざわざ敵対しようとするのか。
(雌伏すると決めたのであれば一年か二年くらいは我慢して欲しいものですがねぇ。これも男の意地ってやつなのでしょうか? 私にはわかりません)
「情報では第二師団の要請で二号機の組み立てを行うそうです」
「ではそれをこちらで回収しよう。なに、最上重工業など聞いたこともない企業から徴収するのは難しいことではない。第二師団が新型を独占することを嫌がる連中もいるだろうしな」
「名案ですな!」
(いや、どこが? それをやったら完全に最上重工業さんと第二師団を敵に回しますよ? やはり彼らとは距離を置くべきでしょう。さしあたっては川上さんとコンタクトを取りましょうか。おそらく藤田さんも同じように動くはず。となると向こうは少なくとも二人。……これは早急に味方を作らなければいけませんね。あぁ、彼らがもう少し使える人材であったなら……いえ、これは言っても詮無きことでした。はぁ。なんと面倒な)
目の前で悪巧みをする二人を冷めた目で見やりつつ、沙織はお嬢様として育てられてきたが故に鍛えられてきた感覚に従い、これから水面下で発生するであろう勢力争いに思いを馳せるのであった。
主席は腹黒系お嬢様だった?
まぁぽやぽやしていたら家を乗っ取られますからね。
そうならないように鍛えられますよね。
閲覧ありがとうございました。