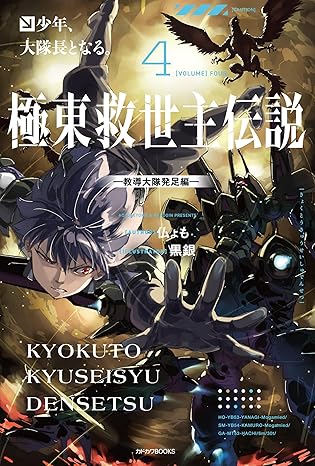10話。シミュレーション
目標をセンターに入れてシュート。
着弾確認。
横っ飛びしながらセンターに入れてシュート。
着弾確認。
着地と同時にセンターに入れてシュート。
着弾確認。
もう一度横っ飛びしながらセンターに入れてシュート。
着弾確認。
着地する前にセンターに入れてシュートして、着地と同時にセンターに入れてシュート。
着弾確認。か~ら~の~着弾確認っと。
うむ。やはり最初から砲弾を装填している武器を魔晶に収納しておけば、装填なしでの射撃が可能だな。火器の収納と交換には多少の慣れが必要だが、これについては文字通り慣れるしかない。
問題は着地と横っ飛びを繰り返していることで脚部にかかる負担が増えることだが、さすがは獣型の下半身。(今のところは)なんともないぜ。
ただし、この挙動は傍から見ると随分と気持ち悪いものだろうということを忘れてはいけない。
これが標準型であれば、横っ飛びや横転なんて――もちろんかなりの習熟度合いが必要になるが――珍しいものではない。
しかしこれが四脚となれば話は別。考えてみるといい。野生動物が予備動作もなくいきなり横っ飛びしたら怖いだろう? それも上半身が人間だったら猶更怖いわな。
さらに横っ飛びしながら射撃まで行うんだ。説明書には『撃った直後でも移動できる』と書かれていたが、こんな方法で移動するとは製作者側も思っていなかったはず。
よって現在俺が行っているコレは、もはや狙撃手の常識を覆す挙動と言ってもいいだろう。
ちなみに、機士が機体を動かす際に重要なのはイメージだと言われている。
それは機士と機体は神経で繋がっているわけではなく、魔晶を通じて繋がっているからだ。
故に機体は機士が想像できないことをすることができないというのが定説である。
そのため武術を習得している人間が機体を操作する場合、真っ先にするよう教えられることは『全身の神経が機体と繋がっていることをイメージすること』なのだとか。
武器は体の延長にあるってわけだな。
そうやって思い浮かべたイメージが鮮明であれば鮮明であるほど、機体もより細かく搭乗者の動きをトレースしてくれるようになる。
ちなみに獣型の場合に思い浮かべるイメージは、ハイハイだ。
そう、あの赤ん坊がやるやつ。
訓練方法は匍匐前進が主なものになるらしいし、ハイハイが嫌ならお馬さんごっことかそういうのを連想させるらしいが、最終的なイメージはハイハイなのだ。
しかしながらハイハイと馬鹿にするなかれ。あれはあれで生物としての本能にしみ込んだ行動なので、本能ではなく理性で体を制御する必要がある武術よりもトレースが容易にできるらしい。
そういった諸々の常識を踏まえた上で、俺の機体はどうか?
神経をつなげるイメージをしようにも自分が四脚であることを想像できるほど器用な人間ではないし、上半身だけ神経を通わせて下半身を切るなんて真似もできない。
まして下半身を動かす際に必要なイメージであるハイハイをするためには上半身が邪魔になる。
故に、下半身に横っ飛びを実行させながら上半身で狙撃を行うなどという挙動は、まともな人間には本来不可能な挙動なのだ。
では何故特に才能があるわけでもない俺にこんな挙動ができるか?
それは偏に俺の中にある前世の知識のおかげだったりする。
ほんのりとしか残っていなかった知識だし今となってはほとんど忘れているが、それでも覚えているものがある。それがロボットものの知識だ。
まぁあれだ。実際に魔物がいて、それを討伐するロボットがある世界に転生しておきながらロボットものの知識を忘れるなんてありえないよね。
かといって細かい技術や整備の仕方などはわからないので、俺が持っている知識はあくまでほんのりとした知識でしかない。
その中で今回役に立ったのが、長年新作が出るのを待ち望んでいたにも拘わらず俺が死ぬまで5以降が出ることがなかった変態の変態による変態のためのロボアクションゲームこと、アーマー〇コアの知識である。
いや、だって、四脚で上半身に人型ってそれしかないだろ?
ガン〇ムやマク〇スにいたかもしれないが、俺は知らないし。
で、この世界では例の粒子が発見されていないせい(おかげともいう)でホバーがない代わりに、十分なバネを備えた下半身が用意されているのだから特に問題はないと判断した俺は、あのゲームと同じような感じで機体を操作することにしたのだ。
即ち神経を巡らせるのではなく、コントローラーで動かすイメージである。(なお持ち方は例のアレ)
結果は、見ての通り。頭は忘れても魂(体)に刻み込まれた記憶は消えていなかったらしい。
完全に思い出すのには少し時間が掛かったし、ゲームとは違うところも多いので当然多少の問題はあるが、大きな問題は見られない。
今なら後半のミッションにだって挑戦できると思う。(クリアできるとは言っていない)
ただし対機体戦を考えた場合、ミリ単位の注意が必要となる近接戦闘では後れを取る可能性を考慮しなくてはならないだろう。
尤も、この機体の開発コンセプトは高威力の砲を用いた遠距離狙撃なので、最初から近接戦闘能力は求められていないんだけどな。
何故かって? 試作型ガン◯ンクに近接戦闘力を求めるのは野暮というものだろう? そういうことだ。
もちろん問題点であることは事実なので対処法を考えなくても良いってわけではないけどな。
―――作戦終了―――
「ん? 終了か」
色々なことを考えながら狙撃をしている間に用意されたカリキュラムは終わったらしい。
戦果は、大型が8と中型が6。焼夷弾の傷痍効果に巻き込まれた小型が22、ね。
あくまでシミュレーターの中のことだからこの成績がどれほど俺の評価につながるのかは不明だが、それでも悪い成績ではない……むしろかなり良好な成績を出せたはずだ。
根拠としては、単騎で大型を仕留めることができたことだ。
今更だが、魔物は魔族や悪魔によって造られた生物である。
勿論原料となっているのは悪魔に支配された地域に住む人間や野生動物だ。
造り方の詳細は不明だが、魔晶を植え込んだり、悪魔的な因子を植え込むことでできるらしい。
そうやって造られた魔物はその大きさで4つの型に分類される。
まず3メートル以下の小型。これは小鬼型や動物型が多く、数も一番多い。
次いで3~10メートルの中型。
人型であればミノタウロスとか牛頭鬼などだし、獣型で言えば熊や虎など大型の魔物が変異したものである。機体の基になっている死体は主にこいつらだ。
お次は10メートル~30メートルの大型。
これは幻想系とか呼ばれるタイプで、牛鬼のような妖怪っぽいやつや、ナウ〇カに出てくる王蟲みたいなのや、マクロ〇Fに出てくるヴァジ〇ラっぽいのが多い。
あとこの辺からメチャクチャ強化された巨人や、謎の光線を吐き出す竜なども出てくるそうだ。
最後が30メートル以上の特大型。
100メートルだろうが500メートルだろうが分類上は特大型となる。ヨーロッパで数体確認されている。フェンリルだとかミドガルズオルムだとかといった神話生物が再現されているだけでなく、大型や中型の魔物を運ぶ空母のような役割を持った個体がいるらしい。
そして魔物は中型以上になると魔力障壁と呼ばれる力場を展開してくるようになる。
これは同等の力、つまり魔力と呼ばれる力が含まれない攻撃の威力を大きく減退させる力があるので、攻撃に魔力を乗せることができない通常兵器で中型以上の魔物を討伐するのはとても面倒なことなんだとか(できないとは言わないが、かなりの労力を必要とする)。
一言で言い表すなら劣化版のA〇フィールドだな。
そんな障壁があるから、魔晶を通じて魔力の籠った攻撃が可能な機体が必要になるんですね。(説明風)
また大きくなれば大きくなるほど多くの悪魔的な因子を含むので、魔力障壁の強度も高くなるし、攻撃方法も物理だけではなく魔法っぽい攻撃――つまり謎のビームによる遠距離攻撃――もしてくるようになる。
これらの事情から、小型や中型はまだしも大型の魔物を討伐する為には複数体の機体、もしくは特別に調整された防衛兵器(バカでかい砲を本体とした機体。機動力も防御力もなく、ただ攻撃力だけに特化しているため、大型も葬ることができる反面、優先的に反撃を受けることになるので損耗率が非常に高い。別名棺桶砲)が必須とされている。
と、まぁ魔物と機体についてはこんなところだろうか。
つまり、現在国防軍では複数の機体にせよ棺桶砲にせよ、大型を相手にする際はある程度の損耗を前提としているので、俺が単騎で――それも無傷で――複数の大型を仕留めることができたというデータは非常に貴重なデータとして扱われるはずなのだ。
尤も、それもこれも入学前に多少調べただけの知識しかない俺がそう思っているだけで、今は単騎で大型を討伐するのが普通になっているのかもしれないが、それでも悪い結果ではない……と思いたい。
そう言った願望を無視して単純にテストパイロットとして気になる点を指摘するなら、焼夷弾は小型を片付けるのには便利だが、攻撃が及ぶ範囲には注意が必要だと思う。
『敵を狙撃したら味方も巻き込まれました』なんて笑い話にもならないからな。
追加するとすれば、単体狙撃用の徹甲弾を用意してもらうか、もしくはマゼラ〇ップ砲みたいに戦車の砲塔をそのまま流用するってのもアリかもしれない。
問題はやはり距離を詰められた場合だろう。相手が大型の場合は後で考えるとして、相手が中型や小型の魔物だった場合の想定はしておくべきだろうと思われる。
一目散に逃げることができるような状況であれば問題ないが、友軍がいて自分だけ撤退することができないような状況になったら一気に手詰まりになるからな。
これを解決するためには近接戦闘用の武器や機関銃的な武器を用意する必要があるだろう。
そうした場合、ただでさえ重いところに武器の重量が追加されるうえ、遠距離狙撃から近接戦闘に切り替えるのは大変だろうから、量産機として評価するのは難しくなるかもしれない。
並べて狙撃するだけならそれこそ砲に細工を施した重戦車を並べた方が早いしな。
ただまぁ俺の仕事はあくまで報告することだ。
その後のことは向こうと将来の俺に任せよう。
「とりあえずこんなところでしょうか。初回ですから色々見落としはあると思いますが、その辺の調整はお願いしても?」
『お、おう。了解した』
ん? なんか焦ってないか? 問題点が多くて凹んだか? 確かに色々問題があったけど試作機に問題があるのは当然だし、何より一つの失敗が命に関わる実戦じゃなくて、安全なシミュレーターで判明したんだから喜んでおけばいいのに。
どうした? 笑えよ、整備士ってな。
―――
(どうなっていやがる!?)
シミュレーターの中のこととはいえ、軽快に戦場を飛び回りながら魔物を狙撃するなんて離れ業を見せながら報告書に書く内容を口ずさむという異常そのものの行動を普通にこなす変た……啓太を見て、隆文は心の中で叫び声を上げていた。
確かに啓太がやっていることは、自分たちが混合型の説明書として渡した書類の中に書かれている挙動である。だがあれはあくまで『カタログスペック上は可能な挙動』つまり『この機体であればできるはず』という製作者一同の理想を書きなぐったようなものでしかないのだ。
実際は射撃の際には動きが止まるし、射撃の際は反動で重心がブレる。横っ飛びも不可能ではないが着地したら脚部に負担がかかる。間違っても着地と同時に射撃を行い、それが当たるかどうかを確認する前に跳躍、なんて挙動をしていたら機体はともかく中の機士が無事で済むはずがない。
そう、理想は理想でしかないというのに、啓太が操る混合型の動きは隆文を始めとした製作スタッフが思い描いていた理想そのもので……。
『とりあえずこんなところでしょうか。初回ですから色々見落としはあると思いますが、その辺の調整はお願いしても?』
思わず見惚れていたところに啓太から声が掛かる。
(こんなところ? こんなところってなんだ?)
告げられた内容はシミュレーションに組まれていたカリキュラムの終了と、シミュレーション中に見つかった問題点の指摘と改善案のほか、調整に関わる細かい数値など、整備士として見れば「確かに」と頷ける内容のものばかり。
啓太は『初回だからこんなもの』というが、同じだけの情報を含むレポートを提出するためには、どんなに少なくても5回以上の試行が必要と思えるような内容である。
こんなものを初回から出されては文句など言えるはずもなく、隆文は再度(どうなっていやがる!)と叫び声をあげながら、なんとか「お、おう。了解した」と、情けない返事をすることしかできなかった。
しかし、隆文とてただの整備士ではない。(変態)企業の社長として見れば、啓太がたたき出したスコアと早々に洗いだした問題点は、その全てが社運を掛けて造り上げた新型機を完成させるために必要なピースである。
(これならやれる。やれるぞ!)
基本的に今の国防軍が機体に求めているのは、高性能だが高価なうえに特殊部品や特殊なメンテナンスを必要としたり、特殊な才能を有した人材でなければまともに動かせないようなピーキーさ、ではない。
それなりの性能であろうとも、誰でも使える上に量産が容易であること。つまり生産性の高さにある。
それは隆文とて重々承知している。
良い企業とは、自分が求めるモノを造る企業のことではなく、顧客が求めるモノを造ることができる企業のことを指す言葉だということも、頭では理解している。
しかし技術者というナマモノは絶えず「今できる最高の機体を造りたい!」という欲望を抱えているものだ。
これまでは『社員を食わせる必要がある』という現実の前に妥協してきた。……恐ろしいことに、これでも隆文は妥協してきたつもりであった。
(だが、これからは違う!)
今まで使い手がいなかったが故にどこまで引き上げれば良いかわからなかった各種数値が計測できるようになったのだ。それも『軍で採用されるかもしれない新型の実験』という、誰憚ることなく金と労力をつぎ込める名目まである。
当然各種能力は限界まで引き上げるし、限界に至ったときの挙動をチェックしてそれより上を目指すことの指針とするつもりである。さらに啓太の挙動を詳細に記録し、データ化することで量産が成った暁にはすべての機体が啓太のような挙動を実行すること――あそこまで変態的な機動は不可能だろうが――ができるようになるかもしれない。
(そうなれば、軍という顧客が混合型を求めるようになる)
それはつまり『自分たちが顧客が求めるモノを造れる良い企業』になるということである。
(乗るしかねぇ! この大波にッ!)
隆文の、否、最上重工業に所属する技術者たちの浪漫と実利が一致した瞬間であった。
「ふへへへへ」
散々馬鹿にされてきた混合型が戦場に並び、魔物を駆逐していく様を想像して思わず怪しい笑い声を上げてしまう隆文。
「おっと! こうしちゃいられねぇ! けど……ふへへへへ」
にやけながら書類を作成し、またにやける。
傍から見ればその様子はあきらかにおかしい人のソレだったし、そもそも戦場に混合型が並ぶという光景が普通の感性を持つ人間にとって悪夢そのものだという事実に、隆文は終ぞ気付くことはなかったのであった。
変態の脳内にV作戦が発案されました。
変態に金と時間とアイディアを与えてはいけない。はっきりわかんだね。
なお、第三次救世主計画はあくまで魔晶との適合率が高い人間や人間と適合しやすい魔晶を生み出すための計画であって、川上兄妹(特に妹)の天才性は計画に全く関係ないところで発芽したものである。
つまり? やったね同胞! ハードルが上がったよ!
閲覧ありがとうございました。