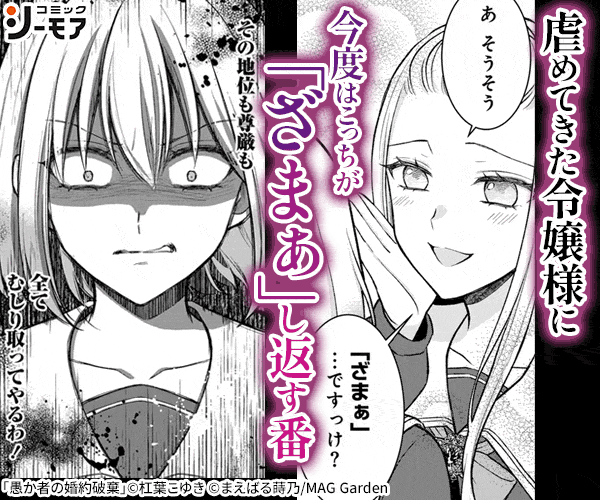8・シュヴァルツの追想 下
「ああああああっ!!」
無我夢中で手のひらをオークへと向ける。オークの頭に、翼に、次々と風穴が開く。
オークは爆散した。次々と、無我夢中でオークを攻撃する。
時にアンドヴァリ公爵令嬢をオークから守りながら、時に彼女に守られながら、シュヴァルツは数え切れないほどのオークを打ち払った。
――その後宮廷魔術師と騎士が増援され、あっという間にオークは鎮圧された。
大人になったシュヴァルツから見れば、小規模なオークの偶発的発生事由だった。
たいしたものではない。
けれどこの時、シュヴァルツは初めて己の力を求められ、己の力で女の子を助けることができたのだ。
そのままシュヴァルツはなぜかアンドヴァリ公爵邸で丁重に扱われ、後日実家ザヴェルト公爵家に捜査の手が入ることを聞かされた。シュヴァルツは活躍を評価され、アンドヴァリ公爵家の本家から遠い庶家の養子に入ることがきまった。
穏やかな生活も、丁重に扱われる事も慣れないシュヴァルツは困惑した。
しかし母の墓を立てる契約をして貰って、初めてほっとして涙を流すことができた。
しばらく経った日。庭園に行くように言われる。
シュヴァルツを待っていたのはたっぷりの甘いお菓子セットと、にこにこ顔で待ち構えていたアンドヴァリ公爵令嬢だった。
「座って。敬語もいらないから。私たち遠い親戚になったんだもの」
「……失礼します」
「だから敬語はいらないってば。もう」
あの日は流されるままに肩を並べて戦った相手だが、こうして改めて会うと身分の違いを感じさせる、あまりに美しい令嬢だった。目を見るとドキドキしてとまらないので、顔を背けながらお茶を飲む。
「あれから私、父様と兄さまに怒られちゃったわ。私の変な能力は研究途中なのだから、実践で使うなって。あなたにずっと会えなかったのもお仕置きだったのよ」
「……そうですか」
「あなたは顔色が良くなったわ。好きな物はある? 食べたいものは?」
「何でも好きです。……その、いいんですか? 一応僕達異性なのに、二人でこんな風にお茶をして」
「あら、お姉さんを意識してくれるの?」
「……」
何も言えない。耳が熱くなる。まだ幼いシュヴァルツだけど、いい匂いのする綺麗な令嬢に、ここまで人なつっこくされると、どう反応すればいいのかわからなくなった。
彼女はシュヴァルツを覗き込んで、ふふ、といたずらっぽく微笑んだ。
「ねえ。私あなたが素敵だと思ったの。私を守ってくれた横顔、覚悟を決めたときの強い瞳、とっても素敵だと思った」
「……はあ」
素っ気ない言い方しかできないのが、恥ずかしい。
しかし彼女は気にしていない様子だった。
「一緒に魔術学園に入れるようにしてもらったし、宮廷魔術局も、貴方の支援をしたいと言ってくれている。あなたさえ良ければ、これから良い関係を築いていきたいのだけど、どうかしら?」
「良い関係とは、どんな関係のことでしょう」
「これから決めていけばいいわ。まずはクラスメイトになるわね。同じ宮廷魔術局に就職して仲間になるのもいいし、友達でもいいし、それに」
「それに?」
「あとは……あなたの気持ちに任せるわ」
シュヴァルツは彼女を見た。にこりと微笑む彼女に、明確にシュヴァルツは己の運命を悟った。
きっと、一生――この人の隣に居るんだ、自分は。
「さ、クッキーを食べましょう! 私が焼いたのよ、食べて食べて」
「真ん中が透き通ってますけど、食べられるんですか?」
「そこは飴細工よ。ステンドグラスみたいで綺麗でしょう?」
くすくすと微笑む彼女の笑顔。それに大人になって見た、ウエディングドレス姿のレイラの姿が重なる。
本物のステンドグラスの光を浴びても、レイラはとても、綺麗だった――
◇◇◇
薄く、甘い菓子の匂いがする。
「……レイラ?」
シュヴァルツはベッドの隣を探る。冷たいシーツが指に触れ、急に夢から現実に引き戻される。
あの生命力に満ちあふれた妻はもう、自分の傍にはいないのだ。
しかし甘い匂いはまだ香っている。
まるでレイラが愛していたビスケットそのままの匂いだ。
「どこから……」