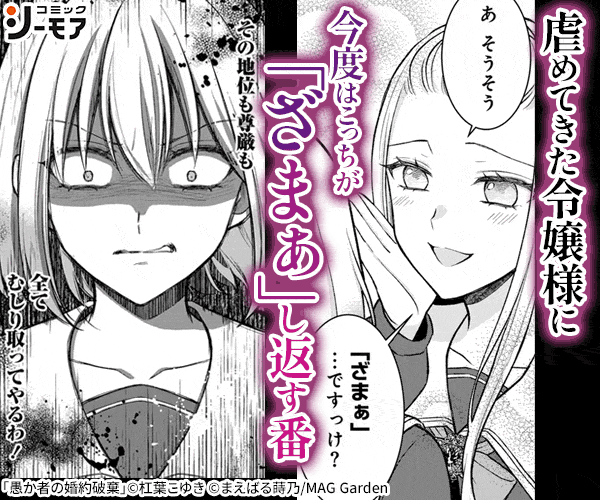7・シュヴァルツの追想 上
――夢を見ていた。
銀髪を靡かせ、いつも僕の手を引っ張って、知らない世界を見せてくれる、あの愛しい人の夢を。
◇◇◇
実父、ザヴェルト公爵家の王都屋敷にて。
7歳のシュヴァルツは問答無用で体を洗われ、裸で隠し部屋に押し込まれた。
夢の中の父の顔はぼやけていた。父の名前も、部屋の細かい場所も思い出せない。
「いいか、お前は異母兄の替え玉として魔術検査に出ろ」
「……でたら、かあさまのおはかをたてるおかね、もらえるんですよね」
「いいから黙っていけ!」
シュヴァルツは今まで着たこともないような服を纏い、馬車できらびやかな建物に連れて行かれる。
言われるままに列に並び、子どもの頭ほどの透明なオーブの前で手をかざす。
四色の強い光が輝き、周りの大人達が歓声を上げた。
異母兄の名を呼ばれ、異母兄の魔力検査結果として登録がつつがなく進んでいく。
明らかに替え玉なのに、誰も咎める人がいなかった。
シュヴァルツはザヴェルト公爵が手をつけたメイドの子供だった。
実父は手切れ金の一つも渡さず、言いがかりをつけて母を解雇し捨てた。
貧民街で身を寄せ合って暮らしていた母が死んで、ゴミ拾いをして生きていたシュヴァルツを、突然実父が迎えに来たのだ。
当然息子にするためではない。貴族令息でありながら「才なし」の異母兄の代わりに魔術検査を受けるためだ。
シュヴァルツは全てを諦めていた。
母は自分を産んだせいで酷い死に方をしたし、貧民街で生きる間に心がすっかり凍っていた。
それでも母の墓を用意できるなら、せめて――産まれてきて迷惑をかけてしまった罪を少しだけ償える気がしていたのだ。
あとはお金を貰って帰るだけだ。
そう思って会場の片隅にいると、突然悲鳴と怒号が聞こえてきた。
「魔物だ!」
「だれか! 宮廷魔術師を呼んでくれ!」
騒然となる場。貴族たちが泣き叫びながら逃げ回っている。羽が生えたオークの大群が、空からよだれを垂らしながら何匹もやってくる。魔術が彼らに飛ぶも、ちょっとやそっとの魔術では焼け石に水だ。
非戦闘要員や要人が多いので、肝心の宮廷魔術師も防戦一方のようだ。
「きゃあああ!」
一人のメイドがオークに引っ張り上げられる。泣きわめいているが、誰も助けない。
むしろ浅ましい貴族達は、メイドを与えればこの場をしのげると思ったのだろう、メイド達を突き飛ばして逃げ出す者が続出した。
メイドの顔が、泣きじゃくっていた母の顔に見えて、シュヴァルツの体は震える。
ザヴェルト公爵が現れ、シュヴァルツの首根っこを捕まえて地面に転がした。
「っ……!?」
「命令だ! お前も時間稼ぎをしてこい! 魔術が使えるから死ぬこともないだろう!」
「ち、父上と僕を守るんだ! いいな、この薄汚い売女の息子!」
呆然とするシュヴァルツに影が落ちる。振り仰ぐと、よだれを垂らしたオークが大きな手を伸ばして覆い被さってきた。シュヴァルツは呆然と、そのツメが自分につかみかかるのを見ていた――
ザシュッ!!
「諦めないで!」
目に入ったのは視界いっぱいに広がる銀髪。真っ赤なドレス。
オークは彼女の前で首をねじ切られ、爆発した。
彼女はすぐにシュヴァルツの手を取り、物陰に隠れる。
近くで見るとまだ彼女も子どもだ。10歳くらいだろうか。
ぞっとするほど綺麗な美少女だった。凜々しい顔に、長い髪。肌は白くて明らかに高位貴族の令嬢だと分かった。守ってもらえた安堵と、少女を守らねばという意志が沸き立つ。
「きみは逃げて、オークは怖いよ、酷い目に遭うよ」
「私は逃げないわ。だってアンドヴァリ公爵家の娘だもの」
瀟洒な手袋を引き上げ、スカートを裂いてスリットを作る。
アンドヴァリ公爵家。実力主義で選ばれる魔術師局長を歴代務める、王国きっての名門だ。
「宮廷魔術師の増員が来るまでの時間稼ぎをしたいの。でも私の能力はちょっと変だから、魔術で爆発させたりはできないの。貴方の力を貸して」
「僕が? 僕はただの……」
「ザヴェルト公爵令息の替え玉してたでしょ?」
「知ってたの?!」
「当然よ。事前調査にあれだけの魔力保持者の記録はなかったから。……ああ、時間はないわ、行くわよ!」
彼女はシュヴァルツの手を引いて駆け出す。
「私がオークの手首をひねって、捕らえられた人を落とすわ! 貴方はその隙にオークを破壊して!」
「破壊って……僕、魔術の勉強したことなくて」
「理屈なんて今はいらない、魔術はイメージよ。人の人生をめちゃくちゃにする酷い奴を想像して、そいつの頭に、思い切り何かをぶつけるって考えて! 氷でも、炎でも、岩でもなんでもいいわ!」
言うなり、彼女は自分に襲いかかるオークを軽やかにかわし、メイドを捕らえたオークに手のひらを向ける。
『曲がれ!』
手首が曲がらない方向に曲がり、メイドが落ちていく。
ちょうど花畑の柔らかな土の上に、彼女は落下した。
オークが睨む。
その視線がアンドヴァリ公爵令嬢に向かっていると気づき、シュヴァルツは血が沸騰するのを感じた。
――母は僕を産んで不幸になったが、決して僕を邪魔扱いしなかった。僕を守ってくれたんだ。
――そして今日は、この公爵令嬢が僕を守ってくれた。ここでやれなければ、僕は……!